宮沢賢治の名作『猫の事務所』のあらすじをこれからご紹介していきますよ。
本作は大正時代に発表された、賢治の生前に出版された貴重な童話のひとつです。
私は読書が大好きですが、特に宮沢賢治の作品には深い感銘を受けてきました。
これから『猫の事務所』の短いあらすじから詳しいストーリーまで、読書感想文を書く皆さんに役立つ情報をたっぷりとお届けします。
登場人物の解説や読書感想文のポイントなど、この物語を理解するための大切な要素もまとめていますので、ぜひ最後までお付き合いください。
『猫の事務所』の簡単で短いあらすじ
『猫の事務所』の中間の長さのあらすじ
『猫の事務所』の詳しいあらすじ
軽便鉄道の停車場近くにある猫の第六事務所は、猫の歴史と地理を調べる機関だった。事務所で働くことは猫たちの憧れで、欠員が出ると多くの若い猫が志願した。しかし定員は4人と決まっており、最も字が上手く詩が読める猫だけが選ばれた。
事務所では年老いた黒猫の事務長の下、一番書記の白猫、二番書記の虎猫、三番書記の三毛猫、そして四番書記の竈猫が働いていた。竈猫はかまどで寝る習慣があるため体が煤で汚れており、通常は他の猫から嫌われる存在だったが、事務長が黒猫だったため書記になることができた。
他の3人の書記は竈猫を嫌っており、特に三毛猫は竈猫の仕事を自分がやりたいと考えていた。竈猫は周りに好かれようと努力するが、かえって誤解を招いてしまう。
ある日、風邪で休んだ竈猫について、三毛猫が悪い噂を事務長に吹き込む。翌日出勤した竈猫は完全に無視される立場となり、泣き続けた。そこへ突然窓の外に獅子が現れ、このような事務所の在り方を否定。猫の第六事務所は廃止となった。
『猫の事務所』の作品情報
『猫の事務所』についての基本的な情報をまとめてみました。
この作品を理解するための背景知識として役立ててくださいね。
| 作者 | 宮沢賢治 |
|---|---|
| 出版年 | 大正15年(1926年) |
| 出版社 | 雑誌『月曜』に初掲載、後に偕成社・筑摩書房など |
| 受賞歴 | 特になし |
| ジャンル | 童話・寓話 |
| 主な舞台 | 猫の第六事務所 |
| 時代背景 | 明確な時代設定はないが、近代的な事務所という設定 |
| 主なテーマ | 差別・いじめ・社会の不条理・偏見 |
| 物語の特徴 | 猫たちの事務所という寓話的な設定で人間社会の問題を描いている |
| 対象年齢 | 子どもから大人まで(教育現場でも使用される) |
『猫の事務所』の主要な登場人物とその簡単な説明
『猫の事務所』には個性豊かな猫たちが登場します。
それぞれがどんな役割を担っているのか、簡単にまとめてみました。
| 名前 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| 黒猫の事務長 | 猫の第六事務所のトップ。眼光鋭く、はじめは公平だったが後に他の書記たちに扇動されてしまう。 |
| 竈猫(かまねこ) | 主人公。四番書記。字が上手く詩も読める優秀な猫だが、かまどで眠るため体が煤で汚れており、他の猫たちから嫌われている。 |
| 三毛猫 | 三番書記。有力者のデータを担当。野心家で事務長の跡目を狙っており、竈猫を最も嫌っている。 |
| 白猫 | 一番書記。探検家の情報を担当。 |
| 虎猫 | 二番書記。旅行の注意点を担当。 |
| 獅子 | 物語の最後に突然現れ、事務所の在り方を否定して廃止を決定する重要な存在。 |
これらの個性豊かな猫たちの関係性が物語を通じて描かれていきます。
特に竈猫と他の猫たちとの関係性に注目しながら読むと、物語の深いメッセージが見えてきますよ。
『猫の事務所』の文字数と読むのにかかる時間
『猫の事務所』はどのくらいの長さで、どれくらいの時間で読めるのか気になりますよね。
ここではその目安をご紹介します。
| 文字数 | 約6,480文字 |
| ページ数 | 約11ページ(1ページ600字計算) |
| 読了時間 | 約13分(1分間に500字読む計算) |
| 読みやすさ | 比較的短く、1日で十分に読み終えられる |
『猫の事務所』は比較的短い童話なので、じっくり味わいながらでも1時間もあれば何度も読み返すことができます。
読書感想文を書く際には、特に印象的な場面を何度か読み直してみることをおすすめしますよ。
『猫の事務所』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『猫の事務所』の読書感想文を書く際に、特に注目すべきポイントをまとめました。
これらを押さえておくと、より深い考察ができるはずです。
- キャラクターの多様性と魅力
- 差別といじめのテーマ
- 物語に込められた社会批判
それぞれのポイントについて詳しく解説していきますね。
キャラクターの多様性と魅力
『猫の事務所』では、黒猫の事務長をはじめとする個性豊かな猫たちが描かれています。
特に主人公の竈猫は、字が上手く詩も読める才能の持ち主なのに、生まれつきの特徴によって差別される存在です。
物語の中で、各キャラクターがどのような立場や考え方を持っているのかを分析すると、人間社会の縮図が見えてきます。
例えば、才能があっても外見で判断されてしまう不条理や、権力を持つ者がどのように他者を排除するかなど、社会の問題が猫たちを通して表現されています。
感想文では、特に竈猫の心情の変化や、他の猫たちとの関係性の変化に注目すると良いでしょう。
竈猫が周りに好かれようと努力するシーンは、読者の共感を誘う重要な場面です。
差別といじめのテーマ
本作の中心テーマは、明らかに「差別」と「いじめ」です。
竈猫は生まれつき皮が薄く、外で寝ることができないためにかまどで寝るしかありません。
そのために体が煤で汚れており、他の猫たちから嫌われています。
この設定には、外見や生まれによって差別される社会の問題が反映されています。
竈猫は自分自身を責め、周囲に受け入れられるように努力しますが、それでも状況は改善されません。この不条理さが物語の悲しさを深めています。
感想文では、現代社会にも通じるこのテーマについて、自分の経験や考えと結びつけて論じると説得力が増すでしょう。
学校や社会でのいじめや差別の問題と関連づけて考察すると、より深い読解につながります。
物語に込められた社会批判
『猫の事務所』は単なる童話ではなく、社会批判の要素を強く持っています。
事務所という組織の中での権力構造や、弱者が排除されていく過程は、人間社会の縮図として描かれています。
特に注目すべきは物語の結末。
獅子の登場によって事務所が廃止されるという展開には、このような差別的な組織の在り方を否定するメッセージが込められています。
感想文では、作者の宮沢賢治がどのような意図でこの結末を選んだのか、そこにどんなメッセージが込められているのかを考察すると良いでしょう。
また、現代社会においても同様の問題が存在するのかどうか、自分の視点で論じてみることも重要です。
※宮沢賢治が『猫の事務所』で伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『猫の事務所』の読書感想文の例(原稿用紙3枚/約1200文字)
宮沢賢治の童話『猫の事務所』を読んだ。最初は単なる猫たちの物語だと思っていたが、読み進めるうちに、この作品がいじめや差別といった深刻な問題を扱っていることに気づいた。
物語の主人公である竈猫は、かまどで寝る習慣があるために体が煤で汚れており、他の猫たちから嫌われている。これは外見や生まれによって人が判断されてしまう現実社会の問題を象徴していると感じた。竈猫は字が上手く詩も読める才能を持っているにもかかわらず、その外見だけで価値を低く見られてしまうのだ。
特に印象的だったのは、竈猫が生まれつき皮が薄いという理由でかまどで寝るしかなかった点だ。これは彼の選択ではなく、生まれつきの特性なのに、それを理由に差別されるという不条理さが胸に刺さった。私が通う学校でも、様々な要因で友達関係が左右されることがあり、この物語に現実味を感じた。
猫の第六事務所における権力構造も興味深かった。黒猫の事務長は最初は公平だったのに、三毛猫などの扇動によって竈猫に対して不公平な態度をとるようになる。これは集団の中でいじめが発生し、それを止められない傍観者の問題を示していると思う。学校のクラスでも時々似たような状況が起こることがあり、考えさせられた。
物語の中で、竈猫が周りに好かれようと必死に努力するシーンは本当に切なかった。何をしても誤解されてしまう彼の姿に、私は自分自身の経験を重ねてしまった。誰かに受け入れられたいという気持ちは誰にでもあるものだと思う。
最も考えさせられたのは物語の結末だった。事務所が突然現れた獅子によって廃止されるという展開には、このような差別的な組織のあり方自体を否定する強いメッセージを感じた。しかし同時に、問題の解決が外部からの力によってもたらされたことに少し物足りなさも感じた。現実世界では、差別やいじめの問題は獅子のような存在が現れて解決してくれるわけではないからだ。
私たちの社会では今でも外見や出自による差別が存在している。この物語が1926年に書かれたことを考えると、宮沢賢治がいかに先見性のある作家だったかがわかる。彼は童話という形式を通じて、大人にも通じる普遍的な社会問題を提起していたのだ。
この作品を読んで、私自身の日常生活でも無意識のうちに誰かを見た目や特徴で判断していないか、振り返るきっかけになった。クラスメイトの一人一人がそれぞれ独自の価値を持っていることを認め、互いを尊重することの大切さを改めて感じた。
『猫の事務所』は短い童話だが、その中に込められたメッセージは非常に深く、現代社会にも通じる問題を提起している。宮沢賢治は単に子どもを楽しませるだけでなく、読者に社会の問題について考えさせる作品を残したのだと思う。今後も彼の他の作品を読んでみたいと思った。
『猫の事務所』はどんな人向けの小説か
『猫の事務所』は幅広い層に向けた作品ですが、特に以下のような方々におすすめです。
- 社会問題に関心がある人
- 寓話的な表現を通して深いテーマを探りたい人
- 教育現場で道徳教材を探している人
- 宮沢賢治の世界観に触れたい人
この作品は、表面上は猫たちの物語ですが、その奥には人間社会の問題が描かれています。
子どもたちには冒険的な側面を楽しんでもらいながら、大人には社会批判としての側面を味わってもらえる多層的な作品です。
特に、学校や職場でのいじめや差別について考えるきっかけにもなるので、教育現場でも広く使われています。
また、宮沢賢治ならではの繊細な表現と独特の世界観を味わいたい文学ファンにもおすすめですよ。
『猫の事務所』と類似した内容の小説3選
『猫の事務所』を読んで感銘を受けた方には、同じように猫を中心に物語が展開する作品や、社会批判的要素を持つ作品をご紹介します。
『吾輩は猫である』 – 夏目漱石
夏目漱石の『吾輩は猫である』も猫の視点から人間社会を観察し批評する作品です。
名前のない一匹の猫が「吾輩」を名乗り、飼い主である珍野苦沙弥先生をはじめとする人間たちの生活や言動を皮肉たっぷりに語ります。
『猫の事務所』と同様に動物の視点を借りて人間社会の矛盾や滑稽さを描いている点が共通していますね。
ただし、『吾輩は猫である』はより辛辣な社会批評と風刺が含まれており、大人向けの要素が強いでしょう。

『猫を抱いて象と泳ぐ』 – 小川洋子
小川洋子の『猫を抱いて象と泳ぐ』は、猫と共に過ごす女性の心の変化が描かれた作品です。
主人公は猫との関わりを通じて、自分自身の内面と向き合っていきます。
『猫の事務所』とは直接的なストーリーの類似点は少ないものの、猫という存在を通して人間の心理や社会を映し出すという手法が共通しています。
繊細な心の動きや孤独といったテーマも両作品に見られる要素です。
『猫と庄造と二人のをんな』 – 谷崎潤一郎
谷崎潤一郎の『猫と庄造と二人のをんな』では、一匹の猫を介して人間関係のもつれが描かれます。
猫に執着する主人公・庄造と彼を取り巻く女性たちの愛憎劇が展開されます。
『猫の事務所』のような社会批判的な要素は薄いですが、猫が人間関係に与える影響や、猫を通して見える人間の本質という点では共通点があります。
また、どちらの作品も猫に特別な存在感を与えているところも似ていますね。
振り返り
今回は宮沢賢治の名作『猫の事務所』について、あらすじから読書感想文のポイントまで詳しく解説してきました。
この作品は一見するとかわいらしい猫たちのお話ですが、その奥には社会の不条理といった普遍的なテーマが隠されています。
短い童話ながらも非常に深いメッセージ性を持ち、子どもから大人まで幅広い層に感銘を与え続けている名作です。
読書感想文を書く際は、キャラクターの多様性のテーマ、社会批判的な側面に注目すると、より深い考察ができるでしょう。
また、現代社会の問題とも結びつけて考えることで、この作品の普遍性を感じることができますよ。
宮沢賢治の繊細な感性と鋭い社会観察眼が凝縮された『猫の事務所』は、これからも多くの読者に愛され続けるでしょう。
ぜひ皆さんも、この機会に手に取ってみてください。

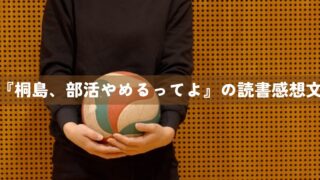
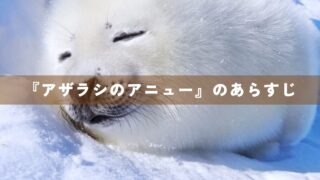
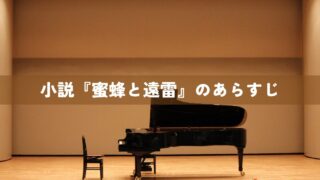
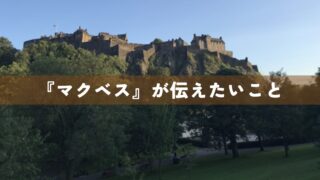

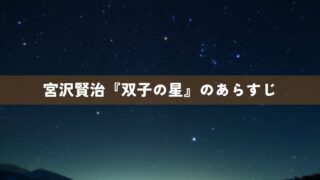
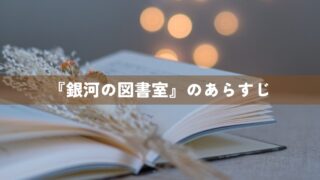


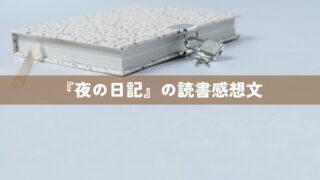
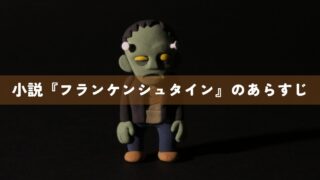
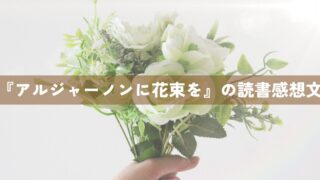



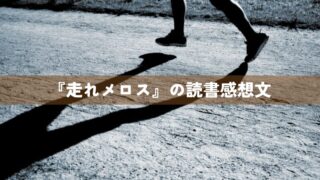

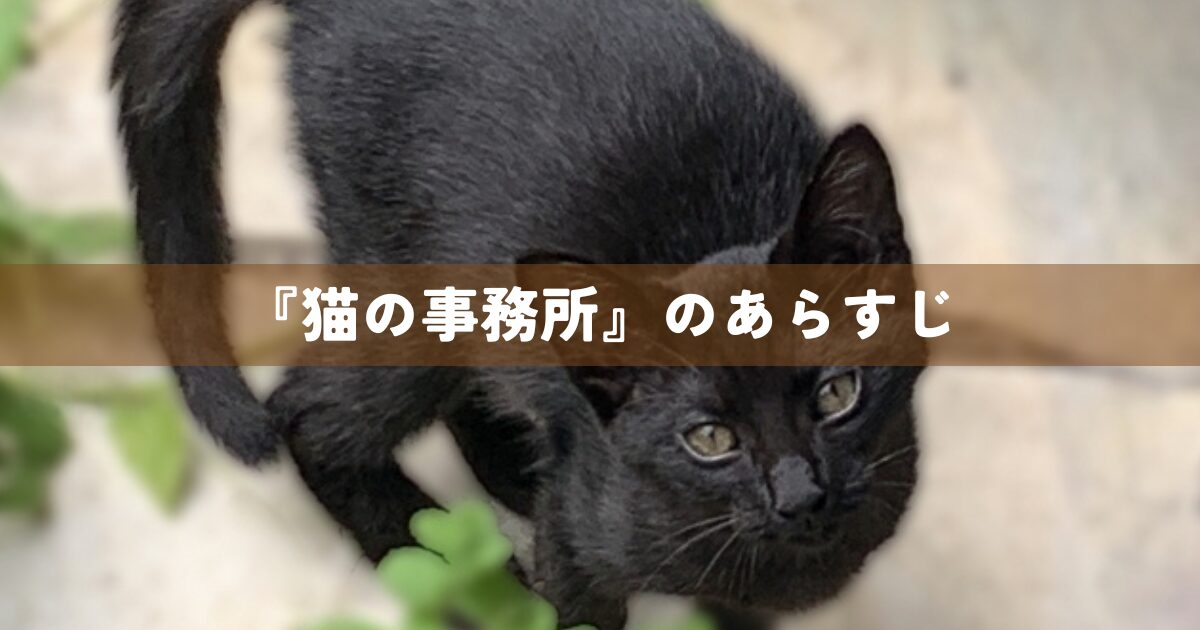
コメント