『船を編む』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れ様です。
三浦しをんさんが手がけた『船を編む』は、辞書編纂という地味に見える仕事を通して、言葉の深さと人間の成長を描いた素晴らしい作品ですね。
2012年に本屋大賞を受賞し、映画化・アニメ化もされた話題作です。
今回は皆さんの読書感想文の書き方をサポートするために、年間100冊以上の本を読む私が例文やテンプレート、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
中学生・高校生の皆さんが感想文で高評価を狙えるよう、コピペではなく自分の言葉で書けるヒントをお伝えします。
それでは早速、『船を編む』の課題にとりかかっていきましょう。
『船を編む』の読書感想文で触れたい3つの要点
読書感想文を書くときは、ただあらすじを並べるだけでは物足りません。
大切なのは「この場面でどう感じたか」「なぜそう思ったのか」を具体的に書くことです。
『船を編む』で特に注目してほしい要点は以下の3つになります。
- 辞書作りへの情熱と職人気質の美しさ
- 主人公・馬締光也の成長と人間関係
- 言葉の力と、それが人をつなぐ意味
それぞれの場面を読みながら「私だったらどう感じるだろう」「なぜこのキャラクターに共感するのか」といったメモを取っておくと良いでしょう。
感想文では「どう感じたか」が最も重要な要素だからです。
読み手に「この人は本当に心を動かされたんだな」と伝わる文章こそが、印象深い感想文になるのです。
辞書作りへの情熱と職人気質の美しさ
馬締たち辞書編集部のメンバーが、気の遠くなるような作業に取り組む姿勢は圧巻です。
一つの言葉の意味を決めるために、何日も何週間も検討を重ねる場面があります。
普段私たちが何気なく使っている言葉にも、こんなに深い意味と歴史が込められているのかと驚かされるでしょう。
ここで大切なのは「自分も何かに夢中になった経験はあるか」「継続することの難しさを感じたことはあるか」といった個人的な体験と結びつけることです。
部活動でも勉強でも、地道な努力を積み重ねた経験があれば、きっと馬締たちの気持ちが理解できるはずです。
また、現代社会では効率や結果ばかり求められがちですが、『船を編む』は丁寧に時間をかけることの価値を教えてくれます。
「急がば回れ」という言葉の本当の意味を、この物語から学べるでしょう。
主人公・馬締光也の成長と人間関係
不器用で口下手な馬締が、辞書作りを通して少しずつ変わっていく様子は見どころの一つです。
最初は営業部で浮いた存在だった彼が、辞書編集部で自分らしさを発揮していく過程に注目してください。
特に西岡との友情や、香具矢との恋愛関係は読んでいて温かい気持ちになります。
ここでは「自分にも馬締のような経験があるか」「人とのつながりで救われた思い出はあるか」といった視点で考えてみましょう。
学校生活でも、最初は居場所がなかったけれど、部活動や委員会で仲間ができた経験がある人は多いはずです。
馬締の成長は決して劇的な変化ではありません。
むしろ、日々の小さな積み重ねによって、ゆっくりと自信を取り戻していく姿が描かれています。
この「等身大の成長」こそが、多くの読者の心を打つ理由なのです。
また、荒木さんのような先輩や、タケおばあさんのような温かい大人の存在も重要です。
人は一人では成長できない、周りの人々に支えられて生きているという当たり前の事実を、改めて実感させてくれるでしょう。
言葉の力と、それが人をつなぐ意味
タイトルの「船を編む」には「言葉の海を渡る舟を編む」という意味が込められています。
辞書は単なる言葉の説明書ではなく、人と人、時代と時代をつなぐ大切な役割を担っているのです。
日頃SNSやメールで簡単に言葉をやり取りしている私たちにとって、言葉の重みについて考え直すきっかけになるはずです。
「言葉一つで人を傷つけることもあれば、救うこともできる」という経験は誰にでもあるでしょう。
友達とのケンカで言い過ぎてしまったり、逆に励ましの言葉で元気をもらったりした思い出を振り返ってみてください。
また、方言や流行語、新しい言葉が生まれる過程についても触れられています。
言葉は生き物のように変化し続けるものだということを、『船を編む』は教えてくれます。
自分が普段使っている言葉も、いずれ辞書に載る日が来るかもしれません。
そう考えると、日常会話ももっと大切にしたくなりますね。
読書感想文では「この作品を読んで、自分の言葉遣いについてどう思ったか」「家族や友人との会話で気をつけたいことは何か」といった具体的な変化を書くと良いでしょう。
※『船を編む』を通して作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

『船を編む』の読書感想文のテンプレート
『船を編む』の読書感想文を書くためのテンプレートがこちらです。
1. はじめに(選んだ理由・読み始めたきっかけ)
この本を手に取ったのは、_____________________________だからです。
(例)辞書作りの裏側に興味があった/友人にすすめられた/映画を先に見て、原作も気になった など
2. あらすじの簡単な紹介
『船を編む』は、国語辞典『大渡海』の編纂に取り組む人々の姿を描いた小説です。
主人公の馬締光也は、不器用ながら言葉への強い情熱を持ち、編集部の仲間と共に辞書完成を目指して努力する物語です。
3. 印象に残った場面や心に響いたこと
私が特に印象に残ったのは_____________________________________場面です。
(例)言葉の意味を巡って編集部で議論するシーン/用例カードを集める地道な作業 など
この部分から_________________________________________と感じました。
4. 登場人物への感想や共感したこと
馬締や編集部の人たちについて、_________________________________________________________________。
(例)馬締の不器用だけれど誠実なところに共感した/西岡の明るさや佐々木の几帳面さが印象的だった など
香具矢や大家さんなど周囲の人たちとの関わりからも、__________________________を感じました。
5. この本から学んだこと、考えたこと
この本を読んで、_______________________________________ことを学びました。
(例)辞書作りには想像以上の努力が必要と知り、言葉の大切さを感じた/地道な作業や仲間との協力の大切さを考えるきっかけになった など
6. 自分の経験や考えと結びつけて書く
私も_________________________________________________________________________________。
(例)人付き合いが苦手な自分でも、馬締のように自分らしい努力を続けたいと思った/身近な言葉や物ごとにも目を向けてみたい など
7. まとめ(全体の感想とおすすめの言葉)
全体として、『船を編む』は__________________________________におすすめしたい一冊です。
この小説を読んで言葉の魅力や、人とつながることの喜びを知ることができました。
このテンプレートに沿って自分の感じたことを素直に入れていくと、作品内容と自分自身の発見・学びがバランスよく伝わる感想文になります。
書きやすいパートから順に埋めていく方法もおすすめです。
『船を編む』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】言葉という舟に乗って
私は『船を編む』を読んで、普段何気なく使っている言葉の大切さについて深く考えさせられた。
この小説は辞書を作る人たちの物語だが、読む前の私は「辞書作りなんて地味だな」と思っていた。
いや、そもそも「辞書作り」について考えたことなどなかったに違いない。
しかし読み進めるうちに、主人公の馬締さんたちの情熱と努力に心を動かされた。
馬締さんは最初、営業の仕事がうまくいかず周りから浮いた存在だった。
私も中学校に入学したばかりの頃は、新しい環境になじめず不安な日々を過ごしていた。
だから馬締さんの気持ちがとてもよく分かった。
人とのコミュニケーションが苦手で、自分の居場所がないと感じる辛さは本当に苦しいものだ。
でも馬締さんは辞書編集部に移ってから、だんだん自分らしさを発揮するようになった。
言葉への深い愛情と、一つ一つの意味を丁寧に調べる真面目な性格が評価されたのだ。
私も部活動で自分の得意なことを見つけたとき、同じような喜びを感じた。
苦手なことばかりに目を向けるのではなく、自分の長所を活かせる場所を見つけることの大切さを学んだ。
辞書を作る作業は本当に気が遠くなるほど大変なのだと初めて知った。
一つの言葉の意味を決めるだけでも、何日もかけて議論を重ねているのだ。
私たちが普段当たり前のように辞書を引いているが、その裏にはこんなにも多くの人の努力があったなんて知らなかった。
特に印象に残ったのは「右」という言葉の意味を説明する場面だ。
「右とは何か」と聞かれても、私を含めて世の中の人のほとんどが的確に説明できないことに気づかされた。
普段使っている言葉でも、正確に意味を伝えることの難しさを実感した。
これからは辞書を見るときも、一つ一つの言葉にもっと敬意を払いたいと思う。
馬締さんと香具矢さんの恋愛も素敵だった。
不器用な馬締さんが一生懸命気持ちを伝えようとする姿は、見ていてほほ微ましかった。
言葉のプロである馬締さんでも、大切な人に想いを伝えることには苦労している。
愛情を言葉にして表現することの難しさと尊さを感じた。
私も友達や家族に感謝の気持ちを伝えるとき、もっと真剣に言葉を選ぼうと思った。
何より感動したのは「辞書は言葉の海を渡る舟」という表現だ。
言葉は人と人をつなぎ、過去と未来をつなぐ大切な役割を担っている。
SNSでは言葉を軽々しく、まるで玩具を扱うようにやり取りする時代だからこそ、一つ一つの言葉の重みを忘れてはいけないと思った。
友達との何気ない会話も、実は心と心を結ぶ大切な舟なのかもしれない。
『船を編む』を読んで、私は言葉を大切にすることの意味と大切さを身に染みて実感した。
これからは辞書を見るときだけでなく、日常の会話でも言葉を選んで話そうと思う。
そして馬締さんのように、自分の好きなことに情熱を注げる人になりたいと心から思った。
『船を編む』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】言葉の力と人生の深み
『船を編む』を読み終えたとき、私の中で何かが静かに変わったような気がした。この作品は辞書編纂という地味な仕事を扱うが、実際は人間の成長と言葉の持つ計り知れない力について考えさせる物語だったのだ。
主人公の馬締光也に、私は最初から強い親近感を覚えた。営業部で浮いた存在になる彼の不器用さや、人とのコミュニケーションに苦労する様子は、まさに高校生の私自身と重なる部分があったからだ。クラスでうまく話せない自分や、思っていることを正確に伝えられないもどかしさを、私も日々感じている。そんな中で、馬締さんが辞書編集部に移ることで、水を得た魚のように居場所を見つけていく姿は感動的ですらあった。
言葉への深い愛情が認められ、自分らしく働けるようになるのだが、この変化に希望を感じた。私自身も今は自分の長所が分からなくても、いつか必ず自分を活かせる場所が見つかるのだと、強く信じられるようになった。
辞書作りの過程で描かれる職人気質の美しさにも心を打たれた。一つの言葉の意味を決めるために、編集部のメンバーたちが何時間もかけて議論し、時には徹夜までする場面がある。
現代社会では効率性や速さばかりが重視されがちだが、『船を編む』は丁寧に時間をかけ、妥協せずに最高のものを追求することの価値を教えてくれる。私たちが普段何気なく使う辞書の一つ一つの項目に、これほど多くの人の情熱と努力が込められているとは、全く知らなかった。
特に印象深かったのは、新しい言葉や流行語をどう扱うかという議論だった。言葉は生き物のように変化し続けるものであり、辞書編纂者たちはその変化を敏感に察知し、取り入れるべきかを真剣に考える。私たち高校生が普段使うスラングや新語も、いずれ辞書に載る日が来るかもしれないと思うと、不思議な気持ちになった。
この作品は、言葉の重要性について深く考えるきっかけにもなった。SNSやメッセージアプリで簡単にやり取りする現代だからこそ、一つ一つの言葉の意味と重みを忘れがちになる。しかし『船を編む』を読んで、言葉がいかに人と人をつなぐ大切な役割を担っているかを、実感した。
「辞書は言葉の海を渡る舟」という比喩は、まさに言葉の本質を表している。私たちは言葉という舟に乗って、他者の心に思いを届け、世界を広げているのだ。
馬締さんと西岡さんの友情も、心に残った。対照的な性格の二人が、辞書作りという共通の目標を通じて、互いを理解し、深い絆で結ばれていく過程は美しかった。西岡さんは最初、辞書編集に情熱を持っていなかったが、馬締さんの影響を受けて次第に仕事の意味を理解し、かけがえのない存在へと変わる。
真の友情とは、互いに刺激し合い、共に成長し合える関係なのだと学んだ。私も友人関係において、もっと相手の好きなことや情熱を理解し、支え合えるようになりたいと思った。
香具矢さんとの恋愛関係も、心温まった。不器用な馬締さんが、一生懸命に自分の想いを伝えようとする姿は、純粋で感動した。言葉のプロである馬締さんでさえ、愛する人に気持ちを伝えることには苦労している。
このことから、感情を言葉にすることの難しさと、それでも伝えようとすることの大切さを学んだ。私も家族や友人に、感謝の気持ちや大切な想いを、もっと素直に表現していこうと決意した。
荒木さんやタケおばあさんのような温かい大人の存在も印象深かった。彼らは馬締さんを優しく見守り、時に導き、成長を支えてくれた。人は一人では成長できない。周りの人々に支えられ、導かれながら少しずつ成熟していくものなのだと実感した。私もいつか誰かの成長を支え、温かく見守れるような大人になりたいと願った。
『船を編む』が描く時間の流れも特徴的だった。辞書の完成には長い年月がかかり、その間に登場人物たちも年を重ね、人生の様々な局面を迎えていく。現代社会では即座に結果を求められることが多いが、本当に価値のあるものを作り上げるには、焦らず、丁寧に時間をかけることが必要なのだと気づかされた。
私自身も何事も急いで結果を出そうとしがちだが、もっと長期的な視点を持って物事に取り組むことの重要性を学んだ。
この作品を読んで、私は言葉に対する意識が大きく変わった。普段の会話でも、もっと相手の立場に立って言葉を選ぼうと心がけるようになった。
また、辞書を引くときも、そこに込められた人々の努力と愛情を思い出すようになった。
『船を編む』は単なる職業小説ではない。人間の成長、友情、愛情、そして言葉の持つ無限の力について、深く考えさせる、忘れられない作品。
馬締さんのように、自分の好きなことに情熱を注ぎ、周りの人々との絆を大切にしながら生きていきたいと心から思った。そして言葉という美しい舟に乗って、多くの人の心に想いを届けられる人になりたいと願っている。
振り返り
今回は『船を編む』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
大切なのは作品のあらすじを説明するだけでなく、自分がどう感じたかを具体的に書くことです。
馬締さんの成長に共感したり、辞書作りの情熱に感動したり、言葉の大切さに気づいたり。
そうした個人的な体験と結びつけることで、読み手の心に響く感想文が完成します。
皆さんも今回の例文やテンプレートを参考にしながら、自分だけの感想文を書いてみてくださいね。
きっと素晴らしい作品が仕上がりますよ。
※『船を編む』の読書感想文の作成に役立つ記事がこちらです。
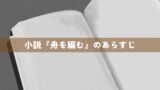
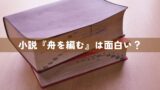

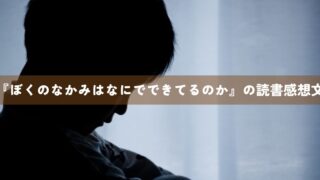

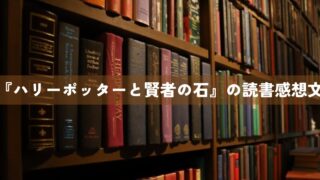

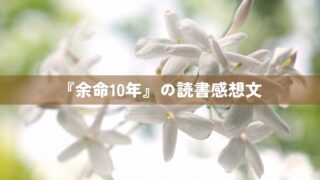
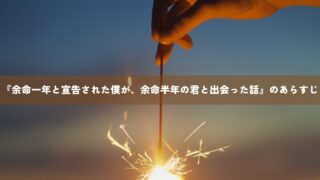
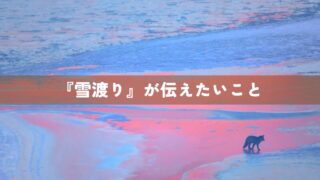







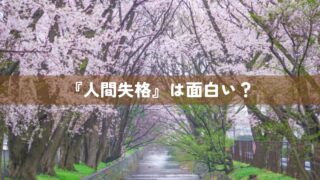
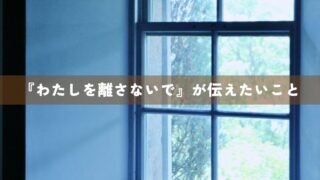

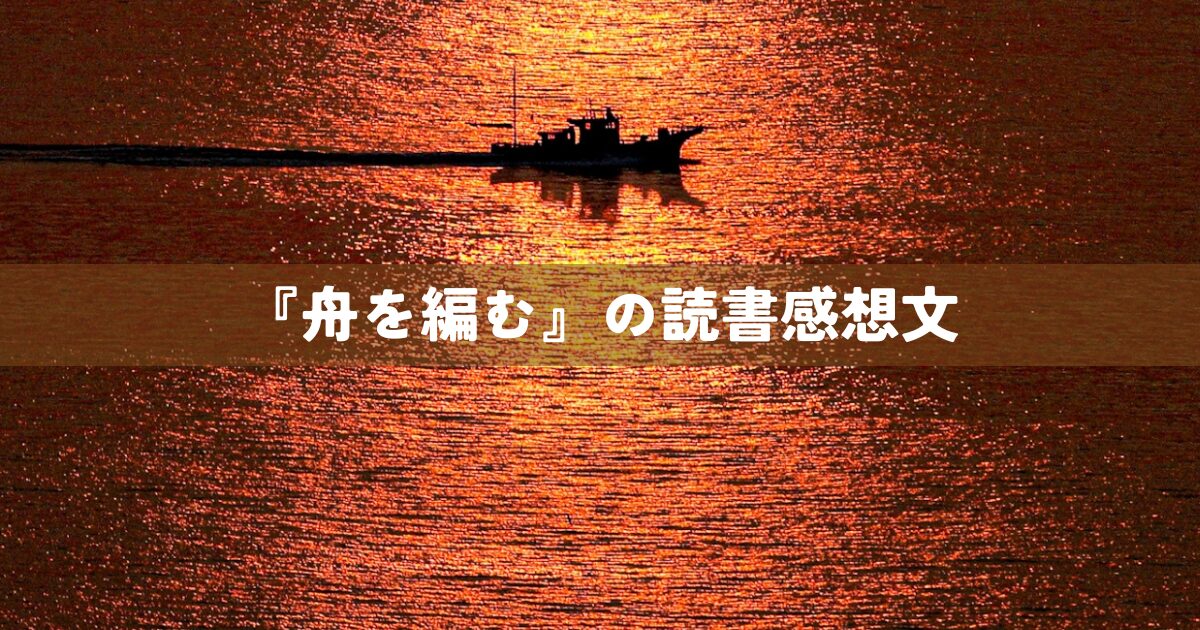
コメント