『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
スペインでもっとも歴史のある児童文学賞「ラサリーリョ賞」を2021年に受賞したビクター・ベルモント作『ねえねえ、なに見てる?』は、色覚に特徴のある少年トーマスが主人公の心温まる物語です。
金原瑞人さんによる翻訳で2024年5月に河出書房新社から出版され、小学校中学年の課題図書にもなっている注目作品ですね。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいるのですが、この作品は「多様性」や「他者理解」について深く考えさせられる素晴らしい絵本だと感じました。
この記事では、『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文の書き方から例文まで、小学校高学年の皆さんにもわかりやすく丁寧に解説していきますよ。
『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文を書くうえで大切な3つのポイント
『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文を書く時に、絶対に外してはいけない重要なポイントが3つあります。
この3つのポイントを押さえて書くことで、読み手に伝わりやすい素晴らしい感想文になりますよ。
- 「見え方のちがい」に気づき、認めることの発見
- 多様性や他者理解の大切さに対する自分の考え
- 「自分のメガネ」で世界を見ていること、その意味
これらのポイントは、作品のメッセージの核心部分でもあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
「見え方のちがい」に気づき、認めることの発見
主人公のトーマスは、自分と家族それぞれが世界の見え方が異なることに気づきます。
色覚に特徴があるトーマス自身は、自分の見え方を特別だと思っていません。
でも、科学者のママ、ゲーム好きのパパ、画家のマルタおばさん、音楽家のおじさん、恐竜好きのいとこのルーカス、そして愛犬のオレオまで、みんながそれぞれ違った「メガネ」で世界を見ていることに気づくのです。
感想文では、「自分が当たり前だと思っていたことも、実は人によって全然違うかもしれない」という発見や、作品を通して感じた驚きや共感を言葉にすることが大切ですね。
トーマスがどんなふうに家族の「見え方」を想像していたかを具体的に書いて、あなた自身がそれをどう感じたかを表現してみましょう。
同じ食卓を囲んでいるのに、みんながまったく違う世界を見ているなんて、本当に驚きですよね。
多様性や他者理解の大切さに対する自分の考え
『ねえねえ、なに見てる?』は「違いがあって当たり前」「多様性は大切」というメッセージを伝えています。
他者との違いを受け入れることで世界が広がること、様々な人とつながれることの楽しさや大切さを、あなたなりにどう考えたかを整理することが重要です。
あなた自身の経験や印象に残った場面を挙げて書くと、感想に深みが生まれますよ。
例えば、友だちと考えが食い違った体験と重ねてみたり、家族の中でも見方が違うなと感じた出来事を思い出したりしてみてください。
トーマスの家族のように、身近な人でも実はまったく違う「メガネ」をかけて生きているのかもしれません。
そんなことを考えながら、多様性を認めることの意味や、他の人を理解しようとすることの大切さについて、あなたの言葉で表現してみましょう。
「自分のメガネ」で世界を見ていること、その意味
本書では、”人それぞれ目に見えない「メガネ」=個性や考え方、興味”を通して世界を見ているという表現が使われています。
読後は「自分はどんなメガネで世界を見ているのか」「他の人のメガネを想像できるだろうか」と自分自身を振り返ることが大切です。
あなたが好きなことや興味のあることによって、物事の見え方が変わっているかもしれませんね。
例えば、スポーツが好きな人は運動している人を見るとついつい技術面に注目してしまったり、音楽が好きな人は街の中でも様々な音に敏感になったりするかもしれません。
日常で生かせる気づきや、”自分と違うものをどのように受け入れたいか”という前向きな視点も感想文のポイントになります。
トーマスのように、「みんなはどんなふうに見えているのかな?」と想像する心を持つことの大切さについても書いてみてください。
読書感想文を書くために『ねえねえ、なに見てる?』を読んだらメモしておきたい3項目~多様性に対してあなたが感じたこと~
『ねえねえ、なに見てる?』を読んだら、感想文を書く前に必ずメモしておきたい項目があります。
これらの項目について「どう感じたか」をしっかりと記録しておくことで、読み応えのある感想文が書けるようになりますよ。
- 「自分と他人の”見え方”が違う」ことへの気づきや驚き
- 多様性や他者理解の意味について自分なりの考察
- 「自分はどんな”メガネ”で世界を見ているか」
なぜ「どう感じたか」が重要なのでしょうか。
それは、感想文は単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身の心の動きや考えの変化を表現する文章だからです。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
「自分と他人の”見え方”が違う」ことへの気づきや驚き
主人公トーマスと家族・動物が同じものを見ていても、ひとりひとり解釈や感じ方がまったく異なるという構造に、どんな発見や驚きがあったかをメモしてください。
科学者のママが食べ物やお皿を科学的な視点で見ているシーンや、画家のマルタおばさんがものごとをキュービズム風に見ているシーンなど、印象に残った場面はありましたか。
どの登場人物の”見方”がいちばん印象に残ったか、その理由も合わせて考えてみましょう。
あなた自身が普段、当たり前だと思っていた「見え方」について、新しい発見があったかもしれませんね。
「みんな同じように見ているはず」という思い込みが崩れた瞬間の気持ちを言葉にしてみてください。
多様性や他者理解の意味について自分なりの考察
作品が示す「違いがあって当たり前」「いろんな価値観を認めることの大切さ」というメッセージを、あなたの日常やこれまでの読書体験と結びつけてどう感じたかを整理しましょう。
「自分がもし登場人物だったら?」と想像したり、今後あなたがどう行動したいかの視点も加えてみてください。
友だちや家族と意見が違った時のことを思い出して、この作品を読む前と読んだ後で、その出来事に対する見方が変わったかどうかも考えてみるといいですね。
トーマスのように、他の人の「見え方」に興味を持つことの大切さについても、あなたなりの言葉でメモしておきましょう。
「自分はどんな”メガネ”で世界を見ているか」
本書が強調する、”目に見えない自分の「メガネ」”とはどんなものなのかを振り返ってみてください。
「自分固有のものの見方や感じ方」は何でしょうか。
好きなスポーツ、趣味、将来の夢、家族構成など、あなたの興味や環境によって、物事の感じ方が他の人と違うかもしれません。
それを自覚したエピソードや、この本を読んで考え直した点などもメモしておきましょう。
また、今まで気づかなかった自分の「メガネ」を発見できたとしたら、それも大切な感想のひとつになります。
これからどんなふうに他の人の「メガネ」を理解しようと思うかも書いておくといいですね。
『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】みんな違う「メガネ」をかけている
『ねえねえ、なに見てる?』を読んで、私はとても驚いた。主人公のトーマスは色の見え方が他の人と違うけれど、自分では全然変だと思っていない。それどころか、「みんなはどんなふうに世界を見ているのだろう」と想像することを楽しんでいる。
いちばん印象に残ったのは、家族みんなが同じ食卓にいるのに、それぞれまったく違う世界を見ているという場面だった。科学者のママは食べ物を科学的に見ているし、ゲーム好きのパパには周りの人がゲームのキャラクターに見えている。画家のマルタおばさんは全部をキュービズムみたいに見るし、音楽家のおじさんは音符で感じている。恐竜好きのいとこのルーカスは何でも恐竜に見立てているし、犬のオレオは食べ物ばかりに注目している。
これを読んで、私は「同じものを見ていても、人によって全然違うんだ」ということに気づいた。今まで、みんな私と同じように見ているものだと思っていたけれど、それは違うのかもしれない。友だちと映画を見た時に感想が全然違ったり、家族と同じ料理を食べても好みが違ったりするのも、みんな違う「メガネ」をかけているからなのだろう。
この本では「人はみんな、それぞれ違うメガネをかけて世界を見ている」と書かれている。私はどんなメガネをかけているのだろうと考えてみた。私は本を読むのが好きだから、街で看板を見てもつい文字に注目してしまう。友だちは絵を描くのが好きだから、同じ景色を見ても色や形に注目している。お兄ちゃんはサッカーが好きだから、テレビでスポーツを見ると技術的なことばかり気になるみたいだ。
今度友だちや家族と話す時は、「この人はどんなメガネで見ているのかな」と考えてみたいと思う。自分と違う意見を聞いた時も、「間違っている」と決めつけるのではなく、「違うメガネをかけているから、違って見えるのかも」と思えるようになりたい。
『ねえねえ、なに見てる?』は、みんな違って当たり前だということを教えてくれる本だった。
『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文の例文(1200字の小学生向け)
【題名】世界はひとりひとり違って見える
『ねえねえ、なに見てる?』を読んで、私の世界の見方が大きく変わった。この本は、色の見え方が他の人と違う少年トーマスが主人公の物語だ。トーマス自身はそのことを特別だとは思っていないが、家族や周りの人がどんなふうに世界を見ているのかを想像することが好きだ。
物語でいちばん心に残ったのは、家族みんなが同じ食卓を囲んでいるのに、それぞれまったく違う世界を見ているという場面だった。科学者のママは食べ物やお皿を科学的な目で見ている。ゲーム好きのパパには、周りの人がゲームのキャラクターのように見えているかもしれない。画家のマルタおばさんは、すべてのものをキュービズムみたいに分けて見ている。音楽家のおじさんは音符やリズムで世界を感じ取り、恐竜好きのいとこのルーカスは何を見ても恐竜に見立てて考える。そして愛犬のオレオは、食べ物ばかりに注目している。
この描写を読んだ時、私は「みんな同じように見ているはず」という今までの思い込みが間違いだったことに気づいた。同じ場所にいて同じものを見ていても、その人の興味や職業、性格によって、世界はまったく違って見えるのだ。これはとても新鮮な発見だった。
私も家族で旅行に行った時を思い出した。私は景色の美しさに感動していたが、写真好きのお父さんは撮影のこと、お母さんは昼食のこと、弟は虫のことばかり気にしていた。
この本を読んで、「違いがあることは当たり前で、それを認めることが大切だ」ということを学んだ。今まで友だちと意見が合わない時、どちらかが間違っていると思っていた。でも、それは間違いだったのかもしれない。みんな違う「メガネ」をかけて世界を見ているから、感じ方が違うのは自然なのだ。
物語の中で「人はみんな、まわりの世界を自分のメガネをかけて見ている」という表現が出てくる。私はどんなメガネをかけているのだろうと考えてみた。私は本を読むことが好きだから、どこに行っても本屋さんや図書館を探してしまう。友だちと映画を見ても、ストーリーばかりに注目してしまう。これが私の「メガネ」なのかもしれない。
友だちのゆうこちゃんは絵を描くのが上手で、いつも色や形に注目している。この前一緒に公園に行った時も、私は「きれいな花が咲いているな」としか思わなかったけれど、ゆうこちゃんは「ピンクのグラデーションが美しい」「花びらの形が面白い」と具体的に観察していた。
これからは、違う意見を聞いた時に「間違っている」と決めつけず、「その人はどんなメガネをかけているのかな」と考えたい。そして、相手の見え方や感じ方に興味を持って、「どうしてそう思うの?」と聞いてみたいと思う。きっと新しい発見があるはずだ。
『ねえねえ、なに見てる?』は、多様性を認めることの大切さを教えてくれる素晴らしい本だった。みんな違って当たり前で、その違いこそが世界を豊かにしているのだということを、これからも忘れずにいたい。
振り返り
『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この作品は「多様性」と「他者理解」という深いテーマを、小学生にもわかりやすく描いた素晴らしい物語です。
感想文を書く時は、主人公トーマスの気づきを通して、あなた自身がどんなことを発見し、どう感じたかを大切にしてくださいね。
「見え方の違い」「多様性の大切さ」「自分のメガネ」という3つのポイントを意識しながら、あなたの体験や考えを織り交ぜて書けば、きっと心に響く感想文になります。
例文も参考にしながら、あなただけの素敵な読書感想文を完成させてください。
みんな違って当たり前という『ねえねえ、なに見てる?』のメッセージを、あなたの言葉で表現してみてくださいね。
※『ねえねえ、なに見てる?』のあらすじは以下の記事でご確認ください。


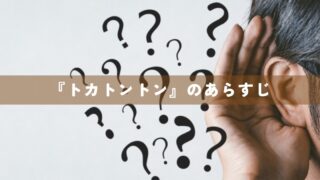


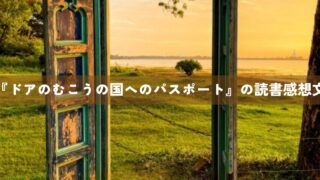
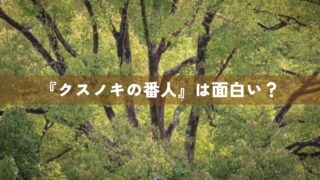
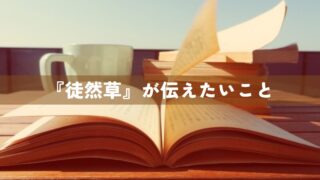
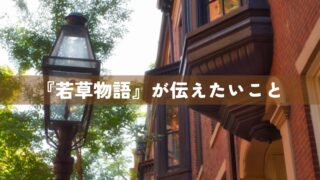





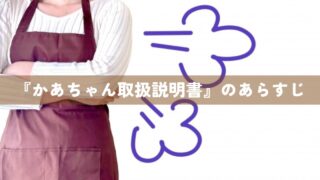
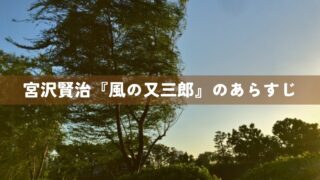




コメント