『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れ様です。
この作品は、明治から昭和にかけて活躍した人類学者・鳥居きみ子さんの生涯を描いたノンフィクション作品ですね。
竹内紘子さんによって書かれたこの人物伝は、くもん出版から出版され、小学校高学年向けの課題図書として選ばれています。
僕は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいるのですが、『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』は意外な掘り出し物でしたね。
女性の社会進出が困難だった時代に、家族とともに研究を進めた先駆的な人物の物語は、現代の中学生にも多くの学びを与えてくれるはず。
この記事では、読書感想文の書き方に悩んでいる皆さんの力になれるよう、重要なポイントから具体的な例文まで、丁寧に解説していきますよ。
『鳥居きみ子』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントを3つご紹介します。
これらのポイントを押さえることで、深みのある感想文が書けるでしょう。
- 困難な時代における女性の生き方と学問への情熱
- 「家族」と「フィールドワーク」の独自の融合
- 「見えない貢献」を「見える」ようにすることの意義
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
困難な時代における女性の生き方と学問への情熱
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読む上で最も重要なのは、きみ子さんが生きた時代背景を理解することです。
明治から昭和にかけて、女性が社会で活躍することは極めて困難でした。
「良妻賢母」が理想とされ、女性は家庭に入って夫や子どもを支えることが当然とされていた時代ですね。
そんな制約の中で、きみ子さんは人類学への情熱を抱き、それを追求し続けました。
もともと小学校教員として働いていた彼女が、音楽学校に進学し、その後鳥居龍蔵との結婚を機に人類学の世界へ足を踏み入れたのです。
特に注目したいのは、きみ子さんが「学者の妻」という枠にとどまらず、自らも積極的に研究活動に参加した点です。
現地の女性たちとの交流を通じて、男性研究者だけでは知ることができなかった伝統的な生活習慣、儀式、歌、織物などの情報を収集しました。
これは民族学の発展に大きく貢献した功績として評価されています。
読書感想文では、きみ子さんの学問への情熱と、それを支えた強い意志について、具体的なエピソードを交えて書くことが重要でしょう。
「家族」と「フィールドワーク」の独自の融合
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のタイトルにもあるように、「家族とフィールドワークを進めた」という点が、この作品の核心部分です。
きみ子さんと龍蔵さんの研究スタイルは、当時としては極めて異例でした。
夫婦だけでなく、子どもたちを含めた家族全体で中国やモンゴルなどの調査地を訪れたのです。
この家族でのフィールドワークが、独自の研究成果を生み出しました。
きみ子さんは現地で教師を務めつつ、生活や伝承などの文化的要素を記録し、後に著作としてまとめています。
長女の幸子さん、次女の緑子さん、次男の龍次郎さんも、それぞれの得意分野で調査に関わり、「鳥居家ならではの研究スタイル」を築き上げました。
龍蔵さんが東京大学を辞めた後に設立した「鳥居人類学研究所」では、きみ子さんが調査に必要な連絡や交渉、通訳、会計などを担当し、まさに共同研究者として活躍しています。
この独自のスタイルがもたらした成果や意義について、感想文で考察することが大切ですね。
「見えない貢献」を「見える」ようにすることの意義
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』は、これまであまり知られることのなかった鳥居きみ子さんの生涯に光を当てた作品です。
著名な人類学者・鳥居龍蔵さんの妻として紹介されることはあっても、きみ子さん自身の功績が詳しく語られることは少なかったのです。
本書は、そんな「見えない貢献」を「見える」ようにする試みとして、大きな意義を持っています。
歴史の中で、女性や縁の下の力持ちとして活躍した人々の功績が、正当に評価されてこなかったという問題を浮き彫りにしています。
きみ子さんの事例を通して、歴史の見方や評価のあり方について考えることができるでしょう。
また、現代を生きる私たちにとっても、この作品は重要なメッセージを発しています。
多様な生き方や働き方、そして性別に関わらず個人の能力が正当に評価される社会の実現に向けて、きみ子さんの生き方は示唆に富んでいます。
読書感想文では、この「見える化」の意義について、自分なりの考えを深めることが大切ですね。
より良い読書感想文を書くために『鳥居きみ子』を読んだらメモしておきたい3項目~彼女の生き方に対してあなたが感じたこと~
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読む際に、「どう感じたか」をメモしておくことは、読書感想文を書く上で非常に重要です。
感想文は単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身の心の動きや考えの変化を表現する場だからです。
以下の3つの項目について、きみ子さんの生き方に対するあなたの感情や考えを記録しておきましょう。
- 印象に残ったエピソードとその理由
- 現代社会との関連性や問いかけ
- 自分の考えや感情の変化
これらの項目を意識してメモを取ることで、より深みのある感想文が書けるでしょう。
印象に残ったエピソードとその理由
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読みながら、特に心に残った場面や出来事をメモしておきましょう。
それは、きみ子さんの行動、言葉、あるいは彼女を取り巻く人々の反応など、何でも構いません。
重要なのは、なぜそのエピソードが印象に残ったのか、その理由も併せて記録することです。
例えば、幼い子どもを連れて異国の地に赴く決断をした場面では、当時のきみ子さんの心情や覚悟がどのようなものだったのか考えてみてください。
現地の女性たちと交流し、男性研究者には得られなかった情報を収集する場面では、きみ子さんのどのような姿勢や工夫がその成果に繋がったのか分析してみましょう。
夫である鳥居龍蔵さんとの関係性の中で、きみ子さんの学術的貢献がどのように位置づけられていたかを示すエピソードも重要ですね。
これらの具体的なエピソードと、あなたがそれに対して感じた驚き、感動、疑問などの感情を記録することで、読書感想文に説得力が生まれます。
現代社会との関連性や問いかけ
きみ子さんの生きた時代と現代社会とを比較し、彼女の生き方や研究が現代の私たちにどのような問いかけをしているかを考えてみましょう。
女性の社会進出やキャリア形成について、きみ子さんの生き方から学べることは何でしょうか。
研究と家庭の両立というテーマについて、きみ子さんの経験は現代の私たちにどのようなヒントを与えてくれるでしょうか。
「見えない貢献」が正当に評価されることの重要性について、本書はどのようなメッセージを伝えているでしょうか。
これらの問いかけに対する自分なりの答えを見つけることで、読書感想文に現代性と普遍性を持たせることができます。
また、きみ子さんの生き方が、現在の学校生活や将来の進路選択にどのような影響を与えるかも考えてみてください。
困難な状況でも自分の信念を貫くことの大切さや、家族や仲間との協力の重要性など、きみ子さんの生き方から学べることは多いはずです。
自分の考えや感情の変化
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読む前と読んだ後で、あなたの考えや感情がどのように変化したかを記録しておきましょう。
読む前は「偉人の妻」というイメージしかなかったが、読後は「独立した研究者」としてのきみ子さんの姿を強く感じるようになったかもしれません。
フィールドワークという研究手法について、より深く理解できるようになったでしょうか。
困難な状況でも自分の信念を貫くことの強さや大切さを学んだでしょうか。
女性の生き方や社会での役割について、新しい視点を得たでしょうか。
これらの変化は、あなたが本書から何を学び取ったかを示す重要な指標です。
変化の過程を詳しく記録することで、読書感想文に成長と学びの軌跡を描くことができます。
また、今後の自分の行動や考え方にどのような影響を与えそうかも考えてみてください。
きみ子さんの生き方を知ったことで、あなた自身の将来への考え方が変わったかもしれませんね。
『鳥居きみ子』の読書感想文の例文(1200字の中学生向けバージョン)
【題名】家族で歩む研究の道
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読んで、私は家族の絆と学問への情熱について深く考えさせられた。
鳥居きみ子さんは、女性が社会で活躍することが困難だった明治から昭和にかけて、夫や子どもたちとともに人類学の研究に取り組んだ先駆的な人物である。
この本を読むまで、私は「偉人の妻」というイメージしか持っていなかったが、実際のきみ子さんは独立した研究者として素晴らしい功績を残していたことを知った。
最も印象に残ったのは、きみ子さんが幼い子どもを連れて海外の調査地に赴いた話である。
現代でも海外での子育ては大変なのに、当時の交通手段や宿泊施設を考えると、その困難さは想像を絶する。
それでも家族一丸となって研究に取り組む姿勢に、私は深い感動を覚えた。
きみ子さんの研究スタイルで特に興味深いのは、現地の女性たちとの交流を通じて情報を収集したことだ。
男性研究者だけでは知ることができなかった伝統的な生活習慣、儀式、歌、織物などの貴重な情報を記録している。
これは、女性だからこそできた研究手法であり、民族学の発展に大きく貢献した。
私は普段、友だちを支えたり応援したりすることに遠慮がちだが、きみ子さんの「支える側」としての生き方に大きな価値があることを学んだ。
家族でのフィールドワークという独自のスタイルも印象的だった。
夫の龍蔵さんが東京大学を辞めた後に設立した「鳥居人類学研究所」で、きみ子さんは連絡や交渉、通訳、会計などを担当し、まさに共同研究者として活躍している。
長女の幸子さん、次女の緑子さん、次男の龍次郎さんも、それぞれの得意分野で調査に関わり、「鳥居家ならではの研究スタイル」を築き上げた。
この家族の協力体制は、現代の私たちにも多くのヒントを与えてくれる。
一人では困難なことも、家族や仲間と協力することで乗り越えられるのだ。
この本が教えてくれたもう一つの重要なことは、「見えない貢献」を「見える」ようにすることの大切さである。
これまで鳥居龍蔵さんの影に隠れがちだったきみ子さんの功績を明らかにすることで、歴史の見方そのものが変わってくる。
現代社会でも、多くの人が陰で支える役割を担っているが、その貢献が正当に評価されることは少ない。
きみ子さんの生き方は、そうした「見えない貢献」にも大きな価値があることを教えてくれる。
私は今回この本を読んで、困難な時代でも自分の信念を貫くことの大切さを学んだ。
また、異なる文化や人々に対して敬意と好奇心を持って接することの重要性も理解した。
きみ子さんのように、新しい世界に一歩踏み出す勇気を、これからも大切にしていきたい。
家族や友だちとの協力を通じて、自分なりの道を見つけていこうと思う。
『鳥居きみ子』の読書感想文の例文(1800字の高校生向けバージョン)
【題名】時代を超えた女性研究者の先駆的な生き方
『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』を読み終えて、私は一人の女性研究者の生き方について深く考えさせられた。
明治から昭和にかけて、女性の社会進出が極めて困難だった時代に、鳥居きみ子さんは夫や子どもたちとともに人類学の研究に取り組み、独自の研究スタイルを築き上げた先駆的な人物である。
この本を読むまで、私は鳥居龍蔵さんの妻という位置づけでしか彼女を認識していなかったが、実際のきみ子さんは独立した研究者として素晴らしい功績を残していたことを知り、歴史の見方そのものが変わった。
最も印象深かったのは、きみ子さんが困難な時代にも関わらず、学問への情熱を追求し続けたことである。
もともと小学校教員として働いていた彼女が、音楽学校に進学し、その後鳥居龍蔵さんとの結婚を機に人類学の世界へ足を踏み入れたのは、決して計画されたものではなかった。
しかし、一度その世界に入ると、きみ子さんは現地の女性たちとの交流を通じて、男性研究者だけでは知ることができなかった伝統的な生活習慣、儀式、歌、織物などの貴重な情報を収集し、民族学の発展に大きく貢献した。
この事実は、女性だからこそできる研究手法の存在を示しており、多様な視点が学問の発展に不可欠であることを教えてくれる。
「良妻賢母」が理想の女性像とされ、「男は外、女は内」という考えが支配的だった時代に、きみ子さんが学問の世界で活躍できたのは、家族でのフィールドワークという独自のスタイルを築いたからである。
夫婦だけでなく、幼い子どもたちを含めた家族全体で中国やモンゴルなどの調査地を訪れるという方法は、当時としては極めて異例であった。
小さい子供を連れて国外の調査に出かけたり、はたまた子どもを知り合いの家庭に養子に出すという信じられない行動をとったりと、現代の価値観では理解しがたいエピソードもある。
しかし、この家族ぐるみでのフィールドワークが、きみ子さんの研究活動を可能にし、独自の研究成果を生み出したのである。
龍蔵さんが東京大学を辞めた後に設立した「鳥居人類学研究所」では、きみ子さんが調査に必要な連絡や交渉、通訳、会計などを担当し、まさに共同研究者として活躍している。
長女の幸子さん、次女の緑子さん、次男の龍次郎さんも、それぞれの得意分野で調査に関わり、「鳥居家ならではの研究スタイル」を築き上げた。
この家族の協力体制は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれる。
一人では困難なことも、家族や仲間との協力によって乗り越えることができるのだ。
この本が提起するもう一つの重要な問題は、「見えない貢献」を「見える」ようにすることの意義である。
これまで鳥居龍蔵さんの影に隠れがちだったきみ子さんの功績を明らかにすることで、歴史の見方そのものが変わってくる。
歴史の中で、女性や縁の下の力持ちとして活躍した人々の功績が正当に評価されてこなかったという問題を浮き彫りにしている。
現代社会においても、多くの人が陰で支える役割を担っているが、その貢献が正当に評価されることは少ない。
きみ子さんの生き方は、そうした「見えない貢献」にも大きな価値があることを教えてくれる。
また、この本を読んで、現代社会との関連性についても考えさせられた。
女性の社会進出やキャリア形成について、きみ子さんの生き方から学べることは多い。
研究と家庭の両立という現代的な課題についても、きみ子さんの経験は重要なヒントを与えてくれる。
多様な生き方や働き方、そして性別に関わらず個人の能力が正当に評価される社会の実現に向けて、きみ子さんの生き方は今なお示唆に富んでいる。
さらに、異なる文化や人々に対して敬意と好奇心を持って接することの重要性も学んだ。
きみ子さんが現地の人々と信頼関係を築き、その生活や伝統を記録した姿勢は、現代のグローバル社会においても見習うべき態度である。
私は今回この本を読んで、困難な時代でも自分の信念を貫くことの大切さが身に染みて分かった。
また、家族や仲間との協力を通じて、一人では成し遂げられないことも実現できるということを理解した。
きみ子さんのように、新しい世界に一歩踏み出す勇気と、周囲の人々との協力を大切にしながら、自分なりの道を見つけていきたいと思う。
時代を超えて受け継がれるべき、きみ子さんの生き方の教訓を、これからの人生に活かしていこうと決意している。
振り返り
この記事では、『鳥居きみ子 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読書感想文を書くためのポイントから、具体的な例文まで詳しく解説してきました。
きみ子さんの生き方は、困難な時代でも自分の信念を貫くことの大切さや、家族との協力の重要性など、現代の私たちにも多くの学びを与えてくれます。
読書感想文を書く際は、単なるあらすじの紹介に終わらず、あなた自身の心の動きや考えの変化を表現することが重要です。
きみ子さんの生き方から何を学び、それが自分の将来にどのような影響を与えるかを考えながら、オリジナルな感想文を作成してくださいね。
あなたにも、きっと素晴らしい読書感想文が書けるはずです。頑張ってください。
※『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじはこちらでご紹介しています。

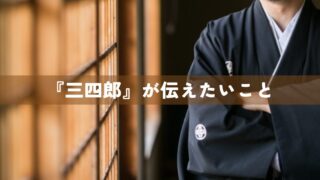




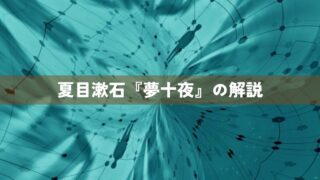
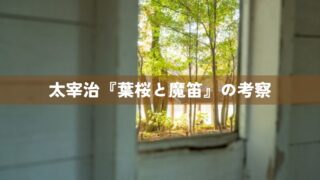
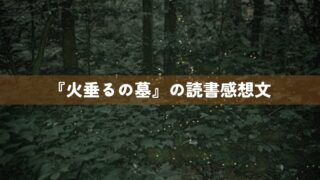
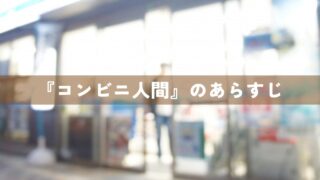
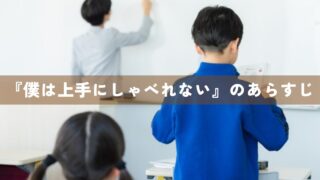
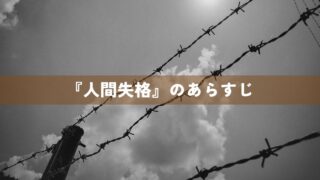

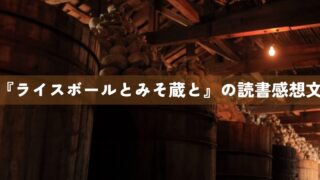
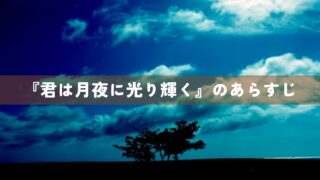
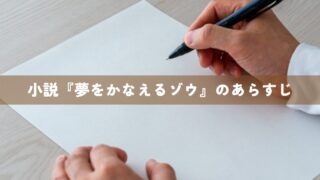

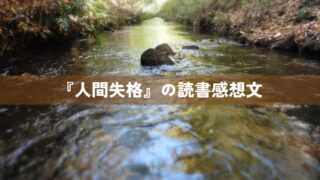


コメント