『窓際のトットちゃん』の読書感想文を書こうとしているみなさん、こんにちは。
今回ご紹介するのは、黒柳徹子さんが自身の小学生時代を描いた自伝的物語『窓際のトットちゃん』。
主人公トットちゃんがトモエ学園という自由で温かい学校で過ごした日々を描いた、心温まる物語です。
この作品は1981年に出版され、第5回路傍の石文学賞を受賞し、総発行部数2500万部を超える大ベストセラーとなりました。
年間100冊以上の本を読む私が、小学生・中学生・高校生のみなさんがより良い読書感想文を書けるよう、書く際の重要ポイントから具体的な例文まで、段階的にサポートしていきますよ。
『窓際のトットちゃん』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『窓際のトットちゃん』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要なポイントが3つあります。
これらのポイントを理解することで、この物語の本質を捉えた深みのある感想文が書けるでしょう。
- 個性の尊重と「その子らしさ」の大切さ
- 自由な発想・自己表現の重要性
- 子どもを信じて見守る大人の姿勢
これらのポイントは、現代の教育や社会にも通じる普遍的なテーマです。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
個性の尊重と「その子らしさ」の大切さ
トットちゃんは最初に通っていた普通の小学校では「変わった子」として見られ、退学することになってしまいます。
しかし、トモエ学園では、その個性がしっかりと認められ、のびのびと成長していくんですね。
この対比は、『窓際のトットちゃん』の最も重要なメッセージの一つといえるでしょう。
小林宗作校長先生は、一人一人の子どもたちが持つ独自の魅力を見つけ出し、それを大切に育てようとします。
トットちゃんがチンドン屋さんを呼び込むために窓から身を乗り出したり、机の蓋をパタパタと何度も開け閉めしたりする行動も、怒られることなく温かく見守られました。
これは現代社会においても非常に重要な視点です。
みんなと違っていても、それが間違いではないということ。
一人一人が持つ個性や特性を理解し、受け入れることの大切さを、『窓際のトットちゃん』は優しく教えてくれます。
感想文では、トットちゃんの個性がどのように受け入れられたのか、そしてそれが現代の教育や自分自身の経験とどう関わるのかを考えてみてください。
自由な発想・自己表現の重要性
トモエ学園の教育方針は、当時としては革新的で自由なものでした。
好きな科目から勉強を始める「自習の時間」や、電車を教室にした学習環境など、子どもたちの興味関心を最大限に活かす工夫がなされていました。
『窓際のトットちゃん』では、このような環境の中でトットちゃんがどのように自分らしさを発揮していったかが描かれています。
散歩しながら学ぶ理科の授業では、トットちゃんの好奇心が存分に発揮されました。
農作業を通して学ぶ体験学習では、土に触れることで得られる実感を大切にしていました。
このような教育を通して、トットちゃんは自分の感情や考えを自由に表現できるようになっていきます。
現代の教育現場でも、この「自由な発想と創造性を育む」という視点は極めて重要です。
『窓際のトットちゃん』を読んで、あなた自身の学校生活や学習体験と比較してみてください。
自由に表現することの喜びや、創造性を発揮することの大切さについて、どのような感想を持ったでしょうか。
子どもを信じて見守る大人の姿勢
『窓際のトットちゃん』で最も印象的なエピソードの一つに、トットちゃんがトイレに落とした財布を探す場面があります。
校長先生は、トットちゃんを叱ることなく、「見つかるといいね」と声をかけるだけでした。
そして、トットちゃんが自分で解決するまで、温かく見守り続けたのです。
この姿勢は、子どもを一人の人格として尊重し、信頼することの重要性を示しています。
大人が安易に介入したり、頭ごなしに叱ったりするのではなく、子どもの力を信じて待つという姿勢です。
小林校長先生は、いつもトットちゃんの話を最後まで聞き、「君は本当はいい子なんだよ」という言葉をかけ続けました。
この言葉は、トットちゃんの自己肯定感を育み、困難な時代を生き抜く力となっていきました。
『窓際のトットちゃん』を通して、あなたの周りの大人たちの接し方について考えてみてください。
信頼されることで得られる安心感や、見守られることで育つ自立心について、どのような気づきがあったでしょうか。
※『窓際のトットちゃん』で作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

より良い読書感想文を書くために『窓際のトットちゃん』を読んだらメモしておきたい3項目~登場人物に対してあなたが感じたこと~
『窓際のトットちゃん』を読んだ後、感想文を書く前にメモしておくべき重要な項目があります。
これらの項目を意識してメモを残しておくことで、より深みのある感想文が書けるでしょう。
- 物語の中で心に残ったシーンや印象的だった出来事
- トットちゃんや周囲の人物の考え方・行動に感じたこと
- 「もしも?」の視点で考えたことや感じたこと、自分との共通点・違い
これらの項目は、あなた自身の感性や価値観を反映させる重要な要素です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
心に残ったシーンや印象的だった出来事
『窓際のトットちゃん』には、読者の心に深く残る印象的なシーンがたくさんあります。
たとえば、トットちゃんがトモエ学園に初めて足を踏み入れる場面です。
電車を教室にした校舎を見て、トットちゃんがどれほど驚き、喜んだかが生き生きと描かれています。
また、小林校長先生がトットちゃんの話を4時間もの間、じっと聞き続けた場面も印象的でした。
このような場面で、あなたはどのような感情を抱いたでしょうか。
わくわくした気持ち、温かい気持ち、感動した気持ちなど、具体的な感情をメモしておきましょう。
プールでの出来事や、山登りの遠足、お弁当の時間など、日常の中の小さな出来事にも注目してみてください。
これらのエピソードから感じた「小さな幸せ」や「友情の大切さ」についても記録しておくと、感想文に深みが増します。
登場人物の考え方・行動に感じたこと
『窓際のトットちゃん』に登場する人物たちの考え方や行動には、学ぶべき点がたくさんあります。
トットちゃん自身の自由な発想力や、何事にも好奇心を持って取り組む姿勢はどうでしたか。
小林校長先生の教育に対する信念や、子どもたちへの愛情深い接し方についてはいかがでしょう。
友達との関わり方や、困っている人への優しさなど、人間関係における学びもあったはずです。
これらの登場人物から「こんな風になりたい」と思った点や、「自分とは違うな」と感じた点をメモしておきましょう。
また、現代の自分たちの学校生活や人間関係と比較してみることも大切です。
『窓際のトットちゃん』の時代と現代では環境は違いますが、人として大切にすべき価値観は変わらないものも多いはずです。
「もしも?」の視点で自分が考えたことや感じたこと
最も重要なのは、『窓際のトットちゃん』を読んであなた自身がどのように感じ、何を考えたかということです。
物語を通して、自分自身の学校生活や友人関係について考えたことはありませんか。
「もし自分がトットちゃんの立場だったら」「もし自分の学校にこんな先生がいたら」といった想像も大切です。
また、自分の個性や特性について改めて考えるきっかけになったかもしれません。
自分らしさを大切にすることの意味や、他の人との違いを受け入れることの大切さについて、どのような気づきがあったでしょうか。
これらの内的な体験や気づきこそが、あなただけの独創的な感想文を作り上げる源となります。
読書は単に物語を楽しむだけでなく、自分自身と向き合う貴重な機会でもあるんですよ。
『窓際のトットちゃん』の読書感想文の例(800字の小学生向けバージョン)
【題名】「みんなちがって、みんないい」
私は『窓際のトットちゃん』を読んで、とても心があたたかくなった。トットちゃんという女の子が、とても自由で元気で、読んでいて楽しくなったからだ。
最初、トットちゃんは普通の小学校にいたけれど、そこではいつも先生に怒られていた。授業中に窓から外を見て、チンドン屋さんを呼んだり、机のふたをパタパタ開けたりしていたからだ。でも、私はトットちゃんが悪い子だとは思わなかった。ただ、好奇心がとても強くて、いろいろなことに興味を持っているだけだと思った。
トモエ学園に転校してからのトットちゃんは、本当に生き生きしていた。電車を教室にした学校なんて、私も行ってみたいと思った。小林校長先生は、トットちゃんの話を4時間も聞いてくれて、「君は本当はいい子なんだよ」と言ってくれた。こんな風に話を聞いてもらえたら、誰でも嬉しいと思う。
私が一番印象に残ったのは、好きな科目から勉強できる「自習の時間」だ。算数が嫌いな子は国語から始めて、国語が嫌いな子は算数から始められる。みんな違っていいんだということが、とてもよく分かった。私の学校でも、こんな勉強の仕方ができたらいいのにと思った。
トットちゃんがトイレに財布を落としてしまった時も、校長先生は怒らずに「見つかるといいね」と言っただけだった。そして、トットちゃんが自分で探すのを見守ってくれた。私だったら、きっとパニックになって泣いてしまうと思う。でも、校長先生に信頼されているトットちゃんは、最後まで頑張って探していた。大人に信じてもらえるというのは、こんなにも力になるんだと思った。
『窓際のトットちゃん』を読んで、私は自分の個性を大切にしたいと思った。みんなと同じでなくても、自分らしくいることが一番大切だということを学んだ。トットちゃんのように、何事にも興味を持って、のびのびと生活していきたいと思う。
『窓際のトットちゃん』の読書感想文の例(1200字の中学生向けバージョン)
【題名】「個性を輝かせる教育の力」
『窓際のトットちゃん』は、黒柳徹子さんの小学生時代を描いた自伝的な物語である。読み終えた時、私は教育の本来あるべき姿について深く考えさせられた。この作品は、一人の少女の成長を通して、個性を尊重することの大切さと、子どもを信じて見守ることの重要性を教えてくれる。
物語の主人公トットちゃんは、最初に通っていた小学校では「問題児」として扱われていた。授業中に窓から身を乗り出してチンドン屋を呼んだり、机の蓋を何度も開け閉めしたりする行動が、先生たちには理解されなかったのだ。しかし、私はトットちゃんの行動を読んでいて、彼女が決して悪い子ではないと感じた。ただ、好奇心が人一倍強く、自分の興味のあることに素直に反応しているだけなのだ。
トモエ学園に転校してからのトットちゃんの変化は劇的だった。小林宗作校長先生は、トットちゃんの個性を否定するのではなく、それを受け入れ、伸ばそうとした。初対面の日に4時間もトットちゃんの話を聞き続けたエピソードは、特に印象深い。現代の忙しい大人たちには、果たしてこれほどまでに子どもの話に耳を傾ける時間と心の余裕があるだろうか。
トモエ学園の教育方針も非常に興味深かった。好きな科目から始められる「自習の時間」は、子ども一人ひとりの学習スタイルや興味を尊重している。電車を教室にするという発想も、子どもたちの学習への意欲を高める素晴らしいアイデアだと思う。散歩をしながら理科を学んだり、農作業を通して様々なことを体験したりする授業は、机に座って教科書を読むだけでは得られない貴重な学びを提供している。
私が最も感動したのは、トットちゃんがトイレに財布を落とした時の校長先生の対応である。普通の大人なら「なぜそんなことをしたの」と叱ったり、代わりに探してあげたりするかもしれない。しかし、校長先生は「見つかるといいね」と声をかけただけで、トットちゃんが自分で解決するまで見守り続けた。これは、子どもを一人の人格として尊重し、その力を信じているからこそできることだ。
現代の教育現場では、画一的な指導や効率性が重視されがちである。しかし、『窓際のトットちゃん』は、教育の本質は一人ひとりの子どもの個性を理解し、それを伸ばすことにあるということを改めて教えてくれる。みんなと違っていることは決して悪いことではなく、むしろその違いこそがその人の魅力なのだ。
私自身も、時々「みんなと同じでなければならない」というプレッシャーを感じることがある。しかし、この本を読んで、自分らしさを大切にすることの重要性を再認識した。トットちゃんのように、何事にも好奇心を持ち、自分の感情や考えを素直に表現できる人になりたいと思う。
『窓際のトットちゃん』は、子どもだけでなく、大人にとっても多くの学びがある作品だ。教育に携わる人はもちろん、子どもと関わるすべての大人に読んでほしい一冊である。
『窓際のトットちゃん』の読書感想文の例(1800字の高校生向けバージョン)
【題名】「真の教育とは何か―『窓際のトットちゃん』が示す人間形成の理想」
黒柳徹子氏による『窓際のトットちゃん』は、一人の少女の小学生時代を描いた自伝的作品であるが、同時に教育の本質について深く考えさせられる普遍的なテーマを内包している。この作品を読み終えた今、私は現代の教育システムや社会のあり方について、改めて問い直したいと思う。
物語の冒頭で描かれるトットちゃんの「問題行動」は、現代でも多くの教育現場で見られる光景である。授業中に窓から身を乗り出してチンドン屋を呼んだり、机の蓋を繰り返し開け閉めしたりする行動は、確かに授業の妨げになるかもしれない。しかし、これらの行動の背景にある子どもの心理を理解しようとする大人がどれほどいるだろうか。トットちゃんの行動は、決して悪意から生まれたものではなく、旺盛な好奇心と純粋な興味の表れなのである。
トモエ学園での小林宗作校長の教育理念は、現代の教育関係者にとって大きな示唆を与える。初対面のトットちゃんの話を4時間にわたって聞き続けたエピソードは、単なる美談を超えて、教育者としての根本的な姿勢を問いかける。現代社会では効率性や成果主義が重視される中で、一人の子どもにこれほどまでの時間と関心を注ぐことができる教育者がどれほど存在するだろうか。
トモエ学園の教育システムも非常に興味深い。好きな科目から始められる「自習の時間」は、現代で言うところの個別最適化学習の先駆けとも言える。子ども一人ひとりの学習スタイルや興味関心を尊重し、それに応じた学習環境を提供することの重要性を示している。また、電車を教室にするという物理的環境の工夫は、学習に対する子どもたちの動機を高める効果的な手法である。散歩をしながらの理科学習や、農作業を通した体験学習は、知識の詰め込みではなく、実体験を通した深い学びを重視している。
私が最も印象深く感じたのは、トットちゃんがトイレに財布を落とした際の校長先生の対応である。この場面は、子どもとの関わり方における大人の姿勢の理想を示している。叱責することなく、代わりに解決してあげることもせず、ただ「見つかるといいね」と声をかけて見守り続ける。これは、子どもを一人の独立した人格として尊重し、その問題解決能力を信頼しているからこそできることである。現代の過保護とも言える教育環境の中で、このような「見守る」姿勢の重要性を改めて認識させられる。
戦争という時代背景も、この作品に深い意味を与えている。トモエ学園が最終的に戦争によって閉鎖に追い込まれるという事実は、理想的な教育環境がいかに脆いものであるかを物語っている。しかし、それでもなお、トモエ学園での経験がトットちゃんの人格形成に与えた影響は計り知れない。校長先生の「君は本当はいい子なんだよ」という言葉は、困難な時代を生き抜く力となったのである。
現代の教育現場では、標準化されたカリキュラムと評価システムが主流となっている。確かに、一定の水準を保ち、公平性を確保するという観点では意味があるかもしれない。しかし、『窓際のトットちゃん』が示すように、真の教育とは一人ひとりの個性を理解し、それを伸ばすことにある。画一的な教育システムの中で、どれほど多くの「トットちゃん」たちが自分らしさを見失っているかもしれない。
私自身も、これまでの学校生活の中で「みんなと同じであること」を求められる場面を多く経験してきた。しかし、この作品を読んで、個性や多様性を認めることの重要性を改めて実感した。トットちゃんのように、自分の興味や関心に素直に向き合い、それを表現することの価値を見直したいと思う。
また、将来教育に関わる仕事に就きたいと考えている私にとって、小林校長先生の教育者としての姿勢は大きな指針となる。子どもたちの話に耳を傾け、その個性を理解し、信頼して見守ることの大切さを心に刻みたい。
『窓際のトットちゃん』は、単なる懐古的な物語ではなく、現代にこそ必要な教育の理想を示した作品である。効率性や競争が重視される現代社会において、一人ひとりの人間としての尊厳と個性を大切にすることの意味を、改めて考えさせられる。この作品が長年にわたって愛され続けているのは、そこに描かれている価値観が時代を超えて普遍的であるからなのだろう。
トットちゃんの純粋な好奇心と、それを受け入れる大人たちの温かさに触れながら、私たちは真の教育とは何かを学ぶことができる。この作品から得た学びを、これからの人生に活かしていきたいと思う。
振り返り
『窓際のトットちゃん』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この記事では、感想文を書く際の重要ポイントから、具体的な例文まで段階的にご紹介しました。
小学生・中学生・高校生、それぞれの学年に応じた感想文の書き方のコツも理解していただけたでしょう。
最も大切なのは、あなた自身がこの物語を読んでどのように感じ、何を考えたかということです。
『窓際のトットちゃん』が教えてくれる「個性の大切さ」「自由な発想の重要性」「信頼して見守ることの価値」を、あなたなりの言葉で表現してみてください。
読書感想文は、単なる作業ではありません。
あなた自身と向き合い、成長するための貴重な機会にもなりますから。
この記事を参考に、きっと素晴らしい感想文が書けるはずです。
あなたらしい感想文の完成を心から応援しています。
※『窓際のトットちゃん』のあらすじはこちらでご確認ください。


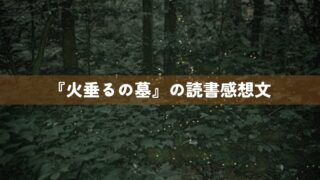
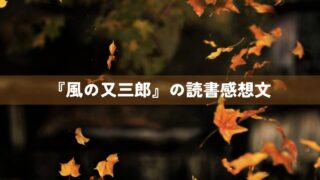
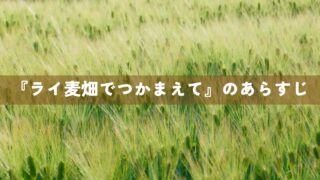



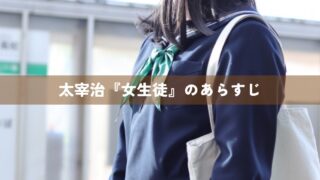


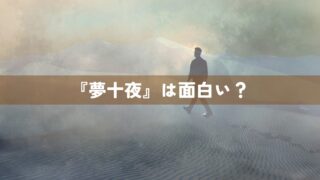
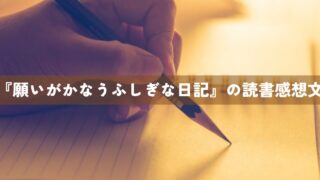

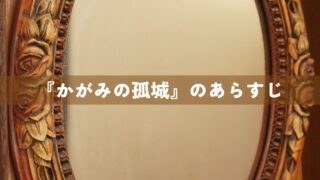


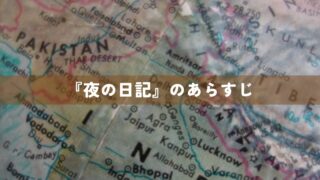


コメント