『杜子春』の読書感想文を書く皆さんに向けて、感想文の書き方をご紹介します。
『杜子春』は芥川龍之介が1920年に発表した短編小説で、中国の古典を元に童話化した作品。
お金持ちになったり貧乏になったりを繰り返す杜子春という若者が、最後に本当の幸せを見つける物語ですね。
今回は年間100冊以上の本を読む読書好きの私が、読書感想文の書き方や例文、題名の付け方から書き出しのコツまで詳しく解説していきます。
小学生・中学生・高校生それぞれの学年に合わせた例文も用意していますので、コピペに頼らず自分なりの感想文が書けるようになりますよ。
『杜子春』の読書感想文で触れたい3つの要点
『杜子春』の読書感想文を書く際に必ず触れておきたい重要な要点が3つあります。
- 物質的な豊かさと精神的な成長の対比
- 人間らしい心の温かさと仙人への憧れの葛藤
- 本当の幸せとは何かという人生の教訓
これらのポイントについて「自分はどう感じたか」をしっかりメモしておくことが大切ですね。
感想文を書く前に、物語を読みながら気になった部分に付箋を貼ったり、ノートに思ったことを書き留めたりしましょう。
「なぜこの場面で心が動いたのか」「この登場人物のどこに共感したのか」といった自分の気持ちを言葉にしておくと、後で感想文を書く時にとても役立ちますよ。
感想文で最も重要なのは「あなたがどう感じたか」という個人的な体験なので、正解や不正解はありません。
それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
物質的な豊かさと精神的な成長の対比
杜子春は仙人からもらった黄金で大金持ちになりますが、すぐに散財してしまいます。
この繰り返しを通じて、お金や物だけでは本当の満足は得られないということが描かれていますね。
現代の私たちも「お金があれば幸せになれる」と思いがちですが、杜子春の体験を通じて別の価値観を学ぶことができます。
あなたは普段の生活で「物よりも大切なもの」を感じた経験はありませんか?
友達との時間や家族との会話など、お金では買えない幸せについて考えてみましょう。
感想文では「杜子春のようにお金を失った経験はないけれど、友達と喧嘩した時に物よりも関係が大切だと感じた」といった具体的な体験を書くと良いでしょう。
人間らしい心の温かさと仙人への憧れの葛藤
物語のクライマックスで、杜子春は地獄で苦しむ母親を見て思わず「お母さん」と叫んでしまいます。
これによって仙人になる修行は失敗してしまいますが、鉄冠子はこの人間らしい感情を褒めるのです。
冷静で感情に左右されない仙人と、愛情深く温かい心を持つ人間の対比が美しく描かれていますね。
あなたは誰かのために我慢できなくなって行動したことはありますか?
家族や友達、ペットのために自分の利益を捨てて動いた経験があれば、杜子春の気持ちがよく分かるはずです。
感想文では「私も妹がいじめられているのを見た時、先生に怒られるかもしれないと思ったけど止めに入った」などの体験を書くと説得力が増します。
本当の幸せとは何かという人生の教訓
『杜子春』は最終的に「本当の幸せ」について深く考えさせる作品です。
お金でも仙人の力でもない、もっと身近で温かいものが真の幸福だと教えてくれます。
杜子春が最後に手に入れたのは、泰山の麓にある小さな家と畑だけでした。
でもそこには人間らしい生活と、他者への思いやりを大切にする心がありました。
あなたにとって「幸せ」とは何でしょうか?
大きな夢や目標も大切ですが、日常の小さな喜びにも目を向けてみてください。
感想文では「私の幸せは家族みんなで夕食を食べる時間だと気づいた」といった身近な発見を書くと読み手に伝わりやすくなりますよ。
※『杜子春』で芥川龍之介が伝えたいことはこちらで考察しています。

『杜子春』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】本当に大切なもの
私は芥川龍之介の『杜子春』を読んで、本当に大切なものは何かを考えた。
杜子春は最初、たくさんのお金をもらってうれしかったと思う。
でも、お金を使いすぎてすぐになくなってしまった。
私も時々お小遣いをもらうとすぐに使ってしまうので、杜子春の気持ちが分かった。
杜子春は何度もお金持ちになったり貧乏になったりを繰り返した。
お金があるときは友達がたくさんいたけど、なくなると誰も相手にしてくれなくなった。
これを読んで、本当の友達というのはお金があってもなくても一緒にいてくれる人なんだと思った。
私にも仲良しの友達がいるけど、お金のことなんて関係なく遊んでくれる。
それがとても幸せなことだと気づいた。
杜子春は仙人に会って、いろいろな試練を受けることになった。
地獄でお父さんとお母さんが苦しめられているのを見ても、声を出してはいけないという厳しい修行だった。
でも最後に、杜子春はお母さんのことが心配で「お母さん」と叫んでしまった。
私はこの場面を読んで泣きそうになった。
もし私だったら絶対に我慢できないと思う。
家族が苦しんでいるのを黙って見ているなんて無理だ。
杜子春が叫んでしまったのは、仙人になれなかったけど、人間として正しかったと思う。
仙人は何でもできてすごいかもしれないけど、家族を大切に思う気持ちの方がもっと大切だ。
私も家族のことが大好きで、みんなが元気でいてくれることが一番幸せだ。
お母さんが風邪をひいたときは、私がおかゆを作ってあげた。
妹が転んで泣いているときは、すぐに助けてあげる。
それが当たり前だと思っていたけど、杜子春の話を読んで、この気持ちがとても大切なものだと分かった。
『杜子春』を読んで、私は本当の幸せについて考えることができた。
お金や特別な力よりも、家族や友達を思いやる気持ちの方が大切だ。
これからも周りの人を大切にして、優しい心を忘れずに生きていきたい。
『杜子春』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】人間らしく生きることの美しさ
私は芥川龍之介の『杜子春』を読み、真の幸福とは何か、そして人間らしく生きることの意味について深く考えさせられた。
この物語は、物質的な豊かさに翻弄される若者が、最終的に人間本来の温かさを取り戻す成長の物語である。
杜子春は仙人・鉄冠子から黄金を与えられ、一夜にして大金持ちになる。
しかし彼は贅沢三昧の生活を送り、あっという間に財産を使い果たしてしまう。
この繰り返しを通じて私が感じたのは、お金というものの危険性だった。
確かにお金があれば欲しいものが買えるし、便利な生活ができる。
でも杜子春のように、お金があることで本当に大切なものを見失ってしまう可能性もあるのだ。
私の周りでも、新しいゲームやスマートフォンを持っている友達に人が集まることがある。
でもその友達がお金に困ったときに、果たして同じように接してくれる人がどれだけいるだろうか。
杜子春の体験を通じて、表面的な人間関係の怖さを感じた。
物語の後半で、杜子春は人間に失望し、仙人になる道を選ぶ。
峨眉山での修行は想像を絶する過酷さだった。
虎や大蛇に襲われても、神に殺されても、地獄で責められても、一言も発してはいけない。
この修行の意味は、人間的な感情を完全に捨て去ることだったのだろう。
しかし私は、この修行に疑問を感じた。
感情を持たない存在になることが、本当に素晴らしいことなのだろうか。
杜子春が最後に「お母さん」と叫んだ場面で、私の疑問は確信に変わった。
地獄で鞭打たれる両親の姿を見て、杜子春は修行の掟を破ってしまう。
でも私はこの瞬間、杜子春が最も美しく輝いて見えた。
どんなに厳しい修行であっても、親を思う気持ちだけは捨てられなかった。
この人間らしい愛情こそが、仙人の力よりもずっと尊いものだと感じたのだ。
私にも似たような体験がある。
部活動で厳しい練習に耐えているとき、疲れて諦めそうになることがある。
でも家族が応援してくれていると思うと、もう少し頑張ろうという気持ちになれる。
家族への愛情が、私に力を与えてくれるのだ。
杜子春が感じたような、人を思う気持ちの強さを私も体験している。
鉄冠子が杜子春の行動を責めるどころか、むしろ喜んだことも印象深い。
仙人は最初から、杜子春が人間らしい心を失わないことを願っていたのかもしれない。
真の成長とは、感情を捨てることではなく、愛情深い心を育てることなのだ。
最終的に杜子春が手に入れたのは、山の麓にある質素な家と畑だった。
大金持ちだったときや仙人を目指していたときと比べれば、とても地味な生活だ。
でも私は、これこそが杜子春にとって最高の幸せだと思う。
誰かを愛し、誰かに愛される。
困っている人がいれば手を差し伸べる。
そんな当たり前の人間らしい生活が、実は最も尊いものなのだ。
『杜子春』を読んで、私は自分の生き方を見つめ直すことができた。
目立つ成果や特別な能力に憧れることもあるけれど、身近な人との絆を大切にすることの方がずっと重要だ。
これからも人間らしい温かい心を持ち続けて、周りの人たちと支え合いながら生きていきたい。
『杜子春』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】人間的な弱さの中にある真の強さ
私は芥川龍之介の『杜子春』を読み、人間の本質とは何か、そして真の強さとは何かについて深く考える機会を得た。
この作品は表面的には中国の古典を翻案した童話のように見えるが、その奥には現代を生きる私たちにも通じる普遍的なテーマが隠されている。
物語の前半で描かれる杜子春の放蕩ぶりは、一見すると単なる若者の愚かさのように思える。
仙人から与えられた莫大な黄金を、彼は何の計画性もなく湯水のように使い果たしてしまう。
しかしこの部分を読みながら、私は現代社会における物質主義の危険性を強く感じた。
私たちの社会でも「お金があれば幸せになれる」という価値観が根強く存在する。
確かに経済的な安定は生活の基盤として重要だが、それが人生の最終目標になってしまうと、杜子春のように本質的な幸福を見失ってしまうのではないだろうか。
杜子春が三度目に財産を失った後、彼の心境に大きな変化が訪れる。
金持ちのときは周囲からちやほやされ、貧乏になると手のひらを返したように冷たくあしらわれる体験を通じて、彼は人間関係の表面性に気づく。
この部分で私が最も印象深く感じたのは、杜子春の人間不信が決して一方的な怒りではなく、深い失望から生まれていることだった。
彼は人間を憎んでいるのではなく、人間の弱さや醜さに心を痛めているのだ。
私自身も似たような経験がある。
中学時代、成績が良かった時期は友人たちが頻繁に話しかけてきたが、一時期成績が落ちたときには明らかに距離を置かれた。
その時の寂しさや虚しさは、杜子春が感じたものと通じるものがあったのかもしれない。
しかし私は杜子春のように人間を見限ることはできなかった。
なぜなら同じ人間の中にも、損得勘定抜きで関わってくれる人たちがいることを知っていたからだ。
物語の中核を占める峨眉山での修行場面は、この作品の最も重要な部分である。
杜子春は鉄冠子から「何があっても口をきいてはならない」という厳しい掟を課せられる。
虎や大蛇の襲撃、神将による拷問、地獄での責め苦という試練の数々を、彼は見事に耐え抜く。
この描写を読みながら、私は人間の精神力の可能性について考えた。
極限状況において沈黙を貫く杜子春の姿は、確かに超人的な強さを感じさせる。
しかし同時に、感情を完全に封印した状態が果たして人間として望ましいものなのかという疑問も湧いた。
物語のクライマックスで、杜子春は畜生道に落ちた両親が鬼たちに打たれる姿を目にする。
そして母親の苦しみに耐えきれず、ついに「お母さん」と叫んでしまう。
この瞬間、私は深い感動を覚えた。
杜子春のこの行動は、修行という観点からは明らかな「失敗」である。
しかし人間としての観点から見れば、これほど美しい行為はない。
親への愛情、他者への共感、苦しむ者を見過ごせない心の優しさ。
これらの感情こそが人間を人間たらしめる最も尊い要素なのではないだろうか。
私は部活動で厳しい指導を受けているとき、感情を押し殺して耐えることの大切さを学んだ。
しかし同時に、仲間が困っているときには自分のことを後回しにしてでも助けようとする気持ちも大切だと感じている。
杜子春の「失敗」は、まさにこの人間らしい温かさを表現したものだった。
鉄冠子が杜子春の行動を咎めるのではなく、むしろ喜んだことも非常に意味深い。
真の師というものは、弟子が完璧な修行者になることよりも、人間として成長することを願うものなのかもしれない。
感情を捨てて仙人になることよりも、愛情深い人間として生きることの方が価値があるという、鉄冠子の深い洞察を感じた。
物語の結末で、杜子春が手に入れたのは泰山の麓にある小さな家と畑だけだった。
大金持ちだった頃の豪華な生活や、仙人になるという壮大な夢と比べれば、極めて質素な暮らしだ。
しかし私は、これこそが杜子春にとって真の幸福だと確信している。
人間らしい感情を大切にし、身の丈に合った生活を送り、必要な分だけを得て満足する。
このような生き方にこそ、現代の私たちが学ぶべき知恵があるのではないだろうか。
私たちは往々にして、より多くのものを求め、より高い地位を目指そうとする。
しかし『杜子春』が教えてくれるのは、人間的な心の温かさを失わない範囲での成長や成功こそが真に価値のあるものだということだ。
この作品を読んで、私は自分の価値観を見直すことができた。
確かに勉強や将来への準備は大切だが、それ以上に周りの人への思いやりや、困っている人を見過ごせない心を育てることが重要だと感じている。
杜子春のように「お母さん」と叫べる人間でありたい。
完璧ではないかもしれないが、愛情深く、人間らしい温かさを持った人として生きていきたいと思う。
『杜子春』は、人間の弱さを否定するのではなく、その弱さの中にある美しさを教えてくれる珠玉の作品である。
振り返り
今回は『杜子春』の読書感想文について、書き方のコツから具体的な例文まで詳しく解説しました。
この記事を読んで、皆さんにも必ず素晴らしい感想文が書けるという自信を持ってもらえたでしょうか。
大切なのは「自分がどう感じたか」を正直に表現することです。
正解や不正解を気にせず、杜子春の物語を通じてあなたが学んだことや気づいたことを大切にしてください。
きっと読む人の心に響く、あなたらしい感想文が完成するはずですよ。
※『杜子春』のあらすじはこちらで簡単に短くご紹介しています。




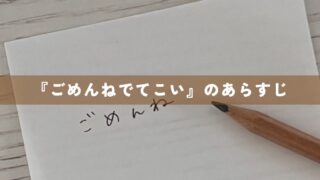


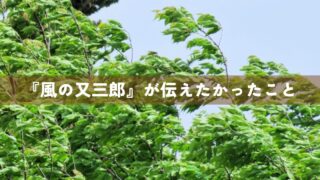



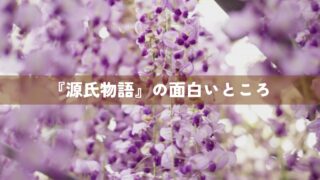
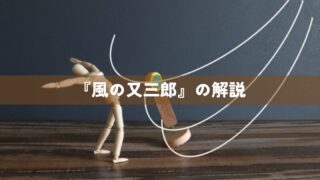
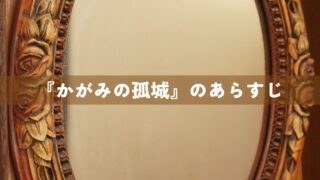


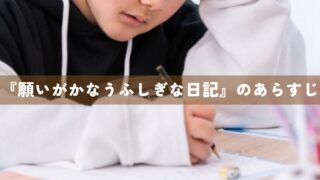

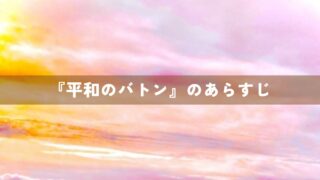

コメント