中高生のみなさんに『平和のバトン』の読書感想文の書き方をご紹介します。
弓狩匡純さんが著者を務めたこの作品は、広島市立基町高校の生徒たちが被爆者の証言を聞き取り、それを油絵として描く「次世代と描く原爆の絵」プロジェクトを中心に描かれたノンフィクション作品ですね。
広島平和記念資料館の協力のもと、2019年にくもん出版から刊行されたこの本は、単なる戦争の記録ではなく、平和への願いを次世代に繋ぐ「バトン」としての意味を込めた深い作品になっています。
僕は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいますが、『平和のバトン』は特に印象に残った一冊でした。
今回は読書感想文の書き方や例文、そして効果的な書き出しやテンプレートまで、中学生・高校生の皆さんがコピペに頼らず自分の言葉で書けるよう丁寧にサポートしていきますよ。
この記事を読み終えた頃には、きっと素晴らしい感想文が書けるはずです。
『平和のバトン』の読書感想文で触れたい3つの要点
『平和のバトン』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントが3つあります。
それらの要点について「どう感じたか」をメモしながら読み進めることで、感想文の核となる部分が自然と見えてきますよ。
メモの取り方としては、読書中に気になった場面や印象に残った言葉があったら、その都度「なぜそう思ったのか」「自分だったらどうするか」といった疑問や感想をスマホのメモ帳や紙に書き留めておくことをおすすめします。
「どう感じたか」が感想文において重要な理由は、単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身の心の動きや価値観の変化を表現することが読書感想文の本質だからです。
まずは以下の3つの要点を確認してみましょう。
- 被爆体験を次世代に継承する意味と責任
- 異なる立場の人々との対話がもたらす理解と和解
- 平和を築くために自分ができる具体的な行動
それでは、それぞれの要点について詳しく解説していきますね。
被爆体験を次世代に継承する意味と責任
『平和のバトン』の最も重要なテーマは、戦争や原爆の記憶を風化させることなく、次の世代へと受け継いでいくことの意味と責任です。
作品の中で高校生たちが被爆者の証言を聞き、それを絵として表現する過程は、まさに「記憶の継承」そのものを描いています。
被爆者の方々が高齢になり、直接体験を語れる人が少なくなっている現実の中で、若い世代がその記憶を受け取り、自分なりの方法で表現し、さらに次へと繋いでいく。
この連鎖こそが「平和のバトン」なのですね。
感想文を書く際は、この継承の重要性について、あなた自身がどのように感じたかを具体的に書いてみてください。
例えば「自分も何らかの形で平和のバトンを受け取る責任があると感じた」「過去の出来事を自分事として捉えることの大切さを学んだ」といった内容です。
また、現代に生きる私たちが平和を当たり前のものとして享受している一方で、その平和は多くの犠牲の上に成り立っていることを忘れてはならない、という気づきについても触れると良いでしょう。
異なる立場の人々との対話がもたらす理解と和解
『平和のバトン』では、戦争という極限状態でも人間同士の理解と和解が可能であることが描かれています。
被爆者の方々の証言の中には、敵国の人々との間に生まれた友情や、文化や立場を超えた心の交流のエピソードが含まれています。
これらの体験談は、戦争の原因となる「無理解」や「偏見」を乗り越えるための「対話の力」の重要性を教えてくれます。
現代社会においても、私たちは様々な場面で「異なる価値観や文化を持つ人々」と接する機会があります。
SNSでの情報の断片化や、自分と似た意見の人とだけ交流するフィルターバブル現象が問題となっている今だからこそ、この作品が示す「対話による理解」のメッセージは特に重要です。
感想文では、この点について「自分も普段から異なる意見の人と対話する姿勢を大切にしたい」「相手の立場に立って考えることの重要性を学んだ」といった個人的な気づきを書いてみてください。
また、学校生活や日常生活の中で実際に体験した「理解し合えた瞬間」があれば、それと結びつけて書くとより説得力のある感想文になりますよ。
平和を築くために自分ができる具体的な行動
『平和のバトン』を読んだ後に最も重要なのは、「では、自分は何ができるのか」という問いに向き合うことです。
平和は抽象的な理想ではなく、私たち一人ひとりの日々の行動によって築かれるものだということを、この作品は教えてくれます。
大きな社会運動を起こすことだけが平和への貢献ではありません。
身近な場所から始められる小さな行動こそが、やがて大きな変化を生み出すのです。
例えば、歴史を単なる暗記科目として捉えるのではなく、そこに生きた人々の想いを想像しながら学ぶこと。
差別的な言葉を使わないよう心がけること。
メディアやSNSの情報を鵜呑みにせず、多角的に物事を考える習慣をつけること。
異なる文化や価値観を持つ人々に対して、偏見を持たずに接すること。
感想文では、これらの中からあなたが特に重要だと感じた行動について、具体的に「なぜそう思うのか」「実際にどのように取り組みたいか」を書いてみてください。
未来への希望と決意を込めて感想文を締めくくることで、読み手にも強い印象を与えることができるでしょう。
※『平和のバトン』のあらすじや内容の要約はこちらにまとめています。
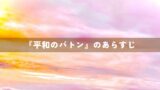
『平和のバトン』の読書感想文のテンプレート
ここからは『平和のバトン』の読書感想文を効率よく書けるテンプレートをご紹介します。
先ほど解説した3つの要点がしっかりと含まれるような構成になっているので、空欄を埋めていくだけで質の高い感想文が完成しますよ。
各ステップごとに進めていきましょう。
ステップ1:導入部分(書き出し)
まずは読み手の関心を引く書き出しから始めます。
以下の空欄を埋めて、あなたなりの導入文を作ってみてください。
「『平和のバトン』というタイトルを見たとき、私は【 】と思った。しかし実際に読んでみると、それは【 】であることがわかった。この本は【 】について深く考えさせられる作品である。」
例:「戦争の悲惨さを描いた本だろう」→「単なる過去の記録ではなく、現代を生きる私たちへのメッセージ」→「平和の尊さと次世代への責任」
ステップ2:印象に残ったエピソードの紹介
次に、あなたが最も印象に残ったエピソードを1つ選んで紹介します。
「私が最も心を動かされたのは【 】のエピソードである。【具体的な内容を2〜3文で説明】。このエピソードから私は【 】ということを学んだ。」
重要なのは、単なるあらすじの紹介ではなく、「なぜそのエピソードに心を動かされたのか」という理由も含めることです。
ステップ3:継承の意味について
被爆体験を次世代に継承することの意味について、あなたの考えを述べます。
「この作品を通して、【 】を次の世代に伝えることの重要性を痛感した。なぜなら【 】からである。現代に生きる私たちは【 】という責任があると感じた。」
例:「戦争の記憶」→「風化させてしまえば同じ過ちを繰り返す可能性があるから」→「平和のバトンを受け取り、次へと繋ぐ」
ステップ4:対話と理解について
異なる立場の人々との対話がもたらす理解について触れます。
「作品の中で描かれた【 】の場面は、対話の持つ力を改めて実感させてくれた。私は普段【 】という経験があるが、この本を読んで【 】の大切さを学んだ。」
自分の実体験と結びつけることで、より説得力のある文章になります。
ステップ5:自分にできる行動
最後に、平和を築くために自分ができる具体的な行動について述べて締めくくります。
「『平和のバトン』を読んで、私は【 】ということを決意した。具体的には【 】や【 】といった行動から始めたいと思う。この本が教えてくれた【 】を胸に、未来の平和に貢献していきたい。」
例:「身近な場所から平和への貢献を始める」→「差別的な言葉を使わない」「多角的に物事を考える習慣をつける」→「平和のバトンを受け継ぐ責任」
『平和のバトン』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】受け継がれる平和への願い
『平和のバトン』というタイトルを最初に見たとき、私は何となく重い内容の本なのだろうと思った。戦争や原爆について書かれた本は、どうしても暗い気持ちになってしまうイメージがあったからだ。しかし実際に読んでみると、単なる悲しい物語ではなく、未来への希望に満ちた作品だということがわかった。
この本で最も印象に残ったのは、広島市立基町高校の生徒たちが被爆者の方の証言を聞いて、それを油絵として描く活動である。高校生たちは最初、戦争のことをよく知らなかった。でも、被爆者の方と何度も話をし、当時の服装や道具について調べているうちに、だんだんとその時代のことが理解できるようになっていく。この過程を読んでいて、私は学ぶということの本当の意味を考えさせられた。
特に心に残ったのは、「ゲートル」という戦時中に使われた足の布について調べる場面だった。高校生たちはそれが何なのかわからず、図書館で調べたり、実際に見つけて触ってみたりする。そうやって一つ一つのことを理解していくことで、被爆者の方の体験がより鮮明に見えてくるのだ。私はこれまで歴史の勉強を暗記科目だと思っていたが、この本を読んで考えが変わった。歴史とは、実際にそこに生きていた人々の生活や思いを知ることなのだと気づいたのである。
また、この本を通して、戦争の記憶を次の世代に伝えることの大切さも学んだ。被爆者の方々は高齢になり、だんだんと少なくなっている。もしこのまま何もしなければ、戦争の悲惨さや平和の尊さを直接知る人がいなくなってしまう。だからこそ、高校生たちが絵を描いて記録として残すことには、とても重要な意味があるのだ。
私は今まで平和というものを当たり前のものだと思っていた。毎日学校に行って、友達と話をして、好きなことをして過ごせるのは普通のことだと考えていた。しかし、この本を読んで、そんな日常がどれほど貴重なものかを実感した。戦時中の人々は、私たちが当たり前だと思っている自由や安全を奪われていたのだ。そして、その経験をした人々が、同じことを繰り返してはいけないと必死に伝えようとしている。
この「平和のバトン」を私たちも受け取る責任があると感じた。それは大きなことをすることではなく、まずは身近なところから始められることだと思う。例えば、友達と意見が合わないときに、相手の話をしっかり聞いてから自分の考えを伝えること。テレビやインターネットで見た情報を鵜呑みにせず、本当にそうなのかを自分で考えてみること。そして、戦争や平和について、もっと深く学んでいくことである。
『平和のバトン』は、過去の記憶を大切にしながら、未来への希望を語る作品だった。私はこの本を読んで、平和は誰かが作ってくれるものではなく、私たち一人一人が築いていくものなのだということを学んだ。被爆者の方々から高校生へ、そして高校生から私たちへと受け継がれる「平和のバトン」を、私もしっかりと受け取り、次の世代へと繋げていきたいと思う。
『平和のバトン』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】記憶を紡ぎ、未来を築く責任
『平和のバトン』を手に取った時、私は漠然と戦争の悲惨さを描いた作品なのだろうと想像していた。しかし、ページをめくるにつれて、これが単なる過去の記録ではなく、現在を生きる私たちに向けられた強烈なメッセージであることがわかった。弓狩匡純氏が描いたこの作品は、被爆体験という重い記憶を、希望という光に変える力を持っている。
最も印象深かったのは、広島市立基町高校の生徒たちが被爆者の証言を油絵として表現する「次世代と描く原爆の絵」プロジェクトである。彼らは最初、戦争について具体的なイメージを持っていなかった。しかし、被爆者の方々と対話を重ね、当時の服装や道具について詳細に調べていく過程で、その時代の現実が次第に見えてくる。特に印象に残ったのは、「ゲートル」という戦時中の装身具について調べる場面だった。高校生たちは図書館で資料を探し、実物を手に取り、その意味を理解しようとする。この一見些細な作業が、実は被爆者の記憶を正確に受け継ぐための重要なプロセスなのである。
私はこの場面を読んで、学習の本質について深く考えさせられた。これまで私は歴史を、教科書に書かれた出来事を暗記する科目だと捉えていた。しかし、本当の学習とは、そこに生きた人々の感情や体験を想像し、自分なりに理解することなのだと気づいた。高校生たちが証言者と向き合う姿勢は、まさにそのような学習の姿勢を体現している。
さらに深く心を動かされたのは、この作品が描く「継承」の意味である。被爆者の方々は、自分たちの体験が風化することへの強い危機感を抱いている。直接体験を語れる人が少なくなっている今、その記憶をどのように次世代に伝えるかは切実な問題だ。高校生たちの絵画制作は、単なる記録保存ではない。それは記憶を自分なりに咀嚼し、新たな表現として組み立てるクリエイティブな行為だと思う。この過程こそが「平和のバトン」を受け取るということなのだろう。
私は現在、戦争を直接経験することなく平和な日常を送っている。毎日学校に行き、友人と語り合い、将来について夢を抱くことができる。しかし、この本を読んで、そんな当たり前の日常がどれほど貴重なものかを痛感した。戦時中の人々は、私たちが当然だと思っている自由や安全を奪われていた。そして、その苦しみを経験した人々が、同じ悲劇を繰り返してはならないと必死に訴えている。
この作品のもう一つの重要なテーマは、異なる立場の人々との対話の力である。被爆者の証言の中には、敵国の人々との間に生まれた友情や理解のエピソードが含まれている。戦争という極限状況でさえ、人間同士の心の交流は可能だったのである。このことは、現代社会にも重要な示唆を与える。私たちは今、SNSやメディアの影響で、自分と似た考えの人とだけ交流し、異なる意見を持つ人を排除しがちである。しかし、真の平和は、違いを認め合い、対話を通じて理解を深めることから生まれるのだ。
私自身、日常生活の中で意見の合わない友人と議論になることがある。以前は相手を論破しようとしていたが、この本を読んでから、まず相手の話を聞き、その背景にある思いを理解しようと努めるようになった。完全に理解し合えなくても、相手を尊重する姿勢を持つことで、関係が改善されることを実感している。
では、私たちは「平和のバトン」をどのように受け取り、次へと繋げていけばよいのだろうか。それは決して大きな社会運動を起こすことだけではない。まずは身近なところから始めることが重要だと思う。例えば、歴史を学ぶ際に、単なる暗記ではなく、そこに生きた人々の思いを想像すること。メディアやSNSの情報を鵜呑みにせず、複数の視点から物事を考える習慣をつけること。異なる文化や価値観を持つ人に対して偏見を持たず、対話の機会を大切にすること。そして、差別的な言葉を使わず、すべての人の尊厳を認めることである。
私は将来、教育の分野で働きたいと考えている。この本を読んで、教育の持つ力の大きさを改めて実感した。正しい知識を伝えるだけでなく、生徒たちが自分で考え、感じ、行動する力を育てることが重要だと感じる。『平和のバトン』で描かれた高校生たちのように、過去の記憶と向き合い、それを自分なりの方法で表現し、未来につなげていく。そんな教育に携わりたいと思う。
この作品は、平和は誰かが作ってくれるものではなく、私たち一人一人が築いていくものだということを教えてくれた。被爆者の方々から高校生へ、そして高校生から私たちへと受け継がれる「平和のバトン」。私はこのバトンをしっかりと受け取り、自分なりの方法で次の世代に繋げていく責任があることを深く感じている。この本との出会いは、私の人生観を大きく変える貴重な体験となった。
振り返り
今回は『平和のバトン』の読書感想文の書き方について、3つの重要な要点からテンプレート、そして具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した内容を参考にすれば、きっとあなたも心に響く素晴らしい読書感想文が書けるはずです。
重要なのは、単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身がこの作品を通してどのようなことを感じ、学び、そして今後どのように行動していきたいかを具体的に表現することです。
『平和のバトン』は、過去の記憶を現在の私たちが受け取り、未来へと繋げていくことの大切さを教えてくれる作品です。
あなたの感想文もまた、この「平和のバトン」の一部となることでしょう。
自分の言葉で、自分の思いを込めて、ぜひ心のこもった感想文を書いてみてくださいね。





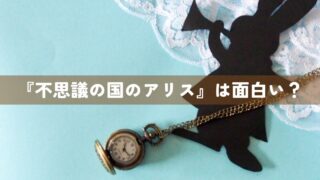
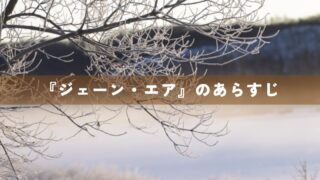

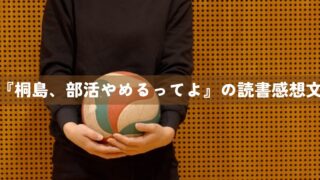






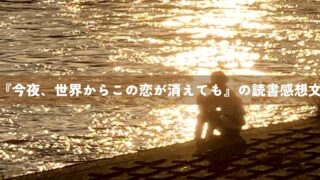


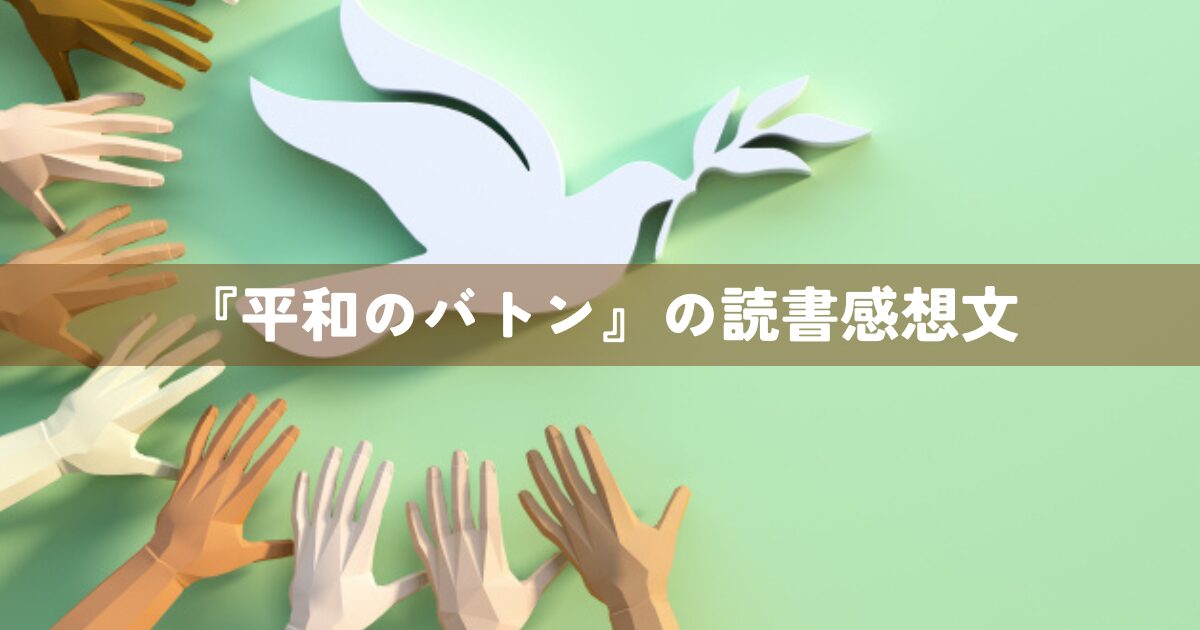
コメント