『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文を書く小学生、いますか?
この絵本は田村孝介さんによる写真科学絵本で、2024年の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にもなっている話題の作品ですよね。
カカオの実から板チョコレートができるまでの工程を豊富な写真で紹介し、食べ物への感謝や社会のつながりに目を向けさせる内容になっています。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいますが、この絵本は小学生のみなさんにとって非常に学びの多い一冊だと感じました。
この記事では『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文の書き方を丁寧に解説していきます。
書き出しから題名まで、コピペではない自分だけの感想文を完成させるためのテンプレートや例文もご用意しましたよ。
『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文に書くべき3つのポイント
『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文を書くときに、絶対に押さえておきたい重要なポイントが3つあります。
- チョコレートができるまでの工程の理解
- 普段何気なく食べている食品の背景を知る大切さ
- 興味をもったことや疑問点、今後の学びへの意欲
これらのポイントを中心に感想文を組み立てることで、内容の濃い読書感想文が書けるでしょう。
読みながら「どう感じたか」をメモしておくと、後で感想文を書くときに役立ちますよ。
それでは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
チョコレートができるまでの工程の理解
まず最初に書くべきなのは、カカオの木の実からチョコレートになるまでの工程について学んだことです。
この絵本を読むまで、みなさんはチョコレートがどうやってできるのか知っていましたか?
カカオ豆の取り出し、発酵、乾燥、輸送、そして工場での焙煎や混ぜ合わせなど、たくさんの段階があることに驚いたのではないでしょうか。
特に発酵という工程は、多くの小学生にとって初めて知ることだと思います。
カカオの種を時間をかけて発酵させることで、あのチョコレート特有のおいしい香りや味ができあがるんですね。
感想文では、どの工程が一番印象に残ったか、なぜそう思ったのかを具体的に書いてみましょう。
豊富な写真を見て感じたことや、工程の複雑さに対する驚きなども書けるでしょう。
普段何気なく食べている食品の背景を知る大切さ
二つ目のポイントは、食べ物に対する感謝の気持ちについてです。
普段は何も考えずに食べているチョコレートも、実は多くの人の努力や自然の恵みがあって成り立っていることを学びましたよね。
遠い国からカカオの種や実が運ばれてくることや、そこで働く人たちの苦労も絵本で知ることができました。
この本を読んで、食べ物に対する見方が変わったのではないでしょうか。
「ありがとう」という気持ちが生まれたり、食べ物を大切にしたいと思ったりしたかもしれません。
感想文では、読む前と読んだ後で食べ物に対する気持ちがどう変わったかを書いてみてください。
また、チョコレート以外の食べ物についても同じようなことが言えることに気づいたなら、それも書けるでしょう。
興味をもったことや疑問点、今後の学びへの意欲
三つ目のポイントは、この本を読んで新たに興味をもったことや、これから学びたいことについてです。
「他の食べ物もどうやってできるのか知りたい」と思った人も多いでしょう。
パンやお米、野菜や果物など、身近な食べ物の作られ方にも興味が湧いたかもしれませんね。
また、フェアトレードという言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。
カカオを作っている国の人たちが正当な対価を受け取れるような取り組みについても関心をもったかもしれません。
感想文では、この本を読んで特に面白いと思ったことや驚いたことを書きましょう。
そして、これから調べてみたいことや学んでみたいことがあれば、それも書いてみてください。
将来の夢や目標につながるようなことがあれば、それも立派な感想になりますよ。
『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文のテンプレート
ここでは『どうやってできるの? チョコレート』の感想文を楽に書けるようにテンプレートをご用意しました。
空欄を埋めるだけで、しっかりとした読書感想文が完成しますよ。
- 【書き出し】この本を読んだきっかけや最初の印象
- 【工程の説明】チョコレートができるまでの工程で印象に残ったこと
- 【感謝の気持ち】食べ物や働く人への感謝について
- 【学びと発見】新しく知ったことや驚いたこと
- 【今後の意欲】これから学びたいことや心がけたいこと
私は『どうやってできるの? チョコレート』という本を読んで、( )ということを知りました。この本を読む前は、( )と思っていました。
チョコレートができるまでには、( )や( )など、たくさんの工程があることがわかりました。特に印象に残ったのは( )という作業です。なぜなら( )からです。
この本を読んで、( )に感謝する気持ちが生まれました。普段何気なく食べているチョコレートも、( )ということがわかったからです。
一番驚いたのは、( )ということでした。また、( )についても初めて知り、興味深く感じました。
これからは( )を心がけたいと思います。また、( )についても調べてみたいです。
『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】チョコレートから学んだ大切なこと
私は『どうやってできるの? チョコレート』という本を読んで、チョコレートができるまでにたくさんの工程と人の努力があることを知った。
この本を読む前は、チョコレートがどこから来てどうやって作られているのかあまり考えたことがなかった。
チョコレートができるまでには、カカオ豆の取り出し、発酵、乾燥、輸送、そして工場での焙煎や混ぜ合わせなど、本当にたくさんの段階があることがわかった。
特に印象に残ったのは発酵という作業だった。
カカオの種を時間をかけて発酵させることで、あのチョコレート特有のおいしい香りや味ができあがるということに驚いた。
発酵というのはパンやお酒を作るときにも使われる方法で、食べ物作りの奥深さを感じることができた。
また、豊富な写真を見ながらカカオの実がどんな形をしているのか、工場でどのような機械を使って作業しているのかもよくわかった。
この本を読んで、普段何気なく食べているチョコレートにも多くの人の努力や自然の恵みがあることに感謝する気持ちが生まれた。
遠い国でカカオを育てている人たちや、輸送に関わる人たち、工場で働く人たちなど、たくさんの人の手を経てチョコレートが私たちの手に届いているということがよくわかった。
一番驚いたのは、カカオの実から種を取り出す作業から始まり、最終的に板チョコレートになるまでに何か月もかかるということだった。
また、カカオが主に赤道近くの暖かい国で育てられているということも初めて知り、地理の勉強にもなった。
これからはチョコレートを食べるときに「ありがとう」という気持ちを忘れずにいたいと思った。
また、パンやお米、野菜や果物など、他の食べ物がどのようにして作られているのかについても調べてみたいと思った。
食べ物を大切にし、作ってくれる人たちに感謝する気持ちを持ち続けていきたいと思う。
『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文の例文(1200字の小学生向け)
【題名】チョコレートが教えてくれた感謝の気持ち
『どうやってできるの? チョコレート』を読んで、チョコレートができるまでの長い道のりと、多くの人々の努力について深く考えることができた。
この本を読む前は、チョコレートはコンビニやスーパーで簡単に買えて、甘くておいしいお菓子という認識しかなかった。しかし、この本を読んで、その考えが大きく変わった。
チョコレートができるまでには、カカオ豆の取り出し、発酵、乾燥、輸送、そして工場での焙煎や選別、すりつぶし、砂糖などとの混合など、本当に多くの工程があることがわかった。
特に印象に残ったのは発酵という作業だった。カカオの種をバナナの葉で包んで数日間発酵させることで、あのチョコレート特有の香りや味ができあがるということに驚いた。発酵は微生物の力を借りて行われる自然の作業で、人間の知恵と自然の力が合わさってチョコレートが生まれることを学んだ。
また、カカオの実から種を取り出す作業も興味深かった。一つの実にたくさんの種が入っていて、それを丁寧に取り出していく様子が写真で紹介されていた。この作業は主に手作業で行われ、多くの人の手間がかかっていることがよくわかった。
工場での作業も複雑で、焙煎では温度や時間を正確に管理する必要があることを知った。焙煎によってカカオ豆の味や香りが決まるため、とても重要な工程だということがわかった。その後、すりつぶしたり、砂糖やミルクと混ぜたりする作業を経て、ようやく私たちが知っているチョコレートになるのだった。
この本を読んで、普段何気なく食べているチョコレートに感謝の気持ちが生まれた。カカオを育てている国の農家から始まり、輸送に関わる人、工場で働く人、お店で売る人まで、本当に多くの人の努力があってチョコレートは私たちの手に届いているのだとわかった。
特に、カカオを育てている国の多くは発展途上国で、そこで働く人々の苦労も想像できた。私たちがおいしくチョコレートを食べられるのは、そうした人たちの頑張りがあるからだということを忘れてはいけないと思った。
一番驚いたのは、カカオの実から最終的に板チョコレートになるまでに数か月もかかることだった。また、カカオの木は赤道近くの暖かい地域でしか育たないことも初めて知った。ガーナやコートジボワール、エクアドルなど、地図で場所を確認しながら読むことで、地理の勉強にもなった。
この本には写真が多く使われ、実際の作業の様子がよくわかったのも良かった。文字だけでは理解しにくいことも、写真のおかげで具体的にイメージできた。
これからはチョコレートを食べるときに「ありがとう」という気持ちを忘れずにいたい。また、チョコレートだけでなく、パンや米、野菜や果物など、他の食べ物についてもどのように作られているのか調べてみたい。食べ物には必ず作ってくれる人がいて、自然の恵みがあることを忘れずに、感謝して大切に食べていきたい。
将来、もし食べ物に関わる仕事に就くことがあれば、この本で学んだことを生かし、みんなにおいしい食べ物を届けられるように頑張りたいと思う。
振り返り
今回は『どうやってできるの? チョコレート』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
チョコレートができるまでの工程、食べ物への感謝、そして今後の学びへの意欲という3つのポイントを押さえることで、内容の濃い感想文が書けるはずです。
テンプレートや例文も参考にしながら、みなさん自身の言葉で感想を表現してみてくださいね。
きっと素晴らしい読書感想文が完成するでしょう。頑張ってください!
■参考サイト:どうやってできるの? チョコレート - 写真/田村孝介 立協 卓 監修・取材協力/ダンデライオン・ チョコレート・ジャパン株式会社 - ひさかたチャイルド



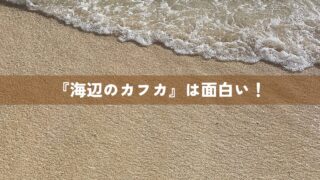




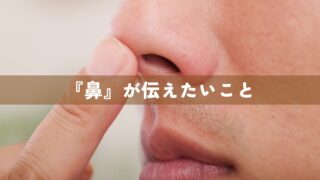

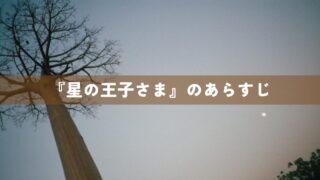
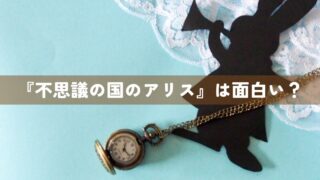

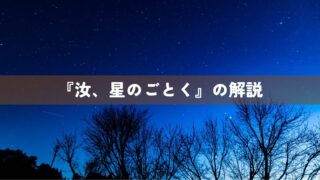


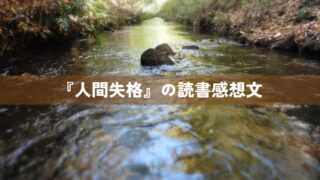


コメント