『人がつくった川・荒川』のあらすじを簡単に短く、そして詳しく紹介していきますね。
この作品は長谷川敦さんが2022年に発表したノンフィクション作品で、第69回青少年読書感想文全国コンクール中学校の部の課題図書にも選ばれた注目の一冊。
荒川の歴史と治水技術、そして首都圏の発展との関わりを描いたこの作品は、環境問題や防災について考えるきっかけも与えてくれる貴重な教材です。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんにとって役立つよう、あらすじから登場人物、さらには類似作品まで丁寧に解説していきます。
それでは、さっそく内容を見ていきましょう。
長谷川敦『人がつくった川・荒川』のあらすじを簡単に短く
長谷川敦『人がつくった川・荒川』のあらすじを詳しく
『人がつくった川・荒川』のあらすじを理解するための用語解説
『人がつくった川・荒川』に登場する専門用語をわかりやすく解説しますね。
歴史や治水技術を理解するために重要な用語をまとめました。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 荒川西遷事業 | 江戸時代初期に行われた 荒川の流路を南に大きく変える大規模な土木工事。 洪水被害の軽減と土地の有効利用を目的とした 歴史的な河川改修。 |
| 荒川放水路 | 荒川の洪水被害を防ぐために 明治時代以降に建設された人工河川。 大規模な放水路で その完成により首都圏の安全が大きく向上した。 |
| 治水 | 洪水を防ぎ、水害を軽減して 人々の生活や財産を守るための技術や対策の総称。 |
| 流域 | 川や河川の水が集まる範囲の土地。 荒川流域には埼玉県や東京都の広範囲が含まれ 約1000万人が生活している。 |
| 氾濫 | 川の水が堤防などの制限を越えて 周囲の土地にあふれ出ること。 過去の荒川では氾濫被害が頻発した。 |
これらの用語を押さえておくと、作品の内容がより深く理解できるはずです。
『人がつくった川・荒川』を読んだ感想
この本を読んで、まず驚いたのは荒川が完全に「人工の川」だったということ。
私たちが普段目にしている荒川の流れは、実は江戸時代から何度も人の手で変えられてきた結果なんですね。
特に印象に残ったのは、青山士(あおやま・あきら)という土木技師の話でした。
パナマ運河建設に携わった経験を持つ彼が、荒川放水路の設計・施工で中心的役割を果たしたという事実は、まさに「歴史が動いた瞬間」を感じさせる内容。
この放水路が100年間一度も決壊していないという事実も、技術者たちの情熱と技術力の高さを物語っていて、本当にすごいと思いました。
一方で、川の流れを変えることで恩恵を受ける地域がある反面、犠牲になる地域もあるという複雑な現実も描かれていて、単純に「良い話」として終わらないところに深みを感じましたね。
江戸のし尿を肥料として活用する循環システムの話も面白かった。
現代のSDGsにも通じる持続可能な社会システムが、すでに江戸時代に確立されていたなんて、日本人の知恵と工夫には本当に感心させられます。
ただ、正直に言うと、河川工事の技術的な説明については、やや専門的で難しく感じる部分もありました。
中学生の課題図書ということですが、一部の内容は高校生以上でないと理解が難しいかもしれません。
それでも、地図やイラストが効果的に使われていて、視覚的に理解しやすい工夫がされているのは良かったです。
現代の地球温暖化による水害リスクについても触れられていて、過去の歴史から現在、そして未来への課題まで一貫して描かれているのも評価できるポイント。
読み終わった後、普段何気なく見ている川や街並みが、実は多くの人たちの努力と犠牲の上に成り立っているんだということを改めて実感しました。
防災意識を高めるという意味でも、非常に価値のある一冊だと思います。
特に首都圏に住む人たちにとっては、自分たちの生活基盤がどのように作られてきたのかを知る貴重な機会になるはずです。
読書感想文を書く学生さんたちには、環境問題や地域の歴史、人間と自然の関係性など、様々な角度からテーマを見つけられる作品として、ぜひおすすめしたいですね。
※『人がつくった川・荒川』の読書感想文の書き方と例文はこちらで解説しています。

『人がつくった川・荒川』の作品情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式タイトル | 『人がつくった川・荒川 水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする』 |
| 作者 | 長谷川敦 |
| 出版年 | 2022年8月 |
| 出版社 | 旬報社 |
| 受賞歴 | 第69回青少年読書感想文全国コンクール 中学校の部 課題図書 |
| ジャンル | ノンフィクション、河川史・環境書 |
| 主な舞台 | 荒川流域(首都圏) |
| 時代背景 | 江戸時代から現代まで |
| 主なテーマ | 治水技術、人間と自然の関係、防災意識 |
| 物語の特徴 | 歴史的事実に基づく教養書、図解・写真多用 |
| 対象年齢 | 中学生以上の一般向け |
| 青空文庫の収録 | なし |
『人がつくった川・荒川』の主要な登場人物とその簡単な説明
『人がつくった川・荒川』に登場する実在の歴史的人物たちを紹介します。
ノンフィクション作品なので、すべて実在した人物たちです。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| 青山士(あおやま あきら) | 明治時代の土木技師で 日本人として唯一パナマ運河建設に携わった経験を持つ。 荒川放水路の設計・施工で中心的役割を果たした人物。 |
| 伊那忠治(いな ただはる) | 江戸時代に荒川の西遷事業を指揮した人物。 荒川の流れを変える 大規模な土木工事の立役者として知られる。 |
| 徳川家康 | 江戸幕府の初代将軍。 荒川の流路変更事業の背景となった 江戸の都市計画を推進した。 |
その他にも明治から近代にかけて荒川の治水事業に携わった多くの土木技師や関係者が登場しています。
『人がつくった川・荒川』の読了時間の目安
『人がつくった川・荒川』の読みやすさと読了時間をまとめました。
約200ページの作品なので、比較的読みやすい分量です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 総ページ数 | 約200ページ |
| 推定文字数 | 不明 |
| 読了時間の目安 | 約3~4時間 |
図解やイラスト、写真が多用されているので、実際の文字数は少なく感じられるはず。
中学生でも無理なく読み進められる内容構成になっています。
『人がつくった川・荒川』はどんな人向けの作品か?
『人がつくった川・荒川』は特に以下のような人たちにおすすめです。
- 環境問題や防災に関心がある中高生
- 地域の歴史や治水技術について学びたい人
- 読書感想文のテーマを探している学生
逆に、純粋なフィクション作品を求めている人や、エンターテイメント性の高い読み物を期待している人には少し物足りないかもしれません。
ただし、歴史や科学技術に興味がある人なら、年齢に関係なく楽しめる内容になっています。
特に首都圏在住の人にとっては、身近な川の歴史を知る貴重な機会になるでしょう。
あの本が好きなら『人がつくった川・荒川』も好きかも?似ている作品3選
『人がつくった川・荒川』が気に入った皆さんにおすすめの類似作品を紹介しますね。
環境問題や川、防災をテーマにした中高生向けの作品を中心に選びました。
志葉玲『13歳からの環境問題』
地球温暖化や異常気象、生物多様性など現代の環境問題全般を中高生向けに解説したノンフィクション作品。
『人がつくった川・荒川』と同様に、環境と人間の関わりについて深く考えさせられる内容で、災害の背景にある環境要因についても詳しく触れられています。
汐文社『調べてわかる!日本の川(全3巻)』
日本の主要な川の自然と人とのかかわり、歴史、水害のリスクなどをわかりやすく紹介する学習書シリーズ。
荒川以外の川についても知ることができ、『人がつくった川・荒川』で得た知識をさらに深められる内容になっています。
池上彰『そうだったのか!現代史』
直接的には川の話ではありませんが、歴史的事実を現代の視点から分かりやすく解説する手法が『人がつくった川・荒川』と共通しています。
複雑な社会問題を多角的に捉える視点を養うという点で、似た読書体験が得られるはずです。
振り返り
『人がつくった川・荒川』は、単なる河川の歴史書を超えて、人間と自然の関係、そして未来への責任について考えさせてくれる貴重な作品でした。
江戸時代から現代まで続く治水技術の発展と、それに携わった人々の努力を知ることで、私たちの日常生活がいかに多くの先人たちの工夫と犠牲の上に成り立っているかが実感できます。
読書感想文を書く学生の皆さんにとっても、環境問題、地域の歴史、防災意識など様々な角度からテーマを見つけられる作品として、きっと役に立つはずです。



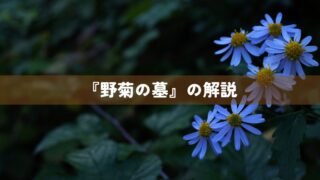









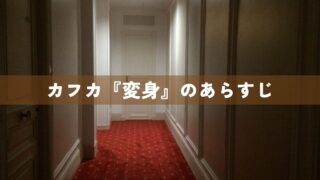
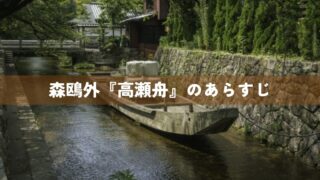

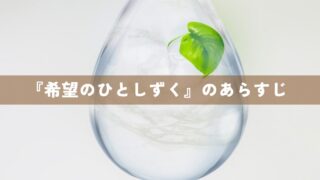
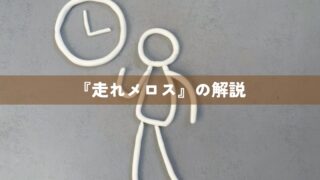

コメント