『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』のあらすじを知りたい方に向けて、簡単に短く、そして詳しくご紹介していきますね。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』は髙津修さん・遠藤義人さん(文)と長崎訓子さん(絵)による、音と耳の仕組みを科学的に解説した絵本です。
2024年青少年読書感想文全国コンクール小学校中学年の部課題図書にも選ばれた注目の作品ですよ。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんに向けて、この絵本の魅力をネタバレなしで丁寧にお伝えします。
この記事を読めば『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の内容がしっかり理解でき、読書感想文を書く際の参考になること間違いなしです。
髙津修・遠藤義人『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』のあらすじを短く簡単に
髙津修・遠藤義人『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』は、音と耳の科学的な仕組みを子どもにもわかりやすく解説した絵本。
まず音の正体について、それが「空気のふるえ(波)」であることを説明している。大きな音は大きくうねり、小さな音は小さく、高い音は細かくふるえるという音波の基本的な性質を、視覚的にも理解しやすいイラストで表現している。
耳の構造についても詳しく解説されており、外耳で音を集め、鼓膜で振動を受け取り、耳小骨で振動を増幅し、内耳の蝸牛で電気信号に変換して聴神経を通じて脳に伝える一連のプロセスが描かれている。
特に興味深いのは、左右の耳に届く音のわずかなズレを脳が感知し、そのズレを手がかりに音の方向や距離を正確に判断するステレオ効果の説明である。この仕組みにより、私たちは音を立体的に感じ取ることができる。
さらに動物たちの聴覚についても触れられており、ネズミが人間には聞き取れない高い声で仲間に合図を送るが、その声が猫にはよく聞こえてしまうという生存競争の実例や、イルカやコウモリの超音波コミュニケーション、クジラやゾウの低周波による遠距離通信など、多様な音の世界が紹介されている。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』のあらすじを理解するための用語解説
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』を理解するために重要な専門用語をまとめました。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 音波 | 空気の振動が波となって伝わるもの。 大きな音は大きな振動波 小さな音は小さな振動波となる。 |
| 鼓膜 | 外耳道の先にある薄い膜。 空気の振動を受けて振動し その振動を中耳に伝える役割をする。 |
| 耳小骨 | 鼓膜からの振動を増幅して内耳に伝える 小さな骨3つの総称。 ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨がある。 |
| ステレオ効果 | 左右の耳で微妙に時間や強さが違う音を捉える能力。 音の出ている方向や距離を判断することができる。 |
| 周波数 | 振動の細かさを表す単位。 高い音は振動が細かく、低い音は振動が粗い。 |
これらの用語を理解しておくと、『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の内容がより深く楽しめるでしょう。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の感想
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』を読んで、まず驚いたのはその科学的な正確さと分かりやすさのバランスでした。
オーディオ専門家である髙津修さんと遠藤義人さんの知識の深さが随所に感じられ、音の波形から耳の複雑な構造まで、本格的な科学知識がこれほどまでにわかりやすく説明されているとは思いませんでした。
特に感動したのは、左右の耳のわずかなズレから音の方向を判断するステレオ効果の説明です。
普段何気なく聞いている音が、実はこんなにも精密な仕組みで処理されているなんて!
私たちの体って本当にすごいんですね。
長崎訓子さんのイラストも素晴らしくて、音の見えない世界が目に見える形で表現されているのには驚かされました。
音波の大きさや細かさを視覚的に表現するなんて、普通では考えつかないアイデアですよね。
子ども向けの絵本でありながら、大人の私も十分に楽しめる内容で、まさに親子で読むのにぴったりの一冊だと感じました。
動物たちの聴覚についての部分も非常に興味深かったです。
ネズミが人間には聞こえない高い声で仲間に合図を送るけれど、それが天敵の猫にはバッチリ聞こえてしまうという事実には、自然界の厳しさと巧妙さを感じました。
イルカやコウモリの超音波、クジラやゾウの低周波コミュニケーションなど、動物たちの多様な音の世界を知ることができて、改めて地球の生き物の多様性に感動しましたね。
ただ、正直に言うと、内容が少し高度すぎるかなと思う部分もありました。
特に耳小骨の働きや内耳の蝸牛の説明あたりは、小学校中学年にはちょっと難しいかもしれません。
でも、そこはイラストがしっかりフォローしてくれているので、絵を見ながらなんとなくイメージをつかむことはできそうです。
私が特に印象に残ったのは、「音の風景」という表現でした。
雨音や鳥のさえずり、街のざわめきなど、日常の音に耳を澄ませることで見えない世界が浮かび上がってくるという発想は、とても詩的で美しいと思いました。
音には目に見えない風景をイメージさせる力があるという言葉に、深く共感しましたね。
読後、実際に目を閉じて周りの音に耳を傾けてみたのですが、普段気づかなかった小さな音がたくさん聞こえてきて、新しい発見がありました。
エアコンの微かな音、遠くを通る車の音、鳥の鳴き声、風の音など、こんなにも豊かな音の世界が私たちの周りに広がっているんですね。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』は、単なる科学絵本を超えて、私たちの感覚を研ぎ澄まし、世界をより深く感じ取る力を育ててくれる素晴らしい作品だと思います。
読書感想文を書く学生さんにとっても、科学的な知識だけでなく、音の世界の美しさや不思議さについて書けるテーマが豊富に詰まった一冊だと感じました。
※『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文の書き方と例文はこちらで解説しています。

『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の作品情報
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の基本的な作品情報をまとめました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作者 | 髙津修、遠藤義人(文) 長崎訓子(絵) |
| 出版年 | 2023年3月 |
| 出版社 | 福音館書店 |
| 受賞歴 | 2024年青少年読書感想文全国コンクール 小学校中学年の部課題図書 |
| ジャンル | 科学絵本、人体・生物、音・耳に関する科学解説 |
| 主な舞台 | 身近な生活環境(音の仕組みの科学的解説) |
| 時代背景 | 現代 |
| 主なテーマ | 音の仕組み、聴覚のメカニズム、動物の聴覚 |
| 物語の特徴 | 豊富なイラストとわかりやすい科学解説 |
| 対象年齢 | 小学校中学年向け(5~6歳以上も親しみやすい) |
| ページ数 | 44ページ |
| 青空文庫の収録 | なし |
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』の登場人物
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』には特定の登場人物は存在しません。
| 登場するもの | 説明 |
|---|---|
| 音 | この絵本の主役となる存在。 空気の振動として様々な形で登場し その仕組みが解説される。 |
| 耳 | 音を感じ取る器官として詳しく解説される。 外耳、中耳、内耳の構造と働きが説明される。 |
| 様々な動物 | ネズミ、猫、イルカ、コウモリ、 クジラ、ゾウなどが登場。 それぞれの聴覚の特徴が紹介される。 |
この作品は科学絵本のため、物語の登場人物ではなく、音と耳の仕組みそのものが主役となっています。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』はどんな人向けの絵本か?
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』がどんな人におすすめかご紹介します。
- 小学校中学年で理科に興味がある子ども
- 科学や自然が好きで、親子で一緒に学びたい家庭
- 読書感想文の課題図書に取り組む必要がある学生
特に2024年の青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選ばれているため、読書感想文を書く予定の小学校中学年の皆さんには最適です。
また、音や耳の仕組みについて専門的でありながらわかりやすい解説が魅力なので、理科が好きな子どもや科学に興味がある大人にもおすすめできますね。
逆に、物語性を求める読者や、もっと簡単な内容を期待している方には少し物足りないかもしれません。
あの本が好きなら『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』も好きかも?似ている絵本3選
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』と似た魅力を持つ絵本をご紹介します。
科学的な知識をわかりやすく伝える絵本や、感覚について学べる作品を選びました。
『よるのおと』
『よるのおと』は夜の自然や周りの音に耳を傾け、静かな世界や動物たちの音に気づく絵本です。
音をイメージする力や聴覚の不思議を詩的に感じられる内容で、『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』と同じように音の世界の豊かさを伝えています。
科学的な解説よりも感覚的な体験を重視している点で、音への関心を深めたい方にぴったりの作品ですね。
『からだのなかで ドゥン ドゥン ドゥン』
心臓の音に焦点を当てて、人間の体の不思議を伝える絵本です。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』が音と耳を扱うように、この作品は体の中から聞こえる音について学べます。
人体の仕組みに興味がある子どもにとって、両方読むことでより深い理解が得られるでしょう。
『みえるとか みえないとか』
視覚をテーマにした絵本で、見える・見えないという感覚の違いについて考えさせてくれます。
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』が聴覚を扱うのに対し、こちらは視覚がメイン。
感覚の多様性や違いを理解する点で共通しており、五感について幅広く学びたい方におすすめです。
振り返り
『聞いて 聞いて!音と耳のはなし』は、音と耳の仕組みを科学的かつわかりやすく解説した優れた絵本でした。
オーディオ専門家による本格的な知識と、親しみやすいイラストが絶妙に組み合わさった作品で、読書感想文の課題図書としても最適な一冊です。
音の世界の奥深さと人間の聴覚の素晴らしさを実感できる内容で、子どもだけでなく大人も楽しめる科学絵本として、多くの方におすすめできる作品ですね。
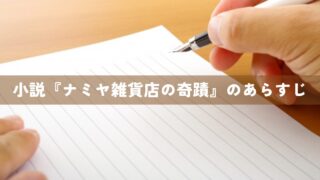
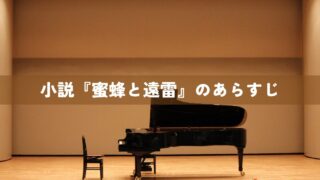

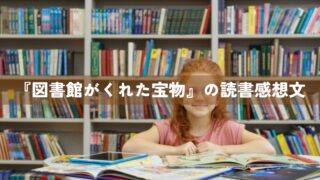

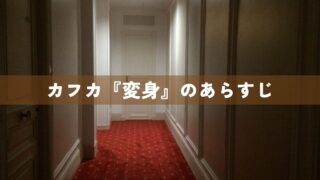

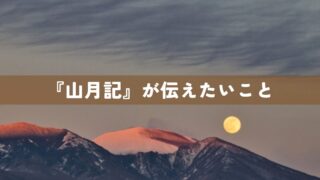
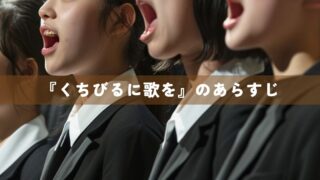
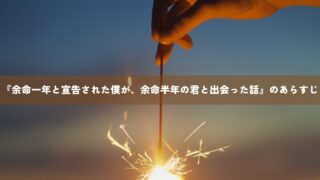
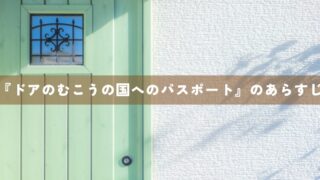
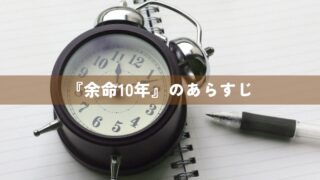



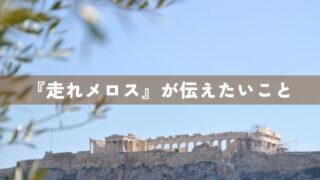



コメント