『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
この作品は、ブレイディみかこさんが息子の中学校生活を通して描いたノンフィクションで、現代社会の問題をリアルに描いています。
年間100冊以上の本を読む私が、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文の書き方を分かりやすく解説していきます。
中学生向けと高校生向けの例文も用意しましたので、題名や書き出しで悩んでいる方にも参考になるはずです。
コピペではなく、あなた自身の言葉で書けるようになるためのポイントも詳しくお伝えしていきますよ。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文で触れたい3つの要点
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を題材に読書感想文を書く際に必ず触れておきたい重要な要点を3つ挙げてみました。
これらの要点について、読みながら「どう感じたか」をメモしておくことが大切です。
- 「エンパシー(共感力)」の重要性
- 多様性が混在する「元・底辺中学校」という舞台
- 母子の対話を通した学びと成長
メモの取り方としては、読書中に付箋を貼ったり、スマホのメモ機能を使って「この場面で私はこう思った」「主人公の気持ちが分かる」といった感想を書き留めておきましょう。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は単なるあらすじの要約ではないため。
あなたがその本を読んでどんな気持ちになったか、何を学んだか、どんな発見があったかを表現することが最も大切(=評価されやすい)なんですね。
「エンパシー(共感力)」の重要性
作品の中で母ちゃんが息子に教える「エンパシー」という概念が、物語全体を貫く重要なテーマとなっています。
「他人の靴を履いてみる」という表現で表される、相手の立場に立って物事を考える想像力のことです。
主人公の息子が、差別的な発言をするクラスメートに対して、単純に「悪い人」と決めつけるのではなく、その背景にある貧困や不安を理解しようとする姿勢が描かれています。
この「エンパシー」について、あなた自身の経験と照らし合わせて考えてみてください。
友達と意見が合わなかったとき、相手の気持ちを考えたことはありますか。
家族と喧嘩したとき、相手の立場になって考え直したことはありますか。
そうした体験を感想文に盛り込むことで、より説得力のある文章が書けるでしょう。
現代社会では、SNSでの炎上や差別問題が日常的に起こっています。
そんな時代だからこそ、この「エンパシー」の概念がどれほど重要かを、あなたなりの言葉で表現してみましょう。
舞台となる多様性が混在する学校
主人公が通う「元・底辺中学校」は、まさに現代社会の縮図として描かれています。
様々な国籍、人種、経済状況の子どもたちが集まる学校で、日々様々な問題が起こります。
貧困で食事に困る子、移民として脇に追いやられる子、ジェンダーに悩む子など、多種多様な背景を持つ生徒たちが登場します。
この多様性について、あなたはどう感じましたか。
日本の学校との違いに驚いたでしょうか。
それとも、実は日本でも似たような問題があると感じたでしょうか。
また、この学校が「元・底辺」と呼ばれていたことについても考えてみてください。
学校にランクを付けることの是非や、偏見がもたらす影響について、あなたの考えを書いてみましょう。
さらに、この多様な環境の中で、子どもたちがどのように成長していくかという点も重要です。
困難な環境だからこそ、子どもたちが身につける強さやたくましさ、そして互いを理解しようとする姿勢について、感想を書いてみてください。
親子の対話を通した学びと成長
この作品の大きな魅力の一つは、母ちゃんと息子の間で交わされる対話にあります。
息子が学校で起こった出来事を家で話し、母ちゃんがそれに対してアドバイスをしたり、一緒に考えたりする場面が印象的です。
注目すべきは、母ちゃんが一方的に教えるのではなく、息子からも学んでいるという点です。
子どもの素朴な疑問や純粋な視点が、大人である母ちゃんにとっても新たな気づきをもたらしています。
あなたと親との関係はどうでしょうか。
悩みを相談したり、学校での出来事を話したりしますか。
もし話さないとしたら、それはなぜでしょうか。
この作品を読んで、親子のコミュニケーションについて何か感じることがあったでしょうか。
また、「大人から子どもが学ぶ」という一般的な考え方に対して、この作品では「子どもから大人が学ぶ」という逆の視点も描かれています。
あなた自身も、大人に何かを教えたり、気づかせたりした経験があるかもしれません。
そうした体験があれば、ぜひ感想文に織り交ぜてみてください。
親子の絆や家族のあり方について、この作品を通して考えたことを素直に表現してみましょう。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】違いを超えて繋がる心
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んで、今まで考えたことのない社会の問題について深く考えさせられた。
この本は、日本人の母とアイルランド人の父を持つ男の子が、イギリスの中学校で様々な人と出会い、成長していく実話だ。
最初にこの本を手に取ったとき、タイトルの意味がよく分からなかった。でも読み進めていくうちに、これが主人公の複雑なアイデンティティを表していることが分かった。黄色人種でもあり、白人でもあり、そして少し憂鬱な気持ちも抱えている。
一番印象に残ったのは、「エンパシー」という言葉だった。母ちゃんが息子に「その人の靴を履いて考えてみなさい」と教える場面で、私はハッとした。普段、友達と意見が合わないときや、理解できない行動をとる人がいるとき、私はすぐに決めつけてしまうことがある。でも、その人にはその人なりの事情や理由があるのかもしれない。そう考えることの大切さを、この本は教えてくれた。
主人公が通う学校は、様々な国の出身者や貧困家庭の子どもたちが通う学校だった。差別的な発言をする生徒がいたり、食べ物に困っている子がいたり、私には想像もできない現実があった。でも、その中で子どもたちは必死に生きている。そして、先生たちも生徒一人一人を見捨てることなく、向き合っている。
この学校の様子を読んでいて、私は自分の恵まれた環境について改めて考えた。毎日当たり前のように学校に通い、友達と楽しく過ごし、家に帰れば温かい食事が待っている。そんな「普通」の生活が、実はとても贅沢なことなのかもしれない。そして、世界には様々な「普通」があることを知った。
母ちゃんと息子の会話も、とても心に残った。息子が学校での出来事を家で話し、母ちゃんがそれに真剣に向き合う。私と母の関係と比べると、私はあまり学校のことを詳しく話していないことに気づいた。面倒くさいと思ったり、どうせ分からないだろうと思ったりして、表面的な話しかしていない。でも、この本を読んで、もっと親と深い話をしてみたいと思った。
この本を読んで、私は「多様性」という言葉の本当の意味を理解できた気がする。多様性とは、ただ違う人たちが集まることではない。その違いから生まれる摩擦や衝突を乗り越えて、お互いを理解しようと努力することなのだと思う。そのために必要なのが「エンパシー」、つまり相手の立場に立って考える想像力なのだろう。
これから私も、中学校生活の中で様々な人と出会うことになる。その時に、相手を簡単に決めつけるのではなく、「なぜそう思うのか」「どんな気持ちなのか」を考えてみたい。そして、自分とは違う考えを持つ人とも、対話を通じて理解し合えるような人になりたい。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、私に多くの気づきを与えてくれた大切な一冊になった。この本で学んだ「エンパシー」の心を忘れずに、これからの学校生活を送っていきたいと思う。」
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】多様性という現実と向き合う勇気
現代社会では「多様性」という言葉が当たり前のように使われている。
学校でも社会でも、違いを認め合うことの重要性が説かれ、差別はいけないことだと教えられる。
しかし、ブレイディみかこ著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んで、私はその「多様性」の裏にある複雑で生々しい現実と初めて真正面から向き合うことになった。
この作品は、イギリス在住の著者が、日本人とアイルランド人のハーフである息子の中学校生活を描いたノンフィクションである。
息子が通う学校は、かつて「底辺」と呼ばれた多様な背景を持つ生徒たちが集まる場所だった。
人種、国籍、経済状況、家庭環境が全く異なる子どもたちが同じ教室で学ぶこの学校は、まさに現代社会の縮図として描かれている。
読み始めてすぐに、私は自分の世界の狭さを痛感した。
これまで私が「多様性」について考えるとき、それはどこか理想的で美しいもののように感じていた。
しかし、この作品が描く現実は違った。
差別的な発言を平然とする生徒、貧困ゆえに食事もままならない子ども、移民として偏見の目に晒される家族。
そこには、私が想像していたような綺麗事では済まされない、リアルな衝突や矛盾が存在していた。
特に印象的だったのは、「エンパシー」という概念である。
母ちゃんが息子に教える「その人の靴を履いて考えてみなさい」という言葉は、単なる思いやりを超えた、より深い人間理解のあり方を示している。
差別的な言動をとる生徒に対して、息子は彼を単純に「悪い人」として断罪するのではなく、その背景にある貧困や将来への不安を理解しようと努める。
この姿勢に、私は深く感動した。
振り返ってみると、私は日常生活において、理解できない行動をとる人や、自分と異なる価値観を持つ人に対して、安易にレッテルを貼ってしまうことが多かった。
SNSで炎上している話題を見ても、「この人はひどい」「あの人は間違っている」と、表面的な判断で終わらせてしまう。
しかし、この作品を読んで、そのような態度がいかに浅薄であるかを思い知らされた。
相手の立場に立って考える「エンパシー」は、多様な社会を生きる上で欠かせない能力なのだと実感した。
また、この作品で描かれる母子の関係にも深く考えさせられた。
息子が学校での出来事を家で話し、母ちゃんがそれに真剣に向き合う姿勢は、理想的な親子関係のあり方を示している。
しかし、それ以上に印象的だったのは、母ちゃんが息子から学んでいるということだった。
大人である母ちゃんが、子どもの純粋な疑問や視点から新たな気づきを得ている。
この逆転した学びの関係に、私は新鮮な驚きを覚えた。
私と両親の関係を振り返ってみると、どうしても親が教え、私が学ぶという一方的な構造になりがちだった。
しかし、実際には私自身も、両親に何かを気づかせたり、考えるきっかけを与えたりすることができるのかもしれない。
この作品を読んでから、家族との会話の質が少しずつ変わってきたように思う。
学校での出来事をより詳しく話すようになったし、社会問題について家族で議論することも増えた。
息子が様々な困難に直面しながらも、決して諦めることなく成長していく姿にも勇気をもらった。
彼は、肌の色の違いによる偏見を感じても、ジェンダーに悩む友人をサポートし、経済的に恵まれない同級生との友情を大切にしている。
そこには、大人よりもよほど柔軟で包容力のある心が表れている。
私たち高校生の世代は、これから大学、就職と、より広い社会に出ていくことになる。
その時に直面するであろう様々な価値観の違いや衝突に対して、この作品が示す「エンパシー」の精神は必ず役に立つはずだ。
この作品を読んで、私は「多様性」という言葉の重みを改めて理解した。
それは単に「違いを認める」という表面的なものではなく、その違いがもたらす摩擦や困難と真正面から向き合い、相手を理解しようと努力し続けることなのだと分かった。
そして、そのプロセスは決して楽ではないが、人間として成長するために不可欠なものなのだろう。
現在の日本社会も、外国人労働者の増加やLGBTQの理解促進など、多様性への対応が求められている。
しかし、制度や建前だけでは解決できない問題がたくさんある。
必要なのは、一人ひとりが「エンパシー」の心を持ち、相手の立場に立って考える努力を続けることなのだと思う。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、私にとって単なる読み物ではなく、これからの生き方を考える上での指針となる一冊となった。
この作品で学んだことを胸に、様々な人との出会いを大切にし、理解し合える関係を築いていけるような大人になりたいと強く思う。
多様性という複雑な現実と向き合う勇気を、この本は私に与えてくれたのである。
振り返り
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
この作品は、現代社会の重要なテーマを扱っているだけに、感想文でも深い内容を書くことができる素晴らしい題材です。
「エンパシー」「多様性」「親子の対話」という3つの要点を押さえて、あなた自身の体験や考えを盛り込めば、きっと説得力のある感想文が完成するでしょう。
例文はあくまで参考程度に留めて、あなたらしい言葉で表現することが何より大切です。
この記事が皆さんの読書感想文作成のお手伝いになれば嬉しいです。
※『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の簡単ながら詳しいあらすじはこちらでどうぞ。

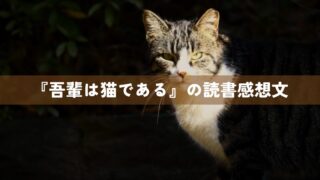
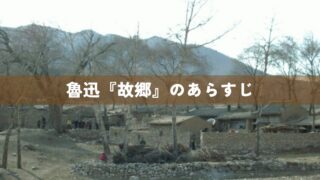


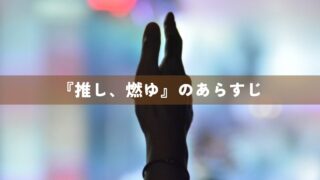





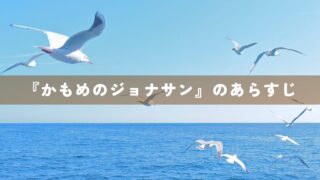








コメント