『鳥居きみ子』のあらすじを解説していきますね。
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』は竹内紘子さんによる感動的なノンフィクション作品です。
明治から昭和という女性の社会進出が困難だった時代に、家族とともに人類学研究に取り組んだ鳥居きみ子の生涯を描いています。
読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、この課題図書について短くて簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、丁寧に解説していきますよ。
それでは、さっそく進めていきましょう。
- 竹内紘子『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを短く簡単に
- 竹内紘子『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを詳しく
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを理解するための用語解説
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の感想
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の作品情報
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の主要な登場人物と簡単な説明
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読了時間の目安
- 『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』はどんな人向けの作品か?
- あの本が好きなら『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』も好きかも?似ている作品3選
- 振り返り
竹内紘子『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを短く簡単に
竹内紘子『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを詳しく
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』のあらすじを理解するための用語解説
『鳥居きみ子』のあらすじに出てくる専門的な用語について、分かりやすく説明しますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 人類学 | 人間の文化や社会、言語、歴史、進化などを 包括的に研究する学問。 本書では異文化や各地の人々の暮らしを中心に扱う。 |
| フィールドワーク | 現地調査のこと。 研究対象となる地域に実際に足を運び、 直接観察や聞き取りを行う調査方法。 |
| 民族学 | さまざまな民族の生活様式や 文化、伝承、習慣などを調べる学問分野。 民族誌はその記録のこと。 |
| 良妻賢母 | 明治時代の理想的な女性像。 女性は家庭に入って 夫や子どもを支えることが当然とされていた。 |
| 家族での協働研究 | 家族全員が一緒に調査や研究活動に参加するスタイル。 それぞれが役割を持って調査旅行や生活をともにした。 |
これらの用語を理解しておくと、きみ子の生涯や業績がより深く理解できますよ。
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の感想
この作品を読んで、私は深く感動しました。
鳥居きみ子という女性の生き方が、現代の私たちにも大きな勇気を与えてくれる素晴らしい内容でした。
まず何よりも驚いたのは、明治から昭和という時代に、女性がこれほど積極的に研究活動に参加していたという事実です。
当時の日本では「男は外、女は内」という考えが当然とされ、女性が学問の世界で活躍することなど考えられませんでした。
そんな制約の中で、きみ子は家族とともにモンゴルや中国まで調査に出かけ、現地の人々と交流しながら貴重な記録を残していった。
この行動力と適応力には本当に頭が下がります。
特に印象的だったのは、きみ子が現地の女性や子どもたちとの関係を築いて、男性研究者では得られない情報を収集していたという点です。
文化人類学において、異なる性別や年齢の視点から見た記録がいかに重要かということを、この作品を通して深く理解できました。
また、家族全員で研究に取り組むという鳥居家のスタイルも非常に興味深かったです。
夫の龍蔵だけでなく、きみ子はもちろん、子どもたちもそれぞれの得意分野で調査に関わっていく。
現代でも珍しいこのような家族ぐるみの研究スタイルが、当時の日本で実現されていたことに驚きました。
読んでいて特に胸が熱くなったのは、きみ子が「学者の妻」という立場にとどまらず、自らも研究者として成長していく過程です。
最初は夫の研究に協力するという形で始まった活動が、次第に彼女自身の専門性を発揮する場へと発展していく。
この変化の過程が丁寧に描かれており、読者として彼女の成長を見守る喜びを感じました。
一方で、現代の価値観から見ると戸惑うエピソードもありました。
乳児を連れて海外調査に出かけるのは大丈夫なの?と思うし、子どもを養子に出すといった現在の子育て観とは大きく異なる選択をしている場面があります。
しかし、これらの選択も当時の社会状況や個人の置かれた立場を考えると、きみ子なりの精一杯の判断だったのだろうと理解できます。
むしろ、そうした困難な状況の中でも研究への情熱を失わず、前向きに生きていく姿勢に感銘を受けました。
この作品を読んで改めて感じたのは、「支える側の人生」にも確かな価値と意味があるということです。
きみ子は夫の研究を支えながらも、自らの専門性を発揮して学問の発展に貢献していました。
現代社会でも、表舞台に立つ人だけでなく、それを支える人々の存在が欠かせません。
きみ子の生き方は、そうした「支える側」の人たちにも勇気と誇りを与えてくれるものだと思います。
※『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読書感想文の書き方はこちらで解説しています。

『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の作品情報
『鳥居きみ子』の基本情報をまとめてみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 竹内紘子 |
| 出版年 | 2024年 |
| 出版社 | くもん出版 |
| 受賞歴 | 第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書 (小学校高学年向け) |
| ジャンル | ノンフィクション・人物伝 |
| 主な舞台 | 日本・モンゴル・中国 |
| 時代背景 | 明治6年(1873年)~昭和21年(1946年) |
| 主なテーマ | 女性の社会進出・家族での協働・人類学研究 |
| 物語の特徴 | 実在の人物を描いた伝記・家族ぐるみの研究スタイル |
| 対象年齢 | 小学校高学年以上 |
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の主要な登場人物と簡単な説明
『鳥居きみ子』に登場する重要な人物たちを紹介しますね。
| 人物名 | 簡単な紹介 |
|---|---|
| 鳥居きみ子 | 本作の主人公。 明治6年生まれの教師・研究者。 女性が学術の世界に立つことが困難な時代に、 現地調査を通して民族学に貢献した。 |
| 鳥居龍蔵 | きみ子の夫。 「知の巨人」と呼ばれた著名な人類学者。 東アジアを広く調査し、家族とともに現地調査を行った。 |
| 坪井正五郎 | 龍蔵の師。 日本人類学の草創期を支えた研究者。 龍蔵の研究活動に大きな影響を与えた。 |
| 鳥居幸子 | きみ子と龍蔵の長女。 |
| 鳥居緑子 | きみ子と龍蔵の次女。 |
| 鳥居龍次郎 | きみ子と龍蔵の次男。 |
登場人物は多くありませんが、それぞれが鳥居家の研究活動において重要な役割を果たしています。
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』の読了時間の目安
『鳥居きみ子』の読了時間について説明しますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ページ数 | 184ページ |
| 推定文字数 | 約110,400文字 |
| 読了時間の目安 | 約3時間40分 |
ノンフィクションなので小説と比べて読み進めるのに時間がかかる場合もありますが、物語性があるので比較的読みやすい作品です。
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』はどんな人向けの作品か?
『鳥居きみ子』は幅広い読者におすすめできますが、特に以下のような人に向いています。
- 新しいことに挑戦したい、変化のある人生を歩みたいと考えている人
- 家族や仲間との協力やチームワークの大切さに興味がある人
- 女性の生き方や社会での活躍について考えたい人
逆に、フィクションの物語性を求める人や、劇的な展開を期待する人には少し物足りなく感じるかもしれません。
しかし、実在の人物の生き方から学べることは多く、年齢や性別を問わず読む価値のある作品だと思います。
あの本が好きなら『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』も好きかも?似ている作品3選
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』と似た要素を持つ作品を3つ紹介しますね。
『人類20万年 遙かなる旅路』アリス・ロバーツ
英国の女性人類学者が、人類大移動の軌跡を自ら旅しながら綴った作品です。
科学的知見と現地体験の両面から描かれており、「現地の生活に入り込んで探る」フィールドワークの姿勢が『鳥居きみ子』と共通しています。
女性研究者の視点から人類学を描いている点でも似ています。
『ク スクップ オルシぺ 私の一代の話』砂沢クラ
明治から昭和初期を生き抜いたアイヌ女性による自伝です。
家族・民族とともに激動の時代を歩み、アイヌ文化や信仰を自身の視点から描いています。
「女性の語り・家族と歩むフィールドワーク」の姿勢が『鳥居きみ子』と強く共鳴します。
『幻のアフリカ納豆を追え!』高野秀行
ノンフィクション作家が西アフリカで現地住民と寝食を共にしながら調査を行った作品です。
「誰も行かない現場に自ら飛び込み、地域の人と暮らし、共に知見を得ていく」スタイルが『鳥居きみ子』のフィールドワーク精神と共通しています。
振り返り
『鳥居きみ子: 家族とフィールドワークを進めた人類学者』は、女性の社会進出が困難だった時代に、家族とともに人類学研究に取り組んだ鳥居きみ子の感動的な生涯を描いた作品です。
明治から昭和という時代背景の中で、「支える側」の人生にも確かな価値があることを教えてくれる素晴らしいノンフィクションでした。
読書感想文を書く皆さんにとって、きみ子の生き方や家族での協働研究というテーマは、現代にも通じる大切なメッセージを含んでいます。
ぜひ一度手に取って、鳥居きみ子という先駆的な女性研究者の人生に触れてみてください。
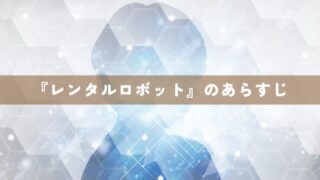
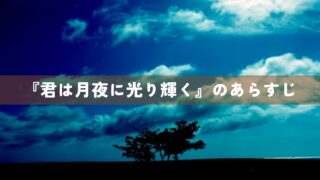
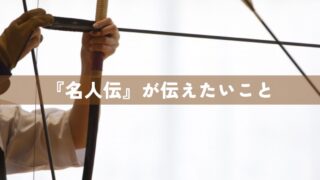


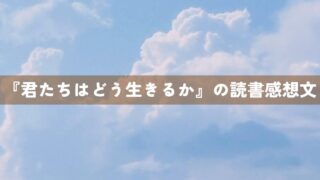


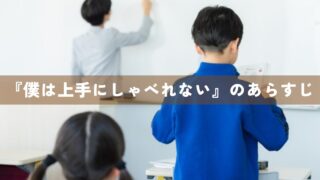
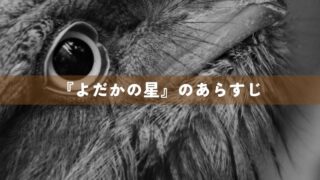
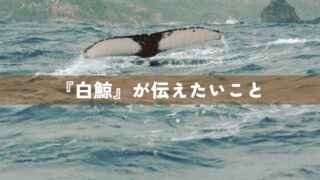

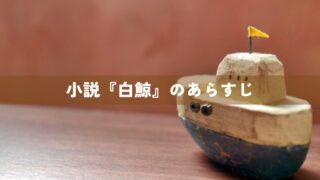

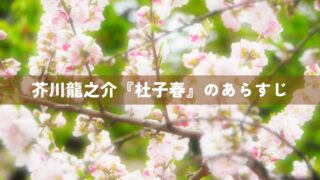

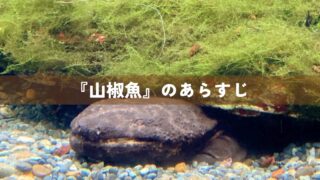


コメント