『モチモチの木』のあらすじについて、詳しく解説していきますね。
『モチモチの木』は斎藤隆介さんが作り、滝平二郎さんが絵を描いた名作絵本です。
1971年に岩崎書店から発行され、現在も小学校の国語の教科書に広く採用されている作品ですよ。
年間100冊以上の本を読む読書家として、この作品の魅力を存分にお伝えしたいと思います。
簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、ネタバレありで丁寧に解説していくので、読書感想文を書く際の参考にしてくださいね。
それでは、さっそく進めていきましょう。
『モチモチの木』のあらすじを簡単に短く(ネタバレ)
臆病な5歳の男の子・豆太は、祖父と山奥の猟師小屋で暮らしている。夜は一人で便所に行けないほど怖がりで、家の前にある大きな栃の木を「モチモチの木」と呼んで恐れていた。ある夜、祖父が急病で倒れる。豆太は恐怖を乗り越えて山道を走り、医者を呼びに行った。その帰り道、モチモチの木が美しく光っているのを見る。祖父は「勇気のある子だけが見られる山の神の祭り」だと教えてくれた。しかし祖父の病気が治ると、豆太は再び元の臆病な子に戻ってしまうのだった。
『モチモチの木』のあらすじを詳しく(ネタバレ)
5歳の豆太は、峠の猟師小屋で祖父(じさま)と二人きりで暮らしている。
小心者の豆太は、夜中に一人で別棟の便所に行くことができず、いつも祖父を起こして付き添ってもらっていた。
家の前には大きな栃の木があり、豆太はその木を「モチモチの木」と呼んでいる。
秋になると美味しい実をつけるこの木だが、夜になると両手を振り上げたお化けのような姿に見えて豆太を怖がらせる。
祖父は豆太に「霜月二十日の夜、モチモチの木には灯がともる」という言い伝えを話していた。
それは「山の神の祭り」と呼ばれ、勇気のある子が一人でいるときにしか見ることができないという。
祖父の幼い頃、豆太の亡き父も見たことがあるらしい。
豆太も見たいと思うが、真夜中のモチモチの木を想像するだけで尿を漏らしそうになってしまう。
ある晩、豆太は祖父の唸り声で目を覚ました。
祖父が急な腹痛で苦しんでいる。
助けるには半里も離れた麓の村まで医者を呼びに行かなければならない。
豆太は勇気を振り絞り、恐怖に震えながらも真夜中の山道を走り抜けた。
医者を呼び出し、事情を説明する。
医者は豆太を背負って山の小屋へと向かった。
その道中、この冬初めての雪が降り出し、モチモチの木は月光を背にして美しく輝いていた。
枝の隅々まで火が灯っているように見える。
それは新雪が月光に照らされているのだった。
これこそが祖父の話していた「山の神の祭り」だったのだ。
医者と豆太の介抱で祖父は回復し、豆太から一部始終を聞いた祖父は言った。
「お前は山の神様の祭りを見た。お前は勇気のある子どもだ。人間、優しささえあれば、やらなきゃならねぇ事は、きっとやるもんだ」
しかし祖父の病気が治ると、豆太はまた元の小心者に戻り、夜は一人で便所に行けないままだった。
『モチモチの木』のあらすじを理解するための用語解説
物語に出てくる重要な用語をわかりやすく説明しますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| モチモチの木 | 豆太の家の前にある大きな栃の木のこと。 昼間は普通の木だが、夜になると恐ろしいお化けのように見える。 物語の象徴的な存在で、豆太の恐怖と成長を表している。 |
| せっちん | 物語中で使われる古い言葉で、トイレ(便所)のこと。 豆太は夜中に一人でせっちんに行けないほど臆病だった。 |
| 霜月二十日 | 旧暦の11月20日にあたる冬至の晩のこと。 この夜にモチモチの木が美しく光るという伝承がある。 物語のクライマックスとなる重要な日付。 |
| 山の神の祭り | 霜月二十日の夜にモチモチの木に灯がともる現象のこと。 勇気のある子が一人でいるときにしか見ることができないとされる。 実際は雪と月光が作り出す美しい光景だった。 |
これらの用語を理解しておくと、物語の深い意味がより分かりやすくなりますよ。
『モチモチの木』の感想
『モチモチの木』を読んで、私は本当に心を打たれました。
この作品は、表面的には子ども向けの絵本のように見えますが、実は大人が読んでも深く考えさせられる内容なんですよね。
まず、豆太のキャラクターが素晴らしいです。
5歳の子どもが夜中に便所に行けないなんて、現代の子どもには理解しづらいかもしれませんが、昔の山奥の生活を考えると、とてもリアルで説得力があります。
私も子どもの頃、夜中にトイレに行くのが怖かった記憶があるので、豆太の気持ちがよく分かりました。
そして、物語のクライマックスがやばかったです。
祖父が倒れたときの豆太の行動に、鳥肌が立ちました。
普段は臆病で何もできない子が、大切な人のために命がけで走る姿は、本当に感動的でした。
ここで作者が伝えたかったのは、「本当の勇気」についてなんですよね。
勇気とは恐怖がないことではなく、恐怖があっても大切なもののために行動することだということが、豆太の姿を通じて見事に描かれています。
滝平二郎さんの切り絵も圧倒的でした。
特にモチモチの木が光る場面は、息を呑む美しさです。
白と黒のコントラストが強烈で、物語の緊張感を高めています。
子どもには少し怖く感じるかもしれませんが、それがまた物語に深みを与えているんです。
祖父の「人間、優しささえあれば、やらなきゃならねぇ事は、きっとやるもんだ」という言葉が、特に印象に残りました。
これは子どもだけでなく、大人の私たちにも響く言葉です。
普段は弱い自分でも、本当に大切な場面では力を発揮できるという希望を与えてくれます。
ただ、一つ気になったのは、物語の最後で豆太が元の臆病な子に戻ってしまうところです。
これについては賛否両論あると思いますが、私はこれがリアルで良いと思いました。
人間は一度の経験で完全に変わるわけではないということを、正直に描いているからです。
でも、豆太の中には確実に「勇気の種」が植えられたはずで、きっと成長とともに花開くのでしょう。
『モチモチの木』は、単なる童話ではなく、人生の本質を描いた名作だと思います。
子どもの読書感想文にも、大人の心の支えにもなる、本当に素晴らしい作品でした。
『モチモチの木』の作品情報
『モチモチの木』の基本的な情報をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 斎藤隆介(文)、滝平二郎(絵) |
| 出版年 | 1971年11月 |
| 出版社 | 岩崎書店 |
| 受賞歴 | 特に大きな文学賞の受賞歴はないが、長年愛され続けている名作 |
| ジャンル | 児童文学、絵本、童話 |
| 主な舞台 | 峠の猟師小屋、山奥の村 |
| 時代背景 | 現代だが、昔ながらの山村の生活 |
| 主なテーマ | 勇気、優しさ、家族愛、成長 |
| 物語の特徴 | 切り絵による美しい絵本、幻想的な雰囲気 |
| 対象年齢 | 小学校低学年(1〜3年生)が中心だが、大人も楽しめる |
| 青空文庫 | 未収録 |
この作品は特に小学校の国語の教科書に長年採用されており、多くの子どもたちに愛されています。
『モチモチの木』の主要な登場人物とその簡単な説明
『モチモチの木』に登場する主要人物を紹介しますね。
| 登場人物 | 説明 |
|---|---|
| 豆太(まめた) | 5歳の男の子で、物語の主人公。 小心者で夜中に一人で便所に行けないほど臆病。 しかし祖父のためには勇気を振り絞ることができる優しい子。 |
| じさま(祖父) | 豆太の祖父で、二人で山小屋に住んでいる。 豆太を温かく見守り、大切な人生の教えを伝える。 物語では急病で倒れ、豆太の勇気を引き出すきっかけとなる。 |
| 医者様 | 麓の村に住む医者。 豆太に呼ばれて山小屋まで来て、祖父の命を救う。 豆太を背負って帰る優しい人物。 |
登場人物は少ないですが、それぞれが物語の中で重要な役割を果たしています。
※短い話ながらミステリアスな面もあり怖いとも言われる『モチモチの木』を解説した記事がこちら。
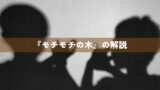
『モチモチの木』の読了時間の目安
『モチモチの木』の読了時間について説明しますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ページ数 | 32ページ(絵本) |
| 推定文字数 | 約1,000文字 |
| 読了時間(子ども) | 15〜20分程度 |
| 読了時間(大人) | 5〜10分程度 |
絵本なので文字数は少なく、とても読みやすい作品です。
小学校低学年の子どもでも一人で読み切ることができる分量ですね。
読み聞かせの場合は、絵をじっくり見せながら読むと20分程度かかります。
『モチモチの木』はどんな人向けの小説か?
『モチモチの木』は、以下のような人に特におすすめしたい作品です。
- 勇気について考えたい子どもや、臆病な自分を変えたいと思っている人
- 家族の絆や祖父母との関係を大切にしたい人
- 美しい絵と感動的な物語を楽しみたい人
この作品は、表面的には子ども向けの絵本ですが、実は大人が読んでも深く考えさせられる内容になっています。
特に、自分の弱さと向き合いながらも、大切な人のために頑張りたいと思っている人には、強く響く作品だと思います。
逆に、ホラーや怖い描写が苦手な人には、モチモチの木の描写が少し怖く感じるかもしれません。
また、すぐに結果が出る爽快な物語を求める人には、少し物足りないかもしれませんね。
あの本が好きなら『モチモチの木』も好きかも?似ている小説3選
『モチモチの木』が好きな方におすすめの、似たテーマを持つ作品を3つ紹介します。
どれも子どもの成長や勇気をテーマにした、心温まる名作ばかりですよ。
『ごんぎつね』新美南吉
『ごんぎつね』は、いたずら好きの狐と人間の心の交流を描いた名作童話です。
主人公が自分の行いを反省し、他者への思いやりを学ぶ成長物語という点で『モチモチの木』と似ています。
どちらも小さな主人公の視点から、優しさや思いやりの大切さを描いているんですね。
自然との関わりや、心の成長を丁寧に描いた作品として、共通点が多い作品です。

『ないた赤おに』浜田広介
『ないた赤おに』は、友達のために自分を犠牲にする赤鬼の物語です。
恐れや偏見を乗り越える勇気と、真の友情を描いた感動的な作品ですね。
『モチモチの木』の豆太が祖父のために勇気を振り絞るのと同様に、大切な人のために自分の恐怖を乗り越える姿が描かれています。
どちらも「本当の勇気とは何か」を考えさせてくれる、深いメッセージを持った作品です。
『花さき山』斎藤隆介
『花さき山』は、『モチモチの木』と同じ斎藤隆介さんの作品です。
子どもの優しさや我慢が、山に美しい花を咲かせるという幻想的な物語ですね。
両作品とも、子どもの心の成長と自然の神秘的な現象を結びつけて描いているという共通点があります。
滝平二郎さんの切り絵も美しく、『モチモチの木』と同じような幻想的な雰囲気を味わえる作品です。
振り返り
『モチモチの木』は、臆病な少年が大切な人のために勇気を振り絞る姿を通じて、本当の勇気について教えてくれる素晴らしい作品でした。
簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、ネタバレを含めて丁寧に解説してきましたが、皆さんの読書感想文の参考になったでしょうか。
斎藤隆介さんの温かい文章と滝平二郎さんの美しい切り絵が織りなす、日本の名作絵本の魅力を存分に味わっていただけたと思います。
この作品は小学校の国語の教科書にも採用されており、多くの子どもたちに愛され続けています。
豆太の成長とともに、私たち自身も勇気や優しさについて深く考えることができる、本当に価値のある作品ですね。



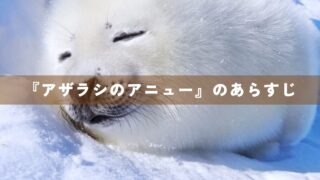


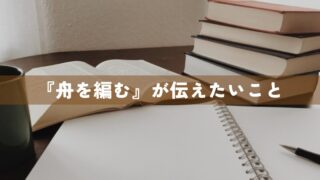

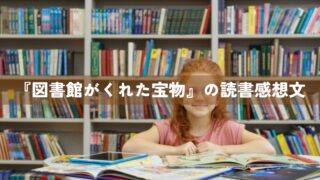

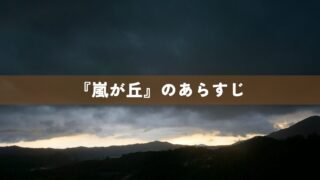
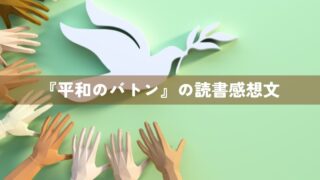




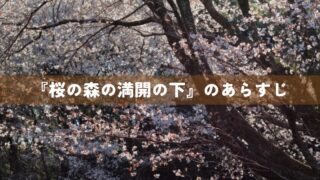
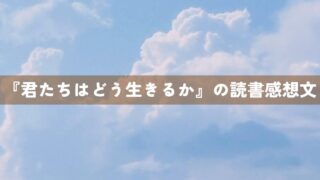
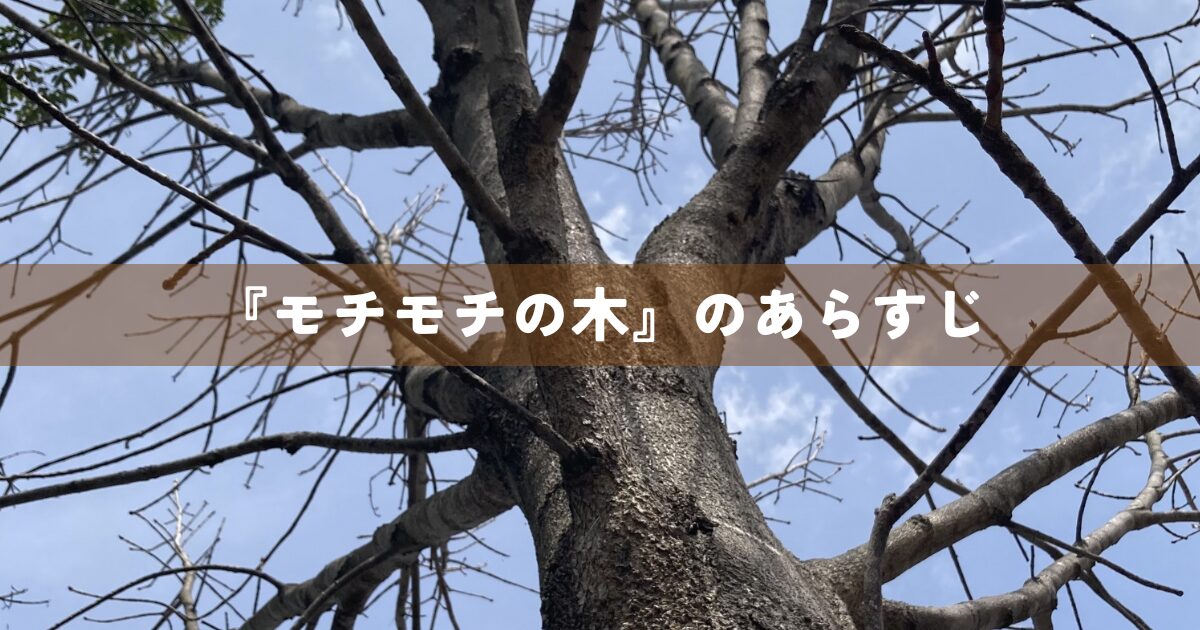
コメント