辞書編纂の情熱が描かれた名作『舟を編む』のあらすじをシンプルに紹介します。
三浦しをんさんの筆による2011年発表の本作は、言葉を愛する人々の心を打つストーリーとして多くの読者に愛されています。
私は年間100冊以上の本を読む読書家ですが、この作品の魅力は何度読んでも色あせません。
この記事では『舟を編む』のあらすじを、簡単に・短くまとめたものから詳しいものまで段階的に紹介し、登場人物や私が読んだ感想もたっぷりお伝えします。
『舟を編む』の短いあらすじ
『舟を編む』の簡単なあらすじ
営業部で厄介者扱いされていた言語学専攻の馬締光也は、定年間近の荒木公平に見出され辞書編集部へ。新しく刊行する辞書『大渡海』の編集メンバーとなった馬締は、その鋭い言語感覚を活かし辞書づくりに没頭していく。
チャラ男の西岡、几帳面な契約社員の佐々木など個性的なメンバーと共に、馬締は辞書という「言葉の海を渡る舟」を編んでいく。下宿先の大家の孫娘・香具矢との交流を通じ、言葉で「伝えたい」「つながりたい」という思いも芽生えていった。
『舟を編む』の詳しいあらすじ
玄武書房に勤める馬締光也は、皮肉が通じず対人コミュニケーション能力の低さから第一営業部で厄介者扱いされていた。しかし、定年間近の辞書編集部のベテラン・荒木公平は、馬締の言語学の知識と鋭い言語感覚を見抜き、新しく刊行する辞書『大渡海』の編集メンバーとして引き抜いた。
辞書編集部には、馬締の対極にあるチャラ男の西岡正志、黙々と事務作業をこなす中年女性・佐々木薫、監修担当の老国語学者・松本朋佑らが所属していた。当初馬締は辞書編集部になじめず悩むが、次第に言葉への情熱を自覚していく。
馬締の暮らす下宿「早雲荘」には、大家のタケと孫娘の香具矢がいた。香具矢は板前見習いとして働いており、馬締のよき理解者となっていく。一方、西岡も辞書に愛情を持ち始め、宣伝広告部への異動後も『大渡海』のサポートを続けることを決意した。
辞書編纂の長い道のりで様々な困難に直面するも、言葉への愛と仲間との絆を深めながら、『大渡海』の完成へと向かう彼らの姿が描かれている。
『船を編む』のあらすじを理解するための用語解説
『船を編む』のあらすじに登場する専門的な用語を解説します。
| 用語 | 意味・説明 |
|---|---|
| 辞書編纂(じしょへんさん) | 辞書を編集して作り上げる作業。 言葉の意味や用例を収集し、 正確な辞書をつくる長い工程を指す。 |
| 大渡海(だいとかい) | 作中で作られる国語辞典の名前。 辞書は「言葉の海を渡る舟」に例えられている。 |
| 言葉の舟 | 辞書を「言葉の大海原を渡る舟」にたとえた表現。 辞書が言葉の海を渡るための道具であることを示す。 |
| 用例採集(ようれいさいしゅう) | 言葉の使われ方を 具体的な文章(用例)から集める作業。 意味や用法を正しく伝えるために重要。 |
| 編集部(へんしゅうぶ) | 辞書作りに携わるスタッフの集団。 各自が言葉の調査や校正、執筆を担当する。 |
『舟を編む』の作品情報
『舟を編む』の基本情報を表にまとめました。
読書感想文を書く際の参考にしてください。
| 作者 | 三浦しをん |
|---|---|
| 出版年 | 2011年 |
| 出版社 | 光文社 |
| 受賞歴 | 第44回メフィスト賞 第28回中央公論文芸賞 2012年本屋大賞 |
| ジャンル | 文学・仕事小説 |
| 主な舞台 | 出版社「玄武書房」と下宿「早雲荘」 |
| 時代背景 | 現代(2000年代) |
| 主なテーマ | 言葉の力、辞書編纂の情熱、人とのつながり |
| 物語の特徴 | 辞書作りという専門的な仕事を通じた人間ドラマ |
| 対象年齢 | 中学生以上 |
『舟を編む』の主要な登場人物とその簡単な説明
『舟を編む』の物語を彩る個性豊かな登場人物たちを紹介します。
それぞれのキャラクターが辞書編纂という共通の目標に向かって力を合わせていく様子が感動を誘います。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| 馬締 光也(まじめ みつや) | 主人公。27歳。 言語学を専攻し、 対人コミュニケーションが苦手だが、 言葉への鋭い感覚を持つ。 |
| 荒木 公平(あらき こうへい) | 辞書編集部のベテラン。 馬締の才能を見抜き、辞書編集部へ引き抜く。 |
| 西岡 正志(にしおか まさし) | 27歳。 馬締とは対照的なチャラい性格だが、 社交的で対人折衝能力が高い。 |
| 林 香具矢(はやし かぐや) | 馬締が住む下宿「早雲荘」の大家の孫娘。 板前見習い。馬締の理解者となる。 |
| 佐々木 薫(ささき かおる) | 辞書編集部の契約社員。 事務作業を黙々とこなす中年女性。 |
| タケ | 早雲荘の大家。香具矢の祖母。 馬締を気にかける優しいおばあさん。 |
| 松本 朋佑(まつもと ともすけ) | 『大渡海』の監修を務める老国語学者。 荒木の能力を高く評価している。 |
| 三好 麗美(みよし れみ) | 西岡の交際相手。 大学時代からの腐れ縁だが、のちに結婚する。 |
| 岸辺 みどり(きしべ みどり) | 13年後の物語で登場する 辞書編集部の女性編集者。 |
| 宮本 慎一郎(みやもと しんいちろう) | あけぼの製紙の営業部員。 『大渡海』に相応しい辞書用紙の開発に尽力する。 |
『舟を編む』の読了時間の目安
『舟を編む』を読むのにどれくらいの時間がかかるのか、目安を表にまとめました。
読書のペースプランニングにご活用ください。
| ページ数 | 259ページ(単行本) |
|---|---|
| 推定総文字数 | 約155,400文字 |
| 読了時間 | 約5時間10分 |
| 1日1時間読書の場合 | 約5日で読了可能 |
| 読みやすさ | 専門用語はあるが文章は平易で読みやすい |
読書のペースは個人差がありますが、1日1時間程度の読書時間で約5日で読み終えることができる長さです。
辞書編集という専門的な内容ですが、文章は平易で読みやすいので、スムーズに読み進められるでしょう。
『船を編む』を読んだ私の感想
「船を編む」、いやはや、本当に良い本でした。普段小説なんて読まない妻が「絶対好きだから」と勧められ読んだら大ヒットでしたね。
辞書を作る話と聞いて最初は「地味かな」と思ったんですが、読み進めるうちに、その地味さの中に秘められた情熱とこだわりがじんわり伝わってきて、もうね、胸が熱くなりました。
主人公・馬締くんの言葉への純粋な愛情と、ひたすら真面目に取り組む姿には、忘れかけていた何かを思い出させられましたよ。
彼を取り巻く個性豊かな面々、特に西岡くんとの対比も絶妙で、人間味溢れる描写に引き込まれました。最初はチャラい奴だと思ってたけど、彼なりの役割と葛藤があって、良い味出してるんですよね。
辞書作りって、果てしない作業じゃないですか。膨大な言葉と向き合い、一つ一つ意味を紡いでいく。まるで大海原を渡る船を、気の遠くなるような時間をかけて編むよう。
その過程で生まれる人間模様や、言葉の奥深さに触れるたび、「日本語ってこんなにも美しいのか」と改めて感動しました。
読み終えた後、自宅の辞書を思わず手に取ってしまいましたよ。何気なく使っていた言葉一つ一つに、こんなにも多くの人の情熱と努力が詰まっているのかと。
普段の仕事でも、もっと言葉を大切にしよう、なんて思ったりして。静かに、でも確実に心に響く一冊。肩の力を抜いて、じっくり味わってほしいですね。
※『船を編む』の読書感想文の中高生向けの書き方と例文はこちらで解説しています。
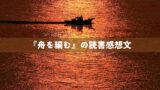
『舟を編む』はどんな人向けの小説か
『舟を編む』は様々な魅力を持つ作品ですが、特に以下のような方におすすめです。
- 言葉や日本語に興味がある人
- 仕事や職人技に打ち込む姿に感動する人
- 地味だけど奥深い題材を好む人
- 人間関係や成長物語に心を揺さぶられる人
- 辞書や本づくりのプロセスに関心がある人
- コミュニケーションの本質について考えたい人
この作品は、辞書編纂という一見地味な題材を扱いながらも、人間ドラマとしての奥行きが深く、読者の心に長く残る物語です。
専門的な仕事に打ち込む情熱や、様々な個性を持つ人々が一つの目標に向かって力を合わせる様子は、多くの人の共感を呼ぶでしょう。
『舟を編む』と類似した内容の小説3選
『舟を編む』の世界観や雰囲気に近い、おすすめの小説を3つ紹介します。
読書の幅を広げるきっかけにしてください。
『星を編む』(凪良ゆう著)
タイトルに「編む」という言葉が含まれているだけでなく、『舟を編む』と同様に、創造的な作業を通じて人々がつながっていく物語です。
人間関係の機微や、何かを作り上げる過程での葛藤と喜びが描かれており、『舟を編む』のファンにもおすすめです。
『エミリの小さな包丁』(森沢明夫著)
料理を通じて人々の心を温める物語。
『舟を編む』が辞書編纂という専門的な仕事を通じて人々をつなげたように、この小説も料理という創造的な作業を通じて人々の絆を描いています。
主人公が自分の才能を発見し成長していくという点でも共通点があります。
『竈稲荷の猫』(佐伯泰英著)
三味線職人を目指す若い職人の姿を描く物語。
『舟を編む』が辞書編纂という専門的な仕事を題材にしたように、この作品も伝統工芸の世界で夢を追いかける人々の姿を描いています。
職人技や専門知識への情熱、そして地道な努力の先にある達成感という点で類似点が見られます。
振り返り
『舟を編む』は辞書編纂という一見地味なテーマを扱いながらも、言葉の力や人とのつながりの大切さを伝える素晴らしい物語です。
この記事では、簡単な・短いあらすじから詳しいものまで段階的に紹介し、読書感想文を書く際のポイントや参考例も提供しました。
辞書は「言葉の海を渡る舟」であり、その舟を編む人々の情熱と苦労を描いたこの小説から、言葉の大切さや仕事への誇り、人との絆など、多くのことを学ぶことができます。
読書感想文を書く際には、言葉と辞書の奥深さ、馬締の成長と人間関係の変化、「舟を編む」という比喩的表現の3点を中心に据えると、作品の本質により深く迫ることができるでしょう。





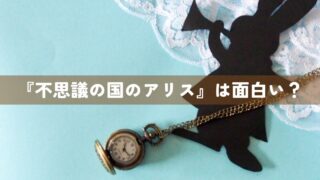





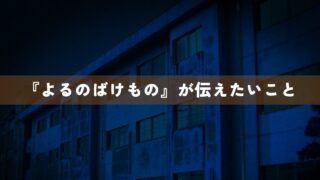




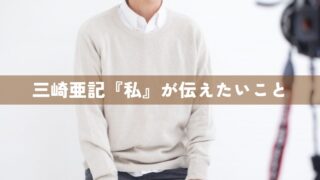

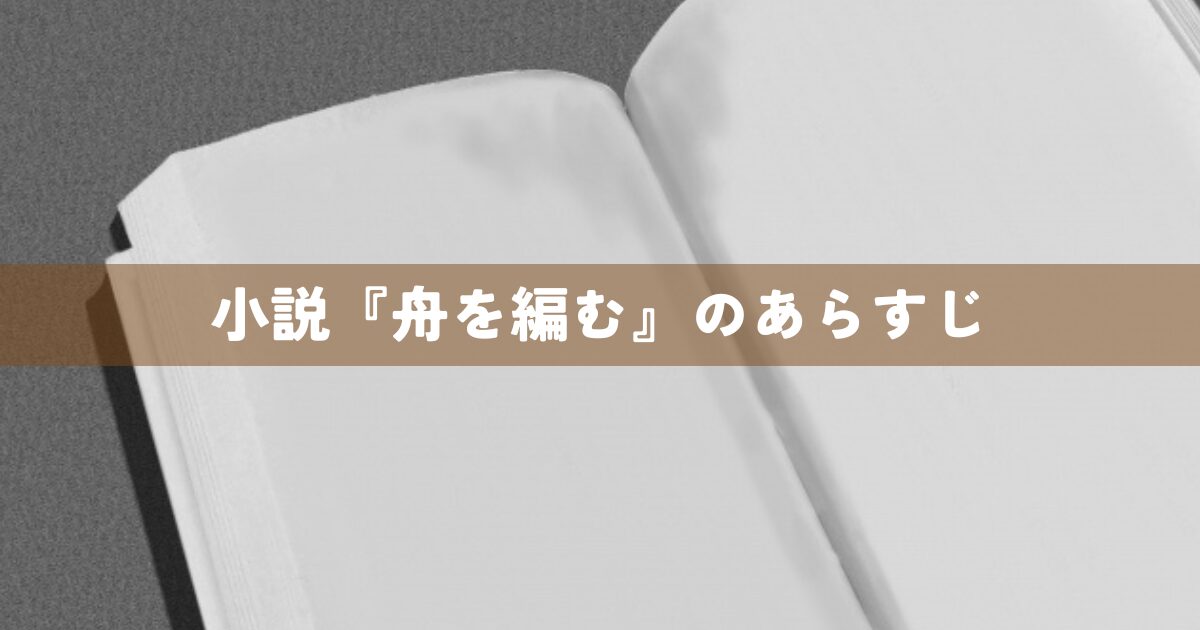
コメント