太宰治の傑作とされる短編小説『女生徒』のあらすじを紹介していきますよ。
『女生徒』は1939年に発表された太宰治の代表作の一つで、思春期の少女の繊細な心の動きを見事に描き出した作品。
私は年間100冊以上の本を読む読書好きですが、特に日本文学の名作には思い入れがあります。
この記事では、読書感想文を書く予定の学生のみなさんに向けて、『女生徒』のあらすじを「短く」「簡単に」そして詳しく紹介していきます。
また、読書感想文を書くうえでの重要ポイントや登場人物、読了時間の目安まで幅広くカバーしていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
『女生徒』の短くて簡単なあらすじ
『女生徒』の中間の長さのあらすじ
『女生徒』の詳しいあらすじ
十四歳の女学生が朝目覚めてから一日を過ごす様子を彼女の視点から描いた物語。亡き父の家で母と暮らす少女は、朝起きた時の感覚をかくれんぼで見つかった時や、箱の中から小さな箱が出てくる虚しさに例える。鏡の前で眼鏡をかけることを嫌がり、庭では愛犬ジャピイには優しく接する一方、汚れたカアには冷たい態度を示す。
朝食を一人で取り新聞を読んだ後、母親が他人の縁談の手伝いで出かけると、彼女は登校準備を始める。母から譲り受けた古い雨傘を持って家を出た少女は、傘から様々な想像を膨らませる。途中、神社の森で兵隊の痕跡である麦を見つけ、労働者たちとの不快な出会いを経験する。
電車の中では席を取られる出来事があり、吊革につかまりながら雑誌を読む。「若い女性の欠点」という記事を読みながら、自分の生き方や周囲の期待に応えようとする葛藤、個性を表現する恐れなどについて思索する。思春期特有の自己嫌悪や孤独感、社会への疑問が少女の繊細な感性を通して鮮やかに描き出された心理小説となっている。
『女生徒』の作品情報
太宰治の短編小説『女生徒』の基本情報をまとめました。
この作品がどのような背景で書かれたのか確認してくださいね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 太宰治 |
| 出版年 | 1939年(昭和14年) |
| 初出 | 『文學界』1939年4月号 |
| 単行本 | 『女生徒』(砂子屋書房、1939年7月20日) |
| 受賞歴 | 特になし(ただし川端康成など当時の文芸評論家から高く評価された) |
| ジャンル | 心理小説・独白体小説 |
| 主な舞台 | 女学生の家と通学路 |
| 時代背景 | 昭和初期 |
| 主なテーマ | 思春期の心理・自己認識・社会との関わり |
| 物語の特徴 | 女学生の一日を独白体で描いた心理小説 |
| 対象年齢 | 12歳以上(中学生以上) |
『女生徒』の主要な登場人物とその簡単な説明
『女生徒』に登場する人物は多くありませんが、それぞれが主人公の心理描写を深める重要な役割を果たしています。
以下の表で主要な登場人物を紹介しますね。
| 登場人物 | 説明 |
|---|---|
| 「私」(主人公) | 14歳の女学生。名前は明かされていない。思春期特有の揺れる感情や孤独感、自己嫌悪、未来への不安を抱えている。 |
| 母親 | 主人公と二人暮らしの未亡人。夫(主人公の父)とは死別している。娘に愛情を注ぎつつも、生活や家計を支えるために努力している。 |
| ジャピイ | 主人公が可愛がる飼い犬。毛並みが美しく、主人公のお気に入り。 |
| カア | もう一匹の飼い犬。汚れているため主人公から冷たく扱われる。主人公の意地悪さや自己嫌悪を象徴的に表す存在。 |
| 姉 | 物語には直接登場しないが、すでに嫁いでいることが言及される。 |
登場人物は少ないですが、それぞれが主人公の内面を映し出す鏡のような役割を持っています。
特に二匹の犬への態度の違いは、主人公の複雑な心理を象徴していて興味深いですね。
『女生徒』の文字数と読むのにかかる時間
『女生徒』はどのくらいの長さの作品なのか、読了時間の目安をまとめました。
読書感想文を書く前の計画を立てる参考にしてくださいね。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総文字数 | 約31,834文字 |
| 推定ページ数 | 約53ページ(1ページ600文字計算) |
| 平均読了時間 | 約64分(500文字/分の読書速度で計算) |
『女生徒』は短編小説なので、集中して読めば1〜2時間程度で読み終えることができます。
でも、主人公の心理描写が繊細で深いので、じっくり味わいながら読むことをおすすめします。
1日30分ずつ読むなら2日程度で読み終えられるでしょう。
『女生徒』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
読書感想文を書く際には、作品の本質をとらえることが大切です。
『女生徒』を読んで感想文を書くなら、以下の3つのポイントは絶対に外せません。
- 思春期特有の心情と葛藤
- 日常生活における繊細な観察
- 内的独白の表現技法
それぞれのポイントについて詳しく解説していきますね。
これらを押さえておけば、読書感想文の内容が深まり、高評価につながるでしょう。
『女生徒』における思春期特有の心情と葛藤
主人公の14歳の少女が抱える内面の揺らぎは、この作品の中心テーマの一つです。
鏡を見る場面では自分の容姿に対する不満、二匹の犬への態度の違いからは自分の意地悪さへの自覚と後悔が見られます。
感想文では、主人公が抱える孤独感や自己嫌悪、将来への漠然とした不安などについて、自分自身の経験と照らし合わせながら考察するとよいでしょう。
例えば、主人公が電車の中で読む「若い女性の欠点」という記事に対する反応からは、社会の期待に応えようとする葛藤と、それに反発する気持ちの両方が読み取れます。
思春期は自分のアイデンティティを模索する時期。
主人公の複雑な感情の描写に共感したポイントや、逆に違和感を覚えた部分を具体的に挙げながら、自分なりの解釈を展開してみましょう。
『女生徒』における日常生活の繊細な観察
この作品の魅力は、日常の何気ない出来事や風景を通して、主人公の内面世界を鮮やかに描き出している点にあります。
朝の目覚め、鏡を見る瞬間、庭での犬との触れ合い、電車での出来事など、一見すると平凡な日常が、少女の感性を通して特別な意味を持ち始めます。
例えば、母から受け継いだ古い雨傘への思いや、神社の森で見つけた麦への反応など、主人公は身の回りの出来事から様々な想像を膨らませます。
感想文では、作品中のこうした細かな描写に注目し、そこからどのような主人公の人柄や価値観が読み取れるかを分析すると良いでしょう。
日常の小さな変化や出来事に対する少女の繊細な反応や思考が、この物語の奥行きを作り出しています。
あなた自身の日常との共通点や違いを考えながら読むと、より深い考察ができるはずです。
『女生徒』における内的独白の表現技法
『女生徒』は「独白体」という形式で書かれています。
これは主人公の心の中で起こる思考の流れや感情の動きをそのまま文章化する手法で、読者は少女の内面世界に直接触れることができます。
例えば、主人公が朝起きた時の感覚を「かくれんぼで見つかった時のような感じ」や「箱の中から更に小さな箱が出てくる虚しさ」に例えるなど、独特の表現が多く用いられています。
こうした比喩表現や連想の飛躍から、少女の豊かな想像力や感性を読み取ることができるでしょう。
感想文では、太宰治がどのように少女の内面を読者に伝えているかという表現技法に着目し、それが読者にどのような印象や効果をもたらしているかを考察すると良いですね。
「意識の流れ」を記述する手法が、この作品の世界観をどう構築しているかを分析してみましょう。
※太宰治が『女生徒』を通じて伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『女生徒』の読書感想文の例(原稿用紙3枚強/約1400文字)
私は今回初めて太宰治の作品に触れた。『女生徒』は短い小説だが、14歳の少女の一日を通して描かれる心の動きが細かく丁寧に書かれていて、読み終わった後もずっと考えさせられた。
まず印象に残ったのは、主人公の複雑な感情表現だ。朝目覚めた時の感覚を「かくれんぼで見つかった時のような感じ」と表現するところから始まり、自分の眼鏡姿を嫌がるところ、二匹の犬への対応の違いなど、彼女の心は常に揺れ動いている。特に印象的だったのは犬に対する態度だ。きれいな犬「ジャピィ」には優しく接するのに、汚れた犬「カア」には冷たくする。そしてそんな自分を自覚して自己嫌悪に陥る。この矛盾した感情が思春期特有のものだと強く感じた。
私も中学生のとき、友達に対して気分によって態度を変えてしまうことがあり、後から「なんであんなことしたんだろう」と後悔することがよくあった。主人公の自分に対する厳しい視線と葛藤に、昔の自分を重ねて読むことができた。
次に心に残ったのは、日常の何気ない出来事への繊細な反応だ。電車で席を取られたこと、雑誌で読んだ「若い女性の欠点」という記事への反応など、ちょっとしたことから多くの思索が広がっていく様子が本当に生き生きと描かれている。特に、母親から譲られた古い雨傘への思いは、親子関係の機微を感じさせた。
私も日常の中で「あれはどうしてだろう」と考え込むことがある。例えば学校の休み時間に友達と話している時、ふと「この会話に意味はあるのかな」と考えてしまったり。主人公が日常の断片から様々な想像を膨らませる姿は、現代の私たちにも通じるものがあると思う。
作品の表現技法も印象的だった。最初は独白体という形式に戸惑ったが、読み進めるうちに少女の内面世界にどんどん引き込まれていった。思考が次々と連想を呼び、時には論理的な順序を無視して飛躍する様子は、人間の心の動きそのものだと感じた。「意識の流れ」を記述するこの手法によって、少女の豊かな感性や繊細な観察眼が鮮明に伝わってくる。
例えば、電車の中で「若い女性の欠点」という記事を読んでいる場面で、主人公は「個性を殺している」と言われることに対して複雑な反応を示す。個性を表現することへの恐れと、それでも自分らしくありたいという願望の間で揺れ動く様子が、彼女の言葉から直接伝わってきて胸に迫った。
この作品が書かれたのは1939年、今から80年以上も前だが、思春期の少女の心理描写は現代にも通じるものがある。SNSやスマホがない時代でも、自分の存在意義や社会との関係について悩む姿は変わらない。むしろ情報があふれる現代より、自分と向き合う時間が多かったからこそ、より深く自己を見つめられていたのかもしれないと思った。
『女生徒』を読んで、私は思春期という時期を客観的に見つめ直すことができた。自分の感情が揺れ動くことは特別なことではなく、誰もが通る道なのだと知り、少し安心した気持ちになった。また、日常の小さな出来事の中に、実は多くの意味や発見があることも気づかされた。
この作品は短いながらも、主人公の繊細な心の動きを通して人間の本質に迫る深い内容を持っている。太宰治が女性の視点をここまで繊細に描けることに驚くとともに、人間の心理を深く理解する作家の力量を感じた。80年以上前の作品でも今なお色あせない『女生徒』の魅力は、人間の本質を描き出すことに成功しているからだと思う。
『女生徒』はどんな人向けの小説か
『女生徒』は独特の魅力を持つ作品です。
どのような人に特におすすめできるか、考えてみました。
- 思春期の複雑な感情に共感したい人
- 繊細な心理描写を楽しみたい人
- 日常の小さな出来事に意味を見出したい人
- 内面の葛藤や自己理解に関心がある人
- 太宰治の文体や表現技法に興味がある人
『女生徒』は思春期の少女の揺れ動く心情を繊細に描いた作品なので、特に10代の読者には自分自身の感情を客観的に見つめる機会を与えてくれるでしょう。
また、心理学に興味がある人や、人間観察が好きな人にもおすすめ。
一見何気ない日常の出来事から広がる想像の世界や、自己と他者との関係性についての考察は、年齢や性別を問わず多くの読者の心に響くはずです。
太宰治の独特の文体や表現技法を味わいたい人にとっても、『女生徒』は入門として最適な一冊と言えますよ。
『女生徒』に類似した内容の小説3選
『女生徒』を読んで感動した方に、似たような魅力を持つ作品を紹介します。
思春期の心情や内面の葛藤を描いた以下の3作品もぜひ読んでみてくださいね。
『恥』 – 太宰治
同じく太宰治が書いた短編『恥』も、女性の内面を深く描写した作品です。
主人公の女性が抱える感情や悩みがリアルに表現され、日常の中での葛藤が印象的に描かれています。
『女生徒』と同様に、太宰独特の繊細な文体が光る作品で、人間の複雑な心理を鮮やかに描き出しています。
特に自己嫌悪や羞恥心といった感情に焦点を当てている点が『女生徒』と共通していて、併せて読むと太宰文学の魅力をより深く理解できるでしょう。
『風が強く吹いている』 – 佐藤多佳子
この青春小説では、主人公たちの成長や友情、そして孤独が描かれています。
思春期から青年期の心の動きや人間関係の複雑さに焦点が当てられていて、『女生徒』と同様に内面的な葛藤を持つキャラクターたちの物語が展開します。
陸上競技を題材にしていますが、その本質は若者たちの内面の成長物語。
『女生徒』とは時代や設定は異なりますが、繊細な心理描写や自己と向き合う姿勢という点で共通点があり、読者の共感を呼ぶ暖かさを持った作品です。
『コンビニ人間』 – 村田沙耶香
この小説は現代社会での生きづらさや、「常識」とは何かを問いかける内容です。
主人公は自分の生活スタイルが周囲と異なることに葛藤しながらも、独自の価値観を持って生きていきます。
『女生徒』の思春期特有の悩みとは年代は異なりますが、社会的な期待や規範に対する違和感、そして独自の感性を持つ主人公が周囲との関係に悩む点では共通するテーマがあります。
現代社会における孤独や疎外感を描いた作品として、『女生徒』の現代版とも言える小説です。

振り返り
この記事では太宰治の名作『女生徒』について、あらすじから読書感想文のポイント、似た作品の紹介まで幅広く解説してきました。
14歳の女学生の一日を描いたこの小説は、思春期特有の揺れ動く感情や孤独感、自己嫌悪などを繊細に描き出した心理小説。
主人公の内面世界を独白体で描く手法によって、読者は少女の心の動きを直接体験することができます。
読書感想文を書く際には「思春期特有の心情と葛藤」「日常生活における繊細な観察」「内的独白の表現技法」という3つのポイントに注目すると、より深い考察ができるでしょう。
短編小説ながらも深い内容を持つ『女生徒』は、思春期の複雑な感情に共感したい人や繊細な心理描写を楽しみたい人におすすめの一冊です。
ぜひ、じっくり味わいながら読んでみてくださいね。




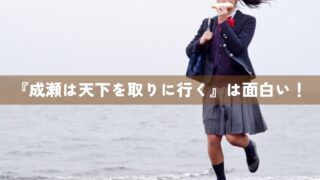
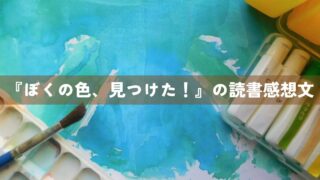
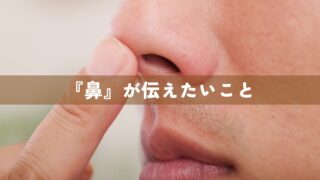

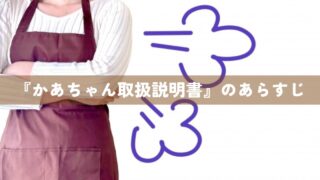

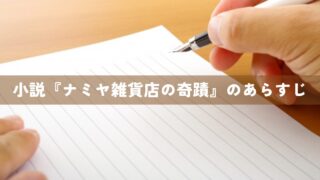





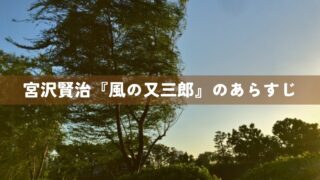
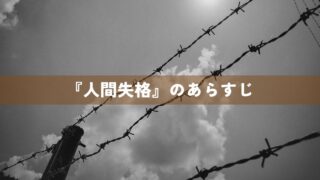
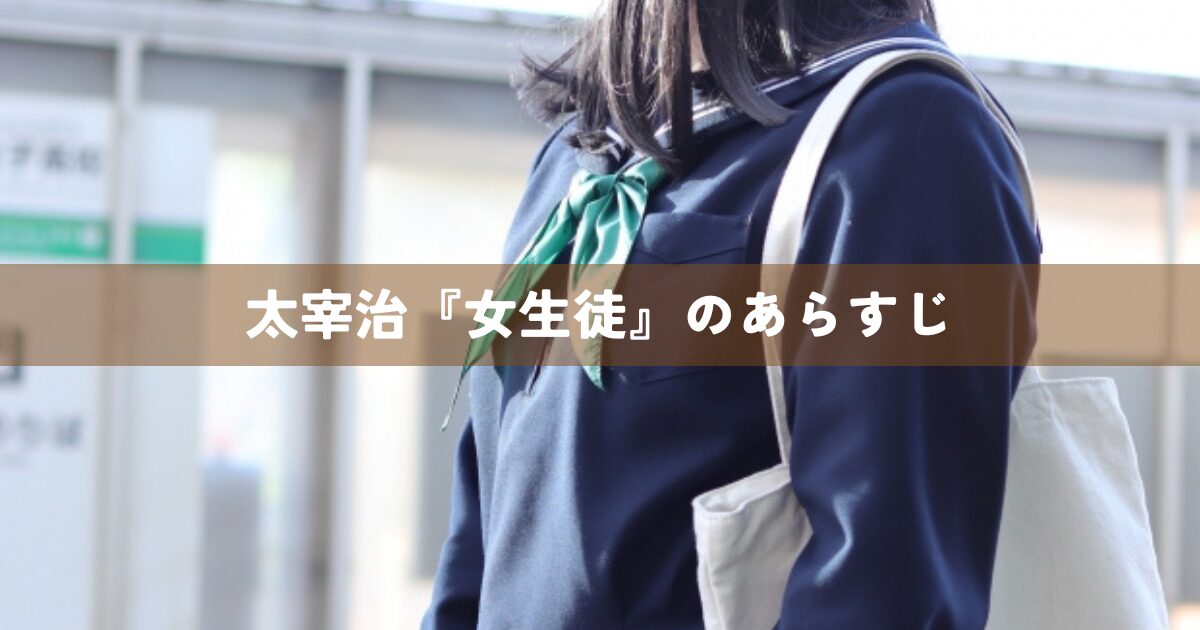
コメント