「辞書編集者の地味な仕事がそんなに面白いの?」
そう思っていませんか?私もそうでした。
本屋大賞を受賞した『舟を編む』を書店で手に取った時、「辞書作りの小説って…退屈そう」と思ったものです。
でも、読み始めてみると、これが驚くほど引き込まれる作品でした。
今思えば、あの時読み始めて本当に良かった。
この記事では、そんな『舟を編む』の魅力をとことん語ります。
「読むべきかどうか迷っている」という方へ、この小説の素晴らしさを熱く語っていきますね。
『舟を編む』は面白い小説か?
結論から言えば、『舟を編む』は間違いなく面白い作品です。
なぜこの小説が多くの読者を惹きつけるのか、その理由をまとめてみました。
- 個性的なキャラクターたちの魅力
- 辞書編纂という知られざる世界の面白さ
- 人間関係や成長の物語としての深み
- 言葉への愛が伝わってくる情熱
- 日常の中の感動が散りばめられた構成
それでは、一つずつ掘り下げていきましょう。
個性的なキャラクターたちの魅力
まず、主人公の馬締光也(まじめみつや)というキャラクターが素晴らしい。
大学で言語学を専攻し、言葉への鋭い感覚を持ちながらも、対人コミュニケーションが苦手という設定です。
彼が辞書編集部に引き抜かれ、そこで自分の才能を開花させていく姿は、読んでいて胸が熱くなります。
そして周囲のキャラクターたちも一筋縄ではいきません。
軽薄に見えて実は仕事熱心な同僚の西岡、定年間近の編集のベテラン荒木、そして老国語学者の松本。
こうした個性的な登場人物たちが織りなす人間模様が、読者を作品世界に引き込みます。
特に馬締と西岡のコントラストが絶妙で、性格も考え方も正反対の二人が互いに影響し合い、成長していく様子は見事としか言いようがありません。
また、馬締の恋愛相手となる林香具矢も魅力的なキャラクター。
板前見習いという設定も珍しく、彼女のまっすぐな性格が物語に彩りを加えています。
辞書編纂という知られざる世界の面白さ
「辞書作り」と聞くと、地味で退屈なイメージがあるかもしれません。
私もそう思っていました。
ところが、この小説を読むと、辞書編纂の世界がこれほど奥深く、そして情熱的なものだとは思いもよらなかったことに気づかされます。
例えば、一つの単語の定義を決めるために編集部全員で議論を交わす場面。
何気なく使っている言葉の定義を厳密に考えることがこれほど難しいのかと驚かされます。
また、23万語もの見出し語を一ヶ月かけて確認していく地道な作業の描写も印象的。
こうした辞書作りの細部が丁寧に描かれることで、普段何気なく使っている「辞書」という存在の重みを実感させられます。
三浦しをんの筆力は、こうした専門的な世界をわかりやすく、そして面白く伝える点にあります。
人間関係や成長の物語としての深み
この小説の魅力は、単に辞書作りを描いているだけではありません。
その過程で生まれる人間関係や、登場人物たちの成長が心を打ちます。
物語の構成も巧みで、前半と13年後を描いた後半で、キャラクターたちの変化が鮮やかに描き出されています。
例えば、初めは辞書に関心がなかった西岡が、次第に辞書作りに情熱を燃やすようになる過程。
また、馬締と香具矢の恋愛模様も繊細に描かれており、二人の関係性の変化が読む者の心を温かくします。
さらに、若手編集者の岸辺みどりが辞書作りに情熱を持ち始める様子など、様々な人間ドラマが展開されます。
この作品は、辞書という「モノ」を作る物語であると同時に、人が成長し、絆を深める物語でもあるのです。
言葉への愛が伝わってくる情熱
『舟を編む』を読んでいると、作者自身の言葉への愛情が伝わってきます。
それは登場人物たちを通して表現されているのですが、その情熱は読者の心にも火をつけます。
「辞書は言葉の海を渡る舟」という表現が作中に出てきますが、まさにこの小説そのものが、私たちを言葉の豊かな海へと誘ってくれる舟なのです。
馬締が何気ない言葉に敏感に反応し、その言葉の本質を見抜く場面は何度も出てきます。
そうした描写を通じて、私たち読者も普段何気なく使っている言葉の奥深さに気づかされるのです。
実際、この小説を読んだ後は、辞書を手に取る機会が増えました。
何気ない言葉の定義を調べてみたり、言葉の成り立ちに思いを馳せたり。
それまで道具でしかなかった辞書が、一冊の宝物に見えてくるから不思議です。
日常の中の感動が散りばめられた構成
この小説の素晴らしさは、大げさな展開やドラマチックな場面に頼らず、日常の中の小さな感動を積み重ねていくところにあります。
辞書という地味な題材を選びながらも、そこから生まれる喜びや苦労、達成感を丁寧に描き出しています。
例えば、長年の作業の末についに辞書が完成した時の喜びは、まるで自分のことのように感じられてしまって。
また、老学者の松本が辞書完成を見ることなく亡くなるシーンは、静かな悲しみに満ちています。
こうした日常の中の小さな感動の積み重ねが、読後に大きな満足感を与えてくれるのです。
時に笑い、時に考え、時に涙する。
そんな豊かな読書体験ができる作品は、そう多くはありません。
『舟を編む』の面白い場面(印象的・魅力的なシーン)
『舟を編む』には、心に残る名場面がたくさんあります。
ここでは特に印象的なシーンをいくつか紹介します。
- 馬締の辞書編集部への異動シーン
- 馬締の巻物の恋文による告白
- 23万語の見出し語確認作業
- 辞書『大渡海』完成の瞬間
馬締の辞書編集部への異動シーン
物語の始まりとなる、馬締が辞書編集部に異動するシーンは印象的です。
営業部では扱いづらい変わり者だった馬締が、荒木によって辞書編集部に引き抜かれる場面。
「あなたが営業部にいるのは宝の持ち腐れだ」と言われた時の馬締の表情が目に浮かびます。
そして辞書編集部の仕事場に足を踏み入れた馬締が、山積みの資料や辞書に囲まれた空間に圧倒される様子。
しかし同時に、自分の居場所を見つけたかのような安堵感も感じられます。
この場面は、物語全体の方向性を示す重要なシーンであると同時に、馬締というキャラクターの本質を表しています。
言葉に対する鋭敏な感覚と純粋な愛情を持ちながらも、それを活かす場所がなかった彼が、ようやく自分の才能を発揮できる場所を見つけた瞬間なんですね。
この先に待ち受ける様々な出来事の伏線となる、物語の原点とも言えるシーンです。
馬締の恋文による告白
馬締が香具矢に恋心を抱き、古風な恋文で告白するシーンは、この小説の中でも特に心温まる場面です。
言葉のプロフェッショナルである馬締が、自分の気持ちを表現するために選んだ方法が「毛筆によるラブレター」という古風な形式だったことに、彼の人柄がよく表れています。
現代的な恋愛観からすれば少し変わっていますが、そこがまた魅力的。
そして香具矢がその告白を受け入れる場面は、読んでいて思わず頬が緩んでしまいます。
この恋愛模様が、辞書作りという地味な仕事の物語に彩りを添え、作品全体のバランスを取っています。
二人の関係性が後半の13年後の場面につながっていくことも、物語構成上見事な伏線となっています。
23万語の見出し語確認作業
辞書編集部が23万語もの見出し語を一ヶ月かけて確認する作業の描写は、辞書作りの地道さを象徴するシーンです。
一般の読者には想像もつかないような作業量ですが、その膨大な作業を黙々とこなしていく編集部のメンバーたち。
特に馬締が一つ一つの言葉に向き合う真摯な姿勢は、読者に深い感銘を与えます。
この場面が素晴らしいのは、単調な作業の描写なのに、全く退屈さを感じさせないところ。
むしろ、言葉との真剣な対話の連続として描かれ、読者も言葉への愛情を共有できるようになっています。
この地道な作業の積み重ねが、最終的には一つの立派な辞書となって結実することを思うと、感慨深いものがあります。
辞書『大渡海』完成の瞬間
長い年月をかけて完成した辞書『大渡海』が、ついに世に出る瞬間の描写は、この小説の感動的なクライマックスです。
馬締をはじめとする編集部のメンバーたちの達成感と喜びが、読者の心にも直接届いてきます。
特に印象的なのは、完成した辞書を手に取る馬締の表情。
それまでの苦労や葛藤、そして喜びが凝縮された瞬間です。
また、この場面では既に亡くなった松本老学者の存在も感じられ、辞書の完成を見ることなく世を去った彼への思いも込められています。
「辞書は言葉の海を渡る舟」というタイトルの意味が、この場面で鮮明に伝わってきます。
馬締たちが長い時間をかけて「編んだ舟」が、ついに大海原へと漕ぎ出す瞬間はこの小説のピークともいえるシーンですね。
※『舟を編む』のあらすじはこちらの記事でご覧ください。
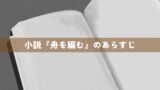
『舟を編む』の評価表
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| ストーリー | ★★★★☆ | 辞書作りという地味なテーマを 人間ドラマとして見事に描き切っている。 ただし劇的な展開を期待する人には物足りないかも。 |
| 感動度 | ★★★★★ | 静かな感動が積み重なり 読了後に大きな余韻を残す。 特に辞書完成シーンは涙なしには読めない。 |
| ミステリ性 | ★★☆☆☆ | 謎解きや伏線回収を楽しむ要素は少ない。 あくまで人間ドラマが中心の作品。 |
| ワクワク感 | ★★★☆☆ | 派手なアクションはないものの 辞書作りの各プロセスに独特の緊張感と高揚感がある。 |
| 満足度 | ★★★★★ | 読み終えた後の充実感は抜群。 言葉への見方が変わるほどの影響力を持つ作品。 |
『舟を編む』を読む前に知っておきたい予備知識
『舟を編む』をより深く楽しむために、いくつか知っておくと良いことがあります。
- 辞書編纂の基本的な流れ
- 作者・三浦しをんについて
- 本作の時代設定と構成
辞書編纂の基本的な流れ
『舟を編む』を読む前に、辞書がどのように作られるのかを大まかに知っておくと、物語をより深く楽しめます。
辞書の編纂作業は、見出し語の選定から始まり、用例の収集、語義の分析と執筆、校正・校閲という流れで進みます。
特に重要なのは、一つの言葉の「定義」をどう書くかという点。
言葉の意味を過不足なく伝えるのは、想像以上に難しい作業なんですね。
作中でも、一つの言葉の定義をめぐって編集者たちが議論を重ねる場面が何度も出てきます。
また、辞書編纂には膨大な時間がかかることも知っておくとよいでしょう。
作中の『大渡海』も、完成までに10年以上の歳月を要しています。
これは決して誇張ではなく、実際の辞書作りでも同様の時間がかかるものなんだそうですよ。
作者・三浦しをんについて
作者の三浦しをんは、様々なジャンルの小説を手がける多才な作家です。
この作品を書くにあたり、実際に岩波書店や小学館の辞書編集部を取材したそうです。
そのため、作中の辞書編集の描写は非常にリアリティがあります。
三浦しをんの特徴は、マイナーな題材や職業にスポットを当て、そこから人間ドラマを紡ぎ出す能力にあります。
彼女の他の作品、例えば『風が強く吹いている』(箱根駅伝)や『まほろ駅前多田便利軒』(便利屋)なども、一見地味な題材を選びながら、読者を引き込む力を持っていますね。
この『舟を編む』も、そうした彼女の真骨頂が発揮された作品と言えるでしょう。
本作の時代設定と構成
『舟を編む』は、時間軸が二つに分かれている点も特徴的。
前半は辞書『大渡海』の編纂が始まる時代、後半はそれから13年後の時代が描かれています。
この構成により、長期にわたる辞書編纂の過程と、それに関わる人々の変化や成長を描くことに成功しています。
また、作中の出版社「玄武書房」は架空の出版社ですが、日本の実在の大手出版社をモデルにしていると言われています。
このように、リアルとフィクションが絶妙に織り交ぜられた設定も、この作品の魅力の一つ。
時代設定についても、特定の年代は明示されていませんが、現代の日本が舞台となっており、読者が自然に物語世界に入り込めるよう工夫されています。
※『舟を編む』で作者が伝えたいことは以下の記事で考察しています。

『舟を編む』を面白くないと思う人のタイプ
どんなに素晴らしい作品でも、全ての人に響くわけではありません。
『舟を編む』がピッタリ合わない可能性がある読者のタイプを挙げてみます。
- アクションや派手な展開を求める人
- 言葉や国語に興味がない人
- 職業小説・仕事小説が苦手な人
派手な展開を求める人
『舟を編む』は、基本的に静かな物語です。
大きな事件や劇的な展開、派手なアクションシーンなどはほとんど出てきません。
辞書編纂という地道な作業の過程と、そこに関わる人々の小さな変化や成長が中心となっています。
そのため、ハラハラするようなサスペンスや、目が離せないような展開を期待する読者には、少し物足りなく感じるかもしれません。
例えば、ミステリーやサスペンス、アクション映画のような刺激を小説に求める人は、この作品のペースにフラストレーションを感じる可能性があります。
しかし、そうした派手さはなくとも、人間ドラマとしての深みや、言葉への愛情が伝わってくる魅力があることも確かです。
言葉や国語に興味がない人
この小説は、言葉や国語、辞書に対する興味や関心がある程度ないと、その魅力を十分に味わうことが難しいかもしれません。
作中では、言葉の定義や用法、語源といった話題が頻繁に登場します。
そうした言語学的な内容に興味がない読者にとっては、専門的に感じられる部分もあるでしょう。
特に、辞書の編集過程で交わされる専門的な議論や、言葉の微妙なニュアンスについての考察などは、言葉に対する感度が高くないと、少し退屈に感じる可能性もあります。
ただし、この作品は専門書ではなく小説なので、登場人物たちの人間関係や成長を楽しむという読み方もできます。
職業小説・仕事小説が苦手な人
『舟を編む』は典型的な「職業小説」「仕事小説」の一つです。
辞書編集という仕事に焦点を当て、その仕事に打ち込む人々の姿を描いています。
そのため、仕事や職業に関する小説自体が苦手、あるいは興味が持てない読者にとっては、テーマ自体が魅力的に映らない可能性があります。
また、仕事に対する情熱や、専門的な仕事へのこだわりといった価値観に共感できないと、登場人物たちの行動や考え方に違和感を覚えるかもしれません。
しかし、一見地味に見える仕事の中にも、人間ドラマがあり、成長があり、感動があることを教えてくれるのが、この作品の大きな魅力でもあります。
辞書の魅力に気づかせてくれる『舟を編む』は面白い!
『舟を編む』は、辞書編集という一見地味な世界を舞台に、豊かな人間ドラマを描いた素晴らしい小説です。
個性的なキャラクターたち、言葉への愛情、そして長い時間をかけた成長と達成の物語。
この作品を読むと、私たちが日頃何気なく使っている「言葉」や「辞書」の持つ奥深さに気づかされます。
確かに、派手なアクションや劇的な展開を期待する人には物足りないかもしれません。
しかし、静かな感動や人間の成長を描いた物語が好きな人には、間違いなく心に残る一冊となるでしょう。
私自身、この小説を読んだ後、辞書を手に取る機会が増えました。
何気ない言葉の定義を調べることが、新しい発見や喜びにつながることを知ったからです。
「辞書は言葉の海を渡る舟」。
この物語のタイトルが示す通り、言葉の海を旅する素晴らしい体験を、あなたもぜひ味わってみてください。
※『船を編む』の読書感想文の中高生向けの書き方と例文はこちらで解説しています。
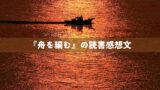



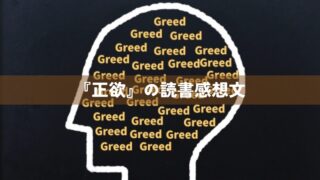
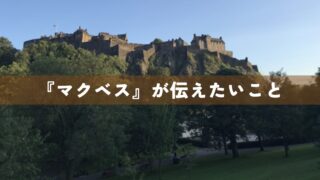



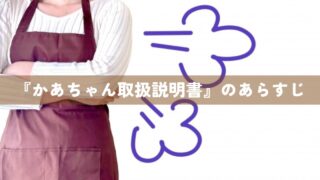
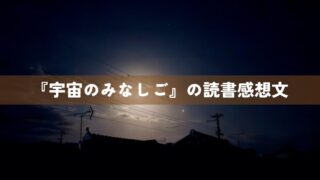




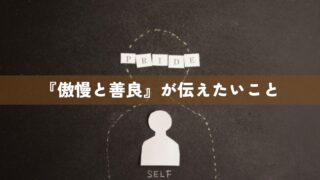
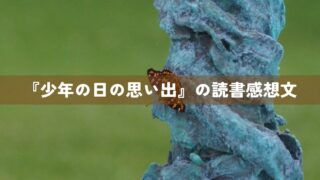

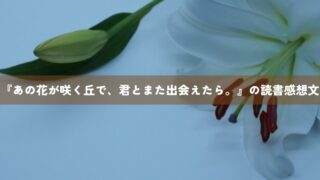
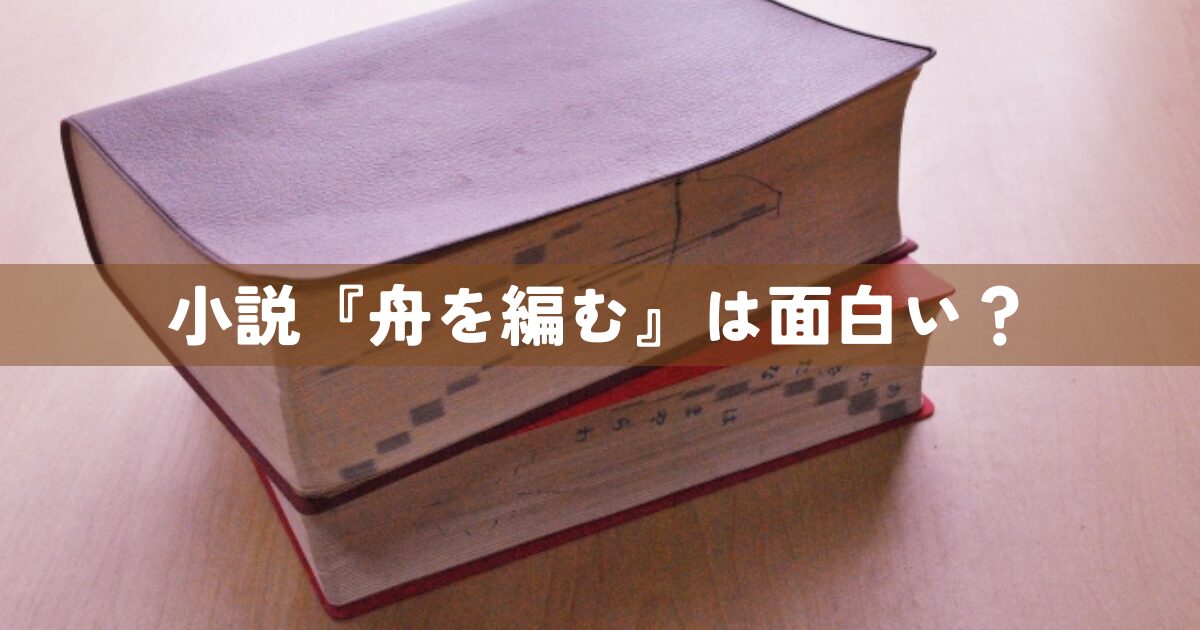
コメント