芥川龍之介『芋粥』のあらすじを簡単・ネタバレありで解説していきますね。
『芋粥』は1916年に発表された芥川龍之介の代表的な短編小説で、『今昔物語集』を元にした古典翻案作品として知られています。
身分の低い侍が抱く「芋粥を飽きるほど食べたい」という小さな夢と、その夢が叶った時の皮肉な結末を描いた作品です。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、要約から登場人物の解説まで丁寧にお伝えしていきます。
人間の欲望の本質や満たされることの虚しさを鋭く描いた傑作を、一緒に読み解いていきましょう。
芥川龍之介『芋粥』のあらすじを簡単に短く(ネタバレ)
芥川龍之介『芋粥』のあらすじを詳しく(ネタバレ)
時は平安時代の元慶か仁和年間。
主人公の五位は摂政・藤原基経の役所に勤める四十歳を過ぎた小役人である。
風采があがらず才覚もない彼は、日頃から同僚たちにばかにされ、道で遊ぶ子どもたちにも罵られる惨めな日常を送っていた。
そんな五位の唯一の夢は、芋粥を飽きるほど食べることだった。
甘葛の汁で煮た芋粥は当時の贅沢品で、五位のような身分では年に一度口にできるかどうかの高級品であった。
ある宴席で五位は「いつになったら芋粥に飽きることができるだろう」とつぶやいてしまう。
それを聞いた将軍・藤原利仁が「では私が飽きるほど食べさせてやろう」と申し出た。
戸惑いながらも五位はその申し出を受け入れる。
後日、利仁に連れられて旅に出た五位は、予告もなく利仁の領地である敦賀まで連れて行かれた。
長い旅路の末、利仁の館に着いた五位の心は既に曇っていた。
翌朝、大鍋いっぱいの芋粥を目の前にした五位は、なぜか食欲を完全に失ってしまった。
長年夢見ていた芋粥への執着は跡形もなく消え去り、五位は虚しさだけを感じるのだった。
『芋粥』のあらすじを理解するための用語解説
『芋粥』に登場する重要な用語をまとめました。
これらを理解することで、『芋粥』の世界観がより深く理解できるでしょう。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 芋粥 | 山の芋を切り入れ、甘葛の汁で煮た粥。 当時は上流階級のごちそうで、 庶民が口にできるのは稀だった。 |
| 五位 | 平安時代の下級官吏の官位名。 主人公の社会的身分は決して高くない。 |
| 甘葛 | 古代日本で使われた高価な甘味料。 芋粥の味付けに用いられる贅沢品だった。 |
| 今昔物語集 | 『芋粥』の元となった平安時代の説話集。 芥川はここから題材を得て独自の小説を創作した。 |
| 元慶・仁和年間 | 平安時代前期の年号。 物語の時代背景を示している。 |
これらの用語を押さえることで、身分社会の厳しさや主人公の置かれた状況がより鮮明に理解できます。
『芋粥』の感想
芥川龍之介の『芋粥』を読み終えて、何だかほろ苦い気持ちになりました。こんなに身につまされる話だったとは!
主人公の五位って、今でいう「負け組」みたいな下級武士なんですよね。日々の生活も大変なのに、彼が持つ唯一の夢が「芋粥を思う存分食べたい」という、なんとも地味で切ない願望。
これが妙にリアルで、思わず「わかるなぁ」と頷いてしまいました。特に、その恥ずかしい願いをポロッと口にしちゃうシーンは、誰にでもある失敗じゃないですか?そんな人間らしさが染みます。
そして、いよいよ夢が叶う瞬間!…なのに、なぜか五位は食べる気が失せちゃうんです。この「あれ?なんかイメージと違う…」という感覚、めちゃくちゃ共感できませんか?
新しいスマホやゲームを買った時の「思ったほどうテンションが上がらない(楽しくない)」みたいな。芥川さん、人間の心理をズバッと見抜いてます。
藤原利仁という金持ちキャラも面白くて、「いい人なのか意地悪なのかよくわからない」というモヤモヤ感。現代にもいそうな、表面上は親切だけど、ちょっと上から目線の人。
文章も読みやすくて、平安時代の話なのに全然古臭くない!むしろ今読んでも「あるある~」と思える場面がたくさん。短い話なのに、読み終わった後もずっと考えさせられました。
最後は少しせつない気持ちになるけど、「夢は叶えない方がいいのかな?」なんて考えちゃったり。でも、そんな複雑な余韻が残る作品って、やっぱり名作なんですよね。
今の時代にも響く、人間の本質を描いた一冊です。
『芋粥』の作品情報
『芋粥』の基本的な作品情報をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 芥川龍之介 |
| 出版年 | 1916年(大正5年) |
| 初出 | 『新小説』 |
| ジャンル | 短編小説・古典翻案 |
| 主な舞台 | 平安時代の都と敦賀 |
| 時代背景 | 平安時代前期(元慶・仁和年間) |
| 主なテーマ | 人間の欲望、満たされることの虚しさ |
| 物語の特徴 | 皮肉な結末、緻密な心理描写 |
| 対象年齢 | 高校生以上 |
| 青空文庫 | 収録済み(こちら) |
『今昔物語集』を原典とした古典翻案作品として、芥川龍之介の代表作の一つに数えられています。
『芋粥』の主要な登場人物とその簡単な説明
『芋粥』に登場する主要な人物たちをご紹介します。
それぞれの人物が物語の中で重要な役割を果たしています。
| 人物名 | 説明 |
|---|---|
| 五位 | 主人公。 身分の低い侍で、みすぼらしく意気地がない。 芋粥を飽きるほど食べることが夢。 |
| 藤原利仁 | 五位の夢を聞いて屋敷に招く将軍。 善意を装いながら、どこか嘲弄の気配を持つ。 |
| 同僚たち | 五位を日常的に嘲笑う人々。 盃に尿を混ぜるなどの意地悪な悪戯を繰り返す。 |
| 子どもたち | 五位を馬鹿にして暴言を投げかける。 侍社会の下層に厳しい存在として描かれる。 |
| 無位の侍 | ただ一人、五位を陰で敬う誠実な人物。 物語の中では脇役だが印象的な存在。 |
これらの人物を通して、平安時代の身分社会の厳しさと人間関係の複雑さが描かれています。
『芋粥』の読了時間の目安
『芋粥』の読了時間について説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字数 | 約14,800文字 |
| 推定ページ数 | 約25ページ |
| 読了時間 | 約30分 |
| 読書日数 | 1日で読める |
| 読みやすさ | やや難しい(古典調の文体) |
短編小説なので1日で読み切れる分量です。
ただし、平安時代の設定や古典調の文体に慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。
じっくり読み込むことで、芥川龍之介の巧妙な心理描写を味わえるでしょう。
『芋粥』はどんな人向けの小説か?
『芋粥』は以下のような人に特におすすめです。
- 人間の心理や欲望について深く考えたい人
- 皮肉や諷刺の効いた文学作品を楽しみたい人
- 短編小説の技巧を鑑賞したい人
特に人間の欲望の本質について考察したい人や、芥川龍之介らしい乾いたユーモアを味わいたい人にはぴったりの作品です。
また、平安時代の歴史や文化に興味がある人にも楽しめるでしょう。
一方で、明るい話を求める人や、ハッピーエンドを期待する人にはあまり向かないかもしれません。
芥川独特の冷徹な視点と皮肉な結末は、読む人を選ぶ面もあります。
あの本が好きなら『芋粥』も好きかも?似ている小説3選
『芋粥』と共通のテーマや作風を持つ作品をご紹介します。
同じような人間の本質を描いた作品がお好みの方は、きっと楽しめるはずです。
ジュール・ルナール『にんじん』
『にんじん』は、冷遇される少年「にんじん」の日常と内面を描いた作品です。
満たされない承認欲求や愛情への飢えという点で、『芋粥』の五位の欲望に通じるものがあります。
五位が芋粥という物質的な欲求に囚われる一方、「にんじん」は家庭内の愛情を渇望しています。
どちらも叶わない、または叶っても満たされない人間の根源的な欲望を描いている点で共通しています。
夏目漱石『坊っちゃん』
『坊っちゃん』は、現代から見るとユーモラスで諷刺的な側面が強い作品です。
『芋粥』が持つ人間の滑稽さや世間に対する皮肉な視点に通じるものがあります。
主人公の坊っちゃんは不器用ながらも正義感を貫こうとしますが、その行動はしばしば周囲とのズレを生み出します。
『芋粥』が五位の欲望を通して人間の本質を暴くように、『坊っちゃん』も主人公の行動を通して社会の欺瞞を暴いています。

太宰治『富嶽百景』
『富嶽百景』は、太宰治自身の内面的な葛藤や満たされない自己肯定感を描いた作品です。
『芋粥』の五位が芋粥への執着を通して自己の存在意義を見出そうとするように、『富嶽百景』の語り手も特定の場所や状況を通して自身の生き方を見つめ直そうとします。
その試みが必ずしも完全な満足をもたらさないという点で、欲望や期待が完全に満たされない人間の本質を描いています。
太宰特有の自虐的なユーモアや皮肉も、芥川に通じる部分があるでしょう。

振り返り
『芋粥』は、人間の欲望の本質と満たされることの虚しさを鋭く描いた芥川龍之介の傑作です。
身分の低い侍・五位の小さな夢とその皮肉な結末を通して、私たちの心の奥底にある普遍的な感情を見事に表現しています。
短編小説としての完成度も高く、無駄のない構成と美しい文章で読者を魅了します。
読書感想文を書く際には、五位の心境変化や物語に込められた人間観察の深さに注目してみてください。
きっと多くの気づきが得られるはずです。
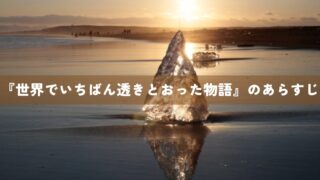
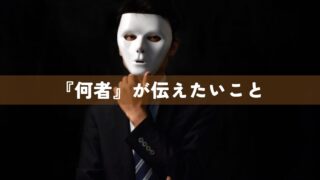



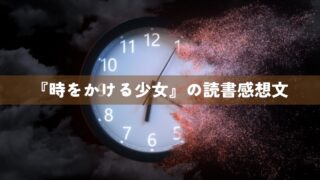

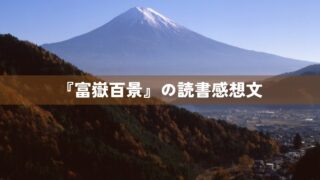

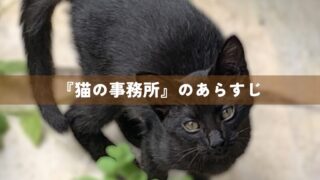

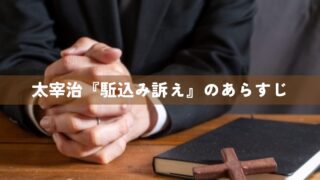

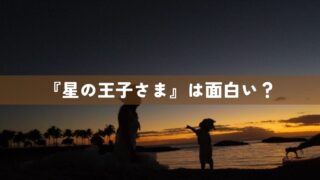
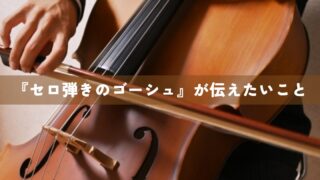
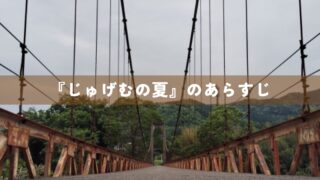
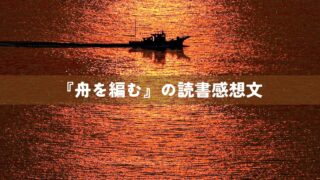
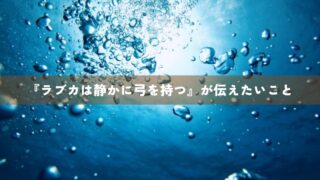
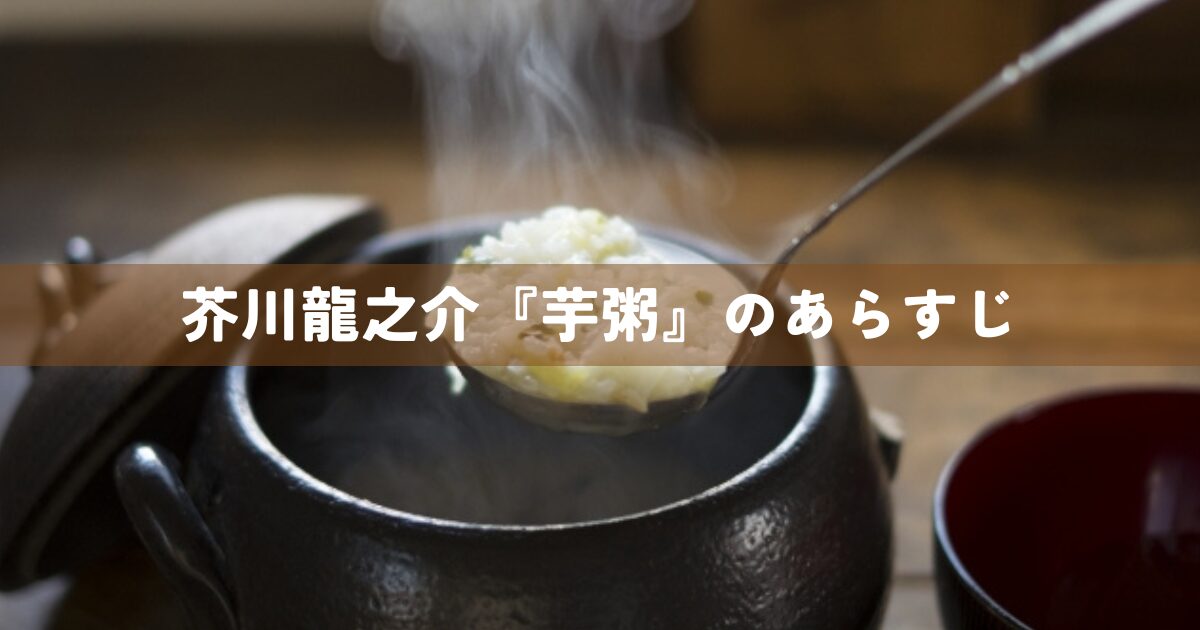
コメント