第71回青少年読書感想文全国コンクール中学校の部課題図書に選ばれた天川栄人さんの『わたしは食べるのが下手』のあらすじと感想をご紹介していきますね。
『わたしは食べるのが下手』は会食恐怖症と摂食障害という食にかかわる悩みを抱える2人の中学1年生が、給食改革に乗り出す物語です。
年間100冊以上の本を読む私が読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、簡単なあらすじから詳しい内容まで、丁寧に解説していきますよ。
それでは、さっそく進めていきましょう。
天川栄人『わたしは食べるのが下手』のあらすじを短く簡単に(ネタバレなし)
天川栄人『わたしは食べるのが下手』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
『わたしは食べるのが下手』のあらすじを理解するための用語解説
『わたしは食べるのが下手』をより深く理解するために、重要な用語を解説しますね。
これらの用語を理解しておくと、登場人物の心情や行動がより分かりやすくなりますよ。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 会食恐怖症 | 人前で食べることに不安や恐怖を感じ、 実際に食事が進まなくなる心の病気。 葵の主な悩みであり、給食の時などに発症する。 |
| 摂食障害(過食嘔吐) | 食べ物を大量に食べるが、 体重増加への恐怖や罪悪感から嘔吐してしまう障害。 咲子の抱える問題である。 |
| 給食改革 | 無理に食べることを強いる学校の給食制度に対し、 葵と咲子が新しい在り方を模索し活動するプロジェクト。 生徒主体で意見を出し合うなど、 食事の時間を前向きに捉える方法を探る。 |
| 保健室登校 | クラスでの給食がつらいとき、 保健室で登校や食事をすることが多い咲子の生活スタイル。 |
『わたしは食べるのが下手』の感想
この作品を読んで最初に思ったのは、今の子どもたちが抱える「食」への気持ちって、すごく複雑なんだなぁということ。
会食恐怖症って言葉は知ってたけど、葵ちゃんを通して、人前で食べることがどれだけつらいことなのか、リアルに感じることができました。給食の時間が「楽しい時間」じゃなくて「地獄の時間」になっちゃう子がいるって、ほんとに胸が痛みますよね。
それから、咲子ちゃんの摂食障害も、ただ「食べ過ぎて吐く」っていう単純なものじゃなくて、見た目へのこだわりや、お母さんとの関係とか、いろんな背景があることがていねいに描かれていて良かったです。
特に心に残ったのは、2人が給食改革プロジェクトで「作る側」の視点を知るシーン。私も料理するとき「おいしく食べてほしいな」「元気になってほしいな」って思いながら作るんですが、まさにそんな気持ちが作品の中で表現されていて、すごく共感しちゃいました!
食べる人と作る人、お互いの気持ちや願いを理解することで、2人の心境が変わっていく様子は、読んでいて心があったかくなりましたよ。
あと、ラマワティっていうイスラム教のキャラクターが出てくることで、宗教的な理由で食べられないものがある人への理解も深まりますよね。「みんな同じもの食べなきゃ」っていう固定観念から、「みんな違っていいんだ」っていう多様性を認める考え方への変化は、今の社会ですごく大事なメッセージだなって思いました。
橘川先生っていうキャラクターもよかったな~。最初は厳しそうな先生だけど、生徒たちの活動を応援して、ちゃんとアドバイスをくれる大人として描かれていて。こういう大人が子どもたちのそばにいることって、ほんとに大切だなって改めて感じました。
正直なところ、現実にはもっと複雑で、簡単には解決できない問題だとも思うんですよね。会食恐怖症や摂食障害は、専門家の治療が必要なこともあるし、学校の取り組みだけで解決できるわけじゃないかもしれません。
それでも、この作品が投げかける「食事って何だろう?」「給食って何のためにあるの?」っていう問いかけは、すごく価値があると思います。
文章も中学生が読みやすくて、重いテーマなのに希望が感じられる内容になっているのがいいですよね。
大人として読みましたが、同じような悩みを抱える子どもたちにとって、きっと心の支えになる作品だなって思いました。
※『わたしは食べるのが下手』の読書感想文の書き方と例文はこちらでご紹介しています。

『わたしは食べるのが下手』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 天川栄人 |
| 出版年 | 2024年 |
| 出版社 | 小峰書店 |
| 受賞歴 | 第71回青少年読書感想文全国コンクール 中学校の部課題図書 |
| ジャンル | 現代小説・青春小説 |
| 主な舞台 | 中学校・保健室 |
| 時代背景 | 現代日本 |
| 主なテーマ | 食の悩み・多様性・自己受容・友情 |
| 物語の特徴 | 会食恐怖症と摂食障害を扱った社会派作品 |
| 対象年齢 | 中学生以上 |
『わたしは食べるのが下手』の主要な登場人物とその簡単な説明
『わたしは食べるのが下手』の重要な登場人物たちを紹介しますね。
それぞれのキャラクターが物語にどんな役割を果たしているか理解できますよ。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| 小林葵 | 中学1年生の女子。 会食恐怖症で給食の時間に強いストレスを感じている。 物語の主人公の1人。 |
| 遠藤咲子 | 葵のクラスメイトで保健室登校をしている。 摂食障害で過食嘔吐を繰り返している。 強気な発言をするがコンプレックスを抱えている。 |
| ラマワティ | 葵のクラスメイトでインドネシア人の女子。 イスラム教徒のため学校給食で食べられない食材がある。 給食改革に賛同する。 |
| 久野浩平(コッペ) | 葵のクラスメイト。 明るくお調子者で給食が大好き。 「コッペ」と呼ばれている。 |
| 橘川先生 | 学校の栄養教諭。 給食の重要性を伝えつつ、 生徒たちの活動にアドバイスを与える。 大人の理解者として重要な役割を果たす。 |
『わたしは食べるのが下手』の読了時間の目安
『わたしは食べるのが下手』がどのくらいの時間で読み終えられるか、目安をまとめました。
読書のペースは人それぞれですが、参考にしてくださいね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ページ数 | 254ページ |
| 推定文字数 | 約152,400文字 |
| 読了時間の目安 | 約5時間 |
| 1日1時間読む場合 | 5日間 |
| 読みやすさ | 中学生向けで読みやすい文章 |
文章が分かりやすく、ストーリーも引き込まれる内容なので、思ったより早く読み進められると思いますよ。
『わたしは食べるのが下手』はどんな人向けの小説か?
『わたしは食べるのが下手』がどんな人に特におすすめできるか、私なりの見解をまとめてみました。
以下のような人には特に響く内容だと思います。
- 食事や人間関係に悩みを抱える中高生
- 多様性や個性を大切にしたいと考える人
- 現代の子どもたちが抱える問題に関心のある保護者や教育関係者
逆に、明るくて軽いストーリーを求める人や、深刻なテーマを扱った作品が苦手な人には、少し重く感じられるかもしれません。
でも、最終的には希望を感じられる内容になっているので、多くの人に読んでもらいたい作品ですね。
あの本が好きなら『わたしは食べるのが下手』も好きかも?似ている小説3選
『わたしは食べるのが下手』が気に入った方におすすめの、似たテーマや雰囲気を持つ小説を紹介しますね。
どれも「普通」ではない主人公が自分らしさを見つけていく物語です。
『コンビニ人間』村田沙耶香
コンビニで働く36歳の女性が主人公の物語です。
周囲から「普通」ではないと見られる主人公が、自分なりの生き方を貫く姿が描かれています。
『わたしは食べるのが下手』と同様に、社会の求める「普通」とは何かを問いかける作品ですね。

『ふがいない僕は空を見た』窪美澄
複数の登場人物がそれぞれに心の不器用さや満たされない思いを抱えながら生きている物語です。
「食べるのが下手」という個人の特性と同じように、登場人物たちの「普通ではない」部分が描かれ、そこからの解放を模索する点が共通しています。
『星の子』今村夏子
特殊な家庭環境で育つ主人公が、世間とのズレに戸惑いながら成長していく物語です。
主人公の意志とは関係なく生まれる「普通ではない」特性に悩む点や、幼い視点から描かれる日常の違和感が、やがて自己受容へと繋がっていく過程が『わたしは食べるのが下手』と通じるものがありますよ。
振り返り
『わたしは食べるのが下手』は、会食恐怖症と摂食障害という現代的な問題を扱いながら、食を通じた人間関係や自己受容を描いた心温まる作品でした。
天川栄人さんが丁寧に描いた登場人物たちの成長は、読む人に希望と勇気を与えてくれるでしょう。
課題図書として選ばれたのも納得の、社会性と文学性を兼ね備えた優れた小説だと思います。
読書感想文を書く際は、自分自身の食体験や人間関係と照らし合わせながら、感想をまとめてみてくださいね。

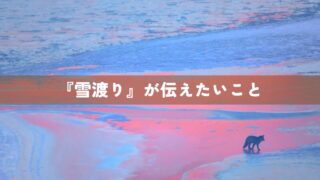


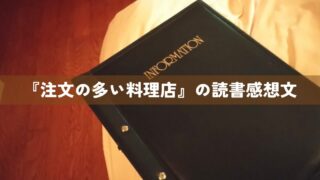

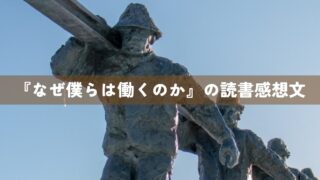


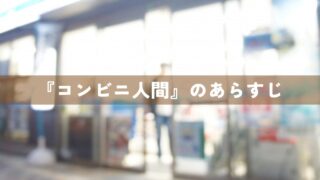
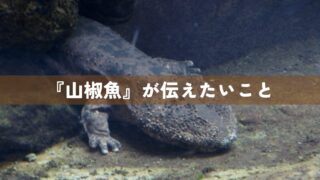

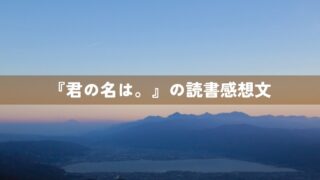
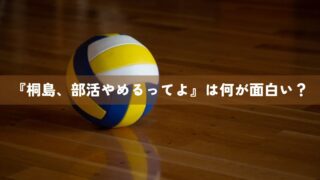


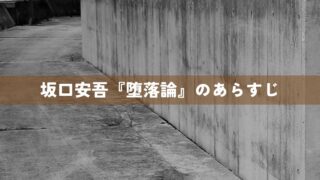


コメント
「わたしは食べるのが下手」は、中学生版の「正欲」でした。
いろんな本を読んでいると、意外な関連性が見つかって面白いですよね。