今日は小川洋子さんの名作『博士の愛した数式』のあらすじについてご紹介していきますよ。
この小説は80分しか記憶が持続しない元数学者と家政婦の「私」、そして「私」の息子「ルート」との心温まる交流を描いた感動作。
私自身、年間100冊以上の本を読む中でも特に心に残った一冊で、第1回本屋大賞を受賞した名作です。
短くて簡単・簡潔なあらすじから登場人物の紹介まで、わかりやすくまとめていきますね。
『博士の愛した数式』の短くて簡潔なあらすじ
交通事故で記憶が80分しか持続しない元数学者「博士」のもとに派遣された家政婦「私」。
彼女の10歳の息子「ルート」も加わり、数学と野球を通じて絆を深めていく三人だったが、博士の義姉の決断により、その関係は終わりを告げられる。
しかし、ルートの勇気ある行動が状況を変えていく。
『博士の愛した数式』の簡単なあらすじ
交通事故で記憶が80分しか持続しない64歳の元数学者「博士」のもとに派遣された28歳の家政婦「私」。
初めは戸惑いながらも、博士の数学への情熱と阪神タイガースへの愛に触れ、「私」の10歳の息子「ルート」も加わって三人の絆は深まっていった。
だが博士の義姉の突然の宣告により、その関係は終わりを告げられる。
しかし、ルートの勇気ある行動が、その後の三人の関係を思いがけない方向へ導いていく。
『博士の愛した数式』の詳しいあらすじ
28歳のシングルマザーである「私」は、新しい家政婦として64歳の元数学者「博士」の家に派遣された。
博士は交通事故により脳に障害を負い、新しい記憶が80分しか持続しないという状態だった。
数学と阪神タイガースを愛する博士は、初めは「私」に対して冷淡だったが、次第に打ち解けていく。
「私」の10歳の息子「ルート」も博士の家に来るようになり、博士はルートに数学を教え、二人は阪神タイガースのラジオ中継を一緒に聴いて楽しんだ。
三人の絆が深まる中、突然博士の義姉から「私」の仕事を終わらせるという宣告がなされる。
諦めかけた「私」だったが、ルートの「博士に会いたい」という強い思いと行動が、三人の関係を再び結びつけるきっかけとなるのだった。
『博士の愛した数式』の作品情報
『博士の愛した数式』の基本情報をまとめました。
| 作者 | 小川洋子 |
|---|---|
| 出版年 | 2003年8月30日 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 受賞歴 | 第1回本屋大賞、第55回読売文学賞 |
| ジャンル | 文学・小説 |
| 主な舞台 | 博士の家 |
| 時代背景 | 現代日本 |
| 主なテーマ | 記憶、家族の絆、数学の美しさ |
| 物語の特徴 | 数学と人間関係を融合させた心温まるストーリー |
| 対象年齢 | 中学生以上 |
主要な登場人物
『博士の愛した数式』に登場する主な人物たちをご紹介します。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| 博士 | 64歳。元数学(整数論)教授。 交通事故で新しい記憶が80分しか持続しない。 数学と子どもと阪神タイガースを愛している。 |
| 私 | 28歳。シングルマザーの家政婦。 博士の家で働くことになり、 次第に博士の数学への情熱や優しさに 尊敬と親しみを抱くようになる。 |
| ルート | 10歳の小学5年生。「私」の息子。 頭が平らなので博士から「ルート」と名付けられる。 阪神タイガースのファンで博士と仲良くなる。 |
| 未亡人 | 72歳。博士の義姉(博士の兄の妻)。 交通事故のせいで足が悪い。博士の面倒を見ている。 |
文字数と読了時間
『博士の愛した数式』の文字数と読むのにかかる時間の目安です。
| 文字数 | 約152,000文字(253ページ/単行本) |
|---|---|
| 読了時間 | 約5時間(1分間に500字で計算) |
| 1日あたり | 1日1時間で5日間 |
| 読みやすさ | 数学の話が出てきますが、 専門知識がなくても楽しめる簡潔な文体 |
比較的読みやすい文体で書かれているので、数学が苦手な人でも安心して読めますよ。
どんな人向けの小説?
『博士の愛した数式』はさまざまな興味や関心を持つ人にとって魅力的な作品です。
- 数学や科学に興味がある人
- 人間関係や感情の描写を楽しみたい人
- 記憶や時間の流れについて考えたい人
- 温かい物語を求めている人
- 非伝統的な「家族」の形に関心がある人
特に数学が苦手でも楽しめる内容になっているので、中学生から大人まで幅広い年齢層におすすめできます。
静かな感動を求める人に特に響く作品ですよ。
※『博士の愛した数式』が伝えたいことはこちらで考察しています。

本作品と似ている小説3選
『博士の愛した数式』を読んで感動した方におすすめの、テーマや雰囲気が似ている作品を紹介します。
『数学ガール』シリーズ(結城浩)
数学の美しさを描いたこのシリーズは、『博士の愛した数式』と同様に、数学の魅力を物語を通して伝えてくれます。
主人公の高校生が数学の問題解決を通じて仲間と交流し、成長していく様子が描かれていて、数学という切り口から人間関係を描く点が共通しています。
『海辺のカフカ』(村上春樹)
複数の人物の物語が交錯し、幻想的な要素や哲学的な問いかけが展開される作品です。
『博士の愛した数式』と同様に、心のつながりが重要なテーマとなっており、自分自身のアイデンティティについての探求が印象的です。

『コンビニ人間』(村田沙耶香)
社会との接点を持たない主人公が、自らの選択と生き方を模索する物語です。
『博士の愛した数式』とは設定こそ異なりますが、独自の価値観を持つキャラクターの内面描写や、人間関係の探求という点で共通点があります。

振り返り
『博士の愛した数式』のあらすじをお伝えしてきました。
80分しか記憶が持続しない博士と家政婦の「私」、息子の「ルート」との交流を描いたこの小説は、記憶を超えた心のつながりの美しさを教えてくれます。
数学を通じた人間関係の描写、記憶障害と純粋な愛情、そして非伝統的な家族の形など、読書感想文を書く際のポイントも紹介しました。
この記事が、読書感想文を書く皆さんの助けになれば幸いです。
※『博士の愛した数式』の読書感想文の書き方はこちらで解説しています。

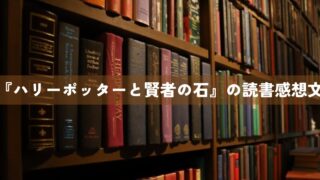
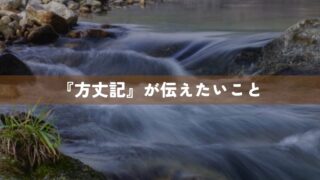




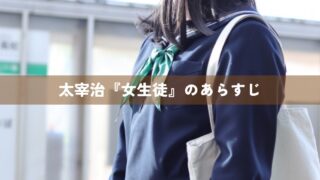

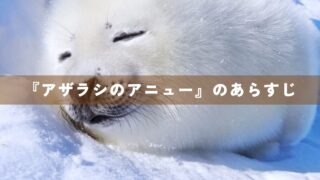
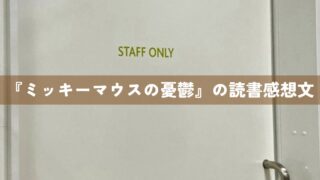



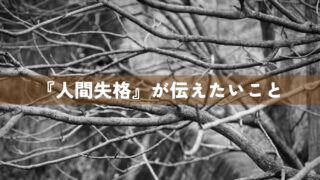

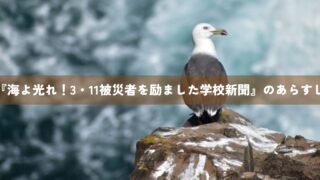


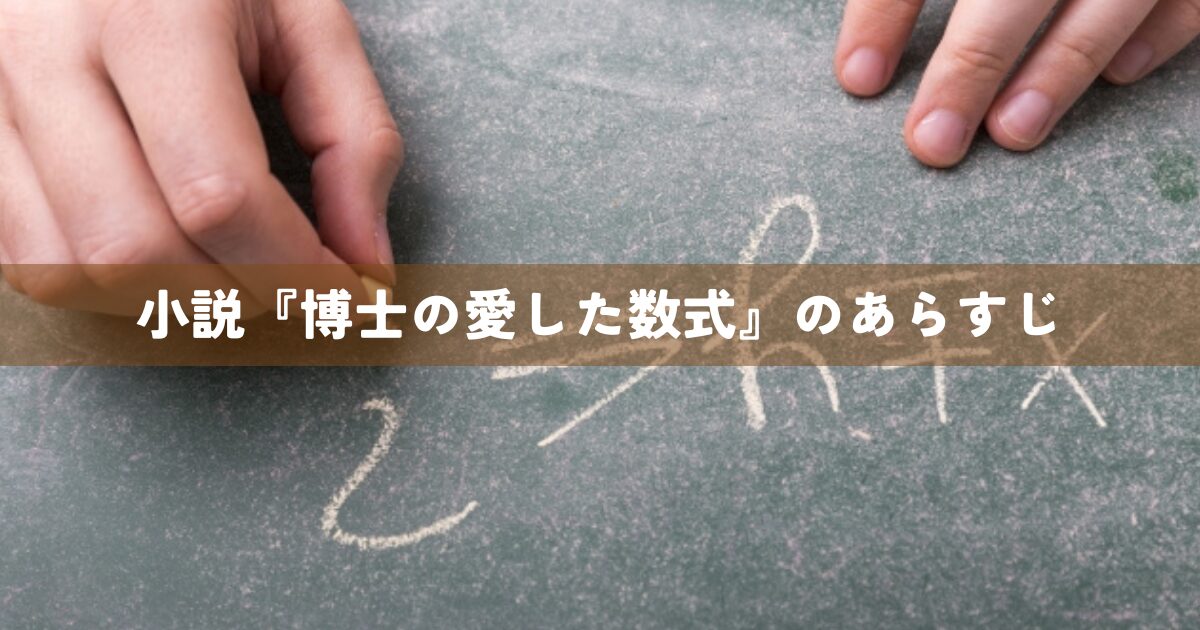
コメント