『六人の嘘つきな大学生』って面白いのか、私も最初は半信半疑でした。
本屋大賞にノミネートされたとはいえ、タイトルから想像する「就活生の小さな駆け引き」なんて、どこか他人事のように感じていたんですよね。
でも、読み始めたら…これが予想外の展開。
気づけば、あっという間に読み終えていました。
今日はそんな私が感じた浅倉秋成の『六人の嘘つきな大学生』の魅力をお伝えしていきます。
「ミステリーは苦手」「就活の話は気が重くなる」そう思っていたあなたにこそ、読んでほしい一冊です。
『六人の嘘つきな大学生』は面白い小説か?
『六人の嘘つきな大学生』が多くの人を魅了する理由は明確です。
どうして面白いのか、具体的にポイントを4つ挙げて詳しく解説してみましょう。
- 伏線の張り方と回収が絶妙
- キャラクターの内面描写が鮮やかで深い
- 現代の就活という身近なテーマと心理戦の組み合わせが斬新
- 予想を裏切る展開の連続
絶妙な伏線回収の妙技
この小説の最大の魅力は、何と言っても伏線の張り方と回収の見事さ。
読み始めた時は単なる就活物語のように思えるのに、物語が進むにつれて緻密に張り巡らされた伏線が次々と姿を現します。
特に中盤で発見される「六通の告発文」は物語のターニングポイント。
それぞれの封筒に書かれた「〇〇(※伏せ字にします)」という内容が、登場人物たちの秘密を暴き、緊張感を一気に高めていくんですよね。
多くの読者が「伏線の狙撃手」と評する浅倉秋成の技術は、終盤になって初めて「あぁ、あの場面はこういう意味だったのか」と気づかせる力があります。
二度三度と読み返したくなる、そんな作品なんですよ。
鮮やかで深いキャラクターの内面描写
六人の大学生それぞれが持つ個性と内面の葛藤が、非常に繊細に描かれています。
表面上は優秀で完璧に見える就活生たちの裏側に隠された「闇」が徐々に明らかになっていく過程が、読者の心を掴んで離しません。
例えば、快活なムードメーカーに見える袴田亮の高校時代のいじめに関わる過去。
慶應大学の秀才・九賀蒼太の隠された本性。
そして主人公の波多野祥吾自身が抱える葛藤と決断。
これらのキャラクターは単なる「良い人」「悪い人」という二元論では片付けられない複雑さを持っています。
あなたも、自分の中の弱さや矛盾と向き合いながら生きているはず。
そんな人間の本質を見つめる物語だからこそ、読む人の心に深く刺さるのだと思います。
就活×心理戦という斬新な組み合わせ
就職活動という多くの日本人が経験する身近なテーマと、サスペンスフルな心理戦を組み合わせた設定は、非常に新鮮です。
IT企業「スピラリンクス」の最終選考という限られた空間と時間。
最初は全員の内定を目指すチームワークだったものが、突然「一人だけ」の選抜に変わるという極限状況。
この設定自体がすでに緊張感を生み出しています。
そして、彼らが互いを評価し合う過程で人間関係が複雑に変化していく様子は、現実の就活や職場でも起こりうる人間模様を反映させているように感じました。
現代社会の競争原理や人間関係の脆さを映し出す鏡のような作品。
それが『六人の嘘つきな大学生』なんです。
予想を裏切る展開の連続
物語が進むにつれて、読者の予想を次々と裏切る展開の妙も、この小説の大きな魅力です。
「この人が犯人だ」と思った瞬間に新たな事実が明らかになり、「いや、違う」と考えを改めさせられる。
そしてまた別の登場人物に疑惑の目を向けると、またも新たな事実が…。
こうした「読者の予想との駆け引き」が、最後まで続きます。
特に物語の終盤で明かされる真相は、多くの読者を「なるほど!」と唸らせる驚きに満ちています。
ただのミステリーに留まらず、人間の本質に迫るドラマとしても読み応えがあるのは、この予想を裏切る展開の連続によるものでしょう。
読み終えた後も、「あの場面はこういう意味だったのか」と考えさせられる余韻が残りますよ。
『六人の嘘つきな大学生』の面白い場面(印象的・魅力的なシーン)
『六人の嘘つきな大学生』には多くの印象的なシーンがありますが、特に心に残る場面をいくつか紹介しましょう。
- 選考過程の急な変更がもたらす衝撃
- 六通の告発文の発見と衝撃的な内容
- 波多野の決断と意外な真相
- 伏線回収の決定的な瞬間
選考過程の急な変更がもたらす衝撃
物語の序盤、IT企業「スピラリンクス」の最終選考に残った六人の大学生たちは、チームとして協力し合い、全員の内定を目指していました。
和気あいあいとした空気の中、彼らは定期的に集まって対策を練り、信頼関係を築いていきます。
しかし、突如届いた鴻上人事部長からのメール。
「選考方法と採用者数を1人に変更する」
この一通のメールが、彼らの関係性を一変させるんです。
私がこのシーンを読んだとき、胃がキュッと締め付けられるような緊張感を味わいました。
友人だと思っていた相手が、突然「ライバル」に変わる瞬間。
就活を経験した人なら、どこか現実味を帯びて感じられるのではないでしょうか。
このシーンの素晴らしさは、登場人物たちの表情や心理の変化が繊細に描かれている点。
表面上は冷静を装いながらも、内心では焦りや不安、そして打算が渦巻いているのが感じられて、一気に引き込まれました。
六通の告発文の発見と衝撃的な内容
最終選考の当日、グループディスカッションの最中に発見される「六通の封筒」。
そして九賀が最初に開封すると、袴田亮の高校時代に部活でいじめがあり「ある大きな事件」が起きていたという衝撃的な告発内容が明らかになります。
そして順に開封される封筒からは、彼らの隠された「闇」が次々と暴かれていくんです。
このシーンの緊張感は圧巻でした。
封筒が開かれるたびに明らかになる秘密。
そして暴露された本人の反応と、それを見つめる他のメンバーたちの複雑な表情。
私はこのシーンを読みながら「次は誰の何が暴かれるんだろう」とページをめくる手が止まりませんでした。
人間の秘密と向き合う恐怖と、それでも真実を知りたいという好奇心を同時に刺激する、巧みな展開だと思います。
波多野の決断と意外な真相
物語のクライマックスに近づくにつれ、波多野祥吾の行動が変わっていきます。
最初から「封筒は開けるべきではない」と主張していた彼が、実は封筒を用意したのは自分だと告白する場面。
そして「僕は嶌さんへ入れる」という言葉を残して最後の投票の時に退出するという意外な展開。
このシーンの素晴らしさは、それまでの波多野の行動が全て「計画的」だったのか、それとも状況に応じた「即興」だったのかが曖昧になっている点です。
読者は波多野の本当の意図を探りながら、自分なりの答えを見つけようとします。
そして「それから」のパートで明かされる彼の真意と背景が、読者に深い感動と驚きをもたらすのです。
人間の複雑な心理と決断の瞬間を描いた名シーンだと思います。
伏線回収の決定的な瞬間
「それから」のパートで、ある事実が明かされます。
これは単なる伏線回収以上の意味を持つ瞬間でした。
物語を通じて張り巡らされた伏線が一気に回収され、読者は「なるほど!」と膝を打ちます。
この瞬間、それまでの物語が全く違った角度から見えるようになるんですよ。
波多野省吾の行動の意味、六人の関係性、そして選考の真の目的まで。
全てが繋がる感覚は、優れたミステリーが持つ醍醐味そのものでした。
この伏線回収の見事さが、多くの読者から「伏線の狙撃手」と評される所以でしょう。
読み終えた後も余韻が残り、もう一度最初から読み直したくなる、そんな力を持った場面ですね。
『六人の嘘つきな大学生』の評価表
| 評価項目 | 点数 | コメント |
|---|---|---|
| ストーリー | ★★★★★ | 伏線の張り方と回収が見事で、 読者を最後まで飽きさせない構成 |
| 感動度 | ★★★★☆ | 人間の弱さと強さを同時に描き、 心に残る余韻がある |
| ミステリ性 | ★★★★★ | 複数の謎が絡み合い、 最後まで真相が読めない巧みな仕掛け |
| ワクワク感 | ★★★★☆ | 次々と明かされる秘密と展開に引き込まれる |
| 満足度 | ★★★★★ | 読み終えた後も余韻が残り、 再読したくなる完成度の高さ |
『六人の嘘つきな大学生』を読む前に知っておきたい予備知識
『六人の嘘つきな大学生』をより深く楽しむために、いくつか知っておくと良いポイントがあります。
- 就活生の心理と現代の就職事情への理解
- ミステリーの「叙述トリック」という手法
- 「二部構成」の物語を読み解く視点
就活生の心理と現代の就職事情への理解
この物語の舞台となるのは、人気IT企業「スピラリンクス」の最終選考です。
現代の就職活動、特に人気企業の選考過程では、協調性とリーダーシップの両方が求められる矛盾した状況があります。
「チームとして協力しながらも、最終的には自分が選ばれなければならない」という心理的プレッシャー。
これを理解していると、登場人物たちの行動や心理の機微がより深く感じられるでしょう。
また、表面的な「良い人」を演じながらも、内心では計算や駆け引きを行う就活生の心理は、社会人になってからの職場の人間関係にも通じるものがあります。
この小説は単なる就活物語ではなく、現代社会における人間関係の縮図として読むことができるはず。
ミステリーの「叙述トリック」という手法
この作品を読む際に知っておくと良いのが、ミステリーにおける「叙述トリック」という手法です。
これは、語り手が意図的に情報を隠したり、誤解を招くような書き方をしたりすることで、読者の推理を惑わせる技法です。
『六人の嘘つきな大学生』では、「就職試験」と「それから」という二つのパートで視点人物が変わります。
それぞれの語り手が何を知っていて何を知らないのか、そして何を隠しているのかを意識しながら読むと、物語の奥行きがさらに深まります。
特に「波多野祥吾」の視点から語られる前半部分と、「嶌衣織」の視点から語られる後半部分の間には、微妙なズレや矛盾があるかもしれません。
そこに着目することで、真相に迫るヒントを得ることができるでしょう。
「二部構成」の物語を読み解く視点
この小説は「就職試験」と「それから」という二部構成になっています。
前半の「就職試験」は、まさに選考の現場で起こる出来事をリアルタイムで描いています。
対して後半の「それから」は、選考から数年後の視点から過去を振り返る形になっています。
この二つの時間軸の間で、登場人物たちの認識や理解がどう変化したのか、そして真実がどのように明らかになっていくのかに注目すると、物語の面白さが倍増します。
また、「それから」のパートでは、前半で描かれた出来事の裏側や真相が明かされていきます。
これは単なる「謎解き」ではなく、人間の記憶や認識の不確かさ、そして時間の経過とともに見えてくる真実というテーマにも繋がっています。
時間の流れと共に変化する「真実」という概念を意識しながら読むと、より深い読書体験ができるでしょう。
※『六人の嘘つきな大学生』のあらすじは以下の記事にまとめています。

『六人の嘘つきな大学生』を面白くないと思う人のタイプ
どんなに評価の高い作品でも、全ての人に合うわけではありません。
『六人の嘘つきな大学生』を読んでも面白さを感じられない可能性がある人のタイプを考えてみました。
- 単純明快なストーリー展開を好む人
- キャラクターに共感できることを重視する人
- 現実的な設定やリアリティを求める人
単純明快なストーリー展開を好む人
この小説の最大の特徴は、複雑に絡み合う伏線と、読者の予想を裏切る展開の連続です。
そのため、物語の筋道がストレートで分かりやすい作品を好む人にとっては、少し難しく感じるかもしれません。
「就職試験」と「それから」という二部構成の間で時間が行き来し、複数の視点から物語が描かれることで、時に物語の流れを追うのが大変になることもあります。
また、伏線が非常に多く張られているため、読みながらすべてを覚えておくのが難しいと感じる人もいるでしょう。
集中して読み進める必要があるため、リラックスしながら楽しく読める軽い読み物を求めている人には、少し負担に感じられるかもしれません。
しかし、その複雑さこそがこの小説の魅力でもあります。
キャラクターに共感できることを重視する人
この小説に登場する六人の大学生たちは、それぞれに「嘘」や「闇」を抱えています。
彼らは完璧な「良い人」ではなく、時に計算高く、自己中心的に行動することもあります。
そのため、登場人物に強く共感できることや、応援したくなるようなキャラクターの存在を重視する読者にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
特に物語が進むにつれて明らかになる彼らの過去や秘密は、時に読者の共感を難しくするものもあります。
しかし、この「完璧ではない人間」の姿こそ、リアルな人間の複雑さを描いた本作の魅力とも言えるでしょう。
完璧なヒーローやヒロインではなく、弱さと強さを併せ持つ「等身大の人間」として彼らを見れば、また違った面白さが感じられるはずです。
現実的な設定やリアリティを求める人
この小説の設定、特に最終選考の形式や展開には、現実の就活とは異なる部分もあります。
実際の企業選考では、「六通の告発文」のようなドラマチックな展開は起こるはずがありません。
また、一つの選考の場でこれほどまでに複雑な人間関係のドラマが展開することも、やや現実離れしていると感じる人もいるかもしれません。
特に就活経験者や人事担当者など、実際の選考過程をよく知る人にとっては、設定の非現実性が気になる可能性があります。
しかし、この小説はあくまでフィクションであり、リアルな就活の描写を目的としたものではなく、人間の本質や関係性を浮き彫りにするための舞台装置として就活を利用していると考えれば、その面白さを十分に味わうことができるでしょう。
心の闇を暴く『六人の嘘つきな大学生』は面白い!
ここまで『六人の嘘つきな大学生』の様々な魅力について紹介してきました。
最初は「就活小説」という枠に収まるかと思われたこの物語は、読み進めるにつれて深い人間ドラマとサスペンスフルなミステリーへと変貌します。
伏線の張り方と回収の妙、複雑な人間心理の描写、そして予想を裏切る展開の連続。
これらが組み合わさることで、読者を最後まで飽きさせない力強い物語になっているのです。
もちろん、この小説が全ての人に合うわけではありません。
複雑な構成や、時に共感しづらいキャラクターたちの行動に戸惑う人もいるでしょう。
しかし、「人間の弱さと強さ」「信頼と裏切り」「表と裏」といったテーマに興味があれば、きっと心を揺さぶられる体験ができるはずです。
私自身、読み終えた後もしばらく余韻に浸っていました。
そして数か月後に再読したときには、初読では気づかなかった伏線や深みを発見できたのです。
読書の好みは人それぞれ。
でも、もし少しでも興味を持ったなら、ぜひ一度手に取ってみてください。
あなたにとって『六人の嘘つきな大学生』がどんな物語になるのか、それを知る権利はあなたにしかないのですから。
※『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文の書き方と例文はこちらにまとめています。
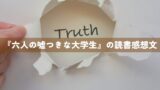

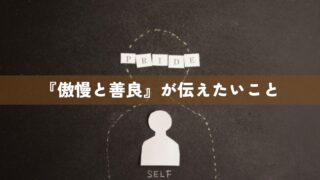


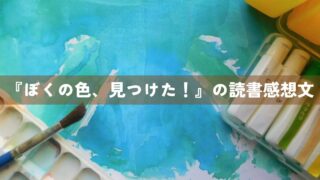

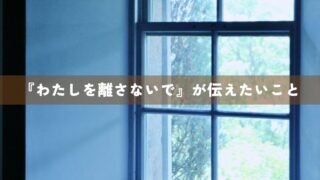








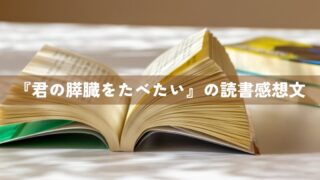
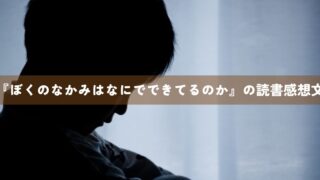


コメント