『宙わたる教室』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部)に選ばれた『宙わたる教室』の読書感想文の書き方を丁寧に解説していきますよ。
『宙わたる教室』は伊与原新さんによる感動的な青春小説です。
定時制高校に通うさまざまな背景を持つ生徒たちが科学部を結成し、火星のクレーターを再現する実験に挑戦する物語。
主人公の柳田岳人をはじめ、アンジェラ、佳純、70代の長嶺など、多様な登場人物が織りなす成長と友情の群像劇として描かれています。
この記事では年間100冊以上の本を読む読書好きの私が、中学生と高校生それぞれに向けた感想文の例文を紹介し、題名の付け方まで、皆さんの読書感想文作成をしっかりサポートしていきます。
『宙わたる教室』の読書感想文で触れたい3つの要点
『宙わたる教室』の読書感想文を書く際に、ぜひ触れてほしい重要な要点を3つ紹介します。
これらの要点について、皆さんがどう感じたかをメモしておくことが大切ですよ。
- 多様な生徒たちが織りなす「学び直し」の人間ドラマと偏見の打破
- 理想的な教師像と「自動的にはわからない」学びの本質
- 科学の面白さと、仲間との協働による目標達成
読書中や読書後に、これらの要点について「自分はどう思ったか」「なぜそう感じたのか」を具体的にメモしておきましょう。
例えば「岳人の成長に感動した理由」「藤竹先生のどの言葉が印象的だったか」「科学実験のどの部分が興味深かったか」といった具合に、感情や思考を詳しく記録してください。
なぜこのメモが重要かというと、読書感想文は単なるあらすじの要約ではなく、あなた自身の心の動きや考えを表現する文章だからです。
メモがあることで、感想文を書く際に具体的で説得力のある内容を書けるようになりますよ。
多様な生徒たちが織りなす「学び直し」の人間ドラマと偏見の打破
『宙わたる教室』の最も魅力的な要素の一つが、定時制高校という舞台で展開される多様な人間ドラマです。
21歳でディスレクシアを抱える主人公の岳人、43歳で学び直すフィリピン系ハーフのアンジェラ、70代で高校に通う長嶺など、年齢も背景も全く異なる生徒たちが登場します。
特に注目してほしいのは、岳人のディスレクシア(読み書き障害)の描写を通して、「文字が読めない=頭が悪い」という社会的な偏見が打ち破られていく過程です。
岳人は数学が得意で、科学実験においても重要な役割を果たしていきます。
これは学習障害や学び直しに対する固定観念を見直すきっかけになるでしょう。
また、定時制高校に通う理由もそれぞれ異なります。
アンジェラは子どもの頃に学校に通えなかった経験があり、佳純は起立性調節障害で不登校になった過去を持っています。
長嶺は集団就職で上京した後、今になって学び直しを決意した人物です。
こうした多様性が、「学ぶことに年齢や背景は関係ない」というメッセージを強く印象づけます。
皆さんも、この多様性について自分なりの感想を持ったはずです。
どの登場人物に最も共感したか、なぜその人物に惹かれたのか、自分の周りにも似たような状況の人がいるかなど、具体的に考えてメモしておきましょう。
理想的な教師像と「自動的にはわからない」学びの本質
科学部の顧問である藤竹先生の存在は、物語の大きな魅力となっています。
藤竹先生は生徒一人ひとりの個性や困難を深く理解し、それぞれの可能性を信じて力を引き出そうとする理想的な教師として描かれています。
特に印象的なのは、藤竹先生の「自動的にはわからない」という言葉です。
これは学びの本質を突いた名言で、受け身ではなく自ら疑問を持ち、試行錯誤しながら学ぶことの重要性を表現しています。
現代の教育現場では、答えをすぐに教えてもらうことに慣れてしまいがちですが、真の学びは自分で考え、失敗を重ねながら理解を深めていくプロセスにあることを教えてくれます。
藤竹先生は単に知識を教えるだけでなく、生徒たちが自分の力で前に進めるよう支える姿勢を一貫して見せています。
岳人の文字を読む困難に対しても、決して諦めることなく、その子なりの学び方を見つけ出そうとします。
アンジェラや佳純、長嶺に対しても同様で、それぞれの事情や特性を理解した上で適切なサポートを提供します。
皆さんも、理想の先生像について考えたことがあるでしょう。
藤竹先生のどの言動が印象的だったか、自分が出会った先生と比較してどう感じたか、将来自分が誰かを指導する立場になったときにどんな姿勢でいたいかなど、教育や学びについて深く考えてみてください。
科学の面白さと、仲間との協働による目標達成
『宙わたる教室』のもう一つの大きな魅力は、火星のクレーター再現実験を通して描かれる科学の面白さと、仲間との協働の大切さです。
理系出身の作者ならではの専門知識が、わかりやすく興味深い形で物語に織り込まれています。
科学実験の描写は詳細でありながら、専門知識がない読者にも理解できるよう工夫されており、科学の奥深さや探求することの楽しさが伝わってきます。
実験は決して順調には進みません。
何度も失敗を重ね、予想外の問題に直面しながらも、生徒たちは諦めることなく取り組み続けます。
この過程で重要なのが、仲間との協働です。
一人では解決できない問題も、それぞれの得意分野を活かし、知恵を出し合うことで乗り越えていきます。
岳人の数学の知識、アンジェラの実践的な経験、佳純の観察力、長嶺の人生経験など、多様な強みが組み合わさることで、より大きな成果を生み出していきます。
最終的に学会発表を成功させるまでの道のりは、単なる科学の物語を超えて、友情や連帯感の尊さを描いた人間ドラマとしても読むことができます。
皆さんも、グループワークや部活動などで仲間と協力した経験があるはずです。
『宙わたる教室』の科学実験と自分の経験を比較して、協働することの意味や価値について考えてみましょう。
また、科学に対する興味や関心がどう変化したかも重要なポイントです。
『宙わたる教室』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】学び直しの勇気
私が『宙わたる教室』を読んで一番心に響いたのは、年齢や背景が違う人たちが一緒に学び、成長していく姿だった。
主人公の岳人は21歳で、文字を読むのが苦手なディスレクシアという障害を抱えている。
最初は自分に自信がなくて、周りから馬鹿にされるのではないかと不安に思っていた。
でも科学部に入って仲間たちと出会い、火星のクレーターを再現する実験に取り組む中で、少しずつ変わっていく。
私は岳人の気持ちがよくわかった。
なぜなら、私も授業で発表するときや、みんなの前で何かをするときに、間違えたらどうしようと不安になることがあるからだ。
でも岳人は仲間に支えられながら、自分にもできることがあると気づいていく。
数学が得意だということを活かして、実験の計算を担当したり、みんなと協力して問題を解決したりする姿を見て、私も勇気をもらった。
43歳のアンジェラさんや70代の長嶺さんが一緒に勉強している姿も印象的だった。
普通だったら、この年齢で高校に通うなんて恥ずかしいと思ってしまいそうだが、二人とも堂々と学び直しに挑戦している。
特に長嶺さんは、集団就職で中学を卒業してすぐに働き始めたため、高校に通えなかった過去がある。
それでも70歳を過ぎてから「今からでも遅くない」と決意して入学した。
この姿を見て、学ぶことに年齢は関係ないということを強く感じた。
藤竹先生の「自動的にはわからない」という言葉も心に残っている。
これは、ただ教えてもらうのを待っているだけでは本当の理解にはならないということだと思う。
自分で疑問を持って、試行錯誤しながら考えることが大切だという意味だろう。
私は今まで、わからないことがあるとすぐに答えを聞いてしまうことが多かった。
でもこの本を読んで、まず自分で考えてみることの大切さを学んだ。
火星のクレーター実験も、最初はうまくいかなくて、何度も失敗を繰り返していた。
でもみんなが諦めずに工夫を重ねて、最終的に学会で発表できるまでになった。
一人ではできないことも、仲間と協力すれば乗り越えられることがよくわかった。
私も部活動でチームワークの大切さを感じることがあるが、この本を読んで改めてその価値を実感した。
それぞれが得意なことを活かして、足りない部分を補い合う。
そうすることで、一人では思いもつかないようなアイデアが生まれたり、大きな目標を達成できたりする。
『宙わたる教室』は、学び直しの勇気と仲間との協働の大切さを教えてくれた。
岳人たちのように、苦手なことがあっても諦めずに挑戦し続けたい。
そして困っている人がいたら、自分にできることで支えてあげたいと思う。
年齢や背景が違っても、一緒に学び成長していけることを知った私は、これからの学校生活をもっと大切にしていきたい。
『宙わたる教室』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】多様性が生み出す学びの可能性
現代社会において、学習の機会は平等に与えられているように見える。
しかし『宙わたる教室』を読むと、実際にはさまざまな事情で学習から遠ざかってしまう人たちが存在することがわかる。
この小説は、そうした人たちが定時制高校という場で再び学びと出会い、科学という共通の興味を通じて成長していく姿を描いた作品である。
主人公の柳田岳人は21歳でディスレクシアという学習障害を抱えている。
文字を読むことが困難なため、これまで劣等感に悩まされ続けてきた。
しかし数学は得意で、論理的思考力も備えている。
岳人の存在は、「文字が読めない=知能が低い」という社会的偏見がいかに的外れであるかを示している。
私はこの設定に強い印象を受けた。
なぜなら、学校教育では読み書きの能力は「最低限必要なもの」という認識であり、それができない生徒は「劣等生」というレッテルを貼られがちだからである。
岳人のように、別の分野に優れた才能を持ちながら、一つの能力の不足によって自信を失ってしまう人は決して少なくないだろう。
43歳のフィリピン人とのハーフ・アンジェラと戦中世代の70代の長嶺の存在も印象深い。
アンジェラは子どもの頃に学校に通えなかった経験があり、長嶺は集団就職のため中学卒業後すぐに働き始めた。
二人とも、若い頃に十分な教育を受ける機会を逃したが、今になって学び直しに挑戦している。
これは「学習に適した年齢」という固定観念を覆す設定である。
私たちは無意識のうちに、学習は若いうちにするものだと考えがちである。
しかし人生100年時代と言われる現代において、いつからでも新しいことを学び始めることができるし、むしろそれが必要な時代になっているのではないだろうか。
科学部の顧問である藤竹先生の存在も重要である。
先生は生徒一人ひとりの事情や特性を理解し、それぞれに適したアプローチで指導している。
特に「自動的にはわからない」という言葉は印象的だった。
これは受け身の学習ではなく、能動的に疑問を持ち、試行錯誤することの大切さを表している。
現代の教育現場では、効率性が重視され、できるだけ早く正解にたどり着くことが求められがちである。
しかし真の学びは、失敗を恐れずに挑戦し、自分なりの理解を深めていくプロセスにあるのではないだろうか。
火星のクレーター再現実験は、この作品の核となる要素である。
一見すると高度で難しそうな実験だが、生徒たちが協力し合いながら取り組む姿は非常に魅力的に描かれている。
実験は順調には進まず、何度も失敗を重ねる。
しかしその度に新しい発見があり、仲間同士で知恵を出し合いながら問題を解決していく。
私はこの過程に、真の協働学習の姿を見た。
現代の学校教育でもグループワークが重視されているが、しばしば形式的なものにとどまってしまう。
しかし『宙わたる教室』で描かれる協働は、それぞれの個性や強みを活かしながら、共通の目標に向かって努力する本物の協働である。
岳人の数学的思考力、アンジェラの実践的な経験、佳純の観察力、長嶺の人生経験など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まることで、一人では到達できない高いレベルの成果を生み出している。
この小説を読んで、私は多様性の価値について深く考えさせられた。
同質的な集団では得られない創造性や問題解決力が、異なる背景を持つ人々が集まることで生まれる。
定時制高校という設定も、この多様性を際立たせている。
年齢も経験も学習能力も異なる生徒たちが、互いを尊重し合いながら学んでいく姿は理想的である。
現実の社会でも、このような多様性を受け入れる環境が増えていけば、より豊かな学びや創造が可能になるのではないだろうか。
また、この小説は科学への興味や関心を高める効果もある。
火星やクレーターといった宇宙に関する内容は、多くの人にとって知識が浅く縁遠いテーマである。
だが複雑な科学的原理も、実験という具体的な活動を通して描かれることで理解しやすくなっている。
私自身、理系分野に特別な興味を持っていたわけではないが、この小説を読んで科学の面白さを感じることができた。
最終的に、生徒たちは学会で発表を成功させ、JAXAからの次の実験への参加も示唆される。
これは彼らの努力が社会的に認められたことを意味している。
学習障害や年齢、過去の挫折といったハンディキャップを乗り越えて、社会に貢献できる成果を生み出したのである。
『宙わたる教室』は、学び直しの可能性と多様性の価値を教えてくれる作品である。
誰もが自分なりの学び方で成長できること、異なる背景を持つ人々が協働することで大きな成果を生み出せることを示している。
私も将来、様々な人々と協力しながら、継続的に学び続けていきたいと思う。
振り返り
『宙わたる教室』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この小説の魅力は、多様な登場人物が織りなす成長ドラマと、科学への興味を通じた仲間との協働にあります。
読書感想文を書く際は、ただあらすじを要約するのではなく、あなた自身がどの場面でどのような感情を抱いたかを具体的に表現することが大切です。
中学生の皆さんは素直な感想を、高校生の皆さんはより深い考察を加えながら、それぞれの視点で感想文を書いてみてください。
紹介した例文は参考程度に留めて、必ずあなた自身の言葉で感想を表現しましょう。
きっと心に響く素晴らしい読書感想文が書けるはずですよ。
※『宙わたる教室』のあらすじはこちらでご紹介しています。



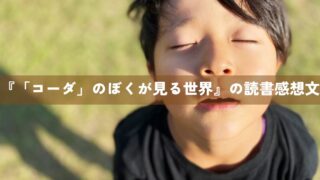
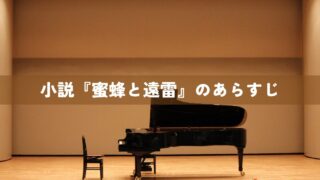
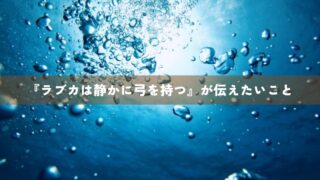
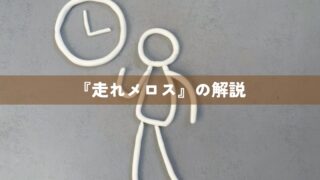


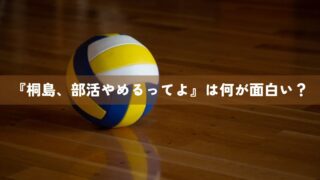


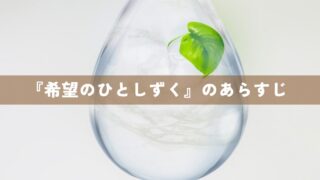

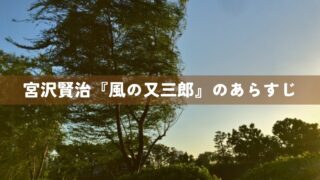


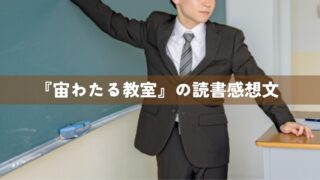

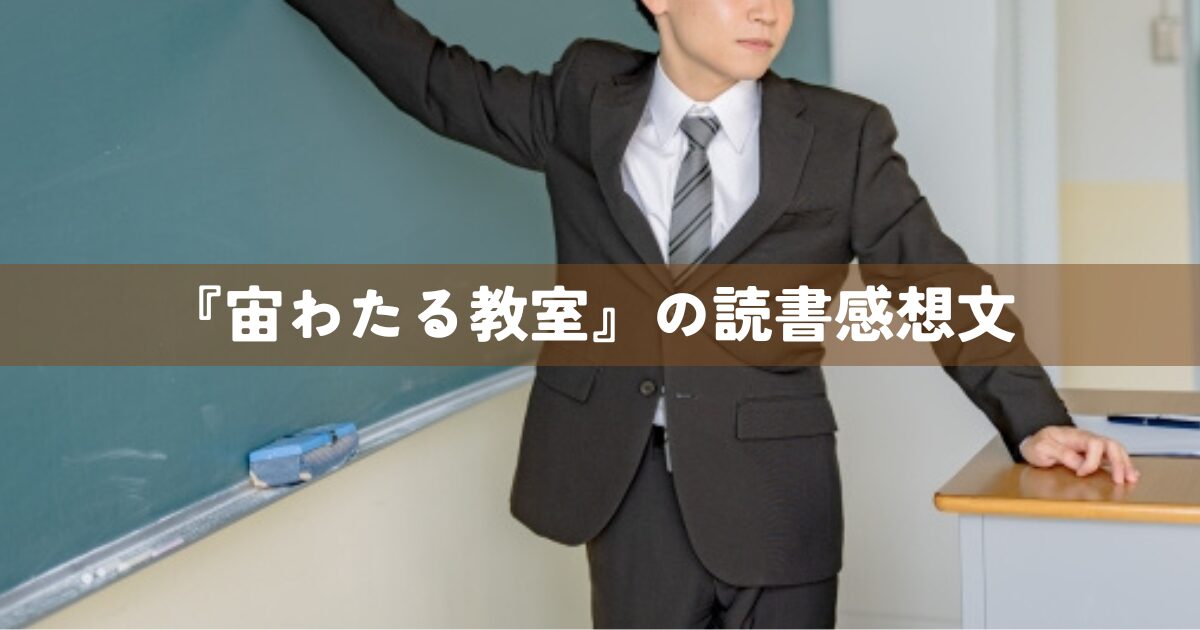
コメント