「『夢をかなえるゾウ』って評判いいけど、結局ただの自己啓発本なんじゃないの?」
そんな理由をつけて敬遠していませんか?
私も最初はそう思っていたんですよ。書店で平積みされた表紙を眺めながら「また自己啓発か…」と素通りしたものです。
でも友人に強く薦められて読んでみたら、これが意外な発見でした。
水野敬也さんのこの小説は、単なる自己啓発書ではなく、関西弁を操るゾウの神様・ガネーシャが、どこにでもいる平凡なサラリーマンに人生を変えるヒントを授ける物語なんですね。
今日は年間100冊以上の本を読む私が、この『夢をかなえるゾウ』の魅力を徹底解説します。
読むべきか迷っているあなたの背中を、そっと押してみたいと思います。
『夢をかなえるゾウ』は面白い小説か?
『夢をかなえるゾウ』が面白いと言われる理由は、単なる教訓や成功法則の羅列ではないため。
この本の面白さは、こんな4つのポイントにあります。
- ガネーシャというキャラクターの魅力
- 笑いと学びが絶妙に融合したストーリー展開
- 誰でも実践できる具体的な課題の数々
- 自己啓発書とエンターテインメントの見事な融合
それでは、これらの要素を詳しく見ていきましょう。
関西弁を操るゾウの神様「ガネーシャ」が最高にユニーク
本書の最大の魅力は、やはり関西弁を話すゾウの神様「ガネーシャ」の存在です。
インドの神様というと厳かで近寄りがたいイメージがありますが、この作品のガネーシャは違います。
甘いものが大好きで、特にあんみつには目がなく、目玉焼きにはベーコンがないと気が済まない、なんとも人間くさい神様なんですね。
それに関西弁をバンバン繰り出すガネーシャの口調が、読んでいてクスッと笑えます。
松下幸之助を「幸ちゃん」、本田宗一郎を「宗ちゃん」と呼ぶ姿も愛嬌たっぷり。
そんなだらしなさと愛嬌を持ちながらも、人生の深い知恵を授けてくれるギャップが、読者を引き込むんですよ。
笑いと学びが絶妙に融合したストーリー展開
この本が単なる自己啓発書と一線を画すのは、エンターテインメント性の高さです。
主人公は三日坊主の性格で、自己啓発に何度も挫折してきた平凡なサラリーマン。
そこに突然現れたガネーシャとの掛け合いが、コミカルでありながらも人生の深い教訓を含んでいるんです。
特に面白いのは、ガネーシャが出す課題が「靴を磨く」「トイレを掃除する」など、一見すると小さなことばかりだということ。
それらの地味な課題が、どのようにして人生を大きく変えていくのかというプロセスが、読者の好奇心を刺激していきます。
「えっ、こんな単純なことで人生変わるの?」と半信半疑になりながらも、主人公と一緒に課題をこなしていくうちに、読者自身も何かに気づかされていく感覚があります。
誰でも実践できる具体的な課題の数々
この本が200万部を超えるベストセラーになった理由の一つは、読んですぐに実践できる具体性にあります。
多くの自己啓発本は「前向きに考えよう」「感謝の気持ちを持とう」など、抽象的な教えで終わることが多いのですが、『夢をかなえるゾウ』は違います。
「靴を磨け」「人の話は最後まで聞け」「トイレを掃除しろ」「募金をしろ」など、具体的な行動指針を示してくれるのです。
これらの課題が、なぜ人生を変えるのか?その理由も丁寧に解説されているため、納得感があります。
読んだその日から行動に移せる具体性が、この本の大きな魅力です。
自己啓発書とエンターテインメントの見事な融合
『夢をかなえるゾウ』の最大の功績は、「自己啓発」と「物語」という二つのジャンルを見事に融合させたことでしょう。
自己啓発本は有益だけれど読みにくい、小説は面白いけれど実用性に欠ける…そんな固定観念を打ち破った作品です。
ページをめくるたびに、笑いあり、涙あり、気づきありの展開に引き込まれます。
そして何より、主人公が少しずつ変わっていく様子に自分自身を重ね合わせることで、「自分も変われるかもしれない」という希望が湧いてくるのです。
読み終わった後、なんとなく靴を磨きたくなる…そんな不思議な魅力を持った本です。
※まず『夢をかなえるゾウ』のあらすじを確認したい方は、こちらへお進みください。

『夢をかなえるゾウ』の面白い場面(印象的・魅力的なシーン)
『夢をかなえるゾウ』には、思わず笑ってしまうシーンから、心に深く刻まれる名言まで、数多くの印象的な場面があります。
特に心に残るシーンをいくつか挙げてみましょう。
- ガネーシャの突然の登場シーン
- トイレ掃除の教えが示されるシーン
- 「靴磨き」がもたらす人生の変化
- 主人公が自分の変化に気づくシーン
それでは、これらの印象的なシーンを詳しく見ていきましょう。
ガネーシャの突然の登場シーン
物語の冒頭、主人公が泥酔して「人生を変えたい」と叫んだ翌朝、枕元に突然現れる関西弁を話すゾウの神様。
このシーンは、多くの読者の印象に残る導入部分です。
唐突な登場と関西弁のギャップが、思わず笑ってしまうポイント。
最初は幻覚か何かだと思った主人公が、だんだんとガネーシャの存在を受け入れていく様子が絶妙に描かれています。
特に、ガネーシャが「自分」という二人称で主人公を呼ぶシーンは、不思議な親近感と違和感が入り混じる独特の雰囲気を生み出しています。
何より、落ち込んでいた主人公の前に、突如として「夢をかなえるゾウ」が現れるというこの設定自体が、読者の想像力をかき立ててくれるんですね。
トイレ掃除の教えが示されるシーン
「トイレ掃除をすることは、一番汚いところを掃除すること。誰かがやりたがらないことをやれば、それが一番喜ばれる」
このガネーシャの言葉が示されるシーンは、単純なようで奥深い教えが込められています。
最初は意味がわからず渋々トイレ掃除をする主人公。
でも、その行為が周囲の評価を変え、自分自身の心も変えていくことに気づいていきます。
このシーンの面白いところは、誰もが「やりたくない」と思うような地味な行為に、実は人生を変える大きな力が秘められていることを気づかせてくれる点。
「成功への近道は、意外と地味で誰もやりたがらないことをコツコツやることなんだよ」というメッセージが、コミカルに描かれているのです。
「靴磨き」がもたらす人生の変化
ガネーシャが最初に主人公に出す課題が「靴を磨け」というものです。
「え?それだけ?」と思うような単純な課題ですが、これが実は深い意味を持っています。
毎朝靴を磨くことで、主人公の姿勢や歩き方が変わり、自然と前向きな気持ちになっていく様子が描かれるシーン。
特に印象的なのは、ピカピカの靴を履いた主人公が、自然と背筋を伸ばして歩くようになり、それが自信につながっていくという展開です。
この「小さな行動が、思いがけない大きな変化をもたらす」という描写は、読者に「自分もできるかも」という希望を与えてくれます。
靴磨きという誰にでもできる行動が、どのように人生を変えていくのか…そのプロセスの描写は、本書の核心部分であり、最も魅力的なシーンの一つです。
主人公が自分の変化に気づくシーン
物語の中盤、ガネーシャの課題をこなしていくうちに、少しずつ変わっていく自分に主人公自身が気づくシーンがあります。
周囲の人間関係が良くなり、仕事でも評価されるようになった主人公が、ふと立ち止まって「自分は変わったのか?」と考えるシーン。
この瞬間、読者も主人公と一緒に成長の喜びを感じることができます。
特に興味深いのは、主人公が「自分が変わった」のではなく「自分を取り巻く世界が変わった」と感じている点です。
実際には主人公自身の行動や態度が変わったことで周囲の反応が変化したのですが、その気づきのプロセスが絶妙に描かれています。
「人が変われば世界が変わる」という当たり前のようで難しい真理を、実感を伴って理解できるシーンです。
※『夢をかなえるゾウ』を通して作者が伝えたいことは、こちらの記事で考察しています。

『夢をかなえるゾウ』の評価表
| 評価項目 | 点数 | コメント |
|---|---|---|
| ストーリー | ★★★★☆ | シンプルながらも引き込まれる展開。もう少し伏線があれば完璧だった |
| 感動度 | ★★★★☆ | 主人公の成長に共感できる。ただし涙腺崩壊レベルではない |
| ミステリ性 | ★★☆☆☆ | 謎解き要素は少なめ。ガネーシャの正体についての疑問は途中で薄れていく |
| ワクワク感 | ★★★★★ | 次の課題は何か?それがどう人生を変えるのか?という期待感が最後まで続く |
| 満足度 | ★★★★☆ | 読了後に何か行動したくなる希望を与えてくれる。続編への期待も膨らむ |
『夢をかなえるゾウ』を読む前に知っておきたい予備知識
『夢をかなえるゾウ』をより深く楽しむために、いくつか知っておくと良いポイントがあります。
- ガネーシャとは何者なのか
- 自己啓発小説としての位置づけ
- シリーズ作品であること
これらの予備知識を持っていると、より深くこの物語を楽しむことができます。
ガネーシャとは何者なのか
作中に登場するガネーシャは、実際にインド神話に登場する神様です。
象の頭と人間の体を持ち、知恵と学問の神様として広く信仰されています。
ただし、本作のガネーシャが関西弁を話したり、甘いものが好きだったりするのは、もちろん作者のフィクションです。
インド神話におけるガネーシャの知恵と豊かさの象徴という側面を理解しておくと、作中でガネーシャが語る成功哲学により深みを感じることができるでしょう。
また、本作ではガネーシャが「自分」という言葉を二人称として使っています。
これは「あなた」という意味であり、関西弁の特徴の一つです。
最初は少し違和感があるかもしれませんが、読み進めるうちに独特の親近感を感じるはずです。
自己啓発小説としての位置づけ
『夢をかなえるゾウ』は、一般的な自己啓発書とは一線を画しています。
通常の自己啓発書が「〜すべき」「〜が大切だ」といった教訓を直接説くのに対し、この作品は物語を通じて自然と教訓が染み込んでくるスタイルです。
つまり、「自己啓発小説」という新しいジャンルを確立した先駆けとも言える作品なのです。
読む際は「教訓を学ぶ」という意識よりも、「面白い物語を楽しむ」という気持ちで接すると、より自然に学びを得ることができるでしょう。
水野敬也さんは、この作品で印税の一部を慈善団体に寄付していることも知っておくと、作品に描かれる「与える喜び」というメッセージがより深く理解できるかもしれませんね。
シリーズ作品であること
『夢をかなえるゾウ』は、現在4巻まで刊行されているシリーズ作品。
第1作が2007年に発売されて以来、多くの読者の支持を集め、シリーズ全体で400万部を超えるベストセラーとなっています。
各巻ではガネーシャが異なる主人公に様々な課題を出すという設定で、第2弾では売れないお笑い芸人、第3弾では結婚願望のあるOLが主人公となっています。
第1作を読んで面白いと感じたら、続編も読んでみることをお勧めします。
同じガネーシャが異なる悩みを持つ人々にどのようなアドバイスをするのか、その一貫性と多様性を楽しむことができますよ。
『夢をかなえるゾウ』を面白くないと思う人のタイプ
どれほどのベストセラーでも、全ての人に刺さるわけではありません。
『夢をかなえるゾウ』を読んでも面白さを感じにくい可能性がある人のタイプを挙げてみましょう。
- 自己啓発的な内容そのものに抵抗がある人
- こてこてのユーモアが苦手な人
- すでに多くの自己啓発本を読んだ経験がある人
自分がこれらのタイプに当てはまるかどうか、確認してみましょう。
自己啓発的な内容そのものに抵抗がある人
『夢をかなえるゾウ』は、エンターテインメント性が高いとはいえ、根底には自己啓発の要素が流れています。
「人は変われる」「努力次第で夢はかなう」というポジティブなメッセージに、根本的な抵抗感を持つ人には、物語として楽しむことが難しいかもしれません。
特に、シニカルな視点や現実主義的な考え方を持つ人には、ガネーシャの教えが「お説教くさい」と感じられる可能性があります。
また、自分自身を変えようという意欲がない時期に読むと、共感しにくい部分もあるでしょう。
変化を求めているタイミングで読むと、より作品の魅力を感じられるはずです。
こてこてのユーモアが苦手な人
本作の最大の特徴である「関西弁を話すガネーシャ」のキャラクター設定。
これが作品の大きな魅力である一方、関西弁独特の言い回しやユーモアのセンスが合わない人にとっては、読みづらさを感じる原因になることも。
特に、ガネーシャが放つギャグやコメディ要素が多いため、このタイプのユーモアが苦手な人には物語に入り込みにくいかもしれません。
また、キャラクターの描写がやや誇張されている部分もあるため、より写実的な小説を好む人には合わない可能性があります。
すでに多くの自己啓発本を読んだ経験がある人
『夢をかなえるゾウ』で語られる成功法則や人生哲学は、基本的には既存の自己啓発の知恵を物語形式で伝えているものです。
そのため、すでに数多くの自己啓発本を読んでいる人にとっては、「目新しさ」を感じにくい可能性があります。
「靴を磨く」「トイレを掃除する」といった具体的な行動指針は独自性がありますが、その根底にある考え方自体は「当たり前」と感じてしまう人もいるでしょう。
ただ、知識として知っていることと、実際に行動に移すことは別物。
既に多くを知っている人こそ、再確認の意味で読む価値があるかもしれません。
『夢をかなえるゾウ』は面白いゾウ(こてこてのギャグ)
『夢をかなえるゾウ』を読み終えた後、何か小さなことから始めたくなる…そんな不思議な力を持った本です。
関西弁を話すゾウの神様・ガネーシャと、どこにでもいる平凡なサラリーマンの物語を通じて、人生を変えるヒントがユーモアたっぷりに描かれています。
特に魅力的なのは、靴磨きやトイレ掃除など、誰にでもできる小さな行動から始まる変化のプロセス。
難しい理論や特別な才能がなくても、コツコツと行動することで人生は変わるという希望を与えてくれます。
もちろん、全ての人に刺さる本ではないかもしれません。
自己啓発的な内容に抵抗がある人や、すでに多くの成功哲学を知っている人には、「目新しさ」を感じにくい部分もあるでしょう。
でも、「何か変化のきっかけが欲しい」「楽しみながら自己成長したい」と思っているなら、間違いなく手に取る価値のある一冊です。
200万部を超えるベストセラーになった理由は、単なるブームではなく、この小説が持つ不思議な「背中を押してくれる力」にあるのだと思います。
私もこの本を読んでから、毎朝靴を磨くようになりました(この習慣は半年ほど続きました)。
それがきっかけで、身だしなみに気を配るようになり、仕事への向き合い方まで変わっていったんですよ。
小さな一歩が、思いがけない大きな変化をもたらす。
そんな経験を、あなたもぜひ『夢をかなえるゾウ』と一緒に始めてみませんか?
※『夢をかなえるゾウ』の読書感想文の例文と書き方はこちらでご紹介しています。

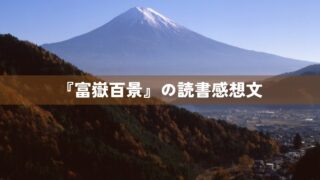
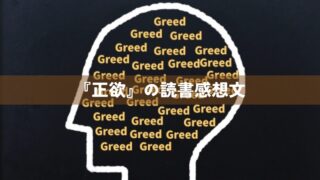
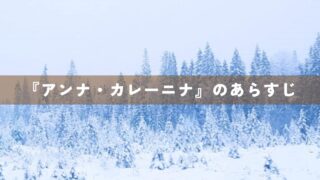
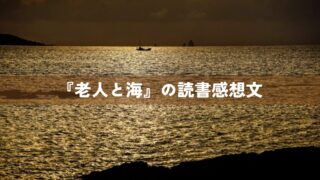

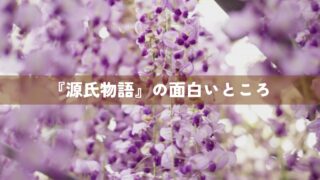

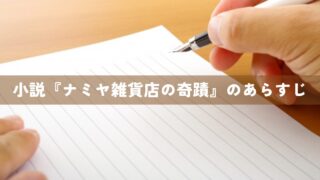
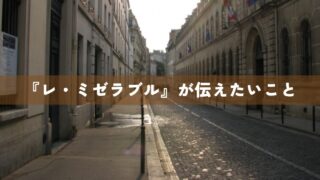

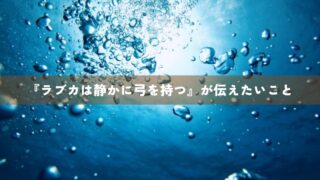

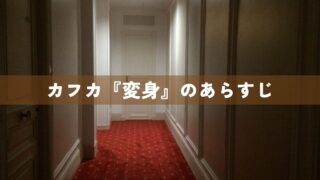
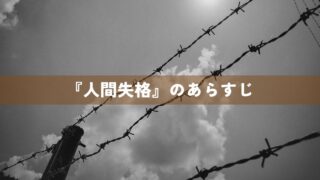

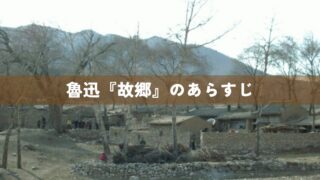

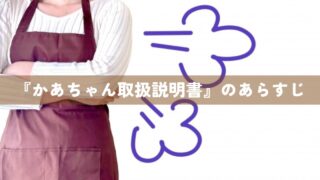

コメント