『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを簡単に短く、そして詳しく解説していきますね。
このブレイディみかこさんによる話題作は、イギリス・ブライトンに住む日本人の母とアイルランド人の父を持つ中学生の息子の実話を描いたノンフィクション。
多様性や人種差別、アイデンティティの問題をリアルに描きながらも、親子の温かい絆と成長を通して現代社会の課題を考えさせてくれる感動的な作品です。
年間100冊以上の本を読む私が、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の魅力を余すところなくお伝えします。
- ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを簡単に
- ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを理解するための用語解説
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の感想
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の作品情報
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の主要な登場人物
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読了時間の目安
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』はどんな人向けの小説か?
- あの本が好きなら『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』も好きかも?似ている小説3選
- 振り返り
ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを簡単に
イギリス・ブライトンに住む日本人の母とアイルランド人の父を持つハーフの中学生「ぼく」が、元底辺中学校と呼ばれる多様な生徒が通う学校で体験する日常を描いたノンフィクション。アフリカから来たばかりの少女、ジェンダーに悩むサッカー少年など、まるで世界の縮図のような環境で「ぼく」は様々な問題に直面する。家に帰ると、パンクな母ちゃんと一緒に人種差別や多様性について話し合い、悩みながらも理解を深めていく親子の姿が温かく描かれる。
ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
イギリス・ブライトンに住むライター兼保育士のブレイディみかこの息子「ぼく」は、日本人の母とアイルランド人の父を持つハーフの中学生だった。
優等生だった「ぼく」が進学したのは、元「底辺」と呼ばれる多様で荒れた公立中学校である。
そこには人種差別的な態度を露骨に示すハンガリー移民の美少年ダニエル、経済的に厳しい環境にいるティム、ジェンダーに悩むサッカー少年など、様々な背景を持つクラスメイトたちがいる。
「ぼく」は学校での体験を家に持ち帰り、パンクな母ちゃんと共に人種差別やジェンダー問題、多様性について話し合う。
肌の色が違うことによる偏見や差別を受けても冷静に受け止め、その理由を理解しようと努める「ぼく」の姿が描かれる。
同時に、日本とイギリスという二つの文化にまたがる自らのアイデンティティについても迷いを抱えながら、「どこにも属さない自由さ」や「多様性の尊さ」を少しずつ理解していく成長物語となっている。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを理解するための用語解説
物語を理解する上で重要な用語を以下にまとめました。
これらの用語を押さえておくことで、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の内容がより深く理解できますよ。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 多様性(Diversity) | 異なる人種、文化、経済背景、性別などが 共存する社会のあり方。 本作は多様な生徒が共に学ぶ学校を舞台に、 多様性の意味や価値を描く。 |
| エンパシー(Empathy) | 「他者の靴を履く」 という比喩で表される共感力。 他人の立場や気持ちを理解し思いやる心で、 物語の根幹にあるテーマ。 |
| アイデンティティ | 自己認識や自分自身の属する 文化的・社会的背景。 「ぼく」が日本人と アイルランド人の混血であることから 生まれる複雑な自己認識。 |
| 元底辺中学校 | 経済的・社会的に厳しい環境にあるとされ、 かつて評価が低かった公立中学校。 さまざまな社会問題が集まる場所として描かれる。 |
| 階級(Class) | 社会的な階層や経済的地位。 不平等や偏見の原因となるもので、 学校の日常や人間関係に影響を及ぼす。 |
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の感想
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んで、私は久しぶりに心の奥底から揺さぶられる感動を味わいました。
この作品のすごいところは、重いテーマを扱いながらも決して説教臭くならないことですね。
ブレイディみかこさんの息子である「ぼく」の視点で描かれる学校生活は、まさに現代社会の縮図そのもの。
人種差別や貧富の差、ジェンダーの問題など、普通なら目を逸らしたくなるような現実が、中学生の日常として淡々と描かれているんです。
特に印象的だったのは、極端な発言を繰り返すダニエルとの関係性でした。
普通なら「そんな子とは友達になるな」と言いたくなるところを、「ぼく」は彼の背景や事情を理解しようとする。
この姿勢に、私は本当に感動しましたよ。
大人の私でも、偏見や先入観でひとを判断してしまうことがあるのに、中学生の「ぼく」の方がよっぽど成熟している。
そして何より素晴らしいのが、母親であるブレイディさんとの会話のシーンです。
息子の悩みに対して、答えを押し付けるのではなく、一緒に考え、一緒に悩む姿勢が本当に温かい。
「エンパシー(共感力)」について語り合う親子の会話は、読んでいて涙が出そうになりました。
タイトルの「イエロー」「ホワイト」「ブルー」が表す意味も、読み進めるうちにじわじわと心に響いてきます。
どの色にも完全には属さない複雑さ、そしてその中で感じる少しの憂鬱さが「ちょっとブルー」という表現に込められているんですね。
一方で、「ぼく」があまりにも「いい子」すぎて、現実の中学生としてはちょっと理想的すぎるかなと感じることもあったんです(実際に「いい子」だから、それをリアルに描いたのかもしれませんが)。
もう少し等身大の反抗心や葛藤があってもよかったのかもしれません。
でも、それを差し引いても、この作品が与えてくれる気づきや感動は計り知れないものがあります。
読み終わった後、私は自分の中の偏見や固定観念について深く考えさせられました。
そして、多様性を受け入れるということの本当の意味を教えてもらった気がします。
現代社会を生きる全ての人に読んでもらいたい、心から推薦できる一冊ですね。
※『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読書感想文の例文と書き方はこちらでどうぞ。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | ブレイディみかこ |
| 出版年 | 2019年(初版)、文庫版は2021年 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 受賞歴 | 本屋大賞ノンフィクション本大賞 |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 主な舞台 | イギリス・ブライトンの中学校 |
| 時代背景 | 現代(2010年代後半) |
| 主なテーマ | 多様性、人種差別、アイデンティティ、親子関係 |
| 物語の特徴 | 実体験に基づく親子の成長を描いたリアルストーリー |
| 対象年齢 | 主に大人向け(中高生以上にも推奨) |
| 青空文庫の収録 | 収録なし |
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の主要な登場人物
物語の理解を深めるため、重要な登場人物を以下にまとめました。
それぞれが抱える背景や問題が、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のテーマを深く掘り下げているんですよ。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| 「ぼく」 | 主人公であり語り手の息子。 日本人の母とアイルランド人の父を持つハーフの中学生。 思慮深く感受性豊かで 多様な価値観の中で成長していく。 |
| 母ちゃん (ブレイディみかこ) |
著者で「ぼく」の母親。 イギリス在住のライター兼保育士。 パンク精神を持ち、息子の悩みに寄り添い共に考える。 |
| 父ちゃん | 「ぼく」の父親でアイルランド人。 長距離トラックの運転手で 寡黙ながら家族にとって重要な言葉を発することも。 |
| ダニエル | 「ぼく」の同級生。 ハンガリー移民の家庭出身の美少年。 差別的な発言をする複雑なキャラクターで、 「ぼく」との関係も描かれる。 |
| ティム | 「ぼく」の友人の一人で 経済的に恵まれない家庭環境にある。 貧困問題の象徴的存在として描かれる。 |
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の読了時間の目安
読書感想文を書く際の計画を立てやすいよう、読了時間の目安をまとめました。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は比較的読みやすい文体で書かれているので、普段あまり読書をしない方でも無理なく読み進められますよ。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 文字数 | 約201,600文字 (336ページ/新潮文庫) |
| 読了時間(通常ペース) | 約6時間40分 |
| 1日1時間読む場合 | 約7日で完読 |
| 1日30分読む場合 | 約13日で完読 |
| 読みやすさ | ★★★★☆(会話形式が多く読みやすい) |
内容も興味深く、一度読み始めると止まらなくなる魅力がありますね。
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』はどんな人向けの小説か?
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は特に以下のような方におすすめです。
現代社会の問題に関心がある方や、親子関係について考えたい方にぴったりの作品ですよ。
- 多様性や人種差別、ジェンダー問題などの社会問題に関心がある人
- 子どもの視点から社会の現実を知りたい親(特に中高生の子どもを持つ親)や教育関係者
- ノンフィクションやリアルな家族の成長物語を好む大人(特に30〜50代の女性読者に支持が高い)
一方で、重いテーマが苦手な方や、フィクションの方が好みという方には少し合わないかもしれません。
でも、難しいテーマを扱いながらも読みやすい文体で書かれているので、普段このようなジャンルを読まない方にもぜひ挑戦していただきたい作品です。
あの本が好きなら『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』も好きかも?似ている小説3選
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んで感動した方に、似たテーマや雰囲気を持つ作品をご紹介しますね。
多様性や社会問題、個人の成長をリアルに描く作品を厳選しました。
村田沙耶香『コンビニ人間』
現代社会の「普通」とは何かを問い、人と違う生き方をする主人公を通じて、多様性や孤独、社会への適応について描く小説です。
社会の常識に縛られない視点や個人の居場所の探求という点で、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』と通じるテーマがありますね。
主人公が社会の「当たり前」に疑問を持つ姿勢が、「ぼく」の多様性への理解と重なります。

カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』
クローンとして生まれた若者たちの青春群像と、社会の理不尽さや人間の尊厳を描いた作品。
人間関係やアイデンティティの葛藤、社会との対峙という側面で共感できるものがあり、読み応えのある深い物語です。
自分が何者であるかを問い続ける主人公たちの姿が、「ぼく」のアイデンティティ探求と似ています。

安堂ホセ『ジャクソンひとり』
多様な文化背景を持つ登場人物の葛藤や共生を描く現代小説で、異なる価値観と社会問題に向き合うリアルな描写が特徴。
社会の中のマイノリティの視点を重視し、共感力を高める内容が『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』と似ていますね。
文化の違いによる摩擦と理解を描く点で、共通するテーマを持っています。
振り返り
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』のあらすじを簡単に短く、そして詳しく解説してきました。
ブレイディみかこさんが息子の実体験をもとに描いたこの作品は、多様性やアイデンティティという重いテーマを、親子の温かい絆を通して読みやすく伝えてくれます。
読書感想文を書く際には、主人公の「ぼく」がどのように成長していくか、そして現代社会の問題にどう向き合っているかに注目してみてくださいね。
きっと皆さんにとっても、多様性について考える大切なきっかけになると思います。



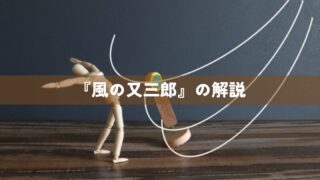







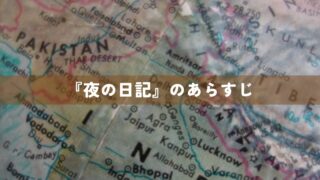

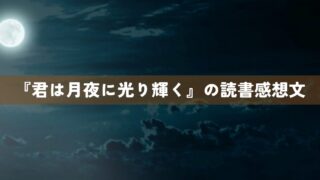





コメント