『君たちはどう生きるか』の読書感想文で悩んでいる皆さん、お疲れさまです。
この記事では、吉野源三郎さんが1937年に発表した名作『君たちはどう生きるか』の読書感想文の書き方を詳しく解説していきますよ。
『君たちはどう生きるか』は、コペルという愛称で呼ばれる15歳の主人公・本田潤一が、叔父さんとの交流や学校生活を通じて人間として成長していく物語。
宮崎駿監督のアニメ映画化でも話題になったこの作品は、時代を越えて愛され続ける青春文学の傑作なんですね。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいるのですが、『君たちはどう生きるか』は何度読み返しても新たな発見がある素晴らしい作品だと感じています。
この記事では、小学生・中学生・高校生それぞれに向けた例文を800字・1200字・2000字で用意し、コピペではなく自分なりの感想文が書けるようサポートしていきます。
読書感想文コンクールでも高く評価される書き方のコツを、分かりやすく説明していきますよ。
『君たちはどう生きるか』の読書感想文で触れたい3つの要点
『君たちはどう生きるか』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要な要点が3つあります。
まず、これらの要点を読みながら「自分はどう感じたか」「自分だったらどうするか」をメモしておくことが大切ですね。
なぜなら感想文は、あなた自身の心の動きや考えを表現する課題だからです。
- ものの見方を変えることの大切さ
- 自分で考え、行動する責任の自覚
- 人間としての総合的な成長と生き方の決意
メモを取る時は、物語の場面を読んで「なぜそう思ったのか」「自分の体験と似ている部分はあるか」「主人公と同じ立場だったらどうするか」という視点で書き留めてください。
このメモが、あなただけのオリジナルな感想文の材料になるんです。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は本の要約ではなく、あなたの心の成長や気づきを表現する文章だからですね。
「ものの見方を変えることの大切さ」
主人公のコペル君は、銀座のデパートから人々を見下ろした時に、自分も世界の一部に過ぎないということに気づきます。
この場面は、天動説から地動説へのパラダイムシフトに例えられているんですね。
コペルニクスが「地球が宇宙の中心ではなく、太陽の周りを回っている」と発見したように、コペル君も「自分が世界の中心ではなく、世界の一部である」ことを理解するのです。
この視点の転換は、私たちの日常生活でもとても重要な意味を持っています。
自分中心の考え方から、より広い視野で物事を捉える姿勢へと成長していく過程が、この物語の大きなテーマの一つなんですよ。
あなたも今まで「自分の考えが絶対に正しい」と思っていたことが、実は一つの見方に過ぎなかったという経験はありませんか。
そんな体験と重ね合わせながら、コペル君の成長を見つめてみてください。
叔父さんがノートに書いた「ものの見方について」の内容も、この要点を理解する上で非常に参考になります。
世の中や人生を考える時に、自分を宇宙の中心に置くのか、それとも広い世界の一部として捉えるのかで、見えてくる景色が全く違ってくるということですね。
「自分で考え、行動する責任の自覚」
物語の中でコペル君は、友人がいじめられている場面や、約束を守れなかった場面など、さまざまな困難な状況に直面します。
特に印象的なのは、雪の日に北見君が上級生から殴られる事件で、コペル君が事前の約束にも関わらず友人を守れなかったエピソードです。
この出来事を通じて、コペル君は「他人の意見に従うだけでなく、自分の経験と考えから正しい行動を選ぶべき」だということを学びます。
叔父さんのノートでも、知識を得るだけでなく、自分の頭で考え、自分の良心に従って行動することの大切さが繰り返し語られているんですね。
これは現代の私たちにも通じる、とても重要なメッセージです。
SNSやインターネットで溢れる情報の中で、何が正しいのかを見極める力が求められている今だからこそ、自分で考え抜く姿勢が大切なんですよ。
あなたも学校生活や友人関係の中で、「みんながやっているから」「先生が言ったから」という理由で行動してしまうことがあるのではないでしょうか。
コペル君の体験を通じて、自分なりの判断基準を持つことの重要性について考えてみてください。
失敗を恐れずに、自分の信念に基づいて行動する勇気を持つことが、人間的な成長につながるということが、この物語から学べる大切な教訓の一つです。
「人間としての総合的な成長と生き方の決意」
『君たちはどう生きるか』の最終的なメッセージは、コペル君が叔父さんとの対話を経て「世の中の誰かのために自分ができることを考え、決断して生きる」ことの尊さを知るところにあります。
物語を通じて、コペル君は精神的な成長を遂げ、最後に叔父さんへの返答として「自分の将来の生き方」について決意をノートに書き綴るんですね。
そして語り手が読者に対して「君たちは、どう生きるか」と問いかけて物語は終わります。
この問いかけは、読者である私たち一人ひとりに向けられた重要なメッセージなんですよ。
コペル君が貧しい友人・浦川君との交流を通じて貧富の差について考えたり、ガンダーラの仏像の話から人類の進歩の力強さに感動したりする場面は、人間が持つべき豊かな感受性を表現しています。
また、水仙の芽の生命力に感動する場面では、小さなものの中にも大きな可能性があることを学びます。
これらの体験を積み重ねながら、コペル君は自己中心性から脱却し、社会の中での自分の役割や責任について深く考えるようになっていくのです。
あなたも『君たちはどう生きるか』を読んで、自分なりの「生き方の決意」について考えてみてください。
どんな人になりたいのか、どんなことを大切にして生きていきたいのか、そういった根本的な問いに向き合うことが、この作品を読む醍醐味の一つなんですね。
※『君たちはどう生きるか』で作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

『君たちはどう生きるか』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】コペル君から学んだ大切なこと
『君たちはどう生きるか』を読んで、私はたくさんのことを考えた。
主人公のコペル君は、私と同じくらいの年だけど、とても深いことを考えている人だと思った。
一番心に残ったのは、コペル君が銀座のデパートから人々を見下ろして、自分も世界の一部だと気づく場面だ。
私もよく、自分のことばかり考えてしまうことがある。
でも、コペル君のように、自分も大きな世界の中の一人なんだと考えると、今まで見えなかったことが見えてくるような気がした。
コペル君が友達の北見君を守れなかった時のことも、とても印象に残っている。
私も友達がいじめられている時に、助けたいと思ったけど怖くて何もできなかったことがある。
コペル君がその後で深く反省して、友達に謝ったところが偉いと思った。
間違いを犯しても、きちんと謝って、次は同じことを繰り返さないように頑張る姿勢が大切なんだと学んだ。
叔父さんがコペル君に書いてくれるノートも、とても勉強になった。
難しい言葉もあったけど、叔父さんがコペル君のことを本当に大切に思っていることが伝わってきた。
私にも、何か困った時に相談できる大人がいるのは、とてもありがたいことなんだと改めて思った。
コペル君が貧しい友達の浦川君と仲良くしている場面では、お金持ちでも貧しくても、人としての価値は変わらないということを学んだ。
私の学校にも、いろいろな家庭の友達がいるけど、みんな大切な友達だ。
『君たちはどう生きるか』を読んで、私も自分なりの「どう生きるか」を考えてみた。
まずは、困っている友達がいたら勇気を出して助けてあげたい。
そして、自分のことだけでなく、周りの人のことも考えられる人になりたい。
コペル君のように、失敗しても諦めずに、いつも正しいことをしようと努力する人になりたいと思った。
この本を読んで、私はまだ子供だけど、これからどんな大人になりたいかを真剣に考えるようになった。
コペル君が最後に決意を書いたように、私も自分なりの目標を持って、毎日を大切に過ごしていきたい。
『君たちはどう生きるか』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】自分で考えることの大切さ
『君たちはどう生きるか』を読んで、私は人間として成長することの本当の意味を考えさせられた。
主人公のコペル君が体験する様々な出来事は、私たち中学生の現実と重なる部分が多く、まるで自分のことのように感じられた。
最も印象深かったのは、コペル君の「ものの見方」が変化していく過程である。
銀座のデパートから人々を見下ろした時に、自分も世界の一部に過ぎないと気づく場面は、自己中心的な考え方から脱却する重要な転換点だった。
私も今まで、自分の視点からしか物事を見ていなかったことが多かったが、コペル君のように広い視野で世界を捉えることの大切さを学んだ。
叔父さんが「コペルニクスのように考えるか、それとも地球が宇宙の中心だと考えるか」という例えで説明していたが、これは天文学だけでなく、人生や社会を考える上でも重要な視点だと思う。
友人関係においても、自分だけが正しいと思い込まずに、相手の立場や気持ちを理解しようとする姿勢が必要なのだと実感した。
コペル君が北見君を守れなかった雪の日の出来事も印象的だ。
約束していたのに勇気が出せず、友達を助けることができなかった場面は、読んでいて胸が苦しくなった。
私も似たような経験があるからだ。
クラスでいじめが起きた時、止めに入るべきだと頭では分かっていても、自分も標的になることを恐れて行動できなかった。
コペル君がその後、深く後悔し、友人たちに謝罪する姿は、自分の弱さと向き合う勇気を示していた。
失敗を犯すことは仕方ないが、その失敗から学び、次回は正しい行動を取ろうとする意志こそが重要なのだと気づかされた。
叔父さんのノートで語られる「自分で考えることの大切さ」も、現代の私たちにとって非常に重要なメッセージだと感じた。
インターネットやSNSで様々な情報が溢れる中、他人の意見に流されるのではなく、自分の頭で考え、自分の良心に従って判断する能力を身につけることが必要だ。
コペル君が粉ミルクの缶から世界中の人々の生産関係を考えたり、浦川君との交流を通じて貧富の差について深く考えたりする場面では、身近なものから社会の構造を理解しようとする姿勢が描かれている。
私たちも日常生活の中で、様々な社会問題について自分なりに考える習慣を持つべきだと思った。
最終的に、コペル君が叔父さんに向けて「自分の将来の生き方」について決意を書き綴る場面では、人間としての成長が描かれている。
単に知識を得るだけでなく、その知識を基に自分なりの人生観を構築し、社会の中で自分が果たすべき役割を見つけることの重要性を学んだ。
私もコペル君のように、「世の中の誰かのために自分ができることは何か」を常に考えながら生きていきたい。
『君たちはどう生きるか』を読んで、私は自分の中学生としての生活を見直すきっかけを得た。
勉強や部活動に追われる毎日だが、その中でも人間として成長するための時間を大切にしたい。
友達との関係では、相手の立場に立って考える姿勢を忘れずに、困っている人がいれば勇気を持って手を差し伸べたい。
そして何より、自分の頭で考え、自分の信念に基づいて行動する人になりたいと強く思った。
『君たちはどう生きるか』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】真の成長とは何かを問う旅
『君たちはどう生きるか』を読み終えて、私は、人が成長するというのは、心が大人になって、自分で正しいことを決められるようになる、すごく難しいプロセスだと深く理解した。
吉野源三郎が1937年に書いたこの本は、今の私たち高校生が直面する色々な問題に対しても、すごく大切なことを教えてくれる、優れた本だと感じた。主人公のコペル君が経験を通して成長していく様子は、今の私たちにもすごく参考になる。
まず、一番印象に残ったのは、コペル君が「見方が変わった」ことだ。銀座のデパートから街の人たちを見た時に、自分もこの広い世界の一部なんだと気づく場面がそうだった。
おじさんがコペルニクスの地動説の話を出して説明してくれた「物の見方」の大切さは、私たちがつい自分中心に考えがちなのをやめるきっかけになると思った。この見方の変化は、人との関わり方や社会に対する考え方を大きく変えるものだと感じる。
私自身も高校生活で、自分の考えが絶対ではなく、色々な考え方があるのだということを学んできた。クラスメイトとの話し合いや、違う国の人たちと交流する中で、コペル君と同じように見方が変わる経験をしている。
次に深く考えさせられたのは、勇気を出して正しいことをする、という問題だ。雪の日に北見君が先輩からひどいことをされた時、コペル君が約束していたのに助けられなかった出来事は、私たちが直面する一番難しい問題の一つだと感じた。
この場面で描かれているのは、正しいと分かっていても、怖かったり、自分を守りたかったりで行動できない人間の弱さである。しかし重要なのは、コペル君がその後深く反省して、友達に謝罪し、自分の行動をもう一度考え直したことだ。
今の社会でも、いじめや、悪いことを見てしまった時など、勇気が試される場面はたくさんある。SNSでひどい言葉を見た時、学校で不正行為を目撃した時、私たちはどうするべきなのだろうと考えさせられた。コペル君の経験は、正しいことをするというのは難しいが、それがどれだけ大切かを教えてくれる。
おじさんのノートに出てくる、色々な考え方も、この本の大きな魅力の一つだ。特に「自分で考えることの大切さ」について書かれている部分は、情報があふれる今の時代を生きる私たちにとって、すごく大事なことだと感じた。
インターネットやSNSでたくさんの情報が手に入るが、それが本当か、役に立つかを自分で見極める力がますます必要になっている。おじさんが強調する「人の意見にただ従うのではなく、自分の経験と頭で判断する」という姿勢は、嘘の情報や、人を煽るような話が多い今の社会で、もっともっと大事になるだろうと思った。
コペル君が粉ミルクの缶から世界のつながりを考えたり、浦川君との出会いから社会の不公平について考えたりする場面では、身近なことから世の中全体を理解しようとする、頭の使い方が示されている。これは、物事を批判的に考える力を育てる上でも、すごく大切なことだと思う。
私たち高校生も、毎日の生活の中で色々な社会問題に触れている。貧富の差、環境問題、世界の動きなど、一見難しそうに見える問題も、コペル君のように身近なことから考え始めれば、もっと深く理解できるのではないだろうか。
また、ガンダーラという場所の仏像の話や、水仙の芽を見て感動する場面では、昔からある文化や、自然の命に対する感動する心が描かれている。今の社会は効率や便利さが大事にされがちだが、人の豊かな心や感情も、バランスの取れた人になるにはすごく必要だと感じた。
最終的に、コペル君がおじさんに自分の決意を書く場面では、本当に成長した姿が示されている。それはただ知識が増えたり、できるようになることではなく、自分なりの人生の考え方を見つけて、社会の中で自分が何をすべきかを分かることなのだと思った。「君たちは、どう生きるか」という最後の問いは、読んでいる私たち一人ひとりに向けられた、人生の大きな宿題である。
私はこの本を読んで、高校生としての自分の生活を根本から見直すきっかけを得た。受験勉強や進路で忙しい毎日の中で、つい忘れがちな「人としてどう生きるべきか」という一番大切な問いと向き合うことの大切さを改めて感じた。
友達との関係では、相手の立場や気持ちを分かろうとする優しい気持ちを大事にしたい。勉強では、ただ覚えるだけではなく、自分で考えて判断する力をつけたい。そして社会の問題に対しては、無関心でいるのではなく、自分なりに考え、できる範囲で行動していく責任を持ちたい。
『君たちはどう生きるか』は、時代を超えて愛読される理由を持つ名作である。コペル君の成長の物語は、今の私たち若い世代にとっても、人生の道しるべになる、貴重な教訓をくれる。この本が投げかける「どう生きるか」という問いに、これからも真摯に向き合い続けていきたい。
振り返り
ここまで『君たちはどう生きるか』の読書感想文について、詳しく解説してきました。
この記事では、小学生から高校生まで、それぞれの学年に適した例文と書き方のポイントをお伝えしました。
重要なことは、コピペに頼るのではなく、あなた自身の体験や感じたことを大切にして、オリジナルの感想文を書くことです。
『君たちはどう生きるか』は、読む人の年齢や立場によって、様々な気づきや学びを与えてくれる素晴らしい作品ですね。
この記事で紹介した3つの要点を参考にしながら、あなたなりの「どう生きるか」を考えて、心のこもった感想文を書いてください。
きっと素晴らしい読書感想文が完成するはずです。頑張ってくださいね。
※『君たちはどう生きるか』のあらすじはこちらでご紹介しています。




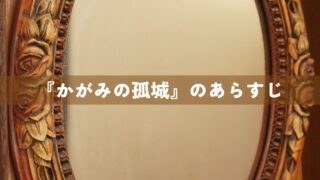




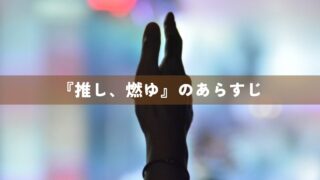



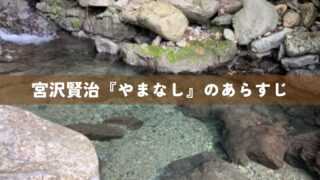


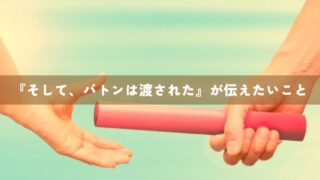
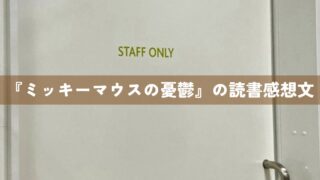

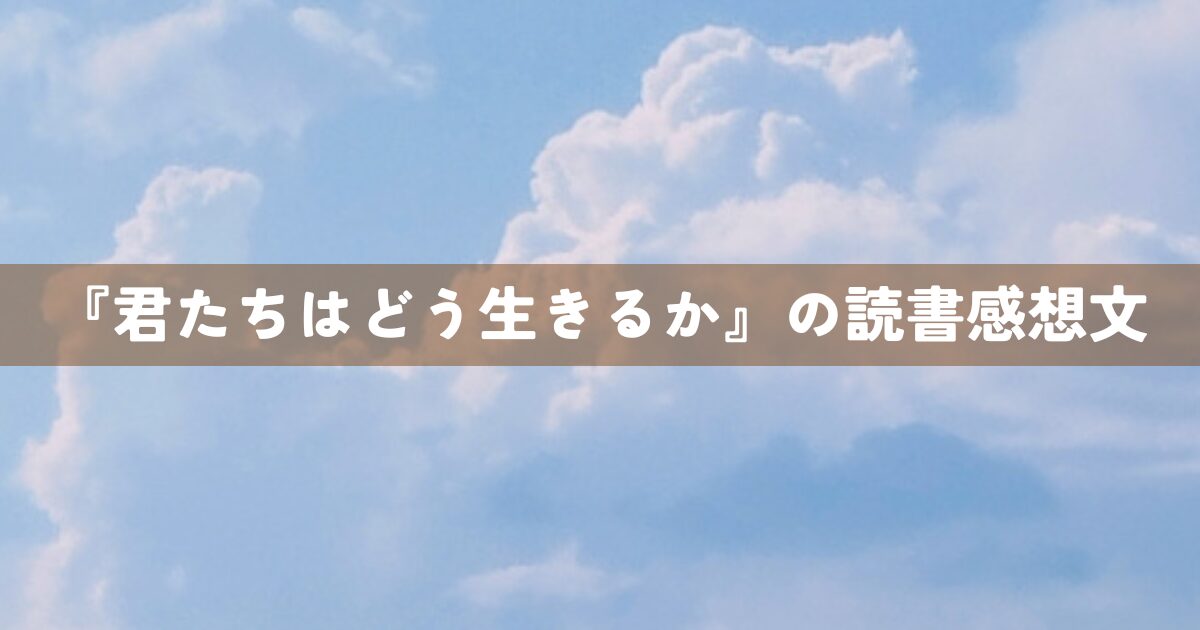
コメント