『ぼくの色、見つけた!』のあらすじを解説していきますね。
この作品は志津栄子さんによる色覚障がいをテーマにした児童文学で、第24回ちゅうでん児童文学賞の大賞を受賞した感動作。
第71回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれた一冊でもあります。
主人公の信太朗くんが自分の個性と向き合いながら成長していく姿が描かれており、多様性や自己受容の大切さを教えてくれる心温まる物語となっています。
私は普段から多くの児童文学を読んでいるのですが、この作品は特に現代の子どもたちが抱える悩みに寄り添った内容で、読書感想文を書く皆さんにとって非常に参考になる作品だと思います。
簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、そして私の率直な感想も含めて、この記事を読めば『ぼくの色、見つけた!』の魅力がしっかりと理解できるはずですよ。
志津栄子『ぼくの色、見つけた!』のあらすじを短く簡単に(ネタバレなし)
志津栄子『ぼくの色、見つけた!』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
小学5年生の井上信太朗は色覚障がいを持ち、特に赤色の判別が困難。
2年生のときに診断されて以降、友達には秘密にして過ごしているが、図工や家庭科など色を使う授業では常に緊張と不安に襲われる。
母親は信太朗を心配するあまり「かわいそう」と口にしてしまい、本人は自分が普通だと思っているのに周囲の反応に戸惑いを感じている。
クラスメイトの足立友行は、かつて信太朗の色選びを間違えたことをからかったため、信太朗は友行に対して苦手意識を持つようになった。
しかし新学年になり、担任の平林先生との出会いが信太朗の心に大きな変化をもたらす。
平林先生の父親も色覚障がいであることをホームルームで知り、信太朗は少し心が軽くなる。
先生が苦手な一輪車に挑戦する姿を見て、弱みを見せてもいいのだと学んだ信太朗は、家族や祖父母の理解に支えられながら成長していく。
ある日、祖父の家へ向かう途中で偶然友行と出会い、お互いのコンプレックスを打ち明け合うことで心の距離が縮まる。
信太朗は自分が人と違う色の世界で生きていることを個性として受け入れ始め、最終的に自分だけの色を見つけ出していく。
『ぼくの色、見つけた!』のあらすじを理解するための用語解説
『ぼくの色、見つけた!』を理解するために重要な専門用語を以下の表にまとめました。
これらの用語を知っておくことで、より深く作品を理解できるでしょう。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 色覚障がい | 色の見え方が一般的な人と異なる状態のこと。 赤と緑の区別がつきにくいなどの特徴がある。 現在は色覚多様性とも呼ばれる。 |
| 自己受容 | ありのままの自分を認めて受け入れること。 他者と違う部分があっても、 それを否定せずに向き合う態度。 |
| 多様性 | 様々な違いや個性を認め合うこと。 人それぞれの特徴を前向きに捉える考え方。 |
| 個性 | その人だけが持つ特徴や性質のこと。 作中では「自分の色」として表現されている。 |
『ぼくの色、見つけた!』の感想
この作品、読んですごく心に響きました。なんていうか、胸がいっぱいになっちゃって。
まず、何よりも信太朗くんの心の動きが、本当にていねいに描かれているのが素敵でしたね。色覚障がいっていう、ちょっと特別な特性を持ってる子の気持ちが、ここまでリアルに描かれた児童文学って、なかなかないんじゃないかなぁ。
信太朗が図工の時間に色を間違えて、お友達にからかわれちゃうシーン、もう読んでて胸がギュッとなりました。子どもの世界って、ちょっとした違いが、すごく大きな悩みになっちゃうこと、ありますもんね。それを作者の志津栄子さんが、先生としての経験を活かして、本当に「そうそう、これこれ!」ってくらいリアルに書いてるのが印象的でした。
特に、お母さんが「かわいそう」って言っちゃう場面は、親の愛情と、子どもの「自分は普通なのに」っていう気持ちがすれ違っちゃうのが、なんとも複雑でした。
お母さんとしては心配で仕方ないんだろうけど、信太朗からしたら「別に自分はこれでいいのに」って思うわけじゃないですか。この微妙な心の動きが細かく描かれてるから、ぐっとくるポイントになってるんだなぁって思いました。
担任の平林先生の存在も、もう最高でした!自分のパパも色覚障がいだって、すーっと自然に話して、信太朗の心のモヤモヤを軽くしてあげるんですよね。それに先生自身が苦手な一輪車に挑戦する姿を見せることで、「苦手なことあってもいいんだよ」ってメッセージを伝えてくれるんです。この部分では、先生って本当にすごいお仕事だなぁって、改めて感じました。
クラスメイトの友行くんとの関係性の変化も、すごく感動しました。最初は信太朗をからかってた友行が、実は自分も背が低いことで悩んでたんだってわかったりして。お互いの苦手なところとか、悩みを打ち明け合うことで、本当の友達になれるんだなぁって、読んでて心が温かくなりました。子どもたちが大きくなっていく中で、こういう理解し合える関係を築けるのって、すごく大切なことだなって教えてくれますよね。
信太朗が最終的に「自分の色」を見つけ出すっていう結末も、本当にグッときましたね。人と違うことを恥じるんじゃなくて、それが「自分の素敵なところなんだ!」って受け入れられるようになる。
この成長の物語は、色覚障がいを持つ子だけじゃなくて、なんだか「自分ってちょっと違うな」って悩んでるすべての子に、きっと勇気をくれると思います。
私自身も子どもの頃に、みんなと違うことで悩んだ経験があるから、もしあの時この本に出会えてたら、もっと早く自分を受け入れられたかもしれないなぁって思いました。
文章も読みやすくて、小学生でもすんなり理解できる内容なのに、大人が読んでも「なるほどね!」って考えさせられる深いテーマが描かれているのが、本当にすごいなと思いました。読書感想文の課題図書に選ばれたのも、そりゃ納得だよねって感じです。
ただ、ひとつだけ気になったのは、信太朗くんを取り巻く大人たちが、みんなすごく理解のある人たちばかりだったことかな。現実にはもうちょっと大変なこともあるんじゃないかなぁって。でも、それでも、希望が持てるというか、明るい気持ちになれる作品であることには変わりないですね。
この本を読んだら、いろんな「違い」について、改めて考えるきっかけをもらえると思います。「みんな違ってみんないい」。そんな当たり前だけど、忘れちゃいそうなことを、じんわり教えてくれる、本当に素敵な作品でした。
※『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文の書き方はこちらで解説しています。
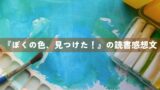
『ぼくの色、見つけた!』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 志津栄子 |
| 出版年 | 2023年 |
| 出版社 | 講談社 |
| 受賞歴 | 第24回ちゅうでん児童文学賞大賞 第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書 |
| ジャンル | 児童文学・成長小説 |
| 主な舞台 | 現代の小学校・家庭 |
| 時代背景 | 現代 |
| 主なテーマ | 色覚障がい・個性・自己受容・多様性 |
| 物語の特徴 | 主人公の心の成長を丁寧に描いた感動作 |
| 対象年齢 | 小学校高学年~中学生 |
『ぼくの色、見つけた!』の主要な登場人物とその簡単な説明
『ぼくの色、見つけた!』の中心となる登場人物たちを重要度の高い順に紹介します。
それぞれのキャラクターが信太朗の成長に重要な役割を果たしています。
| 登場人物 | 紹介 |
|---|---|
| 井上信太朗 | 小学5年生の男の子で物語の主人公。 色覚障がいを持ち、赤色の判別が苦手。 自分の個性を受け入れながら成長していく。 |
| 平林和也先生 | 信太朗のクラス担任。 自身の父親も色覚障がいを持つため、 信太朗の気持ちを理解し支える。 苦手な一輪車に挑戦する姿で生徒に勇気を与える。 |
| 足立友行 | 信太朗のクラスメイト。 最初は信太朗をからかっていたが、後に真の友情を築く。 自分も背が低いことでコンプレックスを抱えている。 |
| 信太朗の母親 | 信太朗を心配するあまり「かわいそう」と言ってしまう。 愛情深いが、時に過保護になってしまう。 物語を通して息子への理解を深めていく。 |
| 信太朗の父親 | 家族のために働く優しい父親。 信太朗を温かく見守り、成長を支える。 家事も積極的に行う現代的な父親像。 |
| 信太朗の祖父母 | 信太朗を愛情深く見守る存在。 時に助言やサポートを提供する。 信太朗の心の支えとなる。 |
| 信太朗のおば | 信太朗の理解者の一人。 温かく見守り、時に励ましの言葉をかける。 |
『ぼくの色、見つけた!』の読了時間の目安
『ぼくの色、見つけた!』の読了時間について、ページ数や文字数から計算した目安を紹介します。
読書感想文を書く際の参考にしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総ページ数 | 224ページ |
| 推定文字数 | 約134,400文字 |
| 読了時間 | 約4時間30分 |
| 1日30分読書 | 約9日で読了 |
| 1日1時間読書 | 約5日で読了 |
文章は読みやすく、小学生でも理解しやすい内容になっています。
集中して読めば一気に読み終えることができる分量ですので、読書感想文の準備にも十分な時間を取れるでしょう。
『ぼくの色、見つけた!』はどんな人向けの小説か?
『ぼくの色、見つけた!』がどのような読者に向いているか、私なりに分析してみました。
特に以下のような人におすすめしたい作品です。
- 自分と他人の違いに悩んでいる子どもや大人
- 家族や友人関係で悩みを抱えている人
- 多様性や個性について考えたい人
この作品は、みんなと違うことで悩んでいる人に勇気を与えてくれます。
色覚障がいという具体的なテーマを通して、自己受容の大切さを教えてくれるからです。
また、家族や友人との関係性についても深く描かれているため、人間関係で悩んでいる人にも参考になるでしょう。
逆に、すでに自分の個性を十分に受け入れている人や、深刻な悩みを抱えていない人にとっては、やや物足りなく感じられるかもしれません。
しかし、多様性について考える機会としては、どのような人にも価値のある作品だと思います。
あの本が好きなら『ぼくの色、見つけた!』も好きかも?似ている小説3選
『ぼくの色、見つけた!』と似たテーマや雰囲気を持つ作品を紹介します。
個性や多様性、自己受容をテーマにした作品が好きな方は、きっと気に入るはずです。
『ベルナのしっぽ』郡司ななえ
盲導犬ベルナと女性ユーザーの日常を描いた実話ベースの小説です。
視覚障がいという「違い」を生きる経験と、周囲の支え、自己肯定感の大切さが物語の軸になっています。
『ぼくの色、見つけた!』と同様に、見え方に関する困難や人と異なることへの葛藤と成長という点で共通しています。
障がいを持つ人の心境や、それを取り巻く人々の理解について学べる作品です。
『スイミー』レオ・レオニ
小さな黒い魚スイミーが、兄弟たちとは異なる自分の特性を活かして仲間を守る絵本です。
スイミーは自分の色(個性)を受け入れ、それを仲間との協調の中で生かす方法を見つけます。
『ぼくの色、見つけた!』の信太朗が自分の色を探すのと同様に、スイミーも自身の特性を認識し、それをポジティブに捉え直す点で共通しています。
個性を大切にしながら、集団の中でも輝ける方法を教えてくれる作品です。
『君の膵臓をたべたい』住野よる
膵臓の病気を患う少女と内向的な少年の交流を描いた青春小説です。
人と違うことへの悩みや、自分らしさを見つけていく過程が丁寧に描かれています。
『ぼくの色、見つけた!』と同様に、主人公が自分の個性と向き合いながら成長していく物語です。
人間関係の大切さや、ありのままの自分を受け入れることの意義を教えてくれる作品として共通点があります。
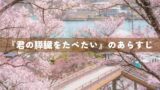
振り返り
『ぼくの色、見つけた!』は、色覚障がいを持つ小学生の成長を描いた心温まる作品です。
主人公の信太朗が自分の個性を受け入れながら成長していく姿は、多くの読者に勇気を与えてくれるでしょう。
志津栄子さんの教師としての経験が活かされた、リアルで感動的な物語となっています。
読書感想文の課題図書として選ばれたのも納得の、現代の子どもたちに必要なメッセージが込められた作品です。
自分と他人の違いに悩んでいる人、多様性について考えたい人にぜひ読んでいただきたい一冊です。
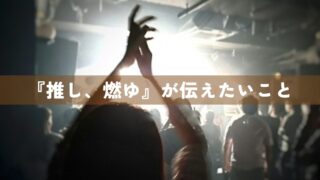
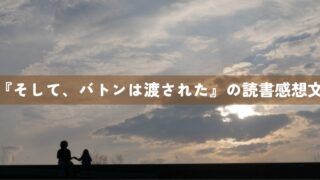



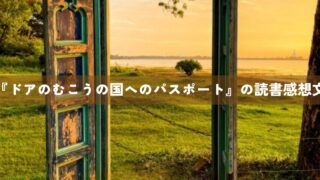
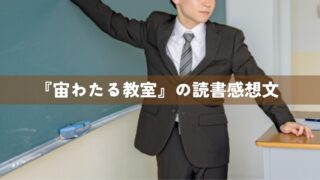
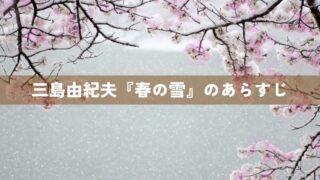

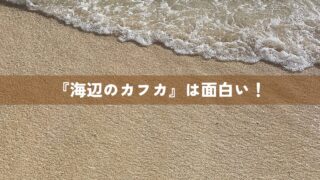



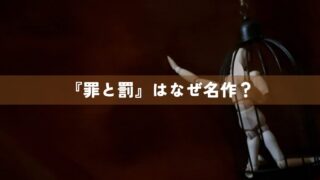


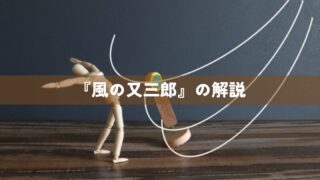

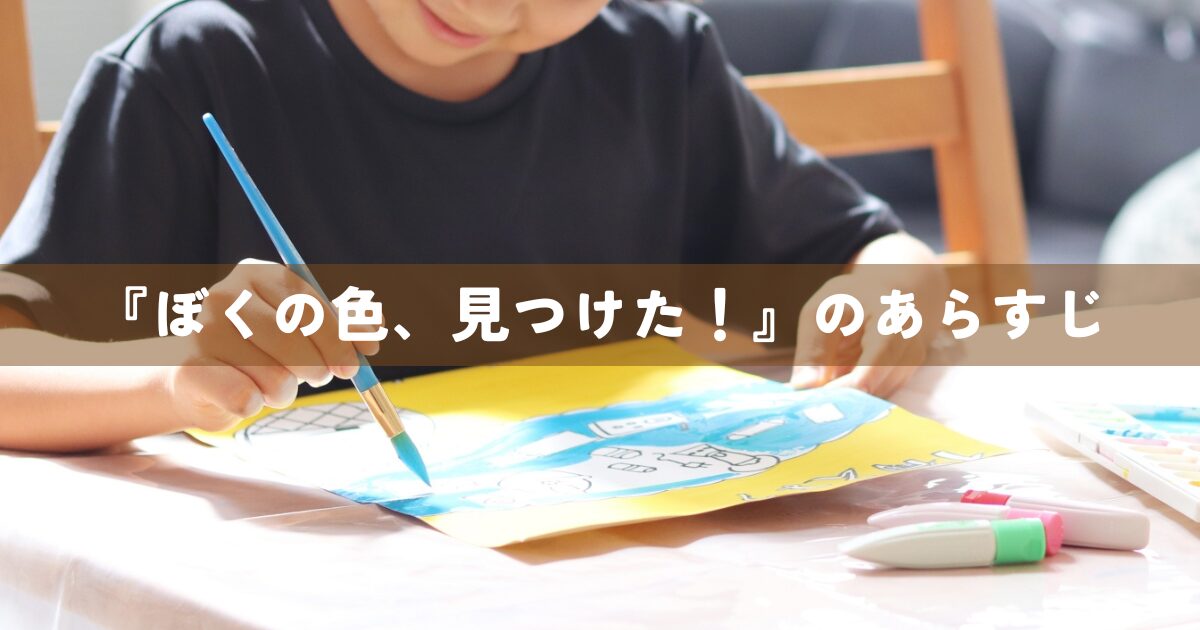
コメント