『清兵衛と瓢箪』のあらすじをにご紹介していきますよ。
『清兵衛と瓢箪』は志賀直哉の短編小説で、ひょうたんをこよなく愛する少年と、その価値観が分からない大人たちとの葛藤を描いた作品。
私は年間100冊以上の本を読みますが、この作品の魅力は主人公・清兵衛の純粋な情熱と大人世界の冷たさの対比にあると感じています。
読書感想文を書く予定の学生のみなさんの力になれるよう、簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、丁寧に解説していきますね。
『清兵衛と瓢箪』の短くて簡単なあらすじ
瓢箪に熱中する12歳の清兵衛は、父親や教員に理解されず困難に直面する。
ある日、素晴らしい瓢箪を見つけた清兵衛だったが、授業中に磨いていたところを教員に見つかり取り上げられてしまう。
怒った父は清兵衛のすべての瓢箪を壊してしまうが、その取り上げられた瓢箪は実は非常に価値のあるものだった。
『清兵衛と瓢箪』の中間の長さのあらすじ
12歳の清兵衛は瓢箪に熱中するあまり、父親からは「子どものくせに」と批判される日々を送っていた。
ある日、清兵衛は素晴らしい瓢箪を10銭で購入し夢中になるが、学校の授業中に磨いていたところを教員に見つかり没収されてしまう。
教員の訴えを聞いた父親は激怒し、彼のコレクションをすべて壊す。
しかし、没収された瓢箪は骨董屋を通じて600円という高値で売られ、清兵衛の目利きの確かさが皮肉にも証明された。
『清兵衛と瓢箪』の詳しいあらすじ
12歳の小学生・清兵衛は瓢箪に熱中し、日々瓢箪を磨いては飽きずに眺めていた。
しかし父親は「子どものくせに」と清兵衛の情熱を快く思わず、来客も「もっと奇抜な瓢箪を集めるべきだ」と清兵衛の趣味を理解しなかった。
ある日、清兵衛は屋台で震えるほど美しい瓢箪を10銭で見つけ購入する。
彼はその瓢箪に夢中になり、学校の修身の授業中にまで磨き続けたため、担任教員に見つかって取り上げられてしまう。
教員は清兵衛の家にまで来て説教し、激怒した父親は清兵衛を殴りつけ、すべての瓢箪を玄翁(げんのう)で割ってしまう。
皮肉なことに、取り上げられた瓢箪は小使いが骨董屋に50円で売り、さらに骨董屋はそれを豪家に600円(現代価格で約120万円)で売却した。
一方、瓢箪を失った清兵衛は次に絵を描くことに熱中し始めるが、父親は絵にも小言を言い始めるのだった。
『清兵衛と瓢箪』の作品情報
『清兵衛と瓢箪』の基本情報をまとめてみました。
読書感想文を書く際の参考にしてくださいね。
| 作者 | 志賀直哉 |
|---|---|
| 出版年 | 1913年(大正2年) |
| 掲載紙 | 読売新聞 |
| 収録文庫 | 集英社文庫、新潮文庫など |
| 長さ | 短編小説 |
| 主な舞台 | 小学校と清兵衛の家 |
| 時代背景 | 大正時代初期 |
| 主なテーマ | 子どもの純粋な情熱と大人の価値観の対立 |
| 物語の特徴 | ユーモラスな筆致ながら、作者の父との確執が投影されている |
| 対象年齢 | 中学生以上 |
『清兵衛と瓢箪』の主要な登場人物とその簡単な説明
『清兵衛と瓢箪』の物語を理解するうえで重要な登場人物をご紹介します。
それぞれのキャラクターの特徴をつかんでおくと、読書感想文を書くときに役立ちますよ。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| 清兵衛 | 主人公。12歳の小学生。瓢箪に熱中し、のちに絵を描くことに熱中する。「清」は清らかさを表し、純粋な性格を表している。 |
| 清兵衛の父 | 大工の職業。清兵衛に厳しく、瓢箪を玄翁で割ってしまう。春の品評会に参加する。 |
| 清兵衛の母 | 教員から清兵衛のことを注意され、泣く。目立った行動はあまりない。 |
| 客 | 清兵衛の父を訪ねてくる人物。奇抜な瓢箪を好む。 |
| 教員 | 小学校の担任。よそから来ている。清兵衛が授業中に瓢箪を磨いていたことを厳しく叱り、瓢箪を取り上げる。 |
| 小使い | 小学校の用務員。年配の賢い男で、教員から受け取った瓢箪を骨董屋に50円で売る。 |
| 骨董屋 | 小使いから買った瓢箪を地方の豪家に600円で売りつける商人。 |
| 婆さん | 清兵衛に10銭で瓢箪を売る屋台の女性。 |
『清兵衛と瓢箪』の文字数と読むのにかかる時間
『清兵衛と瓢箪』は短編小説なので、それほど時間をかけずに読むことができますよ。
文字数と読了時間の目安をまとめました。
| 推定文字数 | 約12,000文字(約20ページ) |
|---|---|
| 読了時間の目安 | 約24分(500字/分の読書速度の場合) |
| 1日あたりの読書目安 | 1日で読み終えられる長さ |
| 読みやすさ | 平易な文章で読みやすい |
短い作品なので、じっくりと内容を味わいながら、一気に読むことができます。
読書感想文を書く場合は、一度読んだあとで、もう一度読み返すことをおすすめしますよ。
『清兵衛と瓢箪』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『清兵衛と瓢箪』の読書感想文を書く際に、特に注目すべきポイントを3つ紹介します。
これらの要素を押さえておくと、より深みのある感想文が書けますよ。
- 子どもの純粋な情熱と大人の価値観の対立
- 真の価値を見抜く目と社会の評価のずれ
- 個性や才能の芽を潰す教育の問題点
それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
子どもの純粋な情熱と大人の価値観の対立
『清兵衛と瓢箪』の中心テーマは、子どもの純粋な情熱と大人の価値観の対立です。
清兵衛は瓢箪に熱中し、その形や色に純粋な美を見出していました。
しかし、父親や来客、教員といった大人たちは、子どもが瓢箪に熱中することを「子どものくせに」と否定的に捉えます。
大人たちは、子どもには子どもの世界があり、瓢箪のような骨董品に興味を持つことは不自然だと考えているのです。
この対立は、大人が自分の価値観を押し付け、子どもの個性や関心を尊重しないという問題を浮き彫りにしています。
読書感想文では、このような大人と子どもの価値観の違いについて、自分の経験と照らし合わせながら考察すると良いでしょう。
真の価値を見抜く目と社会の評価のずれ
清兵衛が10銭で買った瓢箪が、実は600円(現代価格で約120万円)もの価値があったという展開は、この物語の大きな皮肉です。
清兵衛は直感的に瓢箪の美しさと価値を見抜いていましたが、周囲の大人たちはそれを理解できませんでした。
結果的に、彼の目利きの確かさは証明されたものの、そのことを知る者は誰もいません。
この「真の価値を見抜く目」と「社会の評価のずれ」は、私たちの社会でも見られる現象です。
感想文では、世間の評価と本当の価値の関係について、自分の考えを展開すると良いでしょう。
個性や才能の芽を潰す教育の問題点
物語の中で、清兵衛の瓢箪への情熱は教員によって否定され、父親によって完全に潰されてしまいます。
しかし、清兵衛はそれでも諦めず、次は絵を描くことに熱中します。
これは、子どもの個性や才能の芽を大人の一方的な判断で潰してしまう教育の問題点を示しているわけですね。
作品の最後で父親が「絵にも小言を言い出す」という描写は、このような抑圧が繰り返されることを暗示しています。
感想文では、教育における個性の尊重や才能の伸ばし方について、自分の意見を述べると良いでしょう。
※志賀直哉が『清兵衛と瓢箪』で伝えたいことは、こちらの記事で考察しています。

『清兵衛と瓢箪』の読書感想文の例(原稿用紙3枚強/約1300文字)
志賀直哉作品「清兵衛と瓢箪」を読み、私は大人と子どもの価値観の違いについて深く考えさせられた。誰にでも、何かに夢中になった経験があるはずだ。私も小学生の頃、昆虫採集に熱中していたことがある。その気持ちを思い出しながら、主人公・清兵衛の姿に共感を覚えずにはいられなかった。
瓢箪に心を奪われる12歳の少年・清兵衛。彼の瓢箪への愛情は純粋で、その形や色に美しさを見出している。しかし、周囲の大人たちはそんな清兵衛の情熱を理解しない。父親は「子どものくせに」と批判し、来客は「もっと奇抜な瓢箪を集めろ」とアドバイスする。そして学校の教員は、授業中に瓢箪を磨いていた清兵衛を厳しく叱る。
特に印象的だったのは、清兵衛が10銭で買った瓢箪が実は非常に価値のあるものだったという皮肉な展開だ。清兵衛は直感的にその瓢箪の美しさを見抜いていたのに、大人たちはそれを認められなかった。結局その瓢箪は600円(今の価値で約120万円)で売られることになるが、そのことを知る者は誰もいない。
この物語は、子どもの純粋な情熱と大人の冷たい現実主義の対立を描いている。大人たちは自分の価値観で子どもを判断し、その個性や才能の芽を潰してしまう。清兵衛の父親が瓢箪をすべて壊してしまうシーンは胸が痛くなった。自分の子どもの情熱をこんな形で否定するなんて、あまりにも残酷ではないだろうか。
でも、清兵衛はそれでも諦めず、次は絵を描くことに熱中し始める。この強さに感動した。どれだけ否定されても、自分の好きなことを追求し続ける姿勢は素晴らしい。しかし、最後に父親が「絵にも小言を言い出す」という部分は、この悲劇が繰り返されることを暗示していて悲しい気持ちになった。
私はこの作品を読んで、子どもの興味や関心を尊重することの大切さを学んだ。大人は「子どものくせに」と決めつけるのではなく、その情熱を理解し、才能を伸ばす手助けをするべきだと思う。
また、本当の価値を見抜く目を持つことの大切さも感じた。清兵衛は10銭の瓢箪に大きな価値を見出したが、それは金銭的な価値ではなく、美的な価値だった。現代社会では、物事の価値を金銭で測りがちだが、本当の価値とは何なのかを考えさせられる。
この作品には志賀直哉自身の父との確執が投影されているという。作者は、大人の一方的な価値観によって抑圧される子どもの姿を通して、自らの経験を昇華させたのかもしれない。そう考えると、この物語はより深い意味を持って感じられる。
最後に、私は教育のあり方についても考えさせられた。教員が清兵衛の瓢箪を取り上げ、厳しく叱責するシーンは、学校教育の画一性や硬直性を象徴しているように思える。個性や創造性を重んじる教育が大切なのではないだろうか。
「清兵衛と瓢箪」は短い作品だが、子どもと大人の関係、真の価値、教育のあり方など、多くの問題を提起している。私は、この作品から学んだことを胸に、自分の周りの人たちの個性や情熱を尊重していきたいと思う。そして、清兵衛のように、自分の好きなことに素直に情熱を注げる人間でありたい。
『清兵衛と瓢箪』はどんな人向けの小説か
『清兵衛と瓢箪』は、さまざまな年代や関心を持つ読者に響く作品ですが、特に以下のような人に向いている小説といえるでしょう。
- 子どもの純粋な情熱や個性を大切にしたいと考える人
- 大人と子どもの価値観の違いについて考えたい人
- 社会的な評価と本当の価値のずれに興味がある人
- 教育や子育てのあり方について考えたい人
- 日本の近代文学や志賀直哉の作品に関心がある人
- 短い時間でも深いテーマを考えたい人
この小説は単なる子どもの物語を超えて、人間の価値観や社会のあり方について深い洞察を提供しています。
特に、何かに純粋に情熱を注いだ経験がある人なら、清兵衛の気持ちに共感できるでしょう。
『清兵衛と瓢箪』と類似した内容の小説3選
『清兵衛と瓢箪』の世界観や主題に近い作品を3つ紹介します。
読書の幅を広げたい方や、似たような主題を持つ作品を探している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
芥川龍之介『鼻』
芥川龍之介の『鼻』は、異常に長い鼻に悩む僧侶・禅智内供を主人公とした短編小説です。
内供は自分の長い鼻を気にして様々な治療法を試みますが、一時的に短くなった鼻が再び伸びてしまいます。
『清兵衛と瓢箪』と同様、個人の価値観や情熱が他者によって否定される状況がテーマとなっており、社会的な視線や価値観が個人の生き方に与える影響を深く掘り下げています。
宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』
宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』は、下手な演奏を周囲から批判されるチェロ奏者ゴーシュが、動物たちとの交流を通じて成長していく物語です。
ゴーシュが周囲から評価されない中で自身の情熱を持ち続ける姿は、『清兵衛と瓢箪』の清兵衛の姿と重なります。
個性や努力が認められるまでの葛藤と成長を描いている点が共通点で、最終的に才能が開花する点も類似しています。

梶井基次郎『檸檬』
梶井基次郎の『檸檬』は、主人公がレモンを通じて純粋な感情や美しさを感じる様子を描写した短編小説です。
日常の中の小さな発見や美を見出す点で『清兵衛と瓢箪』との共通点があります。
主人公がレモンに感じる特別な感覚は、清兵衛が瓢箪に見出す美的価値に通じるものがあり、社会的な価値観とは異なる個人の感性を大切にするテーマが共通しています。
振り返り
『清兵衛と瓢箪』は、瓢箪を愛する少年と、その情熱を理解できない大人たちの物語を通して、子どもの純粋な情熱、大人の価値観との対立、真の価値を見抜く目などの重要なテーマを提示しています。
この記事では、簡単なあらすじから詳しいあらすじ、作品情報、登場人物、読書感想文のポイントまで幅広く解説しました。
読書感想文を書く予定の学生のみなさんは、特に「子どもの純粋な情熱と大人の価値観の対立」「真の価値を見抜く目と社会の評価のずれ」「個性や才能の芽を潰す教育の問題点」という3つのポイントを意識すると、より深みのある感想文が書けるでしょう。
この小説の魅力は、わずか20ページほどの短い物語でありながら、人間の価値観や社会のあり方について深く考えさせる点にあります。
志賀直哉の繊細な筆致で描かれた清兵衛の物語から、私たちは何を学び、何を考えるのか。
それぞれの読者が自分なりの答えを見つけることができる、それが文学の素晴らしさではないでしょうか。

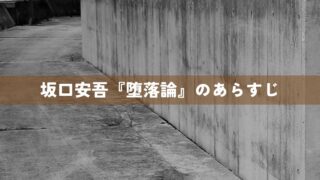



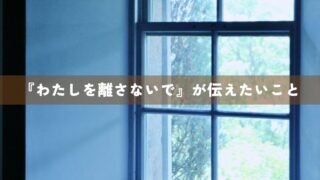



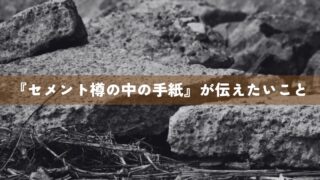
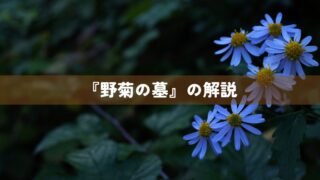

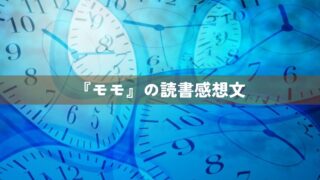


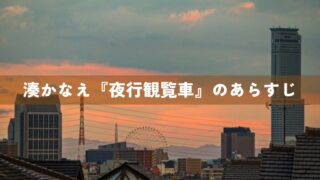

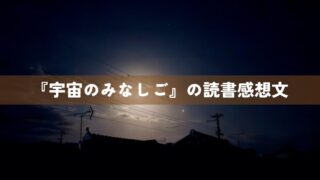
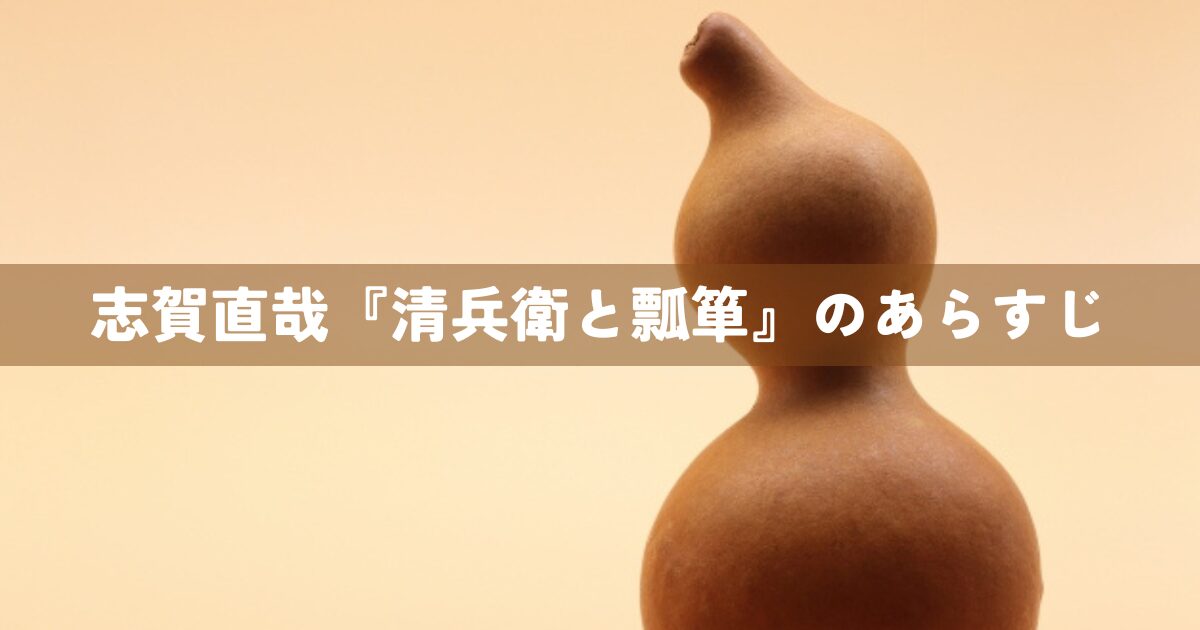
コメント