太宰治の『トカトントン』のあらすじをご紹介していきますよ。
この小説『トカトントン』は、太宰治が1947年に書いた書簡体形式の短編小説。
主人公の青年が好きな作家に宛てた手紙を通して、彼を悩ます「トカトントン」という幻聴の謎と、その青年の内面の葛藤が描かれています。
私は読書が大好きで年間100冊以上の本を読んでいるので、作品の分析は得意中の得意。
読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、短くて簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、丁寧に解説していきます。
『トカトントン』の簡単なあらすじ
『トカトントン』の中間の長さのあらすじ
『トカトントン』の詳しいあらすじ
青森県出身の26歳の「私」は、敬愛する作家に悩みを打ち明ける手紙を書く。横浜の軍需工場で働いていた頃から作家の作品を愛読していた彼は、終戦後、青森の郵便局で働くようになった。
彼を悩ませるのは「トカトントン」という幻聴だった。終戦の日、若い中尉の死を覚悟した演説に感動していた時、兵舎の背後から聞こえてきたその音によって、彼の感動はむなしいものになってしまう。それ以来、小説を書こうとする時も、花江という女性に恋をした時も、政治に関心を持った時も、何かに熱中しようとするたびにその音が聞こえ、すべてがむなしく思えてしまうのだった。
手紙の最後で「私」は、この手紙を書くときさえトカトントンが聞こえ、内容の多くは嘘であると告白する。しかし、幻聴自体は真実だと訴える。
この手紙を受け取った作家は、彼の苦悩を「気取った苦悩」と評し、マタイ伝の言葉を引用して返答した。
『トカトントン』の概要
太宰治の『トカトントン』について、基本的な情報を表にまとめてみました。
作品を理解する上での重要なポイントが一目でわかりますよ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 太宰治 |
| 出版年 | 1947年(初出は『群像』1947年1月号) |
| 収録作品集 | 『ヴィヨンの妻』(筑摩書房、1947年8月5日) |
| ジャンル | 短編小説、書簡体小説 |
| 主な舞台 | 青森県の郵便局とその周辺 |
| 時代背景 | 第二次世界大戦後の日本(敗戦直後) |
| 主なテーマ | 戦後の虚無感、青年の葛藤、自己との対話 |
| 物語の特徴 | 書簡体形式、幻聴「トカトントン」が象徴的に用いられる |
| 対象読者 | 文学愛好者、戦後文学に関心のある人、太宰治ファン |
太宰治らしい独特の世界観が表現された作品で、戦後の青年の心理状態が繊細に描かれています。
『トカトントン』の主要な登場人物とその簡単な説明
『トカトントン』に登場する主な人物たちを紹介します。
登場人物は多くありませんが、それぞれが物語において重要な役割を担っています。
| 登場人物 | 紹介 |
|---|---|
| 「私」(手紙の書き手) | 青森県出身の26歳の男性。終戦まで4年間軍隊にいた後、地元の郵便局で働く。「トカトントン」という幻聴に悩まされている。 |
| 「あなた」(手紙の宛先の作家) | 「私」が敬愛する作家。「私」の手紙を受け取り、マタイ伝を引用して返信する。 |
| 花江(はなえ) | 20歳前の女性。地元の旅館で働く女中。「私」が恋心を抱くが、実際には存在しない可能性もある。 |
| 若い中尉 | 終戦の日に、徹底抗戦を主張した軍人。彼の演説中に「私」は初めて「トカトントン」を聞く。 |
| 局長(「私」の叔父) | 「私」が勤める郵便局の局長。「私」の母の兄にあたる。 |
物語は主に「私」の視点から展開されますが、最後に作家からの返信が示されることで、別の視点からの解釈も提示されています。
『トカトントン』の文字数と読むのにかかる時間
『トカトントン』はじっくり読むのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
文字数と読了時間の目安をまとめました。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 文字数 | 約13,000文字 |
| ページ数の目安 | 約22ページ(1ページ600文字計算) |
| 読了時間の目安 | 約26分(1分間に500字読む計算) |
短編小説なので、通常は1時間もかからずに読めます。
でも、太宰治の作品は言葉の一つひとつに意味が込められているので、ゆっくりと味わいながら読むことをおすすめしますよ。
『トカトントン』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
読書感想文を書くときには、作品の核心に触れる重要なポイントを押さえておくことが大切です。
『トカトントン』について感想文を書く際に外せないポイントを3つ紹介します。
- 「トカトントン」の音が象徴するものと主人公の内面の葛藤
- 戦後の若者の喪失感と価値観の揺らぎ
- 聖書の引用(マタイ伝)が示す人間の生き方についての問い
これらのポイントを押さえて感想文を書くと、作品の深い理解を示すことができますよ。
それぞれについて詳しく解説していきます。
「トカトントン」の音が象徴するものと主人公の内面の葛藤
物語の中心となる「トカトントン」という音は、単なる幻聴以上の意味を持っています。
この音は主人公が何かに熱中したり、感動したりしようとするたびに現れ、彼の情熱をくじいてしまいます。
感想文では、この音が象徴するものについて考察してみましょう。
それは敗戦後の虚無感かもしれませんし、主人公自身の内面にある諦めや不安の表れかもしれません。
あるいは、彼の行動や感情が本物ではないことを教えてくれる警告のようなものかもしれません。
例えば、こんな風に書けますよ。
「『トカトントン』という音は、主人公の心の奥底から湧き上がってくる懐疑の声のように思えます。彼が情熱を注ごうとするたび、その情熱が本物なのか、自分自身に問いかけているようです。音が聞こえると同時に白々しくなるのは、自分の感情や行動に対する誠実さを問われているからではないでしょうか。」
戦後の若者の喪失感と価値観の揺らぎ
この作品が書かれた時代背景は、第二次世界大戦後の混乱期です。
敗戦によって、それまでの価値観が大きく揺らいだ時代でした。
主人公もまた、そうした時代の中で生きる若者の一人として描かれています。
感想文では、主人公の抱える虚無感や喪失感が、当時の社会状況とどのように結びついているのかについて考えてみましょう。
また、彼が小説を書こうとしたり、恋をしたり、政治に関心を持ったりする行動が、新しい価値観を模索する試みであったことについても触れるとよいでしょう。
例えば、こんな風に書けますよ。
「戦争が終わった直後の日本では、多くの若者が目標を見失い、新しい生き方を模索していました。主人公もその一人として、小説を書くこと、恋愛、政治への関心など、さまざまな方向に自分の居場所を探そうとします。しかし、『トカトントン』という音によって、その試みは次々と挫折していきます。この繰り返される挫折は、戦後の若者が感じていた喪失感や方向性の見えない不安を象徴しているように思えます。」
マタイ伝の引用が示す人間の生き方についての問い
作品の最後で、作家が主人公に返す手紙にはマタイ伝からの引用があります。
その引用された言葉は、生き方の本質について問いかけています。
感想文では、このマタイ伝の言葉が主人公の抱える問題にどのような示唆を与えているのか、また、太宰治がこの引用を通して何を伝えようとしたのかについて考察すると、作品の深い理解を示すことができます。
例えば、こんな風に書けますよ。
「作家が引用したマタイ伝の言葉は、表面的な生き方や感情ではなく、より本質的なものに目を向けることの大切さを説いているようです。主人公の『トカトントン』という幻聴は、彼が表面的な熱意や感動に流されようとするとき、より本質的なものへと目を向けさせるための警告なのかもしれません。太宰治はこの引用を通して、戦後の混乱期にあっても、人間が真に恐れるべきは肉体の消滅ではなく、魂の消滅であることを伝えようとしているのではないでしょうか。」
以上の3つのポイントを押さえながら、自分自身の感じたことや考えたことを織り交ぜて感想文を書いてみてください。
『トカトントン』という小さな物語の中に、太宰治は人間の生き方や戦後社会の問題など、大きなテーマを詰め込んでいます。
※太宰治が『トカトントン』を通じて伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『トカトントン』の読書感想文の例(原稿用紙4枚/約1600文字)
太宰治の『トカトントン』を読み終えた直後、奇妙な感覚に包まれた。主人公が悩まされる「トカトントン」という音が、まるで私の心の中にも響いているようだった。この音は単なる幻聴ではなく、人間の内面にある何かを象徴しているのではないかと考えずにはいられなかった。
物語は、青森県出身の26歳の青年が、敬愛する作家に宛てた一通の手紙という形で始まる。彼は終戦後、地元の郵便局で働きながら、奇妙な経験に悩まされていた。何かに熱中しようとするたび、「トカトントン」という音が聞こえてきて、すべてがむなしく感じられてしまうのだ。小説を書こうとしても、恋をしても、政治に関心を持っても、その音とともに情熱は消え失せる。
この「トカトントン」という音が象徴するものについて、私は長い間考えた。それは敗戦後の日本社会全体を覆っていた虚無感かもしれない。あるいは、若者が感じる将来への不安や、自分の行動に対する疑念の表れかもしれない。いずれにしても、この音は主人公の心の奥底から湧き上がってくる何かであり、彼自身と切り離せないものだと感じた。
特に印象的だったのは、主人公が終戦の日に経験したエピソードだ。若い中尉の死を覚悟した演説に感動していた彼だが、「トカトントン」という音を聞いた途端、その感動はむなしいものになってしまう。この場面は、戦時中の価値観が一瞬にして崩れ去る戦後の混乱を象徴しているようにも思えた。かつては絶対的だった価値観が、突然意味をなさなくなる——そんな時代の空気が、この短いエピソードに凝縮されている。
また、主人公が幾度となく新しい情熱を見つけようとする姿には、戦後の若者の姿が重なって見える。彼は小説を書こうとし、田舎の郵便局での仕事に打ち込もうとし、花江という女性に恋をしようとする。しかし、そのたびに「トカトントン」によって挫折してしまう。これは戦後の若者が、新しい価値観や生きがいを模索しながらも、なかなか確かなものを見つけられない葛藤を表しているのではないだろうか。
作品の最後で、作家が主人公に返す手紙に引用されたマタイ伝の言葉も心に残った。この言葉は、表面的な生き方ではなく、より本質的なものに目を向けることの重要性を説いているように思えた。あるいは太宰は、この引用を通して、戦後社会において本当に恐れるべきは何なのかを問いかけているのかもしれない。
この作品を読みながら、私は現代の自分自身の姿と重ね合わせずにはいられなかった。今日の若者も、別の形で「トカトントン」に悩まされているのではないだろうか。SNSでの「いいね」を求めたり、周囲の評価を気にしたり、表面的な成功や幸せの形に囚われたりする姿は、ある意味で主人公の葛藤と重なる部分がある。
太宰治は『トカトントン』という小さな物語の中に、人間の生き方や社会の問題など、普遍的なテーマを詰め込んでいる。それゆえに、70年以上経った今日でも、この作品は私たちの心に強く響くのだろう。「トカトントン」という音は、私たち一人ひとりの心の中にも存在している。それと向き合い、それを超えていくことが、真の成長につながるのかもしれない。
読後、私は自分自身の「トカトントン」について考えてみた。何かに熱中しようとするとき、私の心の中でも何かが「それは本当に意味のあることなのか」と問いかけてくることがある。それは必ずしも否定的なものではなく、より本質的なものへと目を向けさせるための警告なのかもしれない。太宰治のこの小さな作品は、そんな問いを私に投げかけてくれた。
『トカトントン』は、戦後の混乱期に書かれた作品でありながら、現代に生きる私たちにも深い示唆を与えてくれる。それは、表面的な熱意や感動ではなく、より本質的なものに目を向け、真に自分自身と向き合うことの大切さではないだろうか。この物語を通して、太宰治は私たちに、自分自身の内なる「トカトントン」に耳を傾けることの意味を教えてくれているのかもしれない。
『トカトントン』はどんな人向けの小説か
『トカトントン』は、どんな読者に特に響く作品なのでしょうか?
この小説が特に向いている読者層を考えてみました。
- 人生の意味や目的について考えることが好きな人
- 戦後文学や日本の近代文学に関心がある人
- 自分の内面と向き合うことを大切にする人
- 太宰治の文体やテーマに興味がある人
- 短編小説の中に凝縮された深いメッセージを読み解きたい人
『トカトントン』は短い作品ながらも、人間の内面や社会との関わりについて深く考えさせてくれる小説です。
特に、自分自身の生き方や価値観について考えたい人にとって、心に響くものがあるでしょう。
戦後の混乱期という特定の時代を背景にしていますが、そこで描かれる若者の葛藤や自己探求のテーマは普遍的なもの。
現代を生きる私たちにも、共感できる部分がたくさんあります。
『トカトントン』に似た作品3選
太宰治の『トカトントン』を読んで、もっと似たような作品を読んでみたいと思った方のために、テーマや雰囲気が近い作品を3つ紹介します。
どれも『トカトントン』と通じる部分がありながら、それぞれ独自の魅力を持った作品ですよ。
『ヴィヨンの妻』 – 太宰治
『トカトントン』と同じ1947年に発表された太宰治の短編小説です。
才能ある夫を持つ女性が、その夫が抱える様々な問題に向き合いながら、自分の生き方を見つけていく物語。
『トカトントン』と同様に、戦後の混乱期を背景に、人間の内面や生き方について描かれています。
また、登場人物が自分自身と向き合う過程も共通していますよ。
『トカトントン』が男性視点だったのに対し、こちらは女性視点から描かれているのも興味深いポイントです。
『斜陽』 – 太宰治
太宰治の代表作の一つで、没落していく貴族の家族の姿を通して、戦後社会の変化と人間の生き方を描いた作品。
母と娘を中心とした家族の物語で、時代の変化の中での人間の尊厳や生きる意味を問うています。
『トカトントン』と同じく戦後の価値観の変化を背景にしており、登場人物たちの内面の葛藤が繊細に描かれています。
より長編ですが、太宰治の文体の美しさや人間描写の深さを味わいたい方におすすめです。
『こころ』 – 夏目漱石
夏目漱石の代表作で、「先生」と呼ばれる中年男性の過去の罪と苦悩を描いた小説。
主人公の「私」が「先生」と出会い、その生き方に影響を受けていく過程が描かれます。
『トカトントン』とは時代背景は異なりますが、人間の内面の葛藤や罪の意識、生き方の問題など、テーマ的に共通する部分が多くあります。
また、書簡体が用いられる点も似ていますね。
人間の心の闇と向き合いたい方におすすめの一冊です。
振り返り
太宰治の『トカトントン』について、あらすじから読書感想文のポイント、似た作品まで幅広く紹介してきました。
この小説は一見シンプルな物語でありながら、戦後の若者の葛藤や人間の内面の問題など、深いテーマを含んでいます。
「トカトントン」という音が象徴するものは何か、作家が引用したマタイ伝の言葉は何を意味するのか、読者一人ひとりが考えることで、さまざまな解釈が生まれる奥深い作品です。
読書感想文を書く際には、主人公の内面の葛藤や、戦後という時代背景、そして人間の生き方についての問いという3つのポイントを中心に、自分自身の感じたことや考えたことを織り交ぜると、深みのある文章になるでしょう。
たった13,000文字ほどの短編小説ですが、その中に太宰治は多くのメッセージを込めています。
ぜひ、じっくりと味わいながら読んでみてください。
きっと、あなた自身の中にも何かが響くはずです。
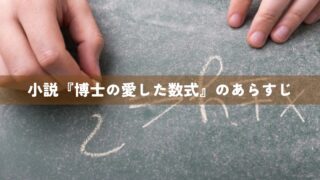
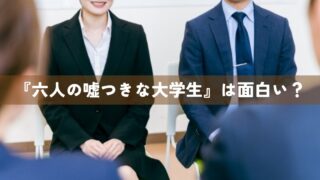

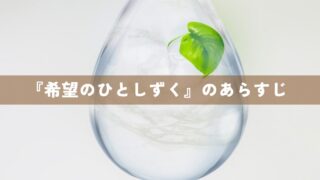
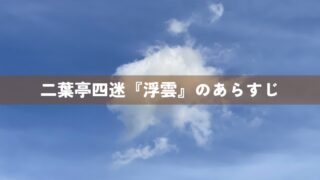


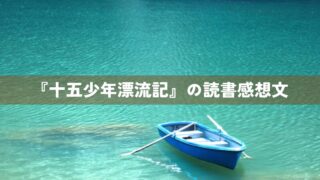
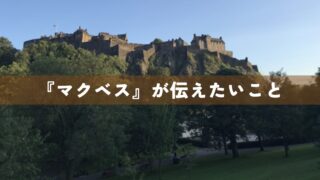
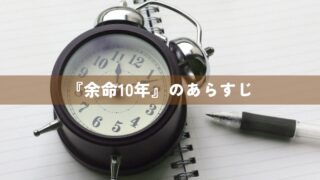

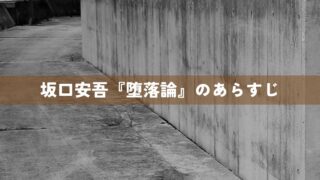
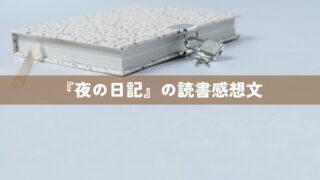

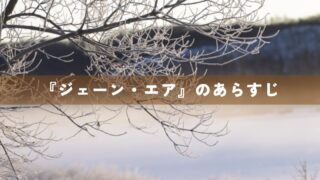
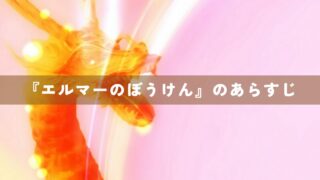


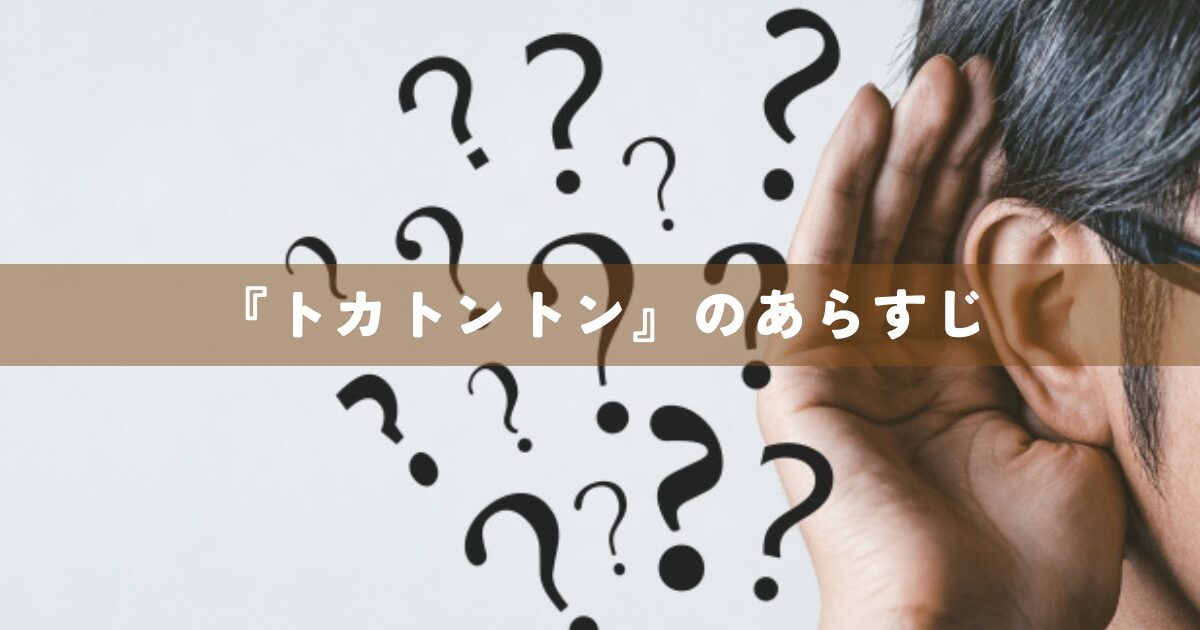
コメント