宮沢賢治の『やまなし』のあらすじを短く簡単に紹介していきます。
『やまなし』は日本の代表的な童話作家・宮沢賢治が1923年に発表した短編童話。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいますが、この作品は何度読んでも心に染みる素晴らしい作品だと感じています。
この記事では『やまなし』のあらすじを短いものから詳しいものまで段階的に紹介し、読書感想文を書く予定の皆さんのお役に立てる情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
『やまなし』の短くて簡単なあらすじ
『やまなし』の中間の長さのあらすじ
『やまなし』の詳しいあらすじ(ネタバレあり)
宮沢賢治の『やまなし』は「五月」と「十二月」の二つの場面で構成された物語である。物語は「小さな谷川の底を写した二枚の青い幻燈」という表現から始まる。
五月の場面では、谷川の底に住むかにの兄弟が「クラムボン」という謎の存在について話している。「クラムボンは笑ったよ」「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ」と繰り返す兄弟。そこへ一匹の魚が現れ、突然水面が泡立ち、青く光る鋭いものが川に飛び込んでくる。それはかわせみで、魚を捕らえて去っていく。恐怖に震える兄弟の前に父親のかにが現れ、「かわせみは私たちには何もしない」と安心させる。子どもたちは「魚はどこへ行ったの」と問いかけるが、流れてきた白い樺の花に目を向ける。
十二月の場面では、成長したかにの兄弟が泡を吹きながら大きさを競っている。そこへ再び父親が現れ、「早く寝ないとイサドへ連れて行かない」と言う。すると突然、水面から黒い丸いものが落ちてくる。「かわせみだ」と思う子どもたちに、父親は「やまなしだ」と教える。やまなしは流れ、親子はその香りに包まれながら追いかける。やまなしは流木に引っかかり静かに漂い、父親は「あと二日もすれば、やまなしが沈み、おいしいお酒ができる」と語る。
『やまなし』の作品情報
『やまなし』に関する基本情報をまとめました。
| 作者 | 宮沢賢治 |
|---|---|
| 出版年 | 1923年(大正12年)4月8日 |
| 初出 | 『岩手毎日新聞』 |
| ジャンル | 童話、短編小説 |
| 主な舞台 | 小さな谷川の底 |
| 時代背景 | 明確な時代設定はなし |
| 主なテーマ | 生と死、自然の循環、成長 |
| 物語の特徴 | 幻想的で詩的な描写、象徴性の高い表現 |
| 対象年齢 | 小学校高学年〜大人 |
『やまなし』の主要な登場人物とその簡単な説明
『やまなし』に登場する主要な人物たちを紹介します。
物語は少ない登場人物で構成されていますが、それぞれが重要な役割を担っています。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| かにの兄弟 | 物語の主人公。谷川の底に住む二匹のかに。「クラムボン」という謎の存在について話し、自然の営みを見つめる視点となる。 |
| お父さんのかに | かにの兄弟の父親。子どもたちに自然界の仕組みを教える役割を持つ。やさしくも賢明な存在。 |
| かわせみ | 五月の場面で魚を捕食する鳥。かにの兄弟にとっては恐ろしい存在だが、自然の摂理を象徴している。 |
| 魚 | かわせみに捕らえられる魚。生命の儚さを象徴する存在。 |
| クラムボン | かにの兄弟が話題にする謎の存在。正体は明かされず、様々な解釈がある。 |
| やまなし | 十二月の場面で川に落ちてくる果実。豊かさや恵みを象徴する。タイトルにもなっている重要な存在。 |
特に「クラムボン」の正体については、光や水の泡、アメンボなど様々な解釈がされていますが、宮沢賢治は意図的に謎めいた存在として描いているようです。
『やまなし』の読了時間の目安
『やまなし』は短編童話なので、比較的短時間で読むことができます。
以下に読了時間の目安をまとめました。
| 文字数 | 約2,813文字 |
|---|---|
| ページ数換算 | 約5ページ(1ページ600文字計算) |
| 平均読了時間 | 約6分(500文字/分として計算) |
| じっくり読む場合 | 約10〜15分 |
| 読みやすさ | 文章は短いが象徴的な表現が多く、じっくり味わうことをおすすめ |
『やまなし』は文章量としては短いですが、宮沢賢治独特の詩的な表現や深いテーマが込められているため、単に速く読むよりも、ゆっくりと味わいながら読むことをおすすめします。
『やまなし』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『やまなし』の読書感想文を書く際に、特に注目したいポイントを3つ紹介します。
これらのポイントを押さえることで、より深みのある感想文が書けるでしょう。
- 自然の循環と生命の関係性
- 対比的な表現と象徴性
- 成長と希望のテーマ
それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
自然の循環と生命の関係性
『やまなし』では、自然界における生命の循環が描かれています。
五月の場面ではかわせみが魚を捕らえるという「食べる側と食べられる側」の関係が描かれる一方で、十二月の場面ではやまなしという果実が自然の恵みとして与えられます。
この「奪う」と「与える」の対比は、自然界のバランスを表していると考えられます。
読書感想文では、このような自然の営みについて、あなた自身がどう感じたかを書いてみるといいでしょう。
例えば、私たち人間も自然の一部であり、何かを得るためには何かを犠牲にしていることや、逆に自然から恵みをいただいていることなど、自分の日常生活と結びつけて考えてみるのも良いでしょう。
対比的な表現と象徴性
『やまなし』では、様々な対比的表現が用いられています。
五月(春)と十二月(冬)、昼と夜、恐怖と安らぎ、死と生など、相反する要素が物語全体を通して描かれています。
特に「かわせみ」と「やまなし」は象徴的な存在で、かわせみは恐怖や死を、やまなしは安らぎや生を象徴していると考えることができます。
読書感想文では、このような対比表現や象徴性に着目し、それがあなたにどのような印象を与えたかを書いてみましょう。
例えば「クラムボン」という謎めいた存在についても、あなたなりの解釈を述べると、独自性のある感想文になるでしょう。
成長と希望のテーマ
『やまなし』は、かにの兄弟の成長も描かれています。
五月の場面では恐怖に震えていた兄弟が、十二月の場面では泡を吹いて遊ぶなど、たくましく成長している様子が描かれています。
また、五月の場面で恐ろしい出来事の後に白い樺の花が流れてくるシーンや、十二月の場面でやまなしが落ちてくるシーンは、困難の後に訪れる希望を象徴していると解釈できます。
読書感想文では、このような成長と希望のテーマについて、あなた自身の経験と照らし合わせて考えてみるといいでしょう。
例えば、あなたが困難を乗り越えて成長した経験や、小さな希望に救われた経験などと結びつけて書くと、より心に響く感想文になるはずです。
※宮沢賢治が『やまなし』で伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『やまなし』の読書感想文の例(原稿用紙4枚強/約1700文字)
私は今回、宮沢賢治の『やまなし』という作品を読んだ。最初は小学生向けの童話だからと簡単に考えていたけれど、読み進めるうちに、この物語がとても深いメッセージを持っていることに気づいた。
物語は「小さな谷川の底を写した二枚の青い幻燈」という美しい表現から始まる。五月と十二月、昼と夜という対照的な二つの場面で構成されており、それぞれに違った雰囲気がある。主人公のかにの兄弟が見る世界は、まるで私たち人間が見ている世界とは全く違う、幻想的な世界のようだった。
まず五月の場面で印象に残ったのは、かにの兄弟が話す「クラムボン」という不思議な存在だ。「クラムボンは笑ったよ」「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ」と繰り返す会話は、子どもらしい無邪気さを感じさせると同時に、謎めいた雰囲気を作り出している。このクラムボンが何なのか、作品中では明かされないけれど、それが逆に読者の想像力を刺激する。私はクラムボンを水面の光や泡、あるいは子どもたちの心の中にある想像上の友達のようなものではないかと考えた。
次に強く心に残ったのは、かわせみが魚を捕らえるシーンだ。かにの兄弟は恐怖に震え、「魚はどこに行ったの?」と父親に問いかける。このシーンは、生きるために他の生き物の命を奪うという自然界の現実を、子どもたちが初めて目の当たりにする瞬間を描いているように思う。
父親のかには「かわせみは私たちには何もしない」と子どもたちを安心させるけれど、それは単に恐怖を和らげる言葉ではなく、自然界での各々の位置付けを教えているのだと感じた。つまり、自然界には食う者と食われる者という厳しい関係があるけれど、それぞれの生き物には役割があり、お互いに影響し合いながら生きているということを示しているのだと思う。
十二月の場面では、成長したかにの兄弟が登場する。彼らは泡を吹きながら遊び、「ぼくの方が大きいよ」「いいや、ぼくの方が大きいよ」と会話を交わす。五月の場面と比べると、彼らが成長し、よりたくましくなっていることが分かる。このように時間の経過とともに生き物が成長していく様子も、自然の営みの一部として描かれている。
特に印象的だったのは、水面から落ちてくる「やまなし」だ。最初、かにの兄弟は恐怖を感じ「かわせみだ」と思うけれど、実際にはやまなしという果実だった。「あと二日もすれば、やまなしが沈み、おいしいお酒ができる」という父親の言葉には、自然の恵みに対する感謝の気持ちが込められているように感じた。
この作品を通して、宮沢賢治は自然界における生と死、恐怖と安らぎ、奪うことと与えることの対比を美しく描いている。五月の場面ではかわせみによる命の奪取が、十二月の場面ではやまなしという自然の恵みが描かれており、この対比が物語に深みを与えている。
私たち人間も自然の一部であり、この物語が示すような自然のサイクルの中で生きている。現代社会では自然との繋がりを忘れがちだけれど、この物語を読んで、改めて自然の中での命のつながりや、季節の移り変わりの美しさについて考えさせられた。
また、この物語から学んだのは、恐怖や悲しみの後には必ず希望があるということだ。五月の場面で魚が捕らえられた後に白い樺の花が流れてくるシーンや、十二月の場面でやまなしが落ちてくるシーンは、困難の後に訪れる希望を象徴していると感じた。
私自身の経験と重ねて考えると、小学校から中学校へ進学した時、新しい環境や勉強の難しさに不安を感じたことがあった。でも、友達との出会いや新しいことを学ぶ楽しさに気づいた時、その不安は希望に変わった。『やまなし』のかにの兄弟のように、私も成長の過程で様々な経験をし、少しずつ強くなっているのかもしれない。
宮沢賢治の『やまなし』は、短い物語ながらも深いメッセージを持った作品だ。自然の営みや命の尊さ、成長と希望というテーマは、今を生きる私たちにとっても大切なことを教えてくれる。この物語を通して、自然との共生や命の循環について、改めて考えるきっかけになった。
『やまなし』はどんな人向けの作品か
『やまなし』は様々な年代の読者に楽しまれる作品ですが、特に以下のような方におすすめです。
- 自然の美しさや神秘性に関心がある人
- 生と死、命の循環について考えたい人
- 詩的で幻想的な表現を好む人
- 深いテーマを持つ童話を楽しみたい人
- 文学的な象徴や比喩表現を味わいたい人
『やまなし』は小学校の教科書にも掲載されている作品ですが、その内容は子どもから大人まで幅広い読者に響くものがあります。
子どもが読むと自然の営みや生き物たちの世界に想像力を膨らませることができますし、大人が読むとその象徴性や哲学的なテーマにより深く考えさせられるでしょう。
『やまなし』に似た作品3選
『やまなし』を読んで感動した方におすすめの、テーマや雰囲気が似ている作品を3つ紹介します。
それぞれが独自の魅力を持ちながらも、『やまなし』と共通するメッセージを持っています。
『風の又三郎』 宮沢賢治
同じく宮沢賢治による作品で、自然と人間の関係性を描いたファンタジー作品。
主人公の少年と神秘的な存在である風の又三郎との交流が、美しい自然描写とともに描かれています。
『やまなし』と同じく、自然の神秘性や人間と自然の関わりというテーマが描かれており、賢治独特の幻想的な世界観を楽しむことができます。
『星の王子さま』 アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
一見シンプルな童話のようでありながら、深い哲学的メッセージを含んだ作品。
小さな星から来た王子さまの目を通して、大人の世界や人間の価値観を問い直します。
『やまなし』と同じく、子どもにも大人にも読まれる作品で、シンプルながらも詩的な表現や象徴性に富んだ内容が特徴です。

『あらしのよるに』 木村裕一
オオカミとヤギという本来は敵同士の動物が、暗闇の中で出会い、友情を育むという物語。
自然界の掟を超えた関係性が描かれており、生命の尊さや共生というテーマが『やまなし』と共通しています。
こちらも子どもから大人まで楽しめる作品で、シンプルなストーリーながらも深いメッセージ性があります。
振り返り
この記事では、宮沢賢治の『やまなし』のあらすじを短いものから詳しいものまで段階的に紹介し、作品情報や登場人物、読了時間の目安などを詳しく解説しました。
特に読書感想文を書く際に役立つポイントとして、自然の循環と生命の関係性、対比的な表現と象徴性、成長と希望のテーマという3つの視点をご紹介しました。
『やまなし』は短い童話でありながら、自然の神秘や生命の循環、成長と希望など普遍的なテーマを含む奥深い作品です。
読む人の年齢や経験によって様々な解釈ができる点も、この作品の魅力のひとつだと言えるでしょう。
読書感想文を書く際には、この記事で紹介したポイントを参考にしながら、ぜひ自分自身の感性や経験と照らし合わせて、オリジナリティのある感想文を書いてみてください。



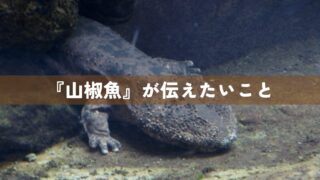
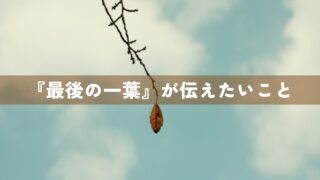
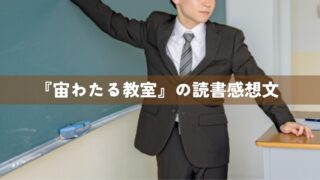
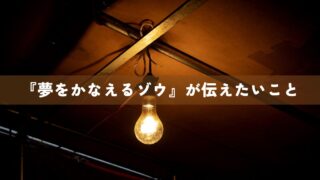

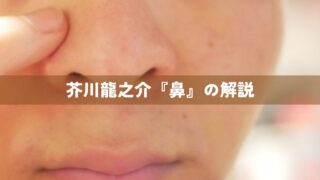



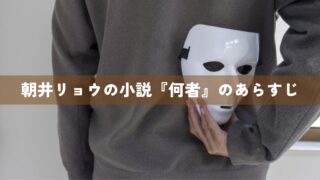


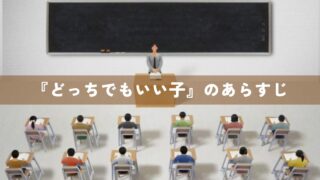


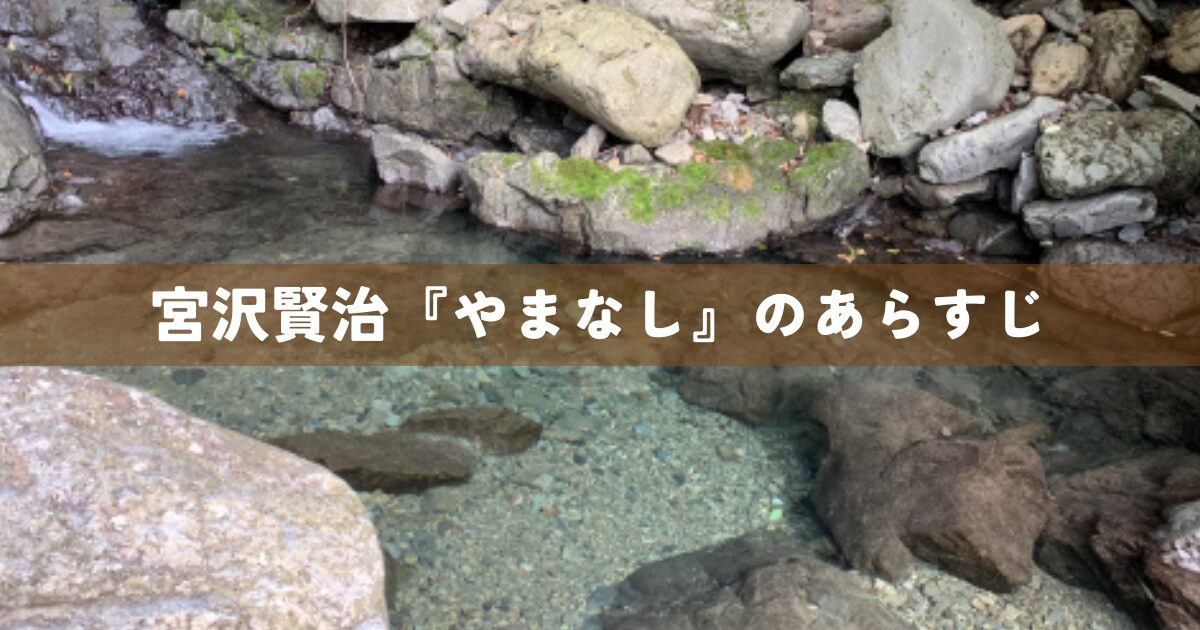
コメント