『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文の書き方について、今回は詳しく解説していきますよ。
この作品は志津栄子さんによる感動的な物語で、第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(小学校高学年の部)にも選ばれています。
主人公の信太朗くんは色覚障がいという特性を持つ小学5年生の男の子。
色が見分けにくいことで日常生活で困ったり、友達との関係で悩んだりする信太朗くんが、やがて「自分だけの色」を見つけて成長していく物語ですね。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいる私が作品のポイントをしっかり押さえて、例文も2パターン用意したので、一緒に見ていきましょう。
『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文を書くうえで大切な3つのポイント
『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要なポイントが3つあります。
- 信太朗くんの心の変化と成長
- 周囲の人々の理解と支え
- 「自分だけの色」という個性の発見
これらのポイントを意識することで、作品の核心を捉えた感想文が書けるでしょう。
それでは、ひとつずつ詳しく見ていきますね。
信太朗くんの心の変化と成長
物語の中で最も重要なのは、主人公の信太朗くんがどのように変わっていくかです。
信太朗くんは最初、色覚障がいを「恥ずかしいもの」「隠すべきもの」だと思っていました。
トマトを区別できなかったり、肉が焼けたタイミングがわからなかったりすることで、自分は普通じゃないんだと悩んでいたんです。
特に2年生のときに診断されてから、友達には秘密にして学校生活を送っていました。
図工の時間に似顔絵のくちびるを茶色に塗ってしまい、クラスメイトからばかにされた経験もあります。
でも、学年が上がって新しい担任の平林先生と出会い、信太朗くんの心に少しずつ変化が生まれます。
先生が自分の苦手なことを素直に話してくれたり、「弱みを見せてもいいんだ」と教えてくれたことで、信太朗くんは自分を受け入れられるようになっていくんです。
最終的に、友達の足立友行くんに自分の色覚障がいを打ち明けることができたのも、大きな成長の証拠ですね。
感想文では、この心の変化に注目して、どの場面で信太朗くんが変わったと感じたか、なぜそう思ったのかを書くといいでしょう。
周囲の人々の理解と支え
この作品では、信太朗くんを支える大人たちや友達の存在がとても大切な役割を果たしています。
お母さんは最初、「かわいそう」と言ってしまったり、色覚障がいを試すようなことをしたりしていました。
でも、それはお母さんなりの愛情表現だったんです。
信太朗くんのことを心配するあまり、どう接していいかわからなかったんですね。
一方で、担任の平林先生は素晴らしい理解者でした。
先生自身のお父さんも色覚障がいを持っていたので、信太朗くんの気持ちをよく理解していました。
ホームルームでその話をしてくれたことで、信太朗くんは「自分だけじゃないんだ」と安心できたんです。
また、友達の足立友行くんとの関係も重要です。
最初はからかってきた友行くんでしたが、実は自分も背が低いというコンプレックスを抱えていました。
お互いに弱みを見せ合うことで、本当の友達になれたんですね。
感想文では、どの人の支えが一番印象的だったか、その理由とともに書くといいでしょう。
自分が困ったときに誰に支えられたかという経験と重ねて書くのもおすすめです。
「自分だけの色」という個性の発見
作品のタイトルにもなっている「自分だけの色」は、この物語の最も重要なテーマです。
信太朗くんは最初、自分の色覚障がいを「欠点」や「不便なもの」だと思っていました。
でも、物語が進むにつれて、「自分にしか見えない世界」があることに気づいていきます。
ゴッホの絵についての話や、虹の7色についての議論を通して、色の見え方は人それぞれ違うということを学びました。
そして、自分の見え方も一つの個性なんだと受け入れられるようになったんです。
絵を描くことにも再び挑戦し、「自分の色」を表現できるようになりました。
これは、色覚障がいを持つ人だけの話ではありません。
みんなそれぞれに「自分だけの色」=個性を持っているんです。
背が高い人、低い人、運動が得意な人、苦手な人、みんな違ってみんないい。
信太朗くんの成長は、そのことを教えてくれる素晴らしい要素なんです。
感想文では、自分の「色」とは何かを考えて書いてみましょう。
自分の個性や特徴について、この作品を読んでどう感じたかを書くといいですね。
より良い読書感想文を書くために『ぼくの色、見つけた!』を読んだらメモしたい3項目~信太朗くんに対してあなたが感じたこと~
読書感想文を書く際には、ただ物語を要約するだけでは不十分です。
あなた自身がどう感じたか、どう考えたかを伝えることが大切なんです。
- 心に残った場面や言葉
- 信太朗くんの行動や気持ちに対する共感や発見
- 自分の経験や考えとの比較
これらのポイントを意識してメモを取っておくと、『ぼくの色、見つけた!』の感想文がぐっと良くなりますよ。
感想文は「感じたこと」を書くものですから、あなたの心の動きを大切にしてくださいね。
心に残った場面や言葉
まず、読んでいて特に印象に残った場面や登場人物の言葉をメモしておきましょう。
例えば、信太朗くんが友行くんに色覚障がいを打ち明ける場面はとても感動的でした。
「なんで教えてくれなかったんだよ」といった趣旨の友行くんの言葉に、友達の優しさが表れていましたね。
また、平林先生が「弱みを見せてもいいんだ」ということを伝えてくれた場面も心に残ります。
眼科の先生の「個性のひとつ」という言葉も、信太朗くんにとって大きな励みになったでしょう。
お母さんが「かわいそう」と言ってしまう場面では、愛情と心配が入り混じった複雑な気持ちが伝わってきました。
どの場面があなたの心に響いたかをメモしておくと、感想文でその理由を詳しく書けるようになります。
なぜその場面が印象的だったのか、どんな気持ちになったのかも一緒に記録しておきましょう。
『ぼくの色、見つけた!』の信太朗くんの行動や気持ちに対する共感や発見
信太朗くんの行動や気持ちを読んで、あなたがどう感じたかをメモしておくことも重要です。
「自分も同じような経験がある」「信太朗くんの気持ちがよくわかる」という共感もあるでしょう。
一方で、「自分だったらこうしたかもしれない」「信太朗くんはすごいな」という発見もあるはずです。
信太朗くんが色覚障がいを秘密にしていた理由について、どう思いましたか。
友達にばかにされるのが怖かったという気持ちは、理解できるものでしょう。
でも、最後に勇気を出して打ち明けた信太朗くんの行動は、とても立派だと思います。
お母さんの「かわいそう」という言葉に対する信太朗くんの反応も考えさせられます。
善意であっても、当事者にとってはつらい言葉になることもあるんだということを学べますね。
あなたが信太朗くんの立場だったらどう感じるか、どう行動するかを考えてメモしておきましょう。
自分の経験や考えとの比較
最後に、この物語を読んで思い出した自分の経験や、普段の考えとの共通点や違いをメモしておきます。
これが感想文を「あなたらしい」ものにする最も大切な要素です。
みんなと違うことで悩んだ経験はありませんか。
背が高い、低い、運動が苦手、勉強が得意すぎる、なんでもいいんです。
信太朗くんの悩みと似ている部分があるかもしれません。
また、友達に本当の自分を見せるのが怖かった経験もあるでしょう。
信太朗くんが友行くんに打ち明けた勇気に、あなたはどんなことを学びましたか。
家族との関係についても考えてみてください。
お母さんが心配してくれるけれど、それがちょっとうっとうしいと感じることもあるでしょう。
信太朗くんとお母さんの関係から、親子のコミュニケーションについて新しい発見があったかもしれません。
自分の経験と比べることで、物語の理解が深まり、感想文もより説得力のあるものになりますよ。
『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文の例文(800字の小学生向けバージョン)
【題名】ぼくにもある「自分だけの色」
『ぼくの色、見つけた!』を読んで、信太朗くんの気持ちがよくわかった。信太朗くんは色覚障がいで、色の見分けがむずかしいことがある。最初は恥ずかしくて友達に言えなかったけれど、最後には自分らしく生きることの大切さを見つけた。
ぼくも人と違うことで悩んだことがある。背が低いことや、みんなより字を書くのが遅いことで、時々いやな気持ちになる。信太朗くんがクラスメイトにからかわれた場面を読んで、「ああ、同じだな」と思った。違うことをばかにする人もいるけれど、それは良くないことだと改めて感じた。
一番心に残ったのは、担任の平林先生の言葉だ。先生は「弱みを見せてもいいんだ」と教えてくれた。信太朗くんはその言葉で勇気をもらい、友達の友行くんに自分の色覚障がいを話すことができた。友行くんも「なんで教えてくれなかったんだよ」と言って、信太朗くんを受け入れてくれた。本当の友達って、こういうものなんだと思った。
信太朗くんのお母さんが「かわいそう」と言ってしまう場面もあった。お母さんは心配してくれているけれど、信太朗くんは困っていないと感じている。家族の愛情は大切だけれど、時々重たく感じることもあるということを学んだ。
物語の最後で、信太朗くんが「自分だけの色」を見つけるところがとても良かった。みんなと同じでなくてもいい。自分にしか見えない世界があって、それを大切にしていいんだ。信太朗くんの成長を見て、ぼくも自分の個性を大事にしようと思った。
この本を読んで、「違う」ことは悪いことではないと学んだ。信太朗くんのように、自分らしく生きることの素晴らしさを見つけたい。ぼくにも「自分だけの色」があるはずだ。背が低くても、字を書くのが遅くても、それがぼくの個性なんだ。これからは、もっと自分に自信を持って生活していこうと思う。
『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文の例文(1200字の中学生向けバージョン)
【題名】個性を受け入れる勇気
『ぼくの色、見つけた!』を読んで、自分らしく生きることの意味について深く考えさせられた。主人公の信太朗は色覚障がいを持つ小学5年生で、色の見分けがつきにくいことに悩んでいる。しかし、物語を通して彼が「自分だけの色」を見つけて成長していく姿は、多くの人に勇気を与えてくれる。
信太朗が直面する困難は、色覚障がいによる日常生活での不便さだけではない。周囲の人々の無理解や偏見、そして自分自身の劣等感との戦いでもある。2年生の時に診断されてから、彼は友達に秘密にして学校生活を送ってきた。図工の時間に似顔絵の唇を茶色に塗ってしまい、クラスメイトからばかにされた経験は、彼の心に深い傷を残した。この場面を読んで、私は小学生の頃、みんなと違うことで笑われた経験を思い出した。
特に印象的だったのは、信太朗の母親が「かわいそう」と言ってしまう場面だ。母親は息子を心配するあまり、色覚障がいを試すような行動を取ってしまう。しかし、信太朗本人は困っていないと感じており、母親の過度な心配がかえって彼を苦しめている。この親子の関係を見て、善意であっても相手を傷つけることがあるということを学んだ。家族の愛情は大切だが、時として重荷になることもある。相手の立場に立って考えることの重要性を痛感した。
物語の転機となるのは、新しい担任の平林先生との出会いだ。先生自身の父親も色覚障がいを持っており、信太朗の気持ちを理解してくれる。先生が「弱みを見せてもいいんだ」と伝えてくれたことで、信太朗は自分を受け入れる勇気を得る。また、先生が苦手な一輪車に挑戦する姿を見せることで、完璧でなくてもいいということを教えてくれた。教師の影響力の大きさを改めて感じた。
友達の足立友行との関係の変化も重要な要素だ。最初は信太朗をからかっていた友行だが、実は自分も背が低いことにコンプレックスを抱えていた。お互いに弱みを見せ合うことで、本当の友情を築くことができた。この場面から、人はみんな何かしらの悩みを抱えているということを学んだ。表面的には強そうに見える人でも、内面では葛藤していることがある。
物語の最後で、信太朗が「自分だけの色」を見つける場面は非常に感動的だった。彼は色覚障がいを欠点ではなく、個性として受け入れることができるようになった。ゴッホの絵や虹の7色についての話を通して、色の見え方は人それぞれ違うということを理解した。自分にしか見えない世界があり、それを大切にしていいのだということを学んだ。
この作品を読んで、私は自分の個性について考えさせられた。人と違うことは恥ずかしいことではなく、むしろ大切にすべきものだということを改めて認識した。信太朗のように、自分らしさを受け入れる勇気を持ちたいと思う。また、周囲の人々の理解と支えがいかに重要かということも学んだ。困っている人がいたら、偏見を持たずに寄り添うことが大切だ。
『ぼくの色、見つけた!』は、多様性と個性を受け入れることの大切さを教えてくれる素晴らしい作品だ。信太朗の成長を通して、読者は自分自身の「色」を見つけるヒントを得ることができる。この本が課題図書に選ばれたのも、多くの人にこのメッセージを届けたいからだろう。私も信太朗のように、自分だけの色を大切にして生きていきたい。
振り返り
今回は『ぼくの色、見つけた!』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
信太朗くんの成長物語を通して、個性を受け入れることの大切さ、周囲の理解の重要性、そして「自分だけの色」を見つけることの素晴らしさを学べる作品でしたね。
読書感想文を書く際は、ただ物語を要約するのではなく、あなた自身がどう感じたか、どう考えたかを大切にしてください。
信太朗くんの経験と自分の体験を重ね合わせることで、きっと心に響く感想文が書けるはずです。
この記事で紹介した3つの重要ポイントと、メモしておきたい3項目を参考にして、あなたらしい読書感想文を完成させてくださいね。
みんなそれぞれに「自分だけの色」があります。
信太朗くんのように、その色を大切にして、自信を持って表現してください。
きっと素晴らしい読書感想文が書けますよ。頑張ってください!
※『ぼくの色、見つけた!』のあらすじはこちらでご紹介しています。



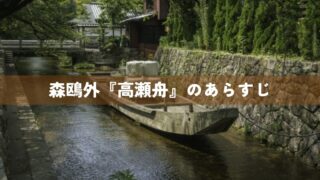


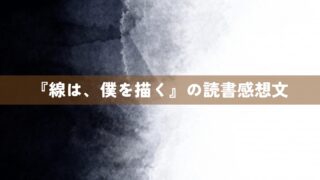
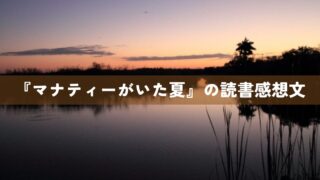
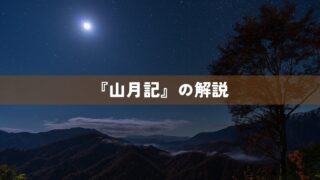
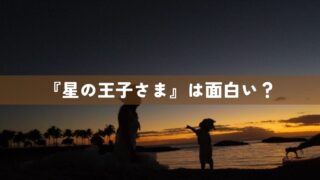

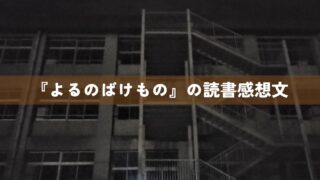
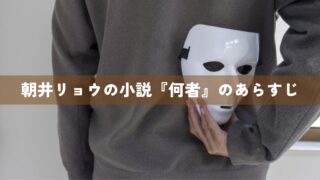

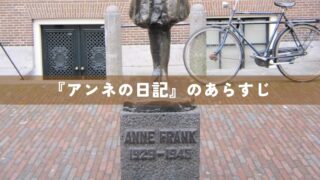




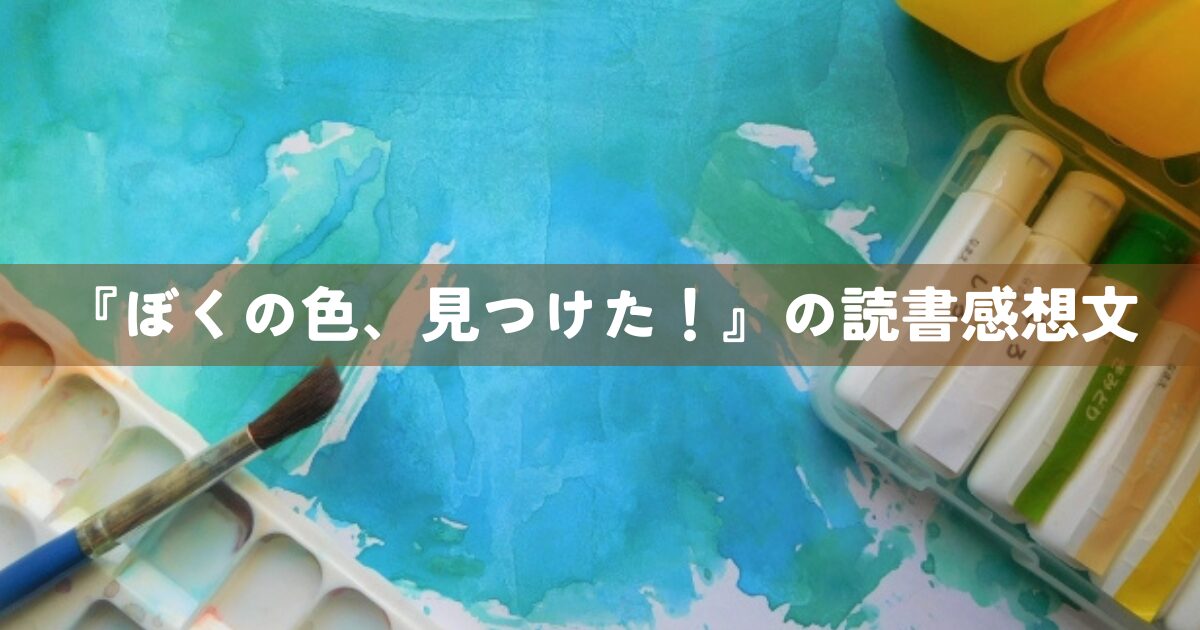
コメント